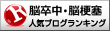
脳卒中・脳梗塞ランキング
脳卒中(脳出血・脳梗塞)後遺症の運動障害のいろいろなリハビリ方法−2
私はボトックス療法は経験したことがありません。
よって想像で考えていますので、間違いもあると思います。
ご指摘・ご教授して戴けると有難いです。
続きです。
ボトックス療法をもう少し説明します。
⑨ ボトックス療法→ボツリヌス毒素製剤を筋肉に注射することにより、脳卒中後の痙縮(筋肉が固くつっぱり動かしにくくなる現症)を改善させリハビリや関節運動を行いやすくする治療法です。
しかし効果が徐々に消えてしまうので年に数回、注射を受けることになります。
特に内反が酷くて歩行出来ない方々のリハビリには、内反の原因となっている筋肉の神経に作用して、動き難い筋肉を弛緩させる働きをするので、リハビリを効率良く進める事を可能にするとても良い療法だと思います。
よって、麻痺側の足の内反が改善されて杖あり歩行・杖なし歩行になるまでは非常に有効だと思います。
内反が改善されて杖歩行が出来るようになり、且つ、麻痺側の手足がある程度動き始めるようになったらビューティーローラーで徹底的に筋肉を解し柔らかくすることをお勧めします。
しかしながら、ボトックス療法は拘縮(筋肉・末端が線維化して硬くなり動き難い状態)には効果が期待出来ないとされています。
理由は、3Мメソッドからの視点で述べると、
ボトックス療法を続けていると、薬の耐性(薬を長く服用していると効果が薄れること)という問題もありますが、
3Mメソッドでは、麻痺側の手足が動き始めた時期(=痙縮の減少と拘縮の台頭)は、運動障害の原因が痙縮から筋肉が硬くなる拘縮に代わって行く時期である考えているからです。
そして、拘縮(末端の線維化)が次第に運動障害の一番の原因になって行く時期だとも考えていますので、効果が次第に薄くなって行くことは自然だと思います。
実際、ボトックス療法は痙縮には効果があり拘縮には予防効果があるものの、拘縮には効果が期待出来ないとなっています。
要するにボトックス療法は神経に働いて動き難くなった筋肉を弛緩させて動き易い状態にする作用はありますが、線維化して硬くなった筋肉自体には効果がないからだと思われます。
つまり、いくらボトックス療法が筋肉を収縮させる神経に働いて動き易く弛緩させても、筋肉自体が線維化して硬くなっている(=拘縮)から無理なのは当然となります。
実際、約5年間でボトックス療法の効果に疑問を持ち止めてしまう(ボトックス療法の筋肉注射が痛い・注射量が次第に増える・高額)ことが多いという報告もあります。
備考→筋肉注射が痛いのは、皮下注射よりも注射針を深く刺すこ事と、筋膜に刺して穴を開ける筋膜穿刺の痛みがあるから。
裏を返せば、ボトックス療法が次第に効果が薄れて行くと言うことは、時間の経過と共に運動障害の原因に関しては、痙縮が減少して、拘縮が運動障害の一番の原因になって行くと言う証拠とも言えるのではないでしょうか?
◎前回のブログに記載していますが、
① TMS
② tDCS
③ ハンズ療法(アイビス)
④ CI療法
⑤ カグラ
⑥ 促通反復療法
⑦ 堀尾法
⑧ ロボットを利用した運動療法
⑨ ボトックス注射でのリハビリ療法
⑩ 再生医療(脳損傷治療薬のアクーゴ=SB623(製品名アクーゴ脳内移植用注)
脳損傷治療薬のアクーゴとは、
アクーゴは、サンバイオ株式会社が開発した脳損傷治療薬で、脳血管疾患である脳卒中後の機能障害や外傷性脳損傷(TBI)の治療に効果が期待されています。(前述)
以上10のリハビリ方法があります。
追加→その他 ミラー療法
鏡による錯視を利用した治療法
ボトックス療法以外は失われた脳の機能を活性化することをメインにして実施されています。
3Мメソッドは従来の9つの方法と異なり「原因に対する治療方法」です。
つまり、麻痺側の手足が動き始めることの意味・評価を、
痙縮が減少して拘縮(末端の線維化)が脳卒中後遺症の運動障害の一番の原因になると判断し、線維化を阻止することによって回復を目指すということです。
●まとめ
ボトックス療法は、緊張した筋肉の緊張を和らげる薬剤を注射して、つっぱりを軽減させますから、硬くなって思うように動けない・動作訓練が出来ない方々にはとても有効だと思います。何と言っても通常の生活が出来ることは、生きる上で最大の喜びです。
しかし、ボトックス療法の薬が効いている内は良いでしょうが、薬効が消えてしまった後は元の筋肉が思うように動き難い状態=痙縮に戻ってしまいます。しかも、更に進んだ状態の拘縮(末端組織の骨格筋・筋膜・腱・靭帯・関節・関節周囲組織が線維化で硬い状態)には効果が期待出来ません。
また、注射の回数が増える毎に効果が薄れたり、注射液の回数が増えても量を増やしても拘縮一番の原因になっていれば薬の問題ではなく効果がないのは当然でしょう。
と言うことは、私の理論から考えると麻痺側の手足が動き始めたら
運動障害の原因が痙縮が減少して拘縮が一番の原因になるですから、
麻痺側の手足が動き始めたらボトックス療法は効果が次第に薄くなって行くと言うことになります。
しかも、薬効も回数を重ねて行く内に効果が少なくなってしまいます(=薬の耐性)。
ボトックス療法もビューティーローラー利用3Мメソッドも、筋肉を解し柔らかくして動き易い状態にすることに変わりはありません。
しかし、3Мメソッドは薬を使用しません。
皮膚を傷付けるという欠点はありますが、薬による副作用もありません。
私は受けたことがないのですが、ボトックスの注射はとても痛いそうです。 前にも述べましたが、理由は、
筋肉注射が痛いのは、皮下注射よりも注射針を深く刺すこ事と、筋膜に刺して穴を開けるという筋膜穿刺の痛みがあるからです。
筋肉注射が痛いのは、皮下注射よりも注射針を深く刺すこ事と、筋膜に刺して穴を開けるという筋膜穿刺の痛みがあるからです。
しかもボトックス療法は注射した部位の感覚は失く麻痺していますが、
反対に、3Мメソッドは麻痺している部位をビューティーローラーの刺激で、
繰り返しの規則的なリズムのある
刺激(共振・共鳴効果で活動電位・電流を効率的が発生)が、
機械的刺激→感覚→知覚→脳の感覚野へと求心路を伝わり麻痺部分の感覚を再生することも期待出来ます。
ビューティローラー使用で感覚を知覚(先)に変えてから、脳内地図を再構築して、当核する位置にペナンブラ領域に新しい回路作成して運動野に繋がり、指令を出して運動障害を改善(後)されて行くのだと思います。(私見)
何と言っても費用は、スポーツジムの会費の1ヶ月約1万円ちょっとで、とても経済的です。
一方、ボトックス療法の費用は
保険診療で行う事ができる治療ですがボツリヌス注射が高価(1バイアル5万円)であるため3割負担の患者さんで注射1回1万5千円くらいになります(ただし,使用するボツリヌスが1本ですむ場合)
しかしながら、ボトックス療法は、特に内反が酷くて歩行出来ない方々のリハビリには、神経に作用して動き難い筋肉を弛緩させる働きをするので、リハビリを効率良く進める事を可能にするとても良い療法だと思います。
◎脳卒中サバイバのゼンデラ Ⅱさんの情報によると
次のことがわかったそうです。
●治療期間中に、ボトックスの投与間隔は徐々に延びる傾向が見られた。
●ただし、これは効果が続くからではなく、患者が治療に対する期待を失ったり、健康状態が悪化したことも影響している可能性がある。
●また、注射の投与量も時間の経過とともに増加する傾向があった。
●治療効果が期待通りでないと感じた患者の89%が、治療開始から5年以内に治療を中止したことが確認された。
●●ボトックス療法は脳卒中後の痙縮管理に一定の効果を発揮するが、長期的な治療では効果が徐々に薄れていく。また、治療効果が期待通りでない場合、多くの患者が5年以内に治療をやめてしまうことがわかった。したがって、患者の期待と現実的な治療目標を明確にすることが、治療の継続と効果の最大化に不可欠である、
●ボトックス注射は対症療法にすぎず、だんだん効かなくなり、ほとんどの人は5年以内に治療をあきらめるとのこと。
参考文→脳卒中サバイバのゼンデラ Ⅱ
さん
◎ボトックス療法のメカニズム→
脳卒中で脳からの運動指令が出ないために、筋肉がダランとした弛緩性麻痺の後に、脊髄反射亢進状態である痙縮(=突っ張り・強張り)の筋肉を、ボトックス療法では支配する神経に働いて筋肉の収縮を阻害し、弛緩させる効果があるとされています。(=痙縮には効果あり)
ボトックス療法は神経と筋肉の間の伝達を阻害することで、筋肉の収縮を減少させる療法です。もう少し説明すると、神経伝達物質のアセチルコリンの放出を抑制することで、筋肉を弛緩させる療法です。
●ボツリヌス菌の毒素を原料とした製剤を筋肉に注射するボトックス療法は筋肉の神経筋接合部の運動神経系興奮ニューロンを興奮させるアセチルコリンの分泌を阻害し抑制する役割があり、作用は神経から筋肉への伝達を遮断します。その結果、筋肉の収縮を抑え、筋肉が動かないようにします。その特性を活かして顔面けいれん、眼瞼けいれん、痙縮(=手足がつっぱる状態)など、筋肉の異常な収縮により起こる疾患に対して使用されます。
脳卒中を発症してからなるべく早い段階でボツリヌス療法を導入することが望ましいですが、発症してから数年経過していても効果的な場合もあります。
拘縮(筋肉・筋膜・腱・靭帯・関節・関節周囲組織など末端が線維化して固まってしまうこと)が強くなると改善は難しいですが、良くなる事があるため治療を一考する余地があります。
参考図→ボツリヌス療法‐広島県福山市 医療法人 玄同会 小畠病院
◎ボトックス注射で生じる7つの欠点とリスク
最初に、
治療に使用するボツリヌス毒素は、人工的に1,000倍以上に薄め、薬として精製されたものですので、安心して利用することが可能です。
ボツリヌス療法の効果は、注射後2~3日目から徐々にあらわれ、通常3~ 4ヵ月間持続します。 効果は徐々に消えてしまうので、治療を続ける場合には、年に数回、注射を受けることになります。
しかし、薬物なので副作用があります。欠点とリスクとは薬の副作用です。
① アレルギー反応 が出ることもある
② 表情が不自然でぎこちなくなる
③ 噛む力が低下して食事の時間が長くなり食事がし難くなる
(②と③は顔に打った場合です・脳卒中経験者には殆ど関係ないと思いますが、、。)
④ 腫れや内出血が生じる
⑤ たるみができる
⑥ 慢性的な頭痛などの症状が出る
⑦ 意図しない箇所の汗が増える
⑧ 注射が痛い(理由は前述)
⑨ 高価である→保険診療で行う事ができる治療ですがボツリヌス注射が高価(1バイアル5万円)であるため3割負担の患者さんで注射1回1万5千円くらいになります(ただし,使用するボツリヌスが1本ですむ場合)
⑩ 定期的に打つ必要がある→ボツリヌス療法の効果は、注射後2~3日目から徐々にあらわれ、通常3~ 4ヵ月間持続します。 効果は徐々に消えてしまうので、治療を続ける場合には、年に数回、注射を受けることになります。
ボトックス注射は連続して打ったとしても効果が薄まることはありませんが、 定期的に打つことで効果がより持続するようになります。
〇11 その他−麻痺側に注射しても感覚を麻痺させているので、感覚の再生を期待出来ない。よって患側の脳の辛うじて行生き残っている神経細胞の領域であるペナンブラ領域に新しい神経回路(新しい多数のシナプス結合)の新生も期待出来ない。
◎ボトックス療法の利点としては
●手足の筋肉がやわらかくなり、動かしやすくなることで、日常生活動作(ADL)が行いやすくなる
●リハビリが行いやすくなる
●関節が固まって動きにくくなったり、関節が変形するのを防ぐことができる(拘縮の予防効果)
●手足のつっぱりによる痛みが減る
●介護の負担が軽くなる
参考→ブログ脳内出血と失語症さんから
今年最後のブログでした。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
私の年末年始は故郷の鹿児島に帰省して93歳の母親と過ごす予定です。
良いお年をお迎え下さい。
来年も宜しくお願いします。
追記→来年の春頃から大阪の小冊子の出版社による私の回復方法の連載が始まる予定です。

