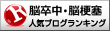
脳卒中・脳梗塞ランキング
私の知っている限りの脳卒中(脳出血・脳梗塞)後遺症の運動障害について調べて概要を記載してみます。
何れも経験はしていませんので、間違いがあれば教えてください。
① TMS
② tDCS
③ ハンズ療法(アイビス)
④ CI療法
⑤ カグラ
⑥ 促通反復療法
⑦ 堀尾法
⑧ ロボットを利用した運動療法
⑨ ボトックス注射でのリハビリ療法
⑩ 再生医療(脳損傷治療薬のアクーゴなど)
以上10のリハビリ療法があります。
追加→その他 ミラー療法
鏡による錯視を利用した治療法
①〜⑧までは患側の脳の辛うじて生き残っている脳神経の領域であるペナンブラ領域を活性化して新しい回路(多数のシナプス結合)の作成を期待してリハビリを実施していると思われます。
一方、
⑨ ボトックス療法は麻痺している筋肉の神経に作用して、動き難い筋肉を弛緩させる働きをすることによって、リハビリを効率良く進めるように実施しています。
3Мメソッドは上記のいずれにも属さずに、
麻痺側の手足が動き始めることの意味・評価を、痙縮が減少して拘縮(末端の線維化)が脳卒中後遺症の運動障害の一番の原因になると判断し、線維化を阻止することによって回復を目指すということです。
つまり、
3Mメソッドは「原因に対する治療方法」です。
⑩ 再生医療(脳損傷治療薬のアクーゴなど)
再生医療(=幹細胞治療)による脳梗塞後遺症の治療は、患者さんの脂肪から幹細胞を採取して培養して増やしてから患者さんに点滴療法で戻す治療法です。そのことにより脳神経細胞の修復および再生と、脳卒中によって傷ついた脳の血管を新しく再生させることで、機能しなくなった脳細胞を復活させて後遺症を改善をする最新の治療法です。
しかし、残念ながら、今は研究途中です。という治療法です。
具体的には、
脳損傷治療薬のアクーゴがあります。=SB623(製品名アクーゴ脳内移植用注)
再生療法の1つであるアクーゴは、サンバイオ株式会社が開発した脳損傷治療薬で、脳血管疾患である脳卒中後の機能障害や外傷性脳損傷(TBI)の治療に効果が期待されています。
外傷性脳損傷による慢性期の運動麻痺の改善を目的とした治療薬として、厚生労働省から条件及び期限付きの製造販売承認を取得しました。
外傷性脳損傷は、交通事故や転倒などで頭部に外から強い力が加わり、頭蓋内の脳組織が損傷することで発生します。
それでは、各リハビリについて説明してみます。
……………………………………………………………
⭕️脳卒中(脳出血・脳梗塞)後遺症の運動障害のいろいろな治療方法‐1
① TMS(Transcranial Magnetic Stimulation・経頭蓋磁気刺激療法)治療→電磁石を用いて電流を起こし、頭蓋骨を通して脳に刺激を与え脳を活性化させる方法。頭皮上から8の字型の電磁石による急な磁場の変化(ファラデーの電磁誘導の法則による)を与えることによって、弱い電流を組織内に誘起させて、脳内のニューロン(神経細胞)を興奮させる方法


参考写真→TMS・脳卒中ラボ+産業医科大学リハビリテーション医学講座
② tDCS→経頭蓋直流電気刺激(tDCS)は頭皮上にスポンジ電極を置き、脳の特定の領域に微弱な直流電気を流すことで脳活動を調節する治療法

参考写真→tDCS・産業医科大学リハビリテーション医学講座
③ ハンズ療法→麻痺した上肢に手関節固定装具と携帯型の随意運動介助型電気刺激装置(IVES・アイビス)を装着して、随意運動を1日8時間、3週間つけ、リハビリの訓練時だけでなく日常生活でも麻痺した手を使う頻度を上げることで上肢機能の改善を目指す治療法

参考写真→ハンズ療法・脳梗塞リハビリスタジオあくてぃぶ
④ CI療法(Constraint-induced movement therapy)→非麻痺側(健側)の上肢を拘束して麻痺側上肢を使用する動作を練習することで、麻痺側の可動性や動き難さを補うことを目的とした治療法

参考写真→CI療法・讀賣新聞オンライン
⑤ カグラ→mediVRを装着して仮想空間上の狙った位置に手を伸ばすリーチング動作を繰り返すことで、姿勢バランスや二重課題型の認知処理機能を鍛える療法

参考写真→mediVRカグラ・大阪−株式会社mediVR
⑥ 促通反復療法→セラピスト(理学療法士作業療法士)さんが麻痺した手や足を操作して意図した運動を反復させる療法(川平法)
麻痺側の手足を操作(促通治療)によって、意図した運動(随意運動)を実現し反復することでそれに必要な大脳から脊髄までの神経回路を再建・強化することを目的とした治療法
1つの治療部位に対して100回を目標に、そのパターンを数分間程度で集中反復することが重要です。

参考写真→促通反復療法・川平先端リハラボ+臨床神経・2013年論文より下堂園恵
⑦ 堀尾法→
堀尾憲市さんの著者「奇跡の復活: 脳卒中麻痺からの生還」
の堀尾法リハビリがあります。
しかし、痙縮を脳からの運動指令が出なくなり脊髄反射亢進状態であることではなく、痙縮であっても脳から麻痺側の手を縮めるという指令が出ているとしています。そのことにより、脳から筋肉を縮める運動指令が出て肘が曲がり指が曲がり縮んでいると説明されています。
痙縮で脳からの運動指令が出ていることには疑問です。
今のリハビリには、脳の再教育がないとして、麻痺側の手足が潜在意識から動くことを信じて手指リセッターで痙縮解除する方法を提唱しています。
詳細は分かりませんが、基本的に反復動作訓練で患側の脳の辛うじて生き残っている脳神経のペナンブラ領域に新しい回路を太くする(脳の再教育)ことを推奨しているように思えます。
参考写真→堀尾法の本
⑧ ロボットを利用した運動療法
ロボットリハビリテーションは、ロボットをリハビリテーションの手段として活用し、身体機能や能力の改善を図るものです。 歩行のサポートをするものや、腕や手の機能をサポートするもの、動きを評価分析するロボットなど、様々な種類のロボットが存在しています。
そして以下の効果が期待出来ます。
a 歩行練習が従来よりも可能になる
b 早期に歩行の自立度や歩行速度が改善する
c 運動機能の改善効果が高い
d 運動量や練習量を増やすことができる
e リアルタイムフィードバックにより運動学習が促進され、モチベーションが向上する
ロボットリハビリテーションには、歩行支援ロボットや上肢訓練用ロボットなどがあります。
◎効果
○歩行支援ロボット
従来では難しかった方でも歩行練習が可能になる
○上肢訓練用ロボット
重度~中等度の上肢麻痺患者に対して、ロボット支援訓練と作業療法を併用することで、より効果的な治療成果が得られる
脳卒中(脳出血・脳梗塞)発症後のリハビリテーションは、
急性期→発症から約1ヶ月まで
回復期→発症約1~6ヶ月まで
のに分けられます。
回復期は後遺症回復の「ゴールデンタイム」と呼ばれています。
定期的なリハビリテーションを継続することで、身体機能の回復がより速やかに進み、再発リスクを低減させる効果があります。
しかし、回復期を過ぎても適正なリハビリを続けていれば運動障害が改善することも分かっています。
参考文→グーグル
⑦ ボトックス療法→ボツリヌス毒素製剤を筋肉に注射することにより、脳卒中後の痙縮(筋肉が固くつっぱり動かしにくくなる現症)を改善させ関節運動を行いやすくする治療法です。
しかし効果が徐々に消えてしまうので年に数回、注射を受けることになります。

また、拘縮(筋肉・末端が線維化して硬くなり動き難い状態)には効果が期待出来ないとされています。
3Мメソッドからの視点で述べると、麻痺側の手足が動き始めた時期(=痙縮の減少と拘縮の台頭)からのボトックス療法は、運動障害の原因が痙縮から拘縮に代わるので効果が薄いと考えています。
次回はその理由を含めて、もう少しボトックス療法について記載しようと思います。





