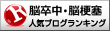
脳卒中・脳梗塞ランキング
アイシング効果−1(アイシング実施開始2023年09/18〜)
◎今までは、痛みがある時にだけアイシングを実施していました。
しかし、2023年09/18から痛みが無くても、痛み防止と超回復のためにアイシングをするようになりました。
現在も、ビューティローラーを使用して、
①ビューティーローラーの機械的刺激と摩擦熱
②サポーター・ベルトの圧迫(腰・麻痺側の太もも→傷防止も兼ねて)
③ゴム板による保温(腰→傷防止も兼ねて)
以上による温泉効果による
血流改善・低酸素状態改善を期待して実施していますが、
より、効果を高めるために、アイシングを実施するようになりました。(アイシング実施開始2023年09/18〜)
スポーツジムからの帰宅後に、家で麻痺側の右腰に氷枕(薄い腹巻きに保冷剤を入れて)によるアイシングをするようにしています。
これは、必要以上の炎症反応を防いで、より効果(超回復)を高めることが目的です。
アイシングすることにより、軽微な筋損傷後に実施すれば筋再生を促進できることが、判明されています。
それは、アイシングにより炎症性マクロファージの集まりが弱まることが主な要因になっています。
アイシングすることによって、熱を冷まして過剰な炎症反応を抑えて腫れや内出血を抑えると同時に早期回復を期待出来ます。
更に超回復にも繋がります。
また、必要以上の炎症反応による神経活動を抑えて痛みを緩和してくれます。また、細胞の代謝を下げることで、過剰な炎症反応を防ぐ効果と 疲労回復にも役立つことが判明しています。
参照写真→アイシング・サルビア整骨院
◎アイシングによる効果図

参照図→医学界新聞・筋損傷の程度に応じたアイシングの効果
寄稿 荒川高光
2023.06.05 週刊医学界新聞(通常号):第3520号より
◎用語解説→
1−マクロファージ→
白血球のうちの1つ。炎症性と抗炎症性の2種類があることが知られている。
2−炎症性マクロファージ→
組織損傷の急性期に、損傷部に集まってくるマクロファージ。損傷した組織を貪食し、炎症反応を引き起こす。
3−炎症→生体の組織が損傷したときに起こる病的反応。発赤 、熱感 、腫脹 、疼痛 という症状が出る。
参照文献→神戸大学大学院保健学研究科(軽微な筋損傷に対するアイシングは筋損傷後の再生を促進する)
⭕スポーツ現場で行われるアイシングは、次の3つに大別できます。
①ケガをした際の応急処置→受傷部の痛みや腫れなどの炎症を抑え、二次的損傷を最小限に制限することが目的です。更に、新陳代謝が低下することにより、発痛物質の生成を減少させることにも有効です。
また、アイシングにより、損傷部の感覚受容器の反応が鈍くなり(閾値の低下)、その結果疼痛を感じにくくなります。更に感覚神経の刺激伝達の遅延が起こり、中枢神経への感覚インパルスの減少が見られるようになります。その結果、疼痛が軽減します。また、疼痛の軽減により筋肉の緊張が減少し、正常部での血液循環が改善されます。
②体温上昇を抑えるための手段→体温の上昇は脳への影響も大きく思考力・集中力の低下にもつながり、けがを予防・防止する目的です。
③クールダウンの一つの手段→スポーツなどの激しい運動をすると筋肉などからの熱の発生で体温が上昇し、それに伴い皮膚の血管が拡張し、血流量が増えます。
また、関節や筋肉の疲労性の炎症もあります。
そして運動終了後には、人間の体はエネルギーを使って普段の体温に戻ろうとしますが、これらの上がった熱をアイシングによって助け体温を下げることを目的に行います
健康な人の場合 筋肉を動かすと血液中に乳酸が溜まり、その量は運動量に比例して増加します。
乳酸が一定量蓄積されると筋肉の張りを生み痛みにつながります。運動後のアイシングは、その部分の張りや痛みを抑えると同時に、血管が収縮され一時的に血液の流れを悪くします。
しかし、アイシング中止後しばらくすると血管は膨張し、血流が活性化して疲労物質の乳酸を勢いよく吸収するリバウンド効果が現れます。
これはCIVD(冷却がもたらす血管拡張効果)といわれ、局所冷却によって一時的な新陳代謝の低下や血管の収縮をおこし、その後、局所冷却をやめたり温水につけるなどの加温を行ったりすることで、収縮させた血管を拡張し、新陳代謝が低下している組織への血流を増やし、疲労などの原因の乳酸やその他の老廃物を除去し、疲労回復を早める効果を狙ったものです。
また筋力の強化のメカニズムは、超回復理論によるもので、運動することで加わる筋繊維への外力により、筋繊維の破壊がおこることにより、その修復過程で元の筋繊維よりも強度が高く太い新しい繊維に超回復がおこると考えられています。
更に関節周囲では、動きや体重負荷によるストレスにより疲労性の炎症がおこります。これらに対しアイシングすることは、応急処置時と同様の効果が得られます。
この結果、運動時の反復した過剰な外力による筋肉・関節など局所の組織の変性を早期に回復させることで、障害の予防にもつながります。
参照文献→fctv.ne.jp
