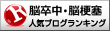
脳卒中・脳梗塞ランキング
⑵筋肉の線維化から筋肉の再生のメカニズム+周辺組織の変性−2
◎筋肉周辺組織(筋膜・靭帯・腱・関節・関節周辺組織・皮膚)の変性について(痙縮→拘縮→強直)
また、
脳梗塞後遺症の筋肉(骨格筋)の痙縮は、動けない・動かないことにより筋膜・靭帯・腱・関節周辺・皮膚などにも影響を及ぼします。
脳梗塞後遺症の痙縮が進行して拘縮に悪化すると、関節などの可動域が制限された状態になり、更に動き辛くなってしまいます。
拘縮よる不動期間が長く続くと、関節包が拘縮の原因の中心になって関節の可動域が制限される状態になります。
◎次に筋肉周辺組織の変性を個別に述べます。
①靱帯は、骨と骨を繋いで強く関節を保持する成分(コラーゲン)と弾性線維(エラスチン)の両方を含む結合組織で構成されている丈夫な線維性の索(さく)の構造になっています。
弾性線維(エラスチン)によって、靱帯はある程度は伸びることが出来て、関節の周囲を取り巻いて関節を連結しています。
靱帯は関節の強化と安定を助け、各関節は特定の方向にだけ動くようになっています。
ベッドに長時間寝ているなど寝たきり生活の不動期間が長く続くと、コラーゲンの増生に伴う線維化が発生して拘縮を後押しします。(寝ている不動期間が長く続くと骨格筋の筋肉ポンプの活動が低くなつて血流障害と低酸素状態になるからと考えられます。→私見)
②腱は、丈夫な組織で出来た線維性の索で、筋肉を骨に繋いでいます。 筋肉は、腱によって骨と繋がっています。
腱の組織は主体が膠原(こうげん)線維(腱線維ともいう)で、互いに強固に結合しあい、線維間には腱細胞が存在しています。 腱組織には血管やリンパ管が少なく、小さな腱ではその内部に血管がみられません。 しかし、神経分布は多く、とくに知覚神経の分布は発達しています。
そのため、血管が少ない靭帯・腱は、一度損傷を受けるとなかなか回復しませんし、知覚神経が広く分布しているために強烈な痛みを感じてしまいます。
③筋膜は筋肉同士の摩擦を防ぎ、身体の滑らかな動きを助ける役割を担っています。
筋膜自身はコラーゲンで出来ており、85%が水分です。
水分不足やストレス、同じ姿勢での長時間作業やベッドでの長時間の寝たきり生活などの不動期間が長く続くと、筋膜の成分が一部分に偏り脱水してしまうことによって接着剤のように変性してしまいます。
そして、隣接している筋肉(骨格筋)や皮膚に接着して固くなります。その上、筋膜同士の癒着も起こしてしまいます。
このことは、筋肉(骨格筋)自体の動きを阻害してしまい拘縮の発生メカニズムに更に寄与します。
◎筋肉周辺組織の変性のメカニズムのまとめ→
脳梗塞後遺症の筋肉(骨格筋)の痙縮→不動期間が長く続くと更なる悪化の拘縮へと悪化します。
拘縮発生時には皮膚・骨格筋・関節包はコラーゲンの増生に伴う線維化の発生が認められ、これが拘縮の発生メカニズムに更に寄与します。
関節の不動(動かないこと)により、皮膚、骨格筋、靭帯、関節包などの軟部組織が壊死して糸の様な組織に置き換わり、伸び縮み能力が失われるという状態、つまり線維化することで 関節可動域(関節が運動することができる角度)減少が引き起こされ固定され癒着して関節強直へと更に悪化します。
●備考→機能的な動作を行うために関節が動く範囲はROM・Range of Motionと言います。
関節強直を予防するためには、
1日2回 それぞれ10回程度の全可動域にわたる運動をすることが大切です。
強直(きょうちょく)は
骨や軟骨の変形までも引き起こします。強直はストレッチや関節の運動では改善が困難です。手術などが必要な場合もあります。
●この状態ではビューティーローラー使用での回復は望めないと思います。
以上は、私なりの理解であり意見です。間違っているところがあればお教え願います。
