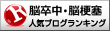
脳卒中・脳梗塞ランキング
⭕脳梗塞後遺症の運動障害のメカニズム(脳梗塞により脳からの指令なし→動かせない状態(=麻痺)→痙縮→拘縮の関係)
●脳梗塞で脳からの指令(運動神経)が無くなると(動かせない状態=麻痺)になり、 脊髄レベル(脊髄〜末端)でのやり取り過剰となって来ます。
①中枢では脳からの指令を伝える運動神経繊維の通り道である椎体路(主)が指令を伝えなくなってしまいます。すると筋肉の収縮強弱をコントロールする椎体外路(枝)が興奮しやすくなって活発に活動してしまい筋肉が過剰に収縮してしまいます。その結果、筋肉の緊張が強い状態になって硬くなってしまいます。(=痙縮・手足の突っ張り)
この状態は血流障害を起こしていて、且つ低酸素状態でもあります。血流障害は修復の材料としての十分な量が供給されない状態が続き、コラーゲンが沈着して線維化が進行します。
このように動かせない状態(=麻痺)が痙縮を生み出します。
一方、また
②末端では伸張反射の亢進
が起こります。脳からの興奮性の信号や抑制性の信号が椎体路(幹)・椎体外路(枝)の経路の損傷を受けていますから、末端の筋肉の運動神経まで届かなくなり筋肉は動かなくなり麻痺を起こします。
また、 抑制性の信号が届かなくなることで反射を抑えていた信号が無くなるために脊髄レベル(脊髄神経〜筋肉)のやり取りが過剰になります。
そして僅かな刺激で筋肉に異常な力が入って勝手に動くという状態になってしまいます。
これは筋肉の中の筋の長さの変化をとらえる受容器である筋紡錘が反応して「筋が伸ばされた」という情報を上行性の感覚信号として(経路が閉ざされているために)脳には伝えられずに脊髄レベルでやり取りすることになり、筋紡錘の伸張反射が亢進してしまい、脊髄の運動神経が勝手に興奮して筋肉が動き過剰に収縮して硬くなってしまうからです。
これはまた筋肉の収縮による筋肉ポンプの血流作用が無くなることを意味します。(=麻痺部分が腫れている原因です)
また、血流障害と血流障害による低酸素状態は修復の材料として充分な量が供給されない事と過剰な損傷修復反応により、筋線維芽細胞によるコラーゲンが吸収されずに沈着することで、線維化が進行してしまいます。そして筋肉の短縮が起こり、クロートゥや内反尖足などの様々な問題を生み出すことになります。
同じように腱・靭帯・筋膜・関節周辺・皮膚などにもコラーゲン繊維が沈着して線維化してしまい硬くなります。
これも痙縮→拘縮を起こす原因です。
●痙縮が長く続くと、筋肉(骨格筋)が繊維化して固まり伸張性の低下が起こって関節の運動が制限され拘縮になってしまいます。
これらが原因で脳梗塞により脳からの指令が出ずに動かせない状態が続くと(=麻痺)が→痙縮→拘縮→と進行・悪化して行きます。
◎参照→
●慶應義塾大学医学部外科
脳神経外科教室 痙縮 参照
●「動かせない状態が痙縮を生み出す」
長崎大学 本田祐一郎理学療法士
参照
以上のように、私なりに理解しているつもりですが訂正箇所があるかも知れません。皆さんの御意見を宜しくお願い致します。
●写真はアディダスの色違い3種類のシューズです。毎日通っているスポーツジムで、気分転換のためにも週毎に替えて使っています。

●You Tube動画→
① ビューティローラー--足裏マッサージ2023年05/28作成動画
https://youtube.com/shorts/kWJCwcxE4EU?feature=share
② ビューティローラー 腰→力こぶ→右足裏(右足内外→太もも外側→足の甲→お尻→ハムストリングス--music
③ベルトマシン右足 外側→内側→太もも表裏左右横→右肩
④スクワットマシンでの 片足→両足→右足首前後左右ストレッチ-- 脳梗塞後遺症の運動麻痺からの回復
--music
