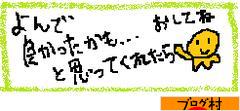昨年、山形へ行った際、
このポスターを見かけました。
「いせもうで でわまいる」
このキャッチコピーがずっと
胸に残っていました。
山形で米沢からセッションに来てくださった
Hさんという方から、
出羽三山のお話を教えていただき、
ぜひ行きたいと思ったものの、
寒さに弱く足も弱い私です。
(Hさんは修験に興味があり、
あちこちの山で山岳修行体験をなさっており、
装束姿のお写真を拝見しましたが
これまた凛々しいのです)
飛行機から見た東北の山、
そしてその峰に立ち並ぶ
初めて見る神々・・・
あの風景がわすれられませんでした。
「いせもうで」
(そうだ!まずお伊勢さんに行こう!)
実は、お伊勢さんには、
一度外宮へお参りしたことがあるだけ。
それも仕事で近くへ行ったついででしたので
かなりの駆け足参拝という状態。
それでも、
(ああ、お伊勢さんとは
こんなにも違うものなのか・・!)と
感動したのを覚えています。
私がこの夏 初めて神宮を訪れた際、
その森へ足を踏み入れたとたん、
辺り一面何とも言えぬ
心地良い花の香りが立ちこめていました。
どこを見回しても花など咲いていないのに、
本当に香しい香りで充ち満ちていたのです。
山育ちの私には
神宮の森のような木の多さには慣れており、
そこに漂う香りが、
慣れ親しんだ山の香りとはまるで違う事に驚きました。
(2012年8月のブログより)
あの時からもう3年・・・。
昨年の終わりから、
色々と新しい扉が開いた気がしている私は、
今こそお伊勢さんに行くときでは・・と
そう思ったのです。
初詣で金神社へ行った際、
年平均にすると、ほぼ毎月お伊勢さんへ
通われてるのではないかというほどの、
伊勢詣デニストの明水さんに、
ぜひご一緒いたしませんか?とお願いした所、
「年末に伊勢へ行った時、
”連れてこい”と言われたのだけど、
私はてっきりこれからできる予定の彼氏の事かと
そう思っていたんですけど・・・
あれはハヌルさんの事だったんですねぇ」
という有り難いお言葉が。
「実は、私、先日の金神社で、
”わかりました。伊勢に行ってきます”と
言ってきちゃったんですよー・・」
そうなのです。
こっ恥ずかしいので記事には書かなかったのですが、
金神社の裏側に並んでいる某社にて、
”いざや” ”いざや”と言われ、
はい、伊勢に行ってきます、と
お返事をしてしまったのでした。
(金神社詣記事はコチラ)
基本面倒くさがりで、
引きこもり放題引きこもりたい人間なので、
そんな遠い所に・・・と思ったのですが。
伊勢に行くタイミングなのでは、と
自分自身でも思っていた時ではありますし。
もう神様のせいにでもして
行くことにしないと、
この出不精は言い訳をみつけて
結局行かずに2016も終わってしまいそう・・。
明水さんのお言葉を聞いて、
お互い、冗談の辻褄合わせでいい!
伊勢で美味しいもん食べましょう!と一致しました。
(もしかしたら、やっぱり、
明水さんは、未来の彼氏さんが
連れて来いと言われた方かも知れませんしね!)
今回は、そんな明水さんに加え、
名古屋の占いバーラボラスとカフェラボラスにて
占い師をなさっている清水ミリアさんの3人で、
伊勢詣でに出発です。
運の良い人と一緒にいると、
幸せが伝染するとよく聞きますが。
ミリアさんは各地のパワースポットや
スピリチュアル情報にとてもお詳しい上に、
素敵な年下彼氏ができたかと思いきや
昨年あっという間に結婚なさったという、
ただいま運気絶好調の幸せスピリチュアリスト。
これはもう、幸せが伝染しそうです

スタートは月夜見宮。

紅白の梅が咲いていました。
桜が一般的になる以前の日本では、
花というと梅の花を指していたそうです。

神路通りを通って外宮へ。
神路通りは古くより月夜見宮より夜な夜な
神が外宮へと通われる神の通路だと
言い伝えられていました。
月夜宮の入り口の正面にある石垣のひとつが、
夜になると馬となって待っており、
神はその馬に乗ってこの道をお通りになられるそうで、
人々は畏れ慎み夜間はこの道を通らぬように
昼でも真ん中を通らぬようにしていたのだそうです。

東邸
道沿いには趣あふれる邸宅がありました。
こちらの石碑には、
「古今伝授創始者を祖に持ち累代文墨の才人輩出」とあります。
こちらの東邸は、美濃国郡上城主の
古今伝授の創始者でもある
東常縁がその祖となる家だそうです。
東常縁は1405年頃の人で、
連歌師の宗祇に古今伝授を行いました。
古今伝受とは、
勅撰和歌集である古今和歌集の解釈を、
秘伝として師から弟子に伝えたもので、
狭義では東常縁から宗祇に伝えられ、
以降相伝されたものを指すのだとか。
岐阜県民の私は、
この宗祇という名前にピンと来ました。
そう名水百選にも選ばれている、
あの郡上八幡の「宗祇水」です。
また、私は行った事がありませんが、
「古今伝授の里」というミュージアムがあり、
そこには「東氏」の記念館があります。
この東氏は、後に、
様々な漢学者や医者を排出した
名家なのです。
また、私の母がいつもいうことには、
かつて郡上は京都とは密接につながっており、
今では想像ができないような
富と知恵と技術があった所であるそうです。
東氏はその郡上の領主であり、
その邸宅がここ神の通り道にある・・
ふと、「古き何か」がそこにあったことを
想像させられますね。
通称外宮と呼ばれる豊受大神宮と、
別宮である多賀宮・土宮・風宮は、
どこもびっくりするほどの人で
参拝するために行列ができていました。
特に人々がわんさかといたのが、
「三つ石」です。
四方にしめ縄が張られており、
石の上にはお賽銭と思われる小銭が
かなり沢山置かれていました。
大勢の人がそのしめ縄の内側へ体を精一杯折り曲げ、
腕を伸ばしているのです。
一見して異様な雰囲気でした。
以前訪れた時には
こんな光景を見た覚えがなく。
「何ですかあれは。」
「ここは今すごいパワーがあると
評判になっているんですよ。
それでみんなあやかろうと、
ああして手を伸ばしているんです(明水さん)」
「人によってはビリビリとした
パワーを感じるそうですよ。(ミリアさん)」
「・・・・なんだか、
あんな風に囲んで手をかざしていると、
まるで焚き火みたいですねぇ。」
正しくは「川原祓所」と言い、
式年遷宮の折の修祓の場で、
つまり神宮神官や奉仕員を祓い清める場所だとか。
それらは帰ってきてから調べて知りました。
ちなみに、人が少し少なくなった時に、
私も焚き火ごっこに参加してみました。
すると、確かに、
しめ縄を手が超えるとピリピリと
感電するようなはっきりとした皮膚感覚があります。
元々はここに宮川支流が流れていた印で、
ここはパワスポでもなんでもないと言う方もいるようですが、
何かしらのエネルギーの流れのようなものが
あるにはあるというのが私の感想です。
しかし、これからまだまだ内宮まで行かねばなりませんし、
とにかく人が多いので、一瞬で移動してしまいましたので、
それ以上の事は現在はわかりません。
(神威のようなものが
そこへ噴き出しているわけでは無いのはわかりました)
次回訪れた際には、
しっかり観てみたいと思います。
外宮の中には、
雷が落ち真っ黒に焦げた楠木があります。
昔の人は、そのような場所を
神が降り立った場所として崇めました。
木の前には小さめの鳥居と、
石作りのお狐さんが並んでいましたが、
いわゆるお稲荷さんとは、
まったく雰囲気が違いますし、
その「放っているもの」もまるで違います。
それは何かほっとするような、
伸びやかで人を寛がせ童心にしてくれるような、
そんな場所でした。
不思議なことに、どことなく、
金神社の持つ雰囲気に似ているのです。
※注:この記事を読んだ明水さんから、
この落雷にあった木は
外宮ではなく「月夜見さんですよー!」と
教えていただきました。
言われてみれば・・・(恥汗)
明水さん ありがとうございました!
何故かここだけは
人が殆どいなかったので、
私達はしばし佇んでいたのでした。
(続く)















クリック応援お願いします


 にほんブログ村
にほんブログ村