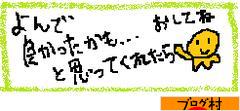ここ何年か日本は韓国文化のブームが続いていますね。
昨年はコスメが、今年はK-POPが大ブレイクしました。
そんな韓国は、非常に伝統を重んじる国。
グレゴリオ暦と呼ばれる普段私達が使っているカレンダーを使いつつ
日常は旧暦(月の暦なので別名太陰暦とも)によって生活をしています。
ちょっと乱暴な言い方をしてしまえば
太陽の暦(グレゴリオ暦)と月の暦(太陰暦)を
二つ同時にバランスをとって使っているのが韓国の文化なのです。
例えばよく知られているように
韓国ではお正月は新暦と旧暦の二回存在します。
実はこれはアジアの国ではあちこちで行われており、
逆に日本のようにすっぱりと改暦して
旧暦が生活に影響しなくなっている方が珍しいのかもしれません。
この旧暦は中国の影響を強く受けた暦であるため
やはり日本と同じように冬至(韓国語でトンジ)があります。
二十四節気の一つであり大雪と小寒の間の毎年12月22日頃になっています。
日本では冬至と言えば 柚子に南瓜が定番ですね。
では韓国ではなんだと思いますか?
実は 小豆粥(パッチュク)なんです。
この小豆粥、日本で想像するお粥とはちょっと違い
ぜんざいに近い感じの食べ物です。
ただし日本のぜんざいと違い塩で味付けを行うので
甘みは小豆それ自体の薄甘さのみになります。
作り方はさほど難しいものではなく
柔らかくなるまでコトコトと煮たアズキを裏漉ししたところへ
2時間程水につけておいた米を加えて30分程かき混ぜて出来上がり。
仕上げにお餅や白玉を乗せていただきます。
お餅といってもトックといい、餅米では作った餅ではないので
日本のお餅のように柔らかく延びるような事はありません。
さて では 何故冬至に小豆粥を食べるのでしょうか?
実はパッチュクを食べる理由は小豆の赤い色にあるのです。
冬至の日とは1年の中でもっとも夜が長く、昼の短い日。
すなわち1年でもっとも陰の気が強い日と考えられています。
古い時代、こうした陰の気が強い日には
病気を司る鬼神がこの世を横行するという考えがありました。
このような鬼神に行き会ったり憑かれた人は
病にかかると信じられていたのです。
そしてこの陰の気が強いもの
即ち鬼神を追い払うためにはどうするかと考えた時
逆に反対の陽の気が強いものを身につければ
鬼神は逃げていくのではないかということになったのです。
小豆のような赤い色は伝統的に陽の気を持つと考えられており
特に好んで冬至の日の魔除けの食事として
食べられるようになったというわけです。
つまりベースにあるのは陰陽五行の考えなのですね。
赤は五行でいえば火
火は全てを焼き払う強い上昇する力です。
小豆だけに留まらず
赤という色の持つ邪を祓う聖なるイメージは
再生する生命力と直結しています。
例えば日本でも鳥居や巫女さんの緋袴
また還暦のお祝いの赤いちゃんちゃんこなど
聖なるものやおめでたいものには欠かせない色となっていますし
食べ物の中で 煮てもその色を失わない小豆は
それこそ日本でも
小正月に小豆粥を食べて1年の健康を願うという
韓国の冬至と日にち違いのそっくりな風習にも使われています。
なにより日常でおめでたい時にお赤飯を炊くという習慣も
赤の力を利用した呪術的な食事なのです。
ところで そんな邪気を祓う小豆は
韓国ではただ食べるだけではなく
家の門に撒いて災難を祓うことも行われてきました。
ただしこちらは建物が汚れるので近年は少なくなったようですが、
日本でもちょっぴり似ている行事として
京都の東林院で「小豆粥散飯式」というものが行われています。
これは1年の邪気を祓うもので
僧侶の読経のなか
小豆粥を少量とりわけ境内の木々にお供えするという行事です。
しかし 小豆の赤の色で良ければ
そのまま御供えすれば良い気もしますね。
何故 小豆粥にするのでしょうか?
この小豆のお粥については韓国では
1849年に洪錫謨が朝鮮の歳時記を書いた『東国歳時記』という本の中で
小豆粥を季節料理として食べる他に、お供え物としたり、
家の門扉にまいて災難を払っているということが既に書かれています。
1849年とは李氏朝鮮の時代であり
最後の国王高宗の一代前の哲宗が即位した年。
日本では江戸時代に当たります。
さらに歴史を遡ぼってみると
中国の六朝時代 梁の宗懍が著した年中行事記で
民間のものとしては現存最古『荊楚歳時記』という本に行き当たります。
この本は揚子江中流域を中心とした荊楚地方の年中歳時記について書いたものですが
「共工氏の息子が冬至の日に亡くなり疫鬼となった。
彼が赤豆を恐がったため、冬至の日にはアズキ粥を作って疫を払うようになった」
と書かれています。
これが小豆粥が鬼神を祓う為に使われた最古の記録であり
この風習が韓国へ伝わり、
そして今も冬至には魔除けを願い小豆粥を食べる習俗になっているのです。
6世紀と言えば日本では聖徳太子のいた時代です。
そんな遠い昔から邪なものを祓うとされてきた小豆粥
さらにそれは日本へ伝わり
小豆は特別な力を持つ食べ物として
おめでたい時に登場するようになったというわけなのでした。
こうやって歴史を知ると
小豆のパワー 見直したくなりますね。
 の方はコチラをお願いします
の方はコチラをお願いします
 にほんブログ村
にほんブログ村