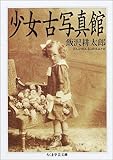この本に、少女について、こんな記述があります。
- ¥1,365
- Amazon.co.jp
少女は漂っている
少女たちは、ひとところに留まることなく、蝶のようにひらひらと漂っている。
手を伸ばしてとらえようとすると、砂粒が指の間を滑り落ちるように、あっという間に逃れ去ってしまう。
それは、はかなくも脆い、幻のような存在である。
だが逆に、すぐに消えうせてしまうものだからこそ、それらが一瞬虚空に描き出す残像が、目蓋の裏に強烈に刻み付けられることになる。
少女は不機嫌である
少女たちは、周囲の人たちや状況に対して、常に違和の感情を持ち続けている。
彼女たちは、いつでも機嫌が悪い。
時々、相手に媚を売って、あるいは単なる気まぐれで、笑い顔を見せることもあるのだが、それは表面にほんの少しさざ波を立てるだけで、すぐにあのメランコリックで不機嫌な表情に戻ってしまう。
もっとも、仏頂面の美少女ほど、魅力的で心そそられる生きものも、ほかにあまりないだろう。
少女は手に負えない
少女たちを手なずけようとする努力は、いつでも水泡に帰する。
彼女らを一つの色に染め上げようとしても、それは無理というもの。
このわがままで身勝手な生きものたちは、お仕着せの衣装を自分たちのやり方で仕立て直そうとする。
だからこそ、逆に制服の少女たちには不思議な魅力があるのだろう。
そこには、支配しようとする力と、その支配から全力で逃れようとする力がせめぎあっている。
多くの場合、最終的には後者の力が勝り、手ひどいしっぺ返しを食うことになる。
少女は小さい
一見ちっぽけなよるべなき存在に見えて、その小ささは逆に武器になる。
大きなものの鈍重で緩慢な動きを嘲笑うように、少女たちは素早く走り回り、めまぐるしい速度で相手を幻惑する。
それは小さいけれども、ダイヤモンドのような硬度を保っていて、そう簡単に押し潰されたりはしない。
むしろ油断すると、その鋭く尖った結晶は、皮膚を傷つけ、食い破ってしまうような危険を秘めている。
少女は脱皮する
気がつくと、少女たちは別のものに変わっている。
子供から少女へ、そして少女から成熟した大人の女性へ。
脱皮は本人にも意識されないことが多く、たとえば身体は脱皮を完了しているにもかかわらず、心はまだ以前の状態に留まっており、見る者を戸惑わせる場合がある。
脱皮を拒否して、永遠に「ひらひら漂い続ける」ことを選ぼうとする者もいる。
だが、その不可能な行為の遂行は、時に自分の心身を傷つけることになりかねない。
少女は似ている
少女たちは、顔つきも体つきもそれぞれ違う。
だが、見続けていると、それらの差異が次第にひとつに溶けあって、「絶対少女」、あるいは「純粋少女」とでもいうべき集合イメージが形をとってくるように思える。
欲望も憧憬も、聖なるものも俗なるものも、エロスもタナトスも、貞淑も破廉恥も、すべてひっくるめて抱え込んだ不在の少女。
少女に対してこのような類のことを感じる人というのは決して珍しくないと思いますが、同じように日々少女について考えている私から見たとき、この記述には違和感を覚えます。
それはおそらく、主観と客観の違いなのだと思います。
この作者は、あくまで少女を他者としてしっかりと線引きしたうえで眺め、分析しています。
少女が何を考えようと知ったこっちゃない、額に入れて鑑賞しよう、という視点です。
そして、まるでコレクションを慈しむかのように、愛情や、フェティシズムとを感じさせます。
私のもつ少女観は、またそれとは違う。
私は、自分の内部に飼っている少女性というものを感じていて、それは確かにこの記述のように、外から見れば「蝶のようにひらひら漂っている」だの、「不機嫌」そうに見えるだの思うかもしれないけれど、そのような他人に及ぼす影響のことははっきりいってどうでもよく、つまり自分のことで精一杯なのです。
「少女」という現象は、抑圧の結果生まれた一種の病のようなものです。
だから私は、「~のように見える」で話を完結してしまうことができません。
私はむしろ、「どうして~のようになってしまうのか」となり、そこからやっと話が始まるのです。
だから、この記述は、あくまで「成人男性のもの」だと、感じるのです。
でもじつは、世の中にはこの成人男性の意識に同調する女の人はいっぱいいます。
なぜならこの成人男性の意識は見た目はあくまで女性・・・というか少女を賛美しているように見えるからです。
自分がそこにいけば、確実にある程度は美味しい蜜にありつけるとなれば、そこに群がってしまうのも頷けます。
このような形で共犯関係が成り立っていくわけです。
それらが悪いことだとは思いませんが、そのような、成人男性の意識、価値観に寄生する形でものを考えて来た結果、女性は本来自分が何なのであるのか、自分自身の好みや嗜好って何なのか、忘れてしまっているように思います。
例えば、この作者は、男性はオブジェ大好きだけど、オブジェを愛する女性はいないか、いても変人だというようなことを述べていますが、果たしてそうなのでしょうか。
そしてその理由を、ペニスがないことと結びつけていますが、本当にそうなのでしょうか。
このような考え方は、フロイトをはじめ、多くの男性が語っていますが、歴史的には、まだ女性が自分でものを考え始めるようになってから、ほんとにちょっとしか時間がたっていないのです。
何千年も自分でものを考える機会に恵まれてきた男性といきなり比較し、現在そうでないからといって、社会的な理由を排除し、生物的な理由だけに結論をもっていくのは、ちょっと早急ではないでしょうか。
「男はわがまま」だとか、「男は眼だけでできている」とか、男は~女は~という考え方は、現在確かにその傾向はあるのでしょうけど、その言い方に慣れてしまうのはちょっと危険だと思うのです。
私は、男性のオブジェ嗜好とは、ある程度自分の好みというものを自覚できた状態で、それに思考を重ねていってできた、「文化」なのではないかと思います。
そしてその男性視点からの文化には、誤魔化し無しで寄り添うのには女性にとって本来無理があり(自分に対して「他者」を要求するのにも限度はあります)、では女性は一体何を指向しているのか、でもそれを知りたくても、それを見つけ出せるほどの蓄積がまだ今の段階では女性にそなわっていない、というのが現状なのではないか、と思うのです。
だから、もしこの先女性ならではの文化が育っていった場合、女性にもそのような、オブジェ嗜好のようなものが出てくることもあるのではないのでしょうか。
オブジェ嗜好とは、思考するということのない、天然、無意識の状態では出てこないものだと思うのです。
学者とかではないので詳しいことはよくわかりませんが、この類の記述を見ると、ときどきそんなことを思います。
あくまで感想レベルなのですが。