さいたま市岩槻(岩付)の戦国領主・太田資正の家臣たちに関する備忘録:
その9.広沢尾張守忠信・信秀
~武州松山城を守った親子二代~
・『太田家譜』の「太田譜代之士」の章にも「広沢尾張守」の名前が見え、広沢尾張守家が、岩付太田氏の譜代の家臣であったことが伺われる。
・広沢尾張守忠信は、天文十六年の松山城合戦(資正が兄の死を聞き岩付城に向かった隙を北条氏康が攻めた合戦)において、資正から松山城を託されるも、上田朝直の裏切りにより討たれる。
(『太田家譜』より。ただし、『太田家譜』はこの出来事を永禄二年こととして記している。中世史家・黒田基樹は上田朝直との関係等から天文十六年の松山城合戦での出来事が年代が誤って伝わったものと推測(黒田基樹(2013)「岩付太田氏の系譜と動向」、『論集 戦国大名と国衆12 岩付太田氏』)。本稿も黒田説を採用する)
・上田朝直は、松山城の城主であった難波田善銀の婿養子の座を狙っていたが、広沢尾張守忠信が婿にするなら資正を薦めたことで頓挫。以降、忠信を恨んだと言われる。(『太田家譜』より)
『太田家譜』によれば、
「永禄二年氏康謀ヲメグラシ三楽松山城ニ籠置所ノ上田闇礫斎逆心サセ、氏康ニ心ヲ通シ氏康之人数ヲ引入テ松山落城ス、其時家臣広沢尾張守忠信入道道正モ討死ス、上田逆心ノ事闇礫斎ハ難波田弾正入道善吟カ甥也、善吟婿養子トセン事ヲ広沢尾張守ニ密談ス、忠信云養子ヲセントスルナラバ太田源五郎可然ト云、此事ヲ闇礫斎聞テ広沢エモ源五郎ニモ遺恨多ク」
【関連:松山城の縄張り】
・広沢尾張守忠信の嫡子が、尾張守信秀。
(『太田家譜』より)
・永禄四年の長尾景虎(上杉謙信)の第1回越山の際には、資正とともに厩橋に参陣。長尾景虎のもとに参じた関東の武将の目録である『関東幕注文』に「広沢尾張守」として記録される。
・『関八州古戦録』では、永禄五年の松山城合戦において、広沢兵庫介信秀(尾張守の誤りか)が資正の命を受けて松山城の二の丸を守ったとする。(太田下野守、三田五郎左衛門は本丸を守った)
・その後、資正の岩付追放後は嫡男・氏資に仕えたらしく、『太田家譜』は永禄十年の三船山合戦で主君・氏資と共に戦い討死したと記す。
(『太田家譜』の「所詮敵二向テ討死セント供セシ広沢尾張守信秀 忠信嫡子・恒岡越前守・河目等ヲ先トシテ五十三騎三舟二至リ大ニ勇ヲ振テ戦ヒ(中略)五十三騎ノ勇士皆枕ヲナラベテ討死ス 」から)
【関連:三船山の位置】
<広沢尾張守忠信・信秀のイメージ>
主君のために戦い、そして討死した親子。岩付太田氏の譜代家臣の中でも、とりわけ忠義を尽くした親子と言えるかもしれない。
父・忠信は、資正の留守を預かり松山城の本丸に入ったことからも、重臣であり、また指揮官としても信頼されていたことが伺われる。
父の死の十数年後、息子・忠信もまた資正のために松山城を守ったのは、運命の皮肉か。あるいは、信秀自身が父の弔いのために志願したのか。
天文年間に、資正と広沢尾張守忠信が同じ松山城で時を過ごしたならば、それぞれの息子である氏資と信秀は、幼い頃から共に遊んで育った関係だったかもしれない。
信秀が、資正・氏資親子の決裂の後に氏資に使えるのを選んだのは、氏資との深い結び付きがあったからだと空想することもできるだろうか。
『太田家譜』は、三船山合戦での氏資と家臣らの討死を伝える記述で、広沢尾張守信秀を筆頭に記し、敢えて「忠信嫡男子」と付している。
親子二代が揃って主君のために戦い散ったことを称え、弔う意図があるように思えてならない。
→太田資正の家臣たちインデックスに戻る
その9.広沢尾張守忠信・信秀
~武州松山城を守った親子二代~
・『太田家譜』の「太田譜代之士」の章にも「広沢尾張守」の名前が見え、広沢尾張守家が、岩付太田氏の譜代の家臣であったことが伺われる。
・広沢尾張守忠信は、天文十六年の松山城合戦(資正が兄の死を聞き岩付城に向かった隙を北条氏康が攻めた合戦)において、資正から松山城を託されるも、上田朝直の裏切りにより討たれる。
(『太田家譜』より。ただし、『太田家譜』はこの出来事を永禄二年こととして記している。中世史家・黒田基樹は上田朝直との関係等から天文十六年の松山城合戦での出来事が年代が誤って伝わったものと推測(黒田基樹(2013)「岩付太田氏の系譜と動向」、『論集 戦国大名と国衆12 岩付太田氏』)。本稿も黒田説を採用する)
・上田朝直は、松山城の城主であった難波田善銀の婿養子の座を狙っていたが、広沢尾張守忠信が婿にするなら資正を薦めたことで頓挫。以降、忠信を恨んだと言われる。(『太田家譜』より)
『太田家譜』によれば、
「永禄二年氏康謀ヲメグラシ三楽松山城ニ籠置所ノ上田闇礫斎逆心サセ、氏康ニ心ヲ通シ氏康之人数ヲ引入テ松山落城ス、其時家臣広沢尾張守忠信入道道正モ討死ス、上田逆心ノ事闇礫斎ハ難波田弾正入道善吟カ甥也、善吟婿養子トセン事ヲ広沢尾張守ニ密談ス、忠信云養子ヲセントスルナラバ太田源五郎可然ト云、此事ヲ闇礫斎聞テ広沢エモ源五郎ニモ遺恨多ク」
【関連:松山城の縄張り】
・広沢尾張守忠信の嫡子が、尾張守信秀。
(『太田家譜』より)
・永禄四年の長尾景虎(上杉謙信)の第1回越山の際には、資正とともに厩橋に参陣。長尾景虎のもとに参じた関東の武将の目録である『関東幕注文』に「広沢尾張守」として記録される。
・『関八州古戦録』では、永禄五年の松山城合戦において、広沢兵庫介信秀(尾張守の誤りか)が資正の命を受けて松山城の二の丸を守ったとする。(太田下野守、三田五郎左衛門は本丸を守った)
・その後、資正の岩付追放後は嫡男・氏資に仕えたらしく、『太田家譜』は永禄十年の三船山合戦で主君・氏資と共に戦い討死したと記す。
(『太田家譜』の「所詮敵二向テ討死セント供セシ広沢尾張守信秀 忠信嫡子・恒岡越前守・河目等ヲ先トシテ五十三騎三舟二至リ大ニ勇ヲ振テ戦ヒ(中略)五十三騎ノ勇士皆枕ヲナラベテ討死ス 」から)
【関連:三船山の位置】
<広沢尾張守忠信・信秀のイメージ>
主君のために戦い、そして討死した親子。岩付太田氏の譜代家臣の中でも、とりわけ忠義を尽くした親子と言えるかもしれない。
父・忠信は、資正の留守を預かり松山城の本丸に入ったことからも、重臣であり、また指揮官としても信頼されていたことが伺われる。
父の死の十数年後、息子・忠信もまた資正のために松山城を守ったのは、運命の皮肉か。あるいは、信秀自身が父の弔いのために志願したのか。
天文年間に、資正と広沢尾張守忠信が同じ松山城で時を過ごしたならば、それぞれの息子である氏資と信秀は、幼い頃から共に遊んで育った関係だったかもしれない。
信秀が、資正・氏資親子の決裂の後に氏資に使えるのを選んだのは、氏資との深い結び付きがあったからだと空想することもできるだろうか。
『太田家譜』は、三船山合戦での氏資と家臣らの討死を伝える記述で、広沢尾張守信秀を筆頭に記し、敢えて「忠信嫡男子」と付している。
親子二代が揃って主君のために戦い散ったことを称え、弔う意図があるように思えてならない。
→太田資正の家臣たちインデックスに戻る
- 関八州古戦録 上 (原本現代訳 28)/ニュートンプレス

- ¥1,080
- Amazon.co.jp
- 関八州古戦録 (下) (原本現代訳 (29))/ニュートンプレス

- ¥1,080
- Amazon.co.jp
- 論集戦国大名と国衆 12 岩付太田氏/岩田書院
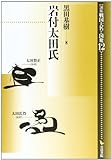
- ¥4,320
- Amazon.co.jp

