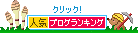みなさんは、「和風総本家」 というクイズバラエティー番組を覚えているでしょうか?。
テレビ大阪の制作でテレビ東京系列で全国放送されていたのですが、令和2年3月19日をもって終了してしまいました。
番組に登場する豆柴の「豆助」は可愛かったですよね~。
幼犬はすぐに大きくなるから半年ごとに交代していたそうです。
最後の23代豆助は白柴でした。
それで、12年前のこの番組のコーナーで、「街角100人に聞いた!家にあった菓子缶アンケート」というのがありました。
番組が調べた6つの菓子缶の中で、家にあったものを選んでもらうというものですが、みなさんの家にもお土産にいただいたクッキーやおかきのカンカン(缶)が必ずあると思います。
で、お菓子缶ってなんか捨てられなくて、何かに使おうと取って置いて、バザーのドル箱や、かき餅の保存用にしたり、道具入れにしたり用途は様々です。
それでは、当時の番組の中で紹介された第6位から1位までを発表しますが、画像を見て、「ウチにもある」とか「実家にあった」と、ついつい懐かしく思い出すんじゃないでしょうか?。
第6位…ますは、昭和2年創業の泉屋です。ここって、日本で最初にクッキーを売った店なのです。手紙入れに使う人が多いそうです。
第5位…大正12年創業の新潟県長岡市の浪花製菓の元祖・柿の種です。丸い蓋なので薬入れとして使う頻度が多いのだそうです。
第4位…八代将軍・徳川吉宗が活躍した時代である延享4年(1747)、江戸・京橋に大阪屋として開業したのを起源とする超老舗、凮月堂の洋風せんべいゴーフルです。お菓子入れとして使う方が多いそうです。
なお、凮月堂は「風」ではなく「凮」と表記するのが正しいのです。
第3位…明治30年創業の豊島屋の鳩サブレーです鎌倉・鶴岡八幡宮参詣の土産として有名です。多くは領収書入れとして使うそうですが納得です。
なんで「鳩」なのかと申しますと、鶴岡八幡宮に掲げられている扁額(へんがく)に、八幡宮の八の字が「向ひ鳩」となっていることに由来します。
昔から別名「鳩宮」と呼ばれていて、白鳩は八幡さまの使いとされています。
第2位…昭和6年創業のモロゾフです。裁縫箱として主に使われるそうです。
そういえば、ウチの母も使ってました。
最後に輝く第1位…昭和17年創業のヨックモックです。ペン・鉛筆入れとしての使われ方が最も多いのだそうです。
ちなみに、缶はブリキ(鉄)なのでサイクル率が非常に高く、回収されたものは100%再び鉄に生まれ変わる地球にやさしい素材なのです。
おまけ…金沢銘菓の生姜煎餅・柴舟といえば、大正6年創業の柴舟 小出さんです。
毎年、6月15日の当社「はじかみ大祭(生姜まつり)」にご奉納賜わっており、お菓子を食べた後は大祭での受付用やドル箱として広く活用させていただいております。
m(。-_-。)m ↓おねがいします!