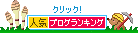昨日は、私が代表をつとめる高齢者を対象とした“地域サロン”開催日(毎月)でしたので、午後より町内会館で実施いたしました。
今回は、地域デジタルアーカイブとして、20年前の画像をパソコンをプロジェクターを使って映し出しました。
21年前の平成14年に斎行された当社1300年大祭や、記念事業としておこなわれた演芸大会の様子、当時の神輿渡御や元獅子舞など、昔懐かしい映像です。
また、金沢市は平成17年度より3年間、「森本ふるさと文化財調査研究会」を立ち上げ、それぞれ3ゼミに分かれて地域の歴史文化を研究することになり、不肖・私は第3ゼミのディレクターを委嘱されました。
そして、公募の市民研究員(※ほとんど地元の方)の皆さんと共に、「加賀獅子舞」「伝統芸能」「古民家・アヅマダチ家屋」など調査しました。
その時撮影したものはCD-Rに記憶保存しました。
今回、その時の映像を映し出したのですが、10年ひと昔と申しますが、17年~20年前の画像でも、みなさん懐かしく感じたようです。
中には、故人となられた方も大勢いて、ここにいる方々も何人か写っていて、20年前の自分の若い画像にほくそ笑んでいました。
今回、企画は大成功でした。
その中で、特に興味深い画像をいくつか紹介します。
【素人歌舞伎(村芝居)】
明治から戦前にかけて、金沢近郊の農村では、青年団が主体となって、素人歌舞伎の興行が盛んにおこなわれていました。
当地、金沢市北部の森本地区でも、
■金沢市今町の「京座(みやこざ)」
■金沢市北森本町の「旭座(あさひざ)」
■金沢市南森本町の「寿座(ことぶきざ)」
の三座があり、当番村が年交代で、北森本と南森本は盂蘭盆の8月15日・16日に、今町は秋祭りに開催し、地元をはじめ近郷近在から見物客で終日盛況を極め、大いに賑わったそうです。
舞台衣装も、はじめは嫁の着物などを借りて演じていたそうですが、衣装や舞台装置もだんだん本格的になり、後に金沢市高岡町の「梅岡座」付きの役者から、衣装や道具などを借用し、演技の指導まで受けました。
芝居小屋は、神社の境内などに建てられ、村中が総出で建材やスノコなどを持ち寄り、花道付きの見事な舞台をつくり上げました。
そんな、古くなつかしい、田舎の村芝居があったんだということを、知っていただければ幸いです。
■今町の「京座(みやこざ)」
資料の残る今町・八幡神社
神社の奉納額には「大正6年9月・秋季祭余興」とある。
こちらの奉納額にも「大正14年9月・秋季祭礼余興記念」とある。
画像をアップすると女方の美形が!。
なかなかのイケメンですが、現在の当主の祖祖父にあたります。
今町「京座」を上演した芝居小屋跡。今は庭と畑となっている。
■北森本町の「旭座」
北森本町・川崎神社には、かつて境内に芝居小屋が建てられ
た。
社務所に掲げられている「旭座演芸大会」の記念写真。
昭和21年8月15日に終戦後一時的に復活した。
北森本男女青年会による演芸大会で、結局これが最終公演となる。
中央の女性は私の同級生Mのお母さんで、当時21歳でとても美人ですが、今も90歳過ぎで健在。
この年、旭座では、
「昔綉(ぬいとり)恋鞘当新吉原仲の町場」
「雌千鳥曽我討入」
「近江源氏先陣館」
「男作五人雁金」(おとこだていつかりがね)
「ひらがな盛衰記」
などが演じられた。
芝居興行を知らせる大正時代の「口演チラシ」で、近郷近在に配った。
■南森本の「寿座」
南森本町・住吉神社。この境内にも芝居小屋が建てられた。
社務所に掲げてある奉納写真額。
昭和10年頃の南森本「寿座」上演写真。
ご存じ、写真左は「白浪五人男」で、「問われて名乗るもおこがましいが…」の日本駄右門。
その他、寿座では、
「かまくら三代記」
「義経千本桜」
などが演じられていた。
「白浪五人男」の弁天小僧菊之助の行灯絵。
弁天小僧といえば、「青砥稿花紅彩画(あおとぞうしはなのにしきえ)・浜松屋の場」での「知らざあ、言って聞かせやしょう」の向上のシーンが有名ですよね。
この伝統ある村芝居も、昭和11年頃まで続きましたが、日中戦争の勃発と、続く、大東亜戦争により芝居は上演の機会を失いました。
戦後、一時期復活の兆しはありましたが、戦後社会の変革により、ふたたび上演することがなくなったのは、さびしい限りです。
【虫送り太鼓】
昔から各農村では、盛夏の土用に、稲虫退散を目的に「虫送り行事」を行なってきましたが、今では、わずかな村落でしか見ることは出来ません。
「虫送り」は太鼓を繰り出し、子供らは松明(たいまつ)をかざしながら、「五穀豊穣・稲虫送り」と唱えて、農道を練り歩いたものです。
そして、広場には、竹や枯れた杉の枝葉、稲藁(いなわら)をうず高く積み上げ点火し、害虫を誘い込んで焼き尽くすのです。私の住む金沢市北部・森本地区の農村では、昭和30年頃までは至るところでおこなわれていた夏の風物詩でした。
しかし、18年前の時点で毎年実施していたのは、河北潟の潟ぶちで「大場潟乃太鼓」として名を馳せている金沢市大場町と、森本地区の中山間地で金沢テクノパークに近い下涌波町と、富山県の県境近くの竹又町の3町会だけでした。
以下の画像は、平成17年7月の第3土曜日に記録調査たものです。
中山間地・下涌波町の虫送り会場
虫送り太鼓のクライマックスは、火の粉散る炎に向かって、若い衆が大きな桶胴太鼓を、拍子をとる小バイのリズムの合わせて、大バイが間奏打ちし、その大音響で害虫を駆除することを目的とします。
下涌波町の虫送り
また、桶胴太鼓は、普段は、区長(町内会長)宅や、集会所の軒先に吊るしてあって、電話やサイレンもなかった時代、「触れ太鼓」といって、太鼓の打ち分けによって、火事等の災害、冠婚葬祭、寄り合いの合図などを、村内に知らせたのでした。

金沢市竹又町の虫送り

点火前に撮影、竹や枯れた杉葉など、夏の暑い時期これだけ準備するのも大変

桶胴太鼓はこの年張り替えたばかりで、金沢市では、獅子頭や獅子舞の蚊帳(かや)や太鼓などを新調する場合は、町内会に対して予算内での補助が出る

そして、壮年団も加わって大バイ・小バイのリズムに合せ、豊年太鼓の打ち初め…
だんだん、火が大きくなって…
しかし、現在竹又町内会では虫送り行事はおこなわれていません。
最後は、金沢市大場町の虫送りを紹介して終わります。
m(。-_-。)m ↓おねがいします!