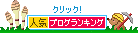9月初旬より、兼務神社の秋祭がはじまるので、耐水紙や和紙で注連縄(しめなわ)などに下げる紙垂を、全兼務社分裁(た)ちました。
当社は、宮司を兼務する神社が非常に多いので、紙垂づくりも膨大な量になります。
耐水紙は糊付け出来ないので、折ったあとはホッチキスで要所を留めます。
ですが、マックスの「コの字針」の量が少なくなったため、別メーカーのプラスのホッチキス針に変えたのすが、両社とも大手なので、遜色はありませんでした。
しかし、以前、百均で買ってきた、ホッチキス針を使ったところ、針が詰まったり、紙の厚さに負けたりして、画像のように失敗して無駄になった針が続出したことがあります。
ホッチキスで留めたあとは、ジュート麻ひもやビニールひもで先端を結んで完成です。
続いて、京都の装束店で購入した耐水御幣紙で、柱の太さ13寸(39㎝)柱の長さ13尺(約390㎝)以上の、大鳥居のある兼務社5社分の紙垂を裁ちました。
次に、和紙で、手水舎や社務所玄関用の紙垂を裁ちました。
和紙の紙垂を折ります。
そして、紅白の水引の白い部分だけ使って、紙垂の上部に目打ちで穴を開け、水引を通して結びます。
なお、紅白の水引は、玉串料を奉納された際の熨斗袋(のしぶくろ)の水引を保存して、再利用しています。
手水舎と社務所玄関用の紙垂も完成しました。
大量の紙垂は、分別する際に間違えないように、このような印字したメモ紙を用意しました。
各神社ごとに取り付ける場所や数を記したメモ紙〔※【例】○○神社 鳥居×2・拝殿向拝〕を添え、秋季季大祭のご案内状とともに各総代さん宅へお届けします。
これだと、一目瞭然で、注連縄に紙垂の取り付け作業される総代さん方も、分かりやすいと思います。
21日の月曜日に、市内と津幡町の兼務神社の全総代さん宅へ、秋季大祭ご案内状と共に、紙垂をお届けする予定です。
m(。-_-。)m ↓おねがいします!