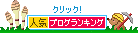昨日も、早朝6時より境内のおそうじを行なったのですが、連日猛暑の中、掃き掃除をしているので暑さに慣れてしまいました。
続いて、駐車場を掃いてから…。
裏参道車道を掃いたのですが、坂道なので、これが一番きついのです。
午前8時にお掃除を終えてから、隣り町会・今町の花卉(かき)栽培農家Iさんの納屋へ向かいました。
毎年、お盆の墓参りでお供えする切り花をお願いしています。
産直なので超割安のお値段にしていただきました。
私の住む金沢市北端は“花園地区”といって、その名のとおり花の産地です。
特に、今町と月影町は、3代藩主前田利常公の奨励により、藩政時代から続く花卉栽培の盛んなところで、お盆の今は、小菊やケイトウなど、出荷の最盛期を迎えています。
で、これが買い求めたお盆用の切り花の束です。
束をほどくと、紫と黄と白の小菊…。
黄色の輪菊(中輪)…。
それに、赤とピンクのケイトウ(鶏頭)からなっています。
なので、さっそく剪定バサミで長さを整え、束ね直して盆花を5束作ったのですが、これは仏式用です。
一方、神道用の盆花は、まず真榊を切って用意しました。
先ほどの仏式用の盆花と違うのは、神道の場合は画像のように真榊を加えて束ねることです。
神道では、榊だけ供えればよいとされていますが、やはりお花がないと寂しいですからね。
そして、墓参りの際は、金沢伝統の箱キリコを献灯します。
箱キリコにロウソクを灯して、ご先祖や親戚、関わりのあった方々を偲びます。
キリコは、まさに金沢の夏の風物詩ともいえますが、それは、「迎え火」「送り火」を意味しているのかも知れません。

当家は神道なので、箱キリコの表に「献燈」や「奉燈」と墨書し、裏には右上に「進上」、左下には家族の各氏名を書いて、中にロウソクを灯して墓前に献じます。
また、浄土真宗や日蓮宗の方は、このように「南無阿弥陀仏」や「南妙法蓮華経」と書かれた箱キリコを墓前に供えます。
私も毎年、お世話になった方々の墓参用に、真宗用のキリコも買い求めています。
ですが、お盆期間が終わった後の片付けや、焼却処分が大変だとの理由で、伝統の「箱キリコ」から「板キリコ」なるものに、10年程前から取って代わられています。
板キリコは「名刺代わり」なのだそうですが、さも、「俺がお参りに来てやったぞ~」という押しつけがましい気がして、私はあまり好きではありません。
それに、燈明を捧げてのキリコですからね…。
ということで、昨日の午前中、仏式用の盆花と箱キリコを持参して、お世話になった方々のお墓参りに行って参りました。
まずは、近所のお寺さんの墓地で、当社神役を長くつとめられて5年前に亡くなられたKさんのお墓に詣でました。
続いては、当家の分家のまた分家さんのお墓です。
このあと、かほく市白尾の寺院墓地に向かい、初盆を迎えた妹の嫁ぎ先のおばあさんのお墓に詣でました。
ふたたび金沢に戻って、今度は北森本町の共同墓地にやって来ました。
若くして急逝した、親友のイクヤの墓ですが、毎年欠かさず墓参しています。
最後は、森本地区の山里の千杉町(せんのすぎまち)に向かい、当社神役を長らくつとめられて、21年前に亡くなられたMさんのお墓です。
Mさんはお酒が好きだったので、毎年墓前には清酒一升をお供えしています。
そして、夕方、盆花とキリコと榊を持参して、当家の累代の墓所(奥都城=おくつき)に家族全員で墓参いたしました。
本当は、15日にお参りする予定でしたが、台風が心配なので、早めました。
当家の墓所は、神社の杜に併設しています。
全員長袖を着ているのは、蚊に刺されないためです。
参道石段途中を右に折れると、累代の墓地となります。
孫のakiがお墓にビールをかけました。
akiのひいおじいさん(私の父)がお酒好きだったからです。
このあと、神道墓なので、お墓ごとに柏手(かしわで)を打ってお参りしました。
m(。-_-。)m ↓おねがいします!