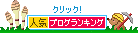大安の今日は、電力系通信会社の通信端局(たんきょく)施設の安全祈願祭(地鎮祭)を奉仕いたします。
なので、昨日は境内掃除のあと、その準備に取りかかったのですが、まずは、和紙と精麻を切って切麻(きりぬさ)を作りました。
お祓い具の一つである切麻は、和紙と麻を細かく切って混ぜたのものです。
地鎮祭や竣工祭等で米・塩と共に敷地四方に撒き、お祓いをするのですが、切麻散米(きりぬささんまい)といいます。
また、大麻(おおぬさ)も裁ちました。
長めのお榊に紙垂と麻を付したこの大麻で修祓(しゅばつ)をおこないます。
大麻(おおぬさ)は大幣(おおぬさ)とも呼び、神事では欠かせないものです。
「ぬさ」は麻の古名で、幣あるいは麻、奴佐と当て字される「ぬさ」の美称が「おおぬさ」です。
神事のお祓(はらい)の用具である大麻ですが、これは木の棒の祓串(はらえぐし)に紙垂と麻を付けたもので、月次祭(つきなみさい)などの小祭や普段のご祈祷で使用しています。
また、神籬(ひもろぎ)用の御幣も耐水紙で奉製しました。
これは、京都の装束店で購入した耐水御幣紙で裁ちました。
神籬(ひもろぎ)は神を招く依代(よりしろ)です。
このように、出張祭典で祭壇奥中央に立て、招神(しょうしん)・降神(こうしん)の儀を行ないます。
地鎮祭斎場内に張り巡らした注連縄(しめなわ)にさげる紙垂(しで)も和紙で裁ちました。
地鎮祭などでは、斎場の四方に立てた忌竹(いみたけ)に、注連縄を張り巡らし、紙垂をさげます。
なお、この和紙は、近くの結納品も扱う文具店で購入したもので、裁断ミスで発生する大量の切れ端を、3年ごとに4千円で購入しています。
障子紙より少し厚目のこの和紙は、幣(ぬさ)や玉串やシメ縄の紙垂(しで)用に切るのにちょうど良い大きさで、大変重宝しています。
シメ縄にさげる紙垂(しで)も完成しました。
最後は、建設会社との打合せの際、資料として渡された儀注(ぎちゅう)を元に、2時間かけて祝詞(のりと)を奉書した次第です。
m(。-_-。)m ↓おねがいします!