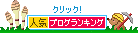連日、兼務神社の春季祭が続いて忙しく、境内のお掃除ができなかったのですが、昨日は、朝8時より掃き掃除を開始しました。
木々が芽吹く今の時期は、バトンタッチしたかのように古葉が落ちるのですが、雨が降った後に地面にこびりついたりして掃きにくいのです。
特に、苔の上の落葉はやりにくく、傷つけないようにそっと落葉だけ掃き出しました。
なので、境内は苔むして緑の絨毯(じゅうたん)のようです。
そして、境内掃除を2時間半ほどで終えて、今度は、先日4月11日の当社例祭で着装した、神主の正装である「正服」を畳むことにしました。
大祭奉仕後、すぐさま衣冠(いかん)を脱いで、社務所の鴨居にハンガーを掛けて干したのですが、ちょうど1週間経ったのでたたむことにしたのです。
上から順に「袍(ほう)」「単(ひとえ)」「奴袴(ぬばかま)」の順に畳みました。
神主の正装は、これ一式で「正服(せいふく)」と呼ぶのですが、冬の装束なので全て正絹です。
袍を畳紙(たとうし)に入れ、さらに布で巻いてから包みました。
単も畳紙にしまい…。
奴袴も同様に仕舞いました。
続いては、「冠(かんむり)」を片付けました。
部分ごとに分けてから袋に入れ、桐箱に納めました。
そして、「冠」に付属する「纓(えい)」ですが、垂れさがっているので「垂纓(すいえい)」といいます。
これを「纓挟板(えいばさみいた)」に納めるのですが、これに挟むと垂纓の形が崩れなくなります。
最後は、持ち具の片付けです。
まずは、「笏(しゃく)」を笏袋に納めました。
「桧扇(ひおうぎ)」という桧(ひのき)でつくられた扇も箱に納めました。
「帖紙(たとう)」も箱に納めました。
ちなみに、衣冠には懐紙を形式化した帖紙(たとう)を必要とします。
帖紙は右のような白檀紙が基本ですが、平安貴族の故事に倣(なら)うと、壮年になると金箔を散りばめた左のような帖紙の使用も可能です。
また、笏と桧扇は帖紙に差し込み、袍に懐中します。
すべてを片付けてから、大きな風呂敷に包みました。
自宅へ移動し、冬の正服一式は装束箪笥に納めました。
冠や垂纓は、桐箱や纓挟板ごと装束箪笥上部の引き戸内に納めました。
これら持ち具も、笏袋や箱に納めて装束箪笥下段の引き出しに仕舞いました。
装束箪笥に全てを収納して、すっきりいたしました。