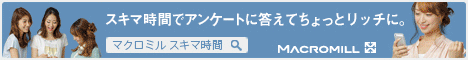空気が澄んでいるのを感じます。いよいよ本格的な秋ですね。実りの秋は食欲の秋!
・・・食べ物も美味しく頂ける時期です♪
こんにちは、本日の季語は「葡萄」・・・秋の季語です。他には「デラウェア」「マスカット」
「ピオーネ」「巨峰」など種類の名も季語ですし、「葡萄園」「葡萄棚」「葡萄狩」なども。
この果実については説明不要ですよね。
葡萄を始めとして、実りの秋は他の果実も季語になっています。「林檎」「桃」「柿」「梨」
「無花果」「石榴」「金柑」また、「胡桃」や「栗」などの木の実も・・・
但し、「蜜柑」は冬の季語なので、秋はまだ青い「青蜜柑」(←酸っぱいけど美味しい!)
※2013.9.21 青蜜柑 ( ^ー゜)σ 青蜜柑掌(て)に乗るほどの希望あり
よく質問があるのは「葡萄酒」は季語ですか?という事なのですが・・・
うーん、葡萄酒やワインだけでは季語とは言えないみたいね。年中通して製品を呑めるので・・
但し、「葡萄酒醸す」(ぶどうしゅ かもす)という季語があり、これは秋の半ば過ぎて収穫した
葡萄に酵母を加えて醗酵させる・・・ワイン作りですね。これは季語です。「葡萄酒造る」も。


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
葡萄栽培の歴史は古く、紀元前3000年頃には既にカスピ海沿岸などで栽培されていたようです。
メソポタミア文明、や古代エジプトに於いてもワインは珍重されていましたし、古代ギリシアで
は、ワイン作りの為に葡萄栽培が大々的になされていました。


【紀元前3000年頃の古代ブルガリアの葡萄畑の図とワイン作りの壷 画像引用www.haskovo.com/】
そして、古代ローマ帝国の時代にはもうワインが帝国中に普及して行ったようです。
その後は、中国へもそして大航海時代には世界中にと葡萄栽培が広まりました。
葡萄やワインがヨーロッパに於いて特別な果実である事はあなたもよく御存知だと思うし
様々な絵画にも登場していますし、豊穣と実りの象徴ともなった果実・・・

【若きバッカス/カラバッジョ/ 画像引用:wikipedia 】
日本に伝来したのは、中国経由で鎌倉時代と言われていますが、栽培されたのは甲斐国勝沼
(山梨県)の一部の地域だけで、本格的に広まるのは明治維新以降になります。
今では様々に改良された美味しい葡萄を味わえる時代、果実としてだけではなくビネガーや
グレープシードオイルとしてもお料理に活用できますもの。


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
本日の句は、特に深い意味も無いありのままの句です。
まあ、うちがビンボーだというのはお分かり頂けたと思いますが (爆
それでは、今日はこれで・・・またね。