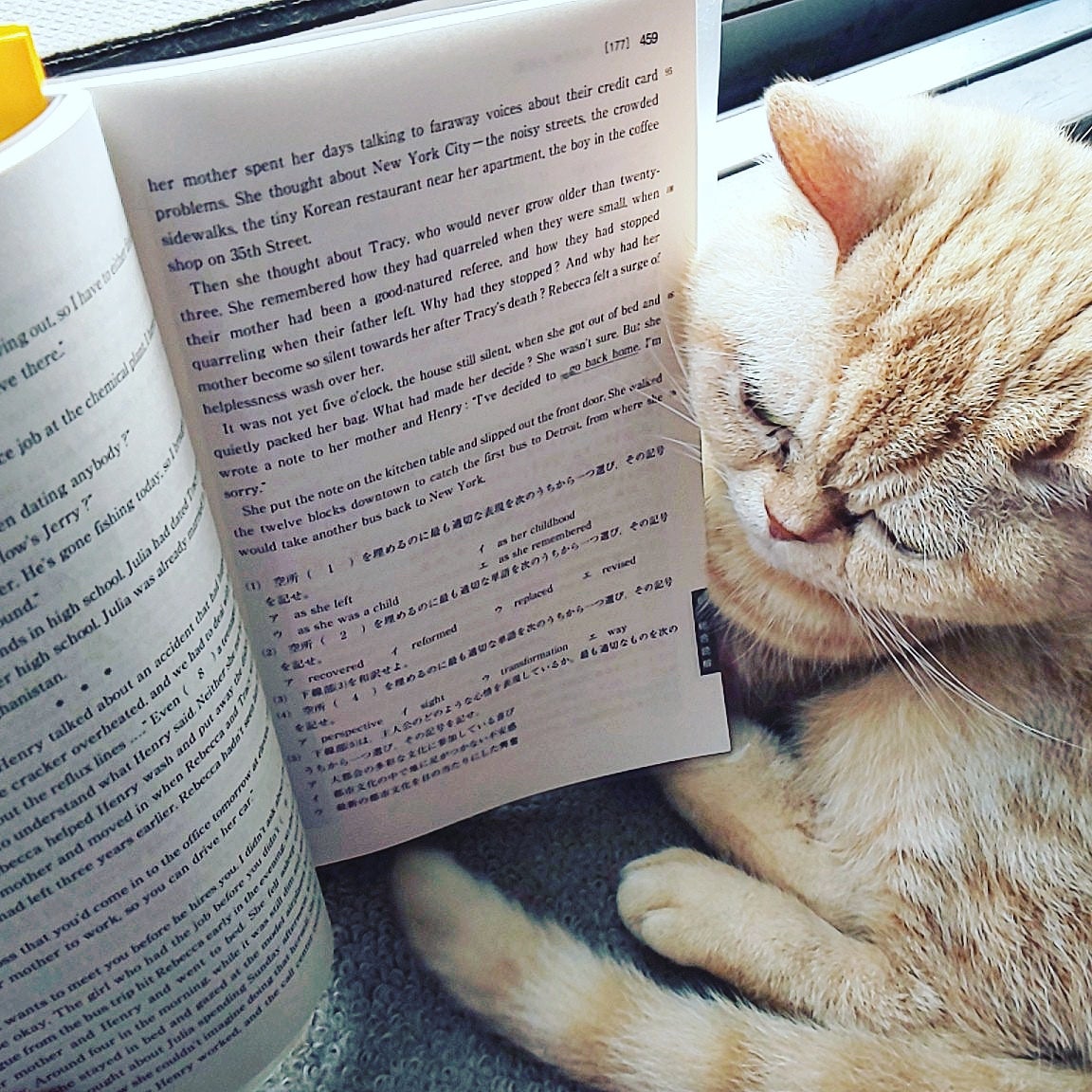
入学試験を受けてきたら疲れていても復習は必ずしよう(付入試問題の解答ヒント)
私大の一般入試が始まりました。
既に何校か受けている人もいるでしょう。
今週、来週にかけて連続して受ける人もいるかもしれません。私の周囲も佳境に入ってきました。
入学試験は模試とは違い、かなり疲れるものだと思います。エネルギー消費も段違いです。
二月だというのに、試験会場に暖房を入れてくれない大学もあるとの報告も受けています。
寒さによるストレスもあるに違いありません。
一日受けて帰宅すると、もう喋るのもいやなくらい疲労を感じているかもしれません。
暖かいものでも摂取して、疲労を回復して下さい。
ひと眠りするのも良いでしょう。次の日も受験予定なら、早く寝た方が良いかもしれません。
ただ、受験してきた内容について、気がかりなことがあれば調べてしまうことです。
知らなかった歴史知識、単語に漢字、
わからなかった問題、考え違いした解答など、
次に備えるためにも、そのままにしておかず調査研究すべきです。
毎年書いていますが、私の受験した際、国語で全く同じ文章が二つの大学で出ました。芥川龍之介の『侏儒の言葉』から抜粋された全く同じ内容が、上智と明治で出題されたのです。
日程的に後に行われた明治大学商学部の国語の問題を解いているとき、もしここを落ちたら「俺は受験生をやめるぜ」と感じるくらい出来ました。
最初から国語の現代文が満点と決まっている試験で落ちたら、受験生の資格は無いでしょう。復習の賜物です。
これは極端な例かもしれませんが、過ちや誤りは正しておいた方が良いのです。それは上に書いた単語や漢字などの場合よりも、自分の解答の悪いクセが判明することがあるからです。
私の周囲でこれまでに見られた、誤解答に導く悪いクセをご紹介して、皆さんのご参考と致しましょう。
あくまで、私が考える悪いクセと対応策です。
もし参考になったら、してみて下さい。
主に英語、国語問題に関しての場合です。
①時間がないか、或いは面倒なので、選択肢の文章だけを見て解答を決めてしまう。
必ず本文に根拠を求めて解答するようにするべきです。
特に、「最後の二つまで絞られたのに間違えた」といったときの主要な理由は、この選択肢内だけで判断することです。
最後の二つまで絞ることができたというのは、解答する能力が秀でているということでは全くありません。
4~6選択肢内くらいまでの選択問題では、読んですぐわかる下らない選択肢が一つか二つ、本文を読んでいれば簡単にわかる選択肢が二つくらいあることが普通です。
つまり、最後の二つまで絞れることはごく当たり前なのです。
そこから最後の一つを正答できるかどうかが入試問題の困難さです。これに対抗するためには本文の内容をしっかり理解して解答しないといけません。
②会話問題などの空欄補充選択肢を、選択肢内だけで判断してしまう。
上記①と似たようなことなのですが、文中の空欄に適切な単語や文章を選択するのに、選択肢だけを見て判断してしまうのです。
なぜ、文中に空欄があるのかということを考えると、当然ながら文章の続きや内容ということを考慮しなければなりません。
会話問題の場合、疑問に対する解答なのか、おどろきなのか、賛意なのか、そして次の会話にどのように展開波及して行くのか、ということを考えないと適切な解答はできません。
これは文中に幾つかの文章を並べ替えて挿入する場合も一緒です。
選択肢内だけで、the とか代名詞とか、内容のつながりとか、文章の順序を判断する要素を見較べていても、挿入箇所の上下の文章も考慮しないと正しい解答には至らない場合があります。
面倒がらずに、利用できる情報は全て利用するべきです。
③問題文はきちんと読んで理解する。
そんなの当り前じゃないか、と思うでしょう。
でも、問題文が英文だったとき、きちんと解釈していますか。
特に、やたら長い慶應の問題文は、あ~、これダロ、読むまでもないや、などとしていませんか。
毎年同じ形式の問題になるとは限りません。
また、適当に読んで、題意と違う解答をしてしまうこともあります。
問題文は英文でないときも、正しく解釈して読みましょう。
④記述解答の字数制限があるのに、いきなり解答していませんか。
字数制限がある場合、そこに盛り込むべき要素は決まっています。
ポイントを拾ってから書き出さないと、中途半端な答えになってしまいます。
書く内容を決めて、どのくらいの字数になるのか推定して、題意を満たしているかを判断してから書き出すべきです。
でないと、一度解答欄に書いてしまうと、受験生心理として書き直したくない気持ちが出てしまい、誤った解答だと感じてもそのままにしてしまい易いのです。
⑤わからない単語に拘らない。
英文にわからない単語が出てくるのは当然だ、くらいの感覚で読んで下さい。
知らない単語があっても、それを無視して読み込みができないと、試験の解答ができないことがあります。
知らない単語を怖がって、コワゴワ、オソルオソル読んでしまうと、わかる内容もわからなくなってしまいます。わからない単語が出てしまうと、ワア~出タァ~となってしまい、そこから先に困難を感じてしまうからです。
英文の隅々までわからなくても、問題には答えられるようになっています。或いは、答えられる問題は多いはずです。
⑥自分の知らない高度な文法などは出ない、仮に出たとしても他の人もわからない。
誤文探しや長文の読み込みのときに、ちょっとでもわからない箇所が出てくると、ダメダ、これは自分の知識では解けないとすぐに感じ易いものです。
そんなことはメッタにありません。
特に誤文探しは、中学程度の文法から疑うべきです。
主語に対する動詞の変化、時制、自動詞か他動詞か、形容詞に形容詞が修飾していないか、主語と動詞が続く文章を導くことができない前置詞に文章が乗っていないか、定冠詞は正しいのか、目的格で良いのか、
など、簡単なことから疑ってみましょう。
そして、どうしてもわからなければ、きっと他の人もわからないくらいの軽い気持ちで探すことです。
⑦捨てる問題を見極める。
幾ら考えてもわからない問題に拘っていてはいけません。
だめなら、ダメと判断するべきです。
でも、そうは言っても、そんなのわからない、と言うかもしれません。
それはそうでしょう、考えてみないとわからないものもあるでしょうから。
そんなときは、あらかじめ考えても良い時間を決めておくのです。
五分までなら、いろいろと考えても良いとか全体の中でどのくらい考慮に割けるかを試験前に決めておくと良い場合があります。
以上、独断的なことも含んでいます。
自分に合うものがあったら参考にしてみて下さい。
せっかく本番の試験を受けてきたのですから、その体験と情報を次に活かすことです。
その先に合格があるはずです。
※入試英語の長文読解問題の解き方について下記で詳しく説明しています。