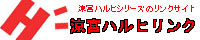終わらない夏が終わっても、
アイツの中では
まだ、終わってなかった。
エンドレスエイトα
何かおかしい。
そう気付き始めたのは、お盆を過ぎた夏の盛りの日のことだった。
そして、朝比奈さんから電話を受け駅前に集合し、長門が八月十七日から三十一日を一万五千四百九十七回繰り返し、今回が一万五千四百九十八回目だと聞かされたのは何日前の事だったか・・・もう忘れちまった。
「なんとか終わったな」
つい数時間前まで騒がしかった自分の部屋は、BGM代わりと言わんばかりに外から虫の声が耳障りなほどに響いている。
昨日までは何一つ手を付けていなかった夏休みの宿題はSOS団団員のおかげでなんとか全て終わった。
これで宿題をやったが家に忘れました、なんて小学生のようなヘマをしないようにと鞄に全てぶち込み、目覚まし時計のアラームをセットする。
現在の時刻は二十一時、つまり夜の九時。
残り三時間で今日が終わり、明日が来る・・・もしくは二週間前に戻る。
どちらにせよ、今日は終わる。
もし、今日の自分の判断が正しければこの一万五千回以上の夏休みを終え、今年初めての九月一日を迎える事が出来るはず。
それなのに、何故だろう?
この違和感は・・・。
既視感とは何か違う、何か別の違和感。
何かを忘れている。
何か大切な事を、忘れている。
忘れてはいけない、何か。
それが何か分からない。
「あー、くそっ!」
声に出してこのモヤモヤ感を吹っ飛ばそうとしても、この感じは消えなかった。
このまま考えていてもしょうがない。
頭を切り替えてリビングで夏休み最後のグダグダを味わおうと、部屋を出る直前。
ピルルと携帯電話が鳴った。
ディスプレイを見ると珍しい人物の名前が表示された。
通話ボタンを押し「もしもし」と出る。
「・・・・・・」
返事が返ってこない。
相変わらずだな。
「長門?」
「・・・・・・」
電話の向こうで微かな音が聞こえた。
もしかしたらコクンと長門が頷いたのかもしれない。
だが、長門。
電話ではその姿が見えないんだ。
出来れば声を発してくれ。
「・・・あなたは古泉一樹に対して忘れている事がある」
「は?」
声が聞こえたと思ったら、意味の分からない事を言われた。
「何を忘れてるんだ?」
「それは分からない」
分からないって、それはまた長門らしくない答えだった。
「八月三十一日、私は毎回古泉一樹から一万五千四百九十六回同じ質問を受けている」
一万五千四百九十六回というと、つまりこの終わらない二週間が繰り返される度に古泉は長門に対して同じ事を聞いている、という事になる。
多少なりとも違う二週間を繰り返してきたというのに。
「長門、古泉はお前に何を聞いた?」
「今日が終わったら明日は来るのか、と」
それは、つまり今の俺たちにとってごく普通の質問だと思う。
いや、待てよ。
一万五千四百九十六回というと、一回目の三十一日はまだ繰り返す前だからおそらく二回目の三十一日から前回の三十一日まで必ず古泉はこの終わらない夏休みに気付いていた事になる。
しかし、長門の話では俺たちが異変に気付いていたのは最近になってからと言っていなかったか?
「あなた達三人が駅に集合しこの先どうするのか話し合ったのは8769回。ただ、古泉一樹は必ず8月31日、二十三時四十五分までにこの異常空間に気付き、八月三十一日、二十三時四十五分に同じ質問をしている」
「それは俺に関係あるのか?」
「・・・そう」
まぁ関係あるから長門はわざわざ俺に電話を掛けてきているのだろうが。
そうなると分からない。
思い当たる節がない。
「古泉はお前から俺に思い出せって言ってきたのか?」
「違う。彼は、明日が来るかどうかを聞いてきただけ」
「だったら、俺は関係なくないか?」
今の会話に俺の名前は出てきてない。
ますます分からなくなった。
「そもそも、この電話は毎回俺に掛けてくれたのか?」
「今回が初めて」
だろうな。
今は9時を過ぎたところだ。
古泉の電話は今の長門には掛かってきていないはず。
「なんで今回は俺に掛けたんだ?」
「明日が、来るから」
それは分かりやすい返答だった。
分かりやすい返答だが、答えはさっぱりポンである。
「もうひとつ彼は聞いていた。天体観測をしなかった日は何回あるのか、と」
「天体観測?」
ああ、長門の家でやったときのことか。
「天体観測はプール同様過去一万五千四百九十八回必ず行っている。その内、涼宮ハルヒが八月十七日に提案したシークエンスは八千五百二十七回、突発的に提案したシークエンスが四千六百五十二回、古泉一樹が提案したシークエンスが二千三百十八回、そしてあなたが提案したシークエンスが一回」
この俺が天体観測なるものを提案したというのか?
自分の言うのもあれだが、天体観測なんて一生口に出さない可能性が高い単語の一つだ。
「俺が言ったその一回っていうのはいつだ?」
「一回目に該当する八月二十一日の夕方、あなたが涼宮ハルヒに提案した」
一回目か・・・。
なんだって俺はそんな提案したんだろうか?
他の時は古泉も提案したんだよな?
いや、アイツは天体望遠鏡なんてスネ夫的アイテムを持っていたのだから提案してもおかしくはない。
「分かった、教えてくれてありがとな。後は自分で考えるさ」
これ以上、長門を付き合わせるのも気が引ける。
一万五千回以上夏休みを付き合わせてきたのだから今更と言えば今更かもしれないが。
「悪かったな」
「・・・・・・」
返事は返ってこない。
そのまま通話を切ろうとするとボソリと声が聞こえた。
「長門?」
「あなたが提案した時のみ、天体観測は学校で行われた」
それだけ言うとプツリと切れた。
学校か・・・。
まぁ、場所はどこでも良かったのかもしれない。
場所よりも、問題はこの違和感だ。
なあ古泉、俺は何を忘れているんだ?
お前は聞いてもいない事をベラベラと話すくせに、肝心なことは伏線を張って語らないっていうのが癖のようだ。
さてどうしたものか。
一番手っ取り早い方法は古泉に電話をして直接聞くことだが、果たしてそんなもので解決するのか?
まあいい、なんでも当たって砕けてみろってヤツだ。
カ行の最後の方を検索し、通話ボタンを押した。
数秒の沈黙の後、圏外か電源が入っていないとのガイダンスが流れてきた。
当たる前に砕けたようだ。
携帯電話をベッドに放り投げ、そのまま自分の身体もベッドに埋める。
「忘れてることか・・・」
キーワードはおそらく俺が唯一誘ったと思われる一番始めの八月二十一日になる。
時計をチラッとみると長い針は数字の五を指している。
まだ時間はある、と思いたい。
「だめだ」
何も思いつかない。
外から聴こえるBGMが煩い。
意識がこの湿度の高い空気に混ざっていく。
俺が目を開けた時、無意識に時計を見た。
ぼんやりとして上手く焦点が合わない。
徐々にピントが合っていくと思わず起き上がった。
時刻は十一時十五分。
もちろん夜の、である。
昼寝並みに睡眠をしてしまった。
のび太君をもう馬鹿に出来ないな、こりゃ。
どうする、俺。
このまま諦めるか?
諦めていいのか?
そんな問答が頭の中で螺旋状に絡まっている中、俺の身体はというとこっそり家を出て自転車に跨がっていた。
ひたすらペダルを漕ぐが、あてがある訳ではない。
とりあえず自分が思い当たる場所を一つずつ行くしか無い。
自分の家から近い所からローラー作戦のように当たってみる。
駅前や喫茶店、商店街を通り一度でも遊んだ覚えのある所をとにかく行ってみた。
これで海や山なんてチャリで行けるような場所じゃなかったら俺は泣くね。
「はぁ・・・」
汗だくになりながら町内を一周してみたが、何か思い出すこともなく、時間は過ぎていった。
虫が群がっている自動販売機でドリンクを買い、喉を潤す。
時刻はまもなく十一時四十五分となる。
今まで通りだと古泉は長門に同じ質問をするのだろう。
ただ、今までと違うとしたら明日が来るということだ。
長門が言うのだからこの終わらない夏休みが終わるのだ。
そして朝になって久しぶりに学校へ向かって一皮むけたクラスメイトの顔を見て、休み明けで自習に近い授業を受ける事となる。
・・・なんだ?
今、何かに引っかかった。
どこかに違和感を感じた。
何だ?
何だった?
「そうだ・・・学校・・・・・・」
まだ行ってない場所。
そして長い夏休みで一度だけ行った場所。
俺は残っているドリンクを一気に飲み干し、ゴミ箱に投げ捨てる。
缶がゴミ箱に入ったか確認しないままペダルを踏みしめた。
ここから学校までおそらく十五分は掛かるだろう。
ちくちょう、なんだってこんな遠い場所で気付くんだ!
校門前の坂道を心臓が破裂するくらいのスピードで上り、校門前に止めた。
何が悲しくて登校時間の八時間も前に学校に来なくちゃならんだ。
これでココがハズレだったらもう、どうしようもないぞ。
校門を乗り越え真っ暗な学校へ入っていく。
幽霊なんて出るなよ?
今はそんなイベントに付き合っている暇はないんだ。
空気を読んでくれ。
下駄箱から自分の靴を取り出し急いで履き替える。
まずは一年の教室を見て、文芸部のある部室棟に行くか。
学校の時計を見ると十二時を回ったところだった。
十二時を回ってもここに俺が居るってことは、無事明日は来たようだ。
疲れた膝はガクガクと震えている。
これはもう、筋肉痛決定だ。
階段を段飛ばしで上り、各教室を見て回る。
特に何もない。
ついでに幽霊も居ない。
ようやく文芸部室に辿り着き、ドアを開ける。
そこにはバラバラになっている天体望遠鏡があった。
それはもう、無惨な状態で。
叩き落としたように。
怒りをぶつけたように。
古泉の心を表したかのように。
「・・・・・・っ!」
俺は屋上へ向かった。
すごく、すごく、すごく胸が痛んだ。
それなのにその理由が分からない。
なんだ、なんでだ?
涙が込み上げてくる。
バンっと勢いよく屋上の重い扉を開けると、そこには古泉が仰向けになって寝そべり、空を見ていた。
「こ、いず・・・みっ!」
上手く声が出なかった。
そして俺は、間に合わなかったのかと力を入れて握っていたドアノブから手を離した。
俺に気付いた古泉が、笑っていたから。
あまりにもいつも通りに笑っていたから。
いつも通り、誰でも包み込むような笑顔で。
いつも通り、誰にも踏み込ませないような笑顔で。
「古泉」
俺はゆっくりと古泉に近づいていく。
古泉は視線を俺に向ける事無く空を眺めている。
「今日は星が綺麗ですよ」
古泉の声が俺の全身に突き刺さる。
ああ、俺はコイツに拒絶されているのだ。
初めて会ったあの時のように、古泉の言葉が氷のナイフのように俺を刺していく。
「その様子だと、覚えてないようですね」
「すまな、い」
「でも、良いんです。それがあなたの答えであるように、これが僕の答えなのだと理解出来ましたから。大丈夫、僕は怒ってませんよ」
「古泉・・・!」
俺は古泉の隣で膝をついた。
雨が降ってきたのか地面にはポツポツと水の後が増えていく。
「どうして泣いているんですか」
困ったように古泉は笑っている。
知らねぇよ、俺だって。
泣きたいのはお前のはずなのに。
傷ついているのはお前のはずなのに。
「僕なら大丈夫ですから」
大丈夫ならこっち見ろよ。
笑っているなよ。
「それよりも、星を見ませんか?」
とても綺麗ですよ、と古泉は星に向かって手を伸ばした。
顔を上げると、そこには星が無数に広がっていた。
「あの日、天体観測を皆さんでした時に、あなたは僕に教えてくれたんです」
静かな声で古泉は言葉を繋ぐ。
まるで、喋っていないと何かが崩れるかのように。
「『あれがデネブ、アルタイル、ベガ』」
それは三年前、俺がハルヒから教わった星の名前だ。
「『俺は一度しか言わないからな』」
古泉は手を下ろした。
「『答えは夏休み最後の夜に聞かしてくれ』」
「こい・・・」
「あなたは本当に一度しか言わないんですね。有言実行もあまり良いものではないようです」
古泉はゆっくりと身体を起こす。
「僕の答えは今日・・・いえ、もう昨日ですね。あなたに伝えました」
「答え・・・」
「もう、今日は八月ではありません。だから僕はあなたが何を言ったのかも、僕が何を答えたのかも、教えません」
それでも、と言いながら立ち上がった。
「あなたが思い出さなくても僕の答えはこの先、ずっと変わりません」
「古泉っ!」
「もし、いつか思い出したら同じ台詞を言って下さいね」
少しだけ空を見上げたら、屋上の扉に向かって歩き出した。
生温い風が古泉の髪を揺らしている。
その後ろ姿が今にも消えそうで、俺は思わず駆け出して、古泉を後ろから抱きしめた。
「古泉、古泉、古泉、古泉、古泉っ!」
「・・・離して下さい」
未だに思い出せない、自分に腹が立つ。
コイツを悲しませた、自分に腹が立つ。
「僕は部室に行って片付けなくては行けませんので、あなたは先に帰っていて下さい」
あの、バラバラになった天体望遠鏡を片付けるのか?
「俺も手伝う」
「いえ、大丈夫です」
古泉の身体が腕の中で震えた。
「僕一人で出来ますから」
「でも・・・」
「僕一人じゃないと、泣けないですから」
「・・・・・・っ」
「だから、一人にさせて下さい」
俺は古泉から身体を離す。
「また放課後、部室でお会いしましょう」
そう言って古泉は階段を下りていった。
一度も俺と目を合わす事無く。
一度も俺の名を呼ぶ事無く。
「畜生!」
俺は、最低だ。
結局、部室に寄らずに俺は学校を出た。
いや、寄れなかった。
寄れるはずないだろう。
今、アイツは何を思いながら泣いているんだ?
校門辺りで部室がある方を見たが、明かりは点いてない。
空を見上げると、無数の星が雲一つない空で輝いている。
彦星さんよ、年に一度しか会えない日に会いに行かなかった俺はどうすればいいんですかね?
織姫ちゃんは怒りそうだな。
泣きながら怒りをぶつけて、どんなに謝っても許してくれなさそうだ。
でも、アイツは怒らないんですよ。
ちゃんと謝れなかったのに許してくれて。
そして、俺が思い出すまで待つと言って、笑ってくれた。
俺は、どうすればいいですかね?
一番悲しんでるアイツが笑ってるんですよ。
俺は、止まらない涙が乾くまで自転車で走り続けた。
夏がもう、終わる。

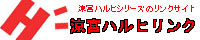
 古泉愛してるぜ×一樹Rank
古泉愛してるぜ×一樹Rank