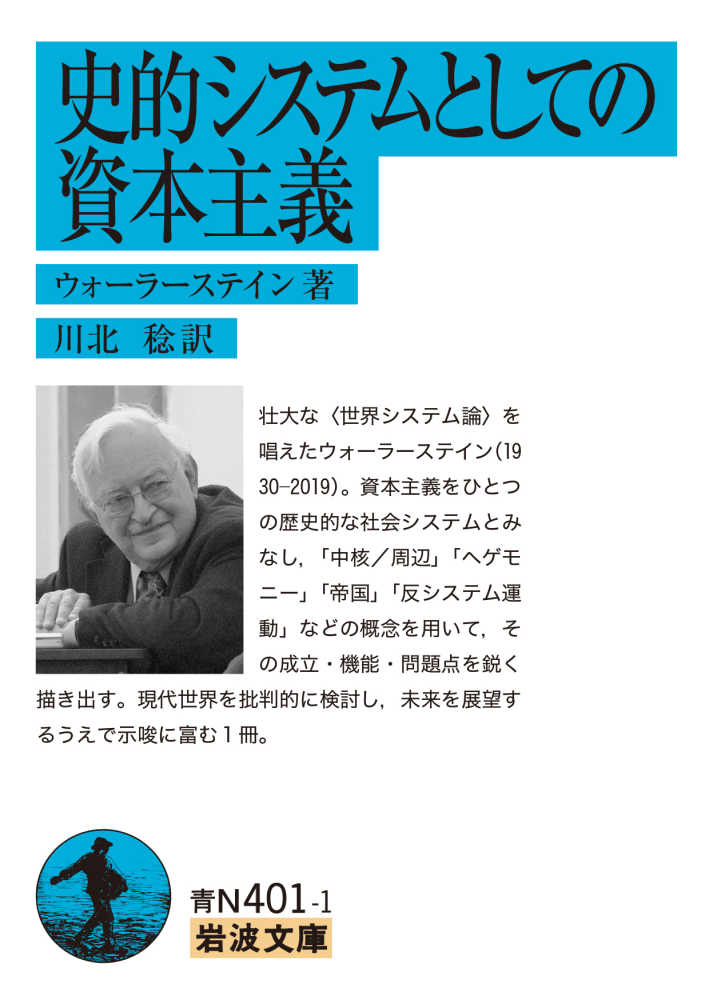〔上〕スーダン・アザンデ族の若者と英国の人類学者エヴァンズ・プリチャード
1927-30年。©journals.openedition.org. 〔下〕ブラジルでフィールド・
ワーク中のクロード・レヴィ=ストロース。1930年代。©dusunbil.com.
2人の人類学者の態度の違いに注意。
【1】 ハワイ大学の講義原稿
前回まで、ウォーラーステイン『入門・世界システム分析』をレヴューしてきましたが、同書は、入門書ないしテキストブックという体裁上、バランスを重視して極端な論述を控える傾向がありました。そのため、ところどころでは筆鋒が鈍くなる‥もう一歩踏み出して言えないのだろうかと、歯がゆく感じる部分もありました。
『史的システムとしての資本主義』は、『入門‥』〔原著英語版〕の 21年前(1983年)の著書ですが、1995年に増補改訂されています。
初版は、1982年春にハワイ大学政治学部で行なった講義がもとになっています。講義後に、聴講生からの批評・批判を受けて、講義用の素稿を大きく書き直したとのことです。それだけに、欧米だけでなく “太平洋の西岸” で起きている事象をも意識しており、現代の私たちに直接かかわる貴重な洞察を含んでいます。
ここでは、『史的システム‥』の第❹章「結論」を取りあげたいと思います。第❹章は、出版(1983年)にあたって、新たに書き下ろされた部分で、ウォーラーステインは、追加の動機を、つぎのように語っています:
『素稿を改変した第1の点は、第❹章を加えたことである。というのは、講義をしているうちに、解釈上の一つの問題が頭にこびりついて離れなくなってしまったからである。すなわち、歴史にとって進歩は必然だという信念が、〔…〕潜在力となって人びとのあいだに広がっていること〔…〕である。この信念こそは、われわれをして、眼前に開けている歴史の選択肢〔…〕をも誤らせるものである〔…〕。それゆえ私はこの問題を、直接取り上げることにしたのである。』
ウォーラーステイン,川北稔・訳『史的システムとしての資本主義』,2022,岩波文庫,pp.9-10. .
なお、1995年改訂版には、「資本主義の文明」という2章の論文が追加されていますので、第❹章のあとで、そちらからも一部を取り上げます。
引用文中の訳語について一言お断りしておきます。訳者・川北稔氏は、原文の “historical capitalism” を「史的システムとしての資本主義」と訳していますが、これは全面的に「史的資本主義」に置き換えます。「史的資本主義」と言うと、あたかも過去の事象のように思われがちですが、ウォーラーステインがこの語で意味しているのは、5世紀ほど前に成立し、かつ、まさに現在の世界を支配している活動中のシステムにほかなりません。それが「史的」と言われるのは、「永久的」ではないからです。15世紀以前の世界には、それは無かったし、これから将来においても、いつかは他のシステムにとって代わられる「史的」存在だからです。historical capitalism のこのような意味に誤解がなければ、「史的資本主義」という直訳を使用しても、問題はないので、引用では、簡明な直訳に置き換えることとしました。
さらにレヴューの途上、私の傍論として、戦後日本の農業について、「世界システム分析」の枠組みを利用して、私なりの見方をスケッチしてみたいと思います。つまり、「戦後日本の農業は、資本主義的[プランテーション]の1類型にすぎなかった。たとえば、戦後の日本政府が、[食料自給率の維持]という・主権国家にとって必須の課題を放棄してきた――放棄せざるをえなかった――のも、資本主義的[世界システム]における日本農業の位置に起因するものであった」ということです。
クラスノヤルスク・ダム。シベリアの大河「エニセイ川」に 1956年から16年間
をかけて建設され、長さ388km, 最大幅15km, 最大深105mのクラスノ
ヤルスク貯水池と、出力6000メガワットの発電所を擁する。©Wikimedia.
「共産主義とは、ソビエト権力・プラス・全土の電化である。」レーニン。
【2】 『史的資本主義』「結論」――
「進歩」という圧倒的なイデオロギー
『進歩の観念こそは、封建制から資本主義への移行過程全体を正当化するものであった。それは、〔…〕〔訳者註――封建〕遺制を打倒する行為を正当化し、弊害を遥かに凌駕する利益があるという理由で、資本主義批判を一掃する役割をも果たした。〔…〕自由主義者が進歩を信じたのはけだし当然であった。
むしろ驚くべきことは、かれらのイデオロギー上の敵対者であったマルクス主義者たちが〔…〕進歩を信じたことである。』なぜ信じたかというと、『進歩への確信〔…〕によって、世界の社会主義運動こそは、歴史の必然的な発展の方向〔…〕だとして、〔…〕正当化されたからである。〔…〕
しかし、進歩に対』する・このような『熱狂的な確信〔…〕は、〔訳者註――マルクス主義者にとって〕2つの点で、いささか問題であった。ひとつには、進歩の観念は、たしかに社会主義を正当化してくれたのだが、〔…〕同時に資本主義をも正当化した。つまり、まずブルジョワジーをもちあげてからでなければ、プロレタリアートに讃歌を捧げることができなかったのである。この点については、マルクスのインドについての記述〔アジア社会停滞論,アジア蔑視――ギトン註〕を見れば、十分な証拠』になる。
第2に、『進歩史観における進歩の尺度は物質主義的なものであったから〔…〕、進歩の観念は裏返しにされて、〔…〕社会主義に反対す〔…〕る根拠とされる〔…〕。生活水準がアメリカに及ばないという理由でソ連を批判することは〔…〕常套化して』いた。
こうして、『マルクス主義者が進歩という進化論的モデルを取りこんだことは、大きな落とし穴になった』
ウォーラーステイン,川北稔・訳『史的システムとしての資本主義』,2022,岩波文庫,pp.155-157. .
【3】 『史的資本主義』「結論」――
科学技術は「進歩」してきたか?
『史的資本主義が、〔…〕諸々の史的システムと比べて進歩を意味しているなどと言うのは、まったく正しくない。〔…〕
進歩を分析するに際して問題になること〔…〕は、そこで用いられる尺度が、どれもこれも一方的なものだということである。』
ウォーラーステイン,川北稔・訳『史的システムとしての資本主義』,pp.157-158. .
以下、ウォーラーステインは9つの理由を挙げて、「進歩の観念」すなわち、世界システムは無限の「進歩」に向かっているという・私たちの抜きがたい観念を批判します。
レヴィ=ストロースのフィールド・ノート。©bnf.fr. 『野生の思考』(1962)で
レヴィ=ストロースは、西欧近代文明が忘却してしまった「野生の」知識
・思考は、文明の科学的思考にも比肩しうるものであることを明らかにした。
その第1は、「科学・技術の進歩」という誰しも認めざるをえない文明の “成果” は、はたして本当なのか? そこに何も問題はないのか? ということです。「進歩の観念」を頑なに否定しようとするオカルト宗教家も、科学技術が進歩してきたことを無視するのは容易ではありません。なぜなら、その布教じたい、こんにちの進歩した技術手段で行なわざるをえないからです。
そうは言っても、まず指摘できるのは、① 科学・技術がおおくの知識を蓄えて発展してきた過程で、逆に「失われた知識もある」ということです。発達、発展といったことは、カスケード状に連なった数多くの「分岐」を経てゆく過程にほかなりません。「分岐」を経るとは、一方の選択肢を採り、他方を棄てることです。進歩・発展が大きければ大きいほど、その途上で棄てられた「もう一方」の数も膨大です。しかもその大部分は、もはや復元できない。われわれは、何を「棄てて」きたのかさえ、容易には知りえないのです。
レヴィ=ストロースは、『野生の思考』において、「未開人」の呪術的思考(具体の論理)は、類推や記号的象徴をふくむ・洗練された知的操作を有しており、たんなる迷信的妄想ではない。そして「文明人」もまた、日常の思考や芸術的活動では、「未開人」と同様の「野生の思考」に依拠している、ということを証明してみせた。しかし、それらの思考は、文明世界の “高度な” 科学では事実上忘れられてしまっており、そこから新たな発見や技術の開発が試みられることは無いといってよい。
同様にして、農業や、生態学にかかわる分野では、「1世代も2世代も前に棄てられたやり方が」、そのほうが「より効率性が高い」という理由で、復活される、ということが「近年しばしば起こっている。」化学肥料をやめて堆肥で代替する、といったことを指しているのでしょう。土地環境の再生費用まで含めて評価すれば、たしかに堆肥のほうが「効率性が高い」と言える。これらは、資本蓄積という資本主義の要請と矛盾しないから復活が可能になっているわけですが、そうでないものまで含めれば、「失われた有用な技術」はどれだけあるか分かりません。「もっとも先端的な最前線の科学においても、1世紀どころか 5世紀も前に〔…〕否定された諸前提が〔…〕再び採り上げられ〔…〕もしている」。たとえば、ウェーゲナーの「大陸移動説」が、「プレート・テクトニクス」理論として再生しているのを挙げることができます。(pp.158-159.)
つまり、①でウォーラーステインが述べているのは、「人間は進歩していない」とか「進歩はありえない」といったことではなく、「一方的な進歩」だけを進歩と見る考えは間違っている、ということなのです。「進歩」とは、選択肢の一方を棄てることだ、という「進歩の観念」が支配的になると、実際にも「一方的な進歩」だけが追求されるようになります。その結果、文明は袋小路に突き当たってしまう。‥‥だとすると、「一方的な進歩」ではないやり方とは、何なのか?
私は、それは、「多様性」の追求、または「多様的な進歩」の追求だと思います。「多様性」を高めることは、「進歩」すること以上に価値のあることだ。あるいは、「多様的な進歩」は「一方的な進歩」よりも価値が高い、と考えることです。場合によっては「分岐」の両方を選択する。あるいは一方を選択する場合でも、採用しなかった選択肢や、古い選択肢を、棄てて顧みないのではなく、将来の再評価に備えて、できるだけ保存しよう、ということです。袋小路に行き当たった現在の資本主義システムを乗り越えるには、このような価値観の転換が必要だと言えないでしょうか。
元興寺・極楽坊 本堂・禅室 奈良市中院町11番地。
奈良の寺院へ行くと、ひとつの建物の屋根に、瓦の形と組み方が異なる部分が隣り合わせになっているものがあります。これは、奈良時代に瓦の形態に革新があったためです。外国の人がこれを見たら、より良いものに革新したのなら、その時点でどうして屋根全体を葺き替えないのか? と疑問に思うかもしれません。観光客目当てでもあるまいに、どうして博物館みたいなことをしているのか? と。
実際上の理由は、全部葺き替える費用を節約するためだったかもしれません。しかし、その後においても、現在まで、古い部分を修理するときは、古い形の瓦を造って、古いやり方で葺いてきたのは、そうしようとするだけの理念(伝統を尊重するというような)がなければできないことでしょう。だいいち、古い技術を保存している職人がいなければできません。つまり、「伝統の保存」を可能にするような分業と社会構造(システム分析で言えば、「ミニシステム」の痕跡)が続いてきたからこそ、できたことと思われるのです。
「進歩もするが、古いものも棄てないでそのまま続ける」というやり方は、外国にはあまり例がないかもしれない。日本が世界に誇れることなのかもしれません。
くりかえしますが、ウォーラーステインの主張は、「進歩はありえない」とか「進歩するな」ということではありません。「一方的な進歩」には落とし穴があるぞ、ということなのです。
【4】 『史的資本主義』「結論」――資本主義は
われわれを豊かにしたか? 幸せにしたか?
② 技術の発達は、人類を労働の苦痛から解放しつつあるのか? むしろ逆に、われわれの労働量をますます増やしてはいないだろうか? ‥‥これが、第2の疑問です。
「史的資本主義は、技術の発達を通じて、人間の手の届く範囲を広げてきた、と言われる。」いわば、技術は、人間の力を増大してきた、と言われます。「投入される人間のエネルギーに対する・生産物の産出量は、着実に増えてきた」。たしかに、アルキメデスの「テコで地球を動かす」宣言を引くまでもなく、道具や機械の技術によって、人間にできる仕事の量と規模が飛躍的に拡大したのはまちがえありません。
しかし、そのことによって、「資本主義的世界=経済」の中にいる個人なり集団なりが、一定時間に、あるいは一生涯のあいだに「投入せざるをえないエネルギーの総量を増やしたのか、減らしたのか。」われわれのエネルギー投入の負担が、資本主義の発展によって軽減されたと「断言できるだろうか〔…〕疑問を抱くべき理由は十分にある。」というのは、われわれの超自我の中には「自らを労働へ向かわせる強迫観念が組み込まれてしまっている、という事実が」あるからだ。そのために、技術がわれわれの仕事の効率を高めれば高めるほど、われわれは軽減された労働に満足するのではなく、むしろ労働(エネルギー投入)を加重する誘惑にかられているのではないか?
「無限の進歩」の道を邁進する資本主義ねずみ。
そこで、第3の疑問が起きます。③ われわれは祖先と比べて、より自由で恵まれた生活を送っているのか? すくなくとも、物質的にはより豊かな暮らしをしている、と言えるか? ‥‥「資本主義以前の史的システムのもとでは」いまほど「物質的に恵まれた人生は送れず、これほど自由でヴァラエティに富んだ生活体験をもつこともできなかった〔…〕ように見える。しかしこの点でも、20世紀を通じて徐々に疑念が広がってきている」。中核・半周辺地域でも、「[生活の質]を問題にしたり、アノミー化・疎外、精神の疾患などについてますます関心を深めたりしている」。周辺地域では、「資本主義的世界システム」に組み込まれる以前よりも物質的に良くなったとは言えない地域と人びとも少なくはない。
そこで、「物質的な豊かさ」以外の・とてもわかりやすい尺度を一つ取り上げてみよう。④ 資本主義と技術の進歩は、世界の「安全性」を高めたか? たしかに、公衆衛生の向上は、幼児死亡率を激減させた。医療手段の発達は、慢性的な疾患とタヒの危険から私たちを保護し、警察・治安機構は突然の暴力から守ってくれるようになった。たしかに「ミクロの次元では」そのとおり。「しかし、マクロのレベルでは、」いつ落ちてくるかわからない大量の核兵器が造り出されている。のみならず、先端的で効率的な兵器を使用したジェノサイドは、地球上の各所でますます頻繁に起きるようになっています。中核地域の人びとが、「それは悲惨なできごとだけれども、自分らの居るところではよもや起きまい」と思っていられるのは、あと何十年のことでしょうか? これらを総合的に評価して、資本主義と技術はわれわれの「安全性」を高めた、と言えるかどうかは微妙です。むしろ…
⑤「残虐行為の相対的な程度」と頻度は、明らかに増大したと言えます。残虐行為は古くからあったとは言っても、「20世紀の世界は、その「技術に関しては、異様なほど洗練された才能を示した。」
⑥「あくなき資本蓄積競争の結果として生じた膨大〔…〕の社会的浪費」は「いまや取り返しのつかないところにまで近づいている」。(pp.158-161.)
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!