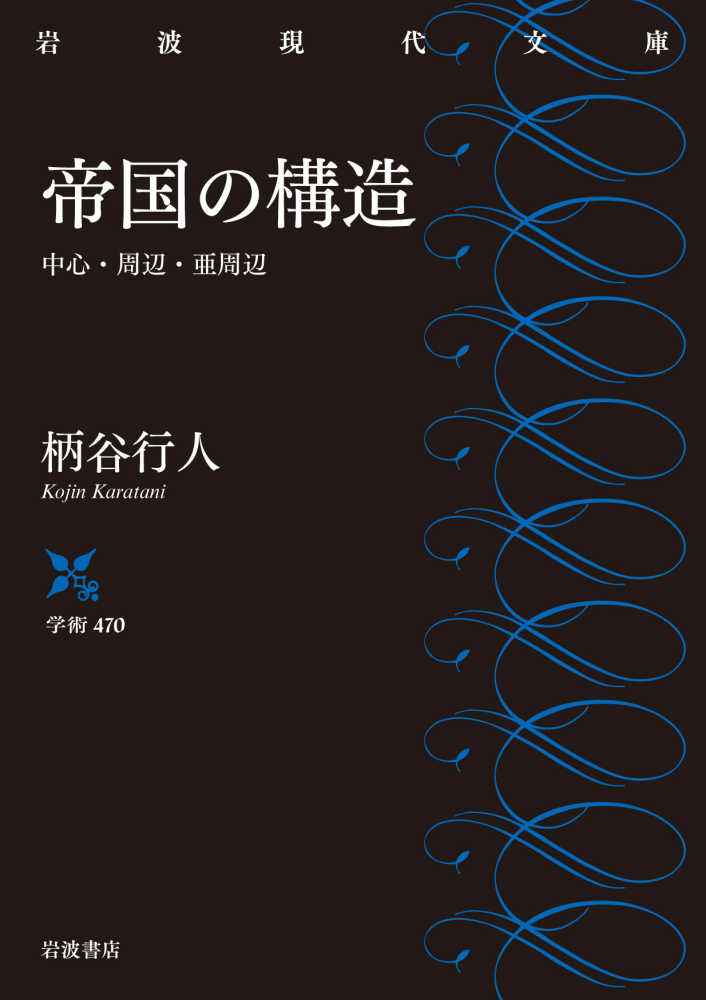オーストリア・ハンガリー二重君主国の国章(中紋章)1915-1918年。
左がオーストリア,右がハンガリーを表わす。©Wikimedia.
【27】 《帝国》の原理とライプニッツ
前節で、清朝末期の「変法自強」派、とくに康有為の「大同世界」理念が、儒教の古典(礼記)に依拠しながら、カントの「世界共和国」に非常に近い理想的未来を描いていることを見ました。19世紀末という彼らの時代から考えれば、カントを読んでいたとしても、たしかにおかしくはない。その意味で、東西思想の綜合ということもできるのかもしれません。
しかし、逆に、カントのほうを見ると、むしろカントが中国の思想に影響を受けて「永遠平和」の構想を育んだかもしれないのです。直接『礼記』を読んだわけではなくとも、中国滞在のイエズス会士と文通のあったライプニッツを通じて、中国の文物・制度に詳しくなっていたことは考えられる。儒学を学んだわけではないとしても、「《帝国》の原理」を摂取していたことは、大いにありうるのです。
今日は最初にその話をします。
『ライプニッツ〔…〕は、中国にいたイエズス会宣教師との文通に基いて、『最新中国情報』や『中国自然神学論』などの著作を書きました。また、易をヒントにして二進法を、漢字をヒントにして記号法による「普遍学」を構想しました。しかし、私がここで言いたいのは、むしろ彼が書いていないようなことがらです。
ライプニッツは、神聖ローマ帝国の選帝侯〔…〕ハノーファーの外交顧問として長く政治に関与しました。〔…〕彼が考えたのはハノーファーの国家を強化することで』も『神聖ローマ帝国を再建することでもな』く、それとは逆に、『神聖ローマ帝国内の諸国家の主権〔国家主権――ギトン註〕を認めたのです。』そして、『主権国家がそれぞれ隣人の立場に身を置いて、公共の福祉を優先すべきであると主張しました。これは、個々の国家の至上(主権)性を認めつつ、同時に、それらが「帝国」の下にあるべきだということを意味します。ライプニッツは、神聖ローマ帝国の再建ではなく、その外にあるフランスなどの多くの主権国家を越えた「帝国」を創設することを考えたのです。
むろん、ライプニッツの努力は失敗に終りました。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.185-186.
つまり、ライプニッツが中国から学んでヨーロッパに実現しようとした「帝国」とは、それ自体が強大な国家であるようなローマ帝国や中国の諸王朝のようなものとは異なったものだった、ということだと思います。それは、現実の帝国国家というより、多分に理念的なものでした。カントが理想(統制的理念)とした「世界共和国」に近いと言えるかもしれません。あるいは、現代において「国連中心主義」を主張する人たちが思い描いているような世界秩序のほうが、より現実的(したがって不完全)なだけ、カントよりもライプニッツに近いかもしれません。いずれにせよそれは、「中心」じたいに権力があって、諸国家を自分の優越的意志に従わせるのではない。むしろ、諸国家の連合体(アソシエーション)として「帝国」があり、諸国家が「帝国」というかたちで中心点を作り出している・そのような世界秩序なのです。
中国ドラマ「康熙帝~大河を統べる王~」より。
ここでようやく明らかになってきたと思うのですが、柄谷氏の言う「帝国の原理」あるいは「帝国の高次元での回復」とは、現実に興亡したアジアや古代の諸帝国そのものとは、かなり異なったものなのです。それは多分に、現代世界で抱かれている “理想” が思い入れられたものです。アジアの歴史を知る者から見れば、それはあまりにも歴史的事実から離れていないか、誤解が過ぎるのではないか、とさえ思われます。しかし、柄谷氏が、“現代の理想” を語るために、なぜ、中国の歴史や諸帝国間の複雑な争奪の過程を、まるで長大な前置きのように辿 たど ってきたかといえば、カントの主張を繰り返すだけでは、“現代の理想” を語るには不十分だからです。その不十分さについては、こちらですでに論じましたので、関心のある方は読んでみてください。
柄谷氏が「帝国の原理」に注目するのは、そこには、近代の「主権国家」原理とは異なる秩序原理が見出せるからです。たとえば、現代の国連中心主義者は、自由・人権・民主主義の “価値” を至上化し、その一方で、「主権国家」の「国益」至上主義を手放しで容認します。これでは秩序とはなりえない。秩序として無理に通用させようとすれば、秩序に従わない “悪者” をたえず創り出して、その封じ込めに動員することによって諸「主権国家」の結束を強いていくほかはない。これでは「永遠平和」からはほど遠いのです。
しかしながら、翻って考えれば、「国際連合」の理念のもとになったカントの「世界共和国」構想自体が、問題を孕んでいたとも言えます。たとえば、「世界共和国」は、あたかも主権国家のように権力を持って各国を従わせるかに読めます。これは、カントの「永遠平和」構想がもった時代的制約(「主権国家」の確立期)のためではないだろうか。
『先行者ホッブズやスピノザは国家論を書きましたが、ライプニッツは書いていない。しかし、彼の〔…〕『モナド論』は政治的に読むことができるものです。それは、多数の国家がモナドとして自立しながら予定調和的に連関するような体系、すなわち「帝国」を意味します。それは多数の主権国家が争う「自然状態」を不可避的と見なすホッブズとは対照的です。〔…〕
ライプニッツは、世界=経済〔「近代世界システム」――ギトン註〕の優位の下で自明化された近代国家の「自然状態」を越える道を、「世界=帝国」を高次元で取り戻すことに見いだそうとした、〔…〕
ライプニッツは清帝国の康熙帝に「驚嘆」しています。これは同時に、ヨーロッパにありうべき「帝国」を期待することです。この観点から見れば、清朝末の思想家らの仕事も、〔…〕いま忘れられているとしても、今後に重要な意味をもつということができます。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,p.186.
註※「康熙帝に驚嘆した」: 「かくも広大な帝国の主権者であ〔…〕る中国皇帝が、それにもかかわらず徳と知を身につけるために絶えざる精進を続け、法に対する尊敬の心と権者に対する敬意の念において臣下を遥かに凌駕することを、〔…〕自らの地位にふさわしいと考えた事実」(ライプニッツ『最新中国情報』)。「ライプニッツを驚嘆させたのは、漢以後、帝国を深く規定してきた超越的な[天]の観念です。皇帝は天によって審判される。しかも、」王朝の倒壊によって「天の審判」は現実化するだけでなく、「史官によって」明確に失政を非難されて「審判されるのです。」(柄谷,pp.132-133.)
ウィーン「ホーフブルク宮殿」。©Hotel Austria Wien. 旧オーストリア=
ハンガリー帝国の王宮。現在は、大統領公邸,国立図書館,会議場などがある。
【28】 《帝国》と「民族自決」――
ハプスブルク帝国の革命家たち
『20世紀に民族問題が生じたのは、主として旧世界帝国の地域です。それは多民族が複合的に統合されていたところだからです。〔…〕民族が互いに分離して存在しているところと、複雑に入り組んだ形で存在しているところでは、当然事情が異なります。民族問題とは、事実上、帝国問題なのです。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,p.187.
中・近世まで「世界帝国」だった地域では、「多民族が〔…〕複雑に入り組ん」で住んでいるために、近代になると民族問題が起きた‥‥。柄谷氏はそう言うのですが、はたしてそうでしょうか?
身の回りを見ても、旧中国帝国の「周辺」である日本や朝鮮では、むしろ「民族が互いに分離して存在」しています。少なくとも「複雑に入り組んだ形で存在して」はいません。私の見るところでは、地球上でもっとも民族(エスニシティ)が「複雑に入り組ん」でいるのは東ヨーロッパです。そこでは、第1次大戦後に「民族自決」を実施しようとして、かえって民族間の紛争を激化させた経緯があります。アフリカでは、民族が「入り組ん」ではいないけれども、他の地域では考えられないほど多数の民族ないし部族が隣り合わせに住んでいます。そこでは、「民族自決」による領土画定は不可能で、旧植民地宗主国が画定した経緯度による国境が大部分です。が、これらの地域はいずれも、「世界帝国」であったことはないのです。
そういうわけで、柄谷氏の認識には疑問がありますが、学ぶべきは “理念” です。細かい事実認識は捨象して、氏の論述を追っていきましょう。
『主権国家の観念と国民国家の観念は、世界帝国がなかった西ヨーロッパに生まれました。そして、世界=経済が優越するなかで、そのような観念が自明化されるようになった。しかしそれは、世界帝国の中心〔ギトン註――と周辺〕ではかんたんに成り立ちません。〔…〕
帝国の周辺が植民地化されるようになったのは 19世紀』。しかし、『帝国の中心には西洋列強も手が出せなかった。だから、事実上崩壊していたにしても、20世紀にまで帝国は存続したのです。
西洋列強が帝国を解体するために用いたのが、「民族自決」というイデオロギーです。これは本来、ヨーロッパ内部のルールとして出て来たものです。だから、ヨーロッパ人が植民地化し支配している地域に関しては適用されなかった〔適用すると、原住民の独立を認めることになってしまうから。――ギトン註〕。ところが、その原理をオスマンや清のような帝国に適用させようとしたのです。いうまでもなくそれによって帝国を解体し、ばらばらになった民族を植民地化するためです。〔…〕
「民族自決」という考えは、帝国主義のためにも使うことができる。たとえば〔…〕ナチスは〔…〕「民族自決」の観念に訴え〔…〕チェコ,ポーランド,オーストリアに住むドイツ系民族を保護するという名目で、その地域を侵略したのである。〔…〕
もちろん、帝国の中にも民族的な意識はあります。〔…〕しかし、』満州族の清王朝を倒して『民族自決を実行すれば、清朝どころか明朝さえ成立しない。いわゆる「漢族」そのものがすでに多民族的だからです。ゆえに、清朝を倒しても、多民族を統合した「帝国」を維持しなければならない。清朝末期の思想家はそう考えた。〔…〕孫文のような革命家も同じです。
ヨーロッパでも、旧帝国〔※〕にいたマルクス主義者がそう考えました。マルクスは、〔…〕民族や国家は、世界市場や資本主義的発展のなかで消滅する、と考えた』が、『帝国から生じる民族問題があるところでは、それだけではすみません。
ウィーン市庁舎前で演説するオットー・バウアー。1930年頃。©Wikimedia.
当時バウアーは、社会民主党所属国会議員として活動し、1927年「リンツ綱領」
で、ソ連ボルシェヴィズムと西欧改良主義の間に立つ「第三の道」を確立した。
交換様式から見れば明らかですが、国家は資本と別の存在根拠をもっています。したがって、〔…〕社会主義国では資本主義は抑えられたが、国家権力は強大になった。また、帝国は諸国家・民族を統合するシステムです。それは一朝一夕で出来あがるものではない。それを「東洋的専制国家」と言って片付けることはできません。帝国が壊れるとき、民族問題が出てくるのは当然です。帝国を解体して民族自決にすればよい、というわけにはいきません。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.187-189,315(8).
註※「ヨーロッパの[旧帝国]」: 柄谷氏の世界史構想では、ヨーロッパは西アジア諸《帝国》の「亜周辺」であって、そこには、ローマ帝国の滅亡後には《帝国》は成立しなかった、とする。しかし、近世の「ハプスブルク帝国」(スペイン,ベルギー,オーストリア,東欧を支配)については、異民族支配の必要、オスマン・トルコ帝国への対抗などの理由で、《帝国》の原理を取り入れた統治が行なわれたとする。その「マルクス主義者」とは、オーストリア=ハンガリー帝国のオットー・バウアー,ポーランド出身のユダヤ人ローザ・ルクセンブルクらが目されている。
つまり、《帝国》の理念が、じっさいの統治機構において、「寛容による諸民族・諸宗教集団の統合」の機能を安定的に果たしうるまでには、長い歴史的蓄積と試行錯誤を必要としたのです。その過程で多くの「帝国」が興亡しました。その《帝国》が、世界システムの発展に順応できず、耐えられなくなって遂に崩壊する時、《帝国》の統合力のもとで抑えられていた「民族問題」:いわば諸民族の “自然状態” が、噴出するのです。それを、「民族自決」といった通り一遍の合理的手法で解決することなどできない。柄谷氏が言うのは、そういうことだと思います。
『マルクス主義者のなかで民族問題に関して考えたのは、まずオーストリア=ハンガリー帝国(ハプスブルク帝国)にいた人たちです。その一人:『民族問題と社会民主主義』〔1907年〕を書いたオットー・バウアーは、民族自決に反対し、オーストリア=ハンガリー帝国の枠組みを維持することを前提にして、新たな民族論を考えた。彼は「文化的共通性」という心理主義的な観点から、民族を「運命共同体から生じた文化共同体および性格共同体」と規定した。そして属人主義(personality principle)の原理に基いて、各人が自由に自己の民族性を表明し、居住地域にとらわれない集合体をつくり、そこで各民族の自立と平等を確立する、という「民族的・文化的自治」を主張したわけです。
それに対して、ドイツのマルクス主義者カウツキーは、〔…〕民族は言語共同体や地域共同体であると主張しました〔※〕。カウツキーの考えは、西ヨーロッパでの経験に基いています。そこでは民族(エスニシティ)とネーションがほぼ一致していました。言語的・地域的な共同体にもとづいて大小の国民国家が形成されてきたわけです。
一方、バウアーは、オーストリア=ハンガリー帝国での経験から出発しています。そこでは、多民族が地域・言語・宗教』によって区画できないほど複雑に『入り組んでいる状況がありました。民族自決はそもそも無理なのです。したがって、民族を「文化的共通性」として、それぞれの自立性,平等性を確保しつつ、それが政治的な単位となることを斥けたわけです。〔…〕国民(ネーション)〔ギトン註――個人〕はそれぞれ、どのような宗教を選んでもいい、どんな言語的・文化的慣習を選んでもいい、ただしそれは政治的活動とは見なされない、ということです。
バウアーの民族論は、帝国というかたちで形成された多民族国家が民族自決によって分解されることを避けるものです。帝国を否定しながらも、それがもたらしたものを維持しようとしたわけです。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.189-191.
註※「民族とは言語共同体である」: カウツキーのこの定義は、「民族自決」主義が根拠とする民族観に近い。たとえば第1次大戦後には、住民の言語人口構成を調査して多数言語の国に所属するように国境を決める手法が理想的とされた。 しかし実際には、住民の使用言語は、優越民族による抑圧の結果である場合も多い。そこで、 “本来の” 民族語の復権を軸とする民族運動が起こることになる(ウクライナ,イスラエルのように)。なお、スターリンの「民族」定義は、カウツキーの定義を、さらにより教条化したものと言える。
ポーランド・ベラルーシ国境の町ビヤリストク(ビャウィストク)。旧市街の中心部。
後方はポーランド・カトリックの大聖堂。©Wikimedia.
【29】 《帝国》と「民族自決」――
ローザ・ルクセンブルクの場合
第1次大戦末期の「ドイツ革命」で鎮圧の刃に倒れたローザ・ルクセンブルクは、ロシア領ポーランドに生まれたユダヤ人で、その後ドイツに亡命していたのです。彼女はカウツキーとは異なって、バウアーに近い考え方で民族自決に反対しています。じっさい、彼女のタヒ後に「民族自決」理念のもとに独立したポーランドでは、ユダヤ人差別はロシア領時代よりも激しくなっているのです。
「ポーランドのロシア帝国からの独立は、マルクス以来唱導されていた」。にもかかわらずルクセンブルクは、ポーランドはロシア領にとどまるべきだと主張しました。「彼女の考えでは、資本主義の歴史的使命は多民族国家を統合することであり、また多数の地域を統合することである。資本主義的な発展のなかで巨大国家が成立する。ロシア帝国では資本主義的発展が可能であり、今後に社会主義が可能である。ゆえに、ポーランドが独立することは、」国家統合による民族問題解決への道を妨げることになる、というのです(p.191.)。
ルクセンブルクの主張は、当時、マルクス主義者のあいだでも理解されませんでしたし、「民族自決」は当然だと考えている一般の自由主義者・民主主義者には、全否定されるほかなかったでしょう。今日でさえ、その主張に現実性があると思う人は少ないのではないでしょうか。しかし、彼女がそう考えた背景には、民族問題もユダヤ人差別も「民族自決」によっては解決しない、という幼少時の被差別体験からする信念があったと思われます。
同様に、幼少時の体験から出発して、彼女とはまったく異なる方向へ進んだ例として、国際語エスペラント運動の創始者ラザロ・ルドヴィーコ・ザメンホフがいます。ザメンホフもロシア領ポーランドのユダヤ人ですが、小学校卒業まで、白ロシア(ベラルーシ)に近い国境の町ビヤリストクで生活しています。そこでは、ドイツ人,ポーランド人,ユダヤ人,ロシア人などが混住しており、人が集まる市場や通りでは日常的に争いが絶えなかったといいます〔ザメンホフ「ボロヴコ宛て手紙」en: Originala Verkaro〕。「民族自決」が実施されれば、ポーランド人だけが幸せになる。そのじつ、人口が最も多いのはポーランド人ではなく、68.2% を占めるユダヤ人なのです〔独語版Wiki: Ludwik Lejzer Zamenhof〕。市街地から外に出れば、圧倒的多数は、ポーランド人でもユダヤ人でもなく、リトワニア人の農民と白ロシア人の小作人でした。ただ、彼らは純朴で、民族的主張をすることなくロシア帝国に従っている「見えない」人びとなのです。
ザメンホフが、民族間の共通言語と共通宗教(「人類人主義」という・カント倫理を崇拝する典礼を唱えた)を広めれば「あらゆる社会問題は解決する」と考えたのは、 “民族イコール言語” という当時の常識観念を超えられなかったせいでしょう。そして、晩年には、エスペラント運動者のあいだに起こるユダヤ人排斥と排外主義の動きに心を痛めながら〔Originala Verkaro〕、第1次大戦の渦中に亡くなるのです。
ロシア帝国の支配のもとで民族的抑圧からの解放を模索し、その解決策として当時圧倒的世界世論となっていた「民族自決」にも強く反対した・この2人の生涯は、象徴的な意味をもっています。たしかに、その「民族自決」反対論には、もっともと思われる根拠がある。が、彼らが提唱した未来への道に現実性が乏しいことは、誰しも否定できないでしょう。それというのも、多民族・多宗教を統合しうる「《帝国》は、近代世界システムのもとでは、存在することができない」からです。
ルクセンブルクとザメンホフの “敗北” は、柄谷氏のこのテーゼを裏面から証明していると言えます。
ところで、以上は、ロシア帝国に支配された異民族領域での話です。ロシア本国では、どうだったのでしょうか? レーニンは? そしてスターリンは?‥
次回はそこから始めて、ふたたび中国に戻り、毛沢東以後の現代中国を見て、このレヴューを終えます。
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!