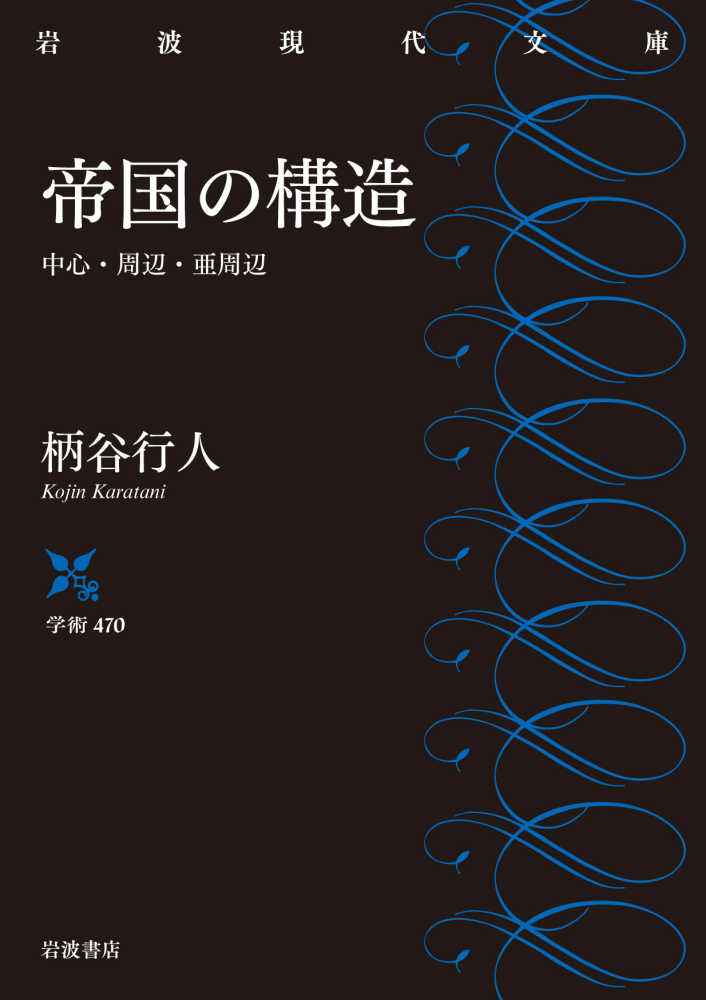トプカピ・サライ(トプカプ宮殿)。現イスタンブール旧市街の丘の上にあり、
15~19世紀に、オスマン・トルコ帝国君主の居城だった。©Medium.com.
【19】 モンゴルの残照――オスマン帝国
「オスマン帝国は、支配者がトルコ系で、モンゴル帝国とは別のものです」が、「広い意味でモンゴル帝国を受け継いだと言えます。」たとえば、オスマン王朝君主は、イスラム法(シャリーヤ)の守護者を意味する「スルタン」,ペルシャ語で王を意味する「シャー」,モンゴル語の「ハーン」の3つの称号を持っていた(p.158.)
『オスマン帝国ではイスラム教を公認していますが、〔ギトン註――宗教的寛容という〕帝国の原理が優越していました。〔…〕人頭税さえ納めれば、信仰の自由を認められ、土地その他の財産を所有できた。また、ミッレトと呼ばれる信徒の共同体があり、ユダヤ教徒もギリシャ正教徒もそれぞれ自律的集団として存在していました。』イスラム法(シャリーヤ)『だけでなく、スルタンの権威に基く世俗法がありました。また、宗教・エスニシティを越えて、国家機構に優秀な人材を抜擢・養成するデヴシルメ制と呼ばれる制度がありました。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,p.159.
『オスマン帝国では、とくに自領内のルーメリア(ヨーロッパ領)やアルメニアなどに居住する非トルコ系・非ムスリム系諸族住民の構成する共同体に対して保護と支配とを兼ねる特殊な宗教自治体〔ミッレト〕を設けた。この制度のもとでギリシア正教・アルメニア教会派・ユダヤ教の各教徒は納税を条件に習慣と自治を認められ、多民族・多文化・多宗教の調和社会が一定程度築かれた。』
Wiki「ミレット制」 .
『ミッレトは,自己の集団や集団内部の紛糾事の処理について責任を負い,また毎年行われるべき租税取立てに関して,オスマン政府に全面協力する責任を負う首長,すなわちミッレト・バシがおり,その管理・責任のもとに置かれるのが慣わしであった。ミッレトは,自己の法律や法廷をもち,かなり大幅に内部自治権を容認されていた。
オスマン政府は、ギリシア正教徒,アルメニア人,ユダヤ教徒の三大ミッレトをとくに重視した〔「近代化」=「帝国」解体後は、逆にアルメニア人,ギリシャ人,クルド人を迫害して今日に至る――ギトン註〕。ギリシア正教徒にはギリシア人,ブルガリア人,セルビア人などが含まれていた。オスマン政府は,ミッレト・バシが公正な態度を欠く場合にのみ,ミッレト住民保護のため干渉を加えることがあった。一方また,ミッレト住民は,自己の宗教と伝統文化とそれぞれの生活環境の中で,比較的平穏に生活できた。』
コトバンク「ミッレト」 .
柄谷氏によれば、トルコ人のオスマン帝国は、支配下の諸民族の文化・宗教に寛容で、ユダヤ教徒も、アルメニア系/ギリシャ・スラヴ系キリスト教徒も差別しなかった。なるほど、近代トルコのような・アルメニア人等の激しい迫害は、当時は無かったでしょう。「ミッレト」は、正教の民衆支配を巧妙に利用した統治手法と言えます。しかし、「デヴシルメ」↓となると、そう気安く「帝国の原理」を称賛できるかどうか。。。
ボスニアのドリナ川にかかるソコルル・メフメト・パシャ橋(ドリナの橋)
1577年、オスマン・トルコ帝国の宰相ソコルル・メフメト・パシャが、
かつて自分がデヴシルメで連れ去られた渡河点に建設させた。©Wikimedia.
『デヴシルメは「強制徴用」を意味し、イスラーム国家体制と共に同国の中央集権体制を支えた。
アナトリア地方やバルカン地方に住むキリスト教徒の少年を定期的に強制徴用(デヴシルメ)し、イスラム教に改宗させて教育・訓練した。この制度は奴隷(マムルーク)を商人から買い、軍人化するイスラムの伝統の発展形で、デヴシルメ制によって徴用された者は、スルタン個人の奴隷でもあった。
コンスタンティノープル征服後は、デヴシルメ出身者は、軍人にとどまらず宮廷侍従や官僚、地方官としても登用された。』
Wiki「デヴシルメ」 .
『デヴシルメ Devsirme〔…〕とは、オスマン帝国の常備軍制度であるイェニチェリ制度のもとで、バルカン半島のキリスト教徒の少年を強制的に兵士として徴用すること。〔…〕デヴシルメとは、トルコ語で「集めること」を意味し、オスマン帝国に特異な常備軍兵士の補充方法であった。他のイスラーム諸王朝でのマムルークは、奴隷として購入しなければならないので費用がかかるが、デヴシルメは強制徴用なので費用がかからない利点があった。〔…〕
デヴシルメは、主にオスマン帝国の征服地であるバルカン半島において、3年から数年に一度、不定期に実施され、キリスト教徒の農民の子供たち(ムスリムでない事が条件とされた)の中から、一人っ子を除く 8歳から20歳ぐらいの健康な少年が選ばれる。護送されて中央に送られてイスラーム教に改宗させられ、「スルタンの奴隷(カプクル)」に加えられる。彼らの中からさらに選ばれた者が、訓練を受けてイェニチェリの兵士となった。イエニチェリになる以外に、官僚に抜擢され、中には宰相に出世する者もあった。〔…〕
このデヴシルメ制度は、当のバルカンの人びとに、どう受けとめられていたのだろうか。
徴用され、父母・兄弟と故郷から引き離され、異教徒の宮廷で「奴隷」とされることは、とりわけ母親にとっては耐えがたい苦痛であったにちがいない。デヴシルメの役人が来るとの報に接すると、子どもを山に隠したり、急遽割礼をほどこしてムスリムに改宗させた親もあったという。徴用された少年たちは集団をなしてイスタンブルへと引き立てられていった。〔…〕〔永田雄三・他『成熟のイスラーム世界』,世界の歴史15,中央公論新社,p.107〕
デヴシルメが、バルカンの人びとにとって否定的にとらえられていたかというと、微妙な問題を含んでいる。デヴシルメによってスルタンの奴隷とされた中にも、スルタンの側近に使えて特権を与えられ、故郷の一族にもその恩恵がおよんだ例が多かったことも、事実である。』
『世界史の窓』「デヴシルメ」 .
『スレイマン・ナーメ』(1558年)に描かれたデヴシルメ。
オスマン朝スルタン・スレイマンⅠ世がバルカンに赴いて、
イエニチェリにする少年を徴集している。©Wikimedia.
ノーベル文学賞を受賞したボスニアの作家イヴォ・アンドリッチの小説『ドリナの橋』では、ボスニアにおけるデヴシルメを、次のように描いている。すこし長くなりますが、引用しておきます。
『さて、その 11月のある日、荷をつんだ馬の長い列が川の左岸について、夜を過ごした。武装兵を従えたイェニチェリ軍団の隊長がコンスタンティノープルへもどる途中であった。東部ボスニアの村々で一定数のキリスト教徒の子弟たちを生身税――アジャミ・オグラン――として徴集して来た後であった。この前の徴集から 6年たっていたので、今度はえらび出すのも簡単なら収穫も多かった。大した苦労もせずに、10歳から 15歳までの丈夫で生きのよい男の子を、必要数だけ見つけ出したのだった。
もっとも、親の中には子供を森にかくしたり、低能やびっこの真似をさせたり、さらにはぼろを着せ汚物をつけたりして、なんとか隊長の目を逃れようと努めた者も多かった。自分の子の指を切り落としてかたわにしてしまった親も何人かあった。
徴発された少年たちは長い列を組んだ小さなボスニアの馬で運ばれた。馬には果物を入れるような編んだかごが、両側にひとつずつぶらさがっている。その各々に一人の少年が小さな包みと一個の肉まんじゅうといっしょにはいっていた。〔…〕一様にぎしぎしと揺れる・このかごから、さらわれた少年たちの、元気はいいがおびえた顔が、のぞき出している。〔…〕
しんがりの馬の群れから少し離れた所を、三々五々と、息を切らしながら、少年たちの親や縁者が、この異様なキャラバンに加わっている。なにせ、少年たちは永遠に連れ去られて行くのだ。見知らぬ世界で去勢されて〔「去勢」はされない。キリスト教徒の誤解――ギトン註〕トルコ人に仕立て上げられ、自分の信仰と出生を忘れてから〔これも、誤解として描いている――ギトン註〕、生涯をイェニチェリ軍団かトルコ帝国内の他の重要部署で終えるために。
ついてくるのは、たいてい女だった。さらわれて行く少年の母親、祖母、姉などがほとんどである。〔…〕しかし道は長く、地面は固い。女のからだは弱く、オスマンたちは頑健で無慈悲だ。しだいしだいに女たちは遅れがちになり、走るのに疲れ、鞭に追われて、一人また一人と見込みのない努力をあきらめていく。ここヴィシェグラードの渡し場では、どんな強情な女でも行く手をさえぎられた。舟には乗せてもらえないし、川をこす道は無いのだもの。〔…〕』
イヴォ・アンドリッチ/松谷健二・訳『ドリナの橋』,第4版,1997,恒文社,pp.40-41.
ヴィシェグラード市街を流れるドリナ川。「ドリナの橋」から下流を
望む。左岸に、イヴォ・アンドリッチの生家がある。 ©lion3/ 4travel.jp.
↑このクダリを初めて読む人は、オスマン帝国はキリスト教徒に対して、なんと残酷な支配をしたのだろうと感じるかもしれません。しかしそれは、この部分だけを切り取って読んでいるせいです。
この小説に描かれている悲惨な挿話の数々――それらを「ドリナの橋」は数世紀にわたって目撃した――のうちでは、これはまだしも我慢できる程度の残虐さにすぎません。
たとえば、「デヴシルメ」の犠牲者として少年時代にドリナ川を渡った体験を持つ宰相ソコルル・パシャは、渡河時の恐ろしさを記憶していて、そこにりっぱな石橋(ドリナの橋)を架けることを命じます。そして、建築士の進言に従って、乳飲み子の双子を探し出し、人柱として橋の中央に塗り込めるのでした。
↑上に掲載した『スレイマン・ナーメ』の絵画では、「デヴシルメ」の少年たちは、まるで中世キリスト教絵画のような敬虔な面持ちで、人びとの祝福を受けています。それももちろん、事実を歪めているでしょう。その一方で、アンドリッチの小説や中公『世界の歴史』の素材となったキリスト教徒の伝承もまた、どれだけ事実を歪めているかは不明なのです。
さまざまな見方がありえます。しかし、私たちがそこで見落としてならないのは、これら一人ひとりの微細な経験、さまざまな原子的局面は、たんなる喜怒哀楽の物語ではない。むしろそこに “世界史” が凝縮されて現れている、ということです。たとえばこれが、「東」と「西」、キリスト教徒とイスラム、「《帝国》の原理」と「近代化」の諸矛盾、といった後世のさまざまな問題群につながってゆくことは、見やすいことであるはずです。
「ドリナの橋」(ソコルル・メフメト・パシャ橋) ©lion3/ 4travel.jp.
『『ドリナの橋』においては、〔…〕東と西の世界からの抑圧のもとにある・数世紀にもわたるボスニアの悲劇を描きながら、暴虐、洪水、疫病、侵略など、あらゆる災いと悪を克服しようとする人びとの堅忍不抜の精神に注目する。〔…〕
この小説の本当の主人公は、歴史である。』こんな悲惨で理不尽な出来事ばかりの連なりに、いったいどんな意味があるのか?‥という『歴史の意味の問題が、隷属と暗黒と残虐の国ボスニアの歴史の史料に基いて提起されている。〔…〕
災いと苦難、タヒと悲惨は避け得ぬものとして厳存しながらも、人生は永遠のものとしてあることを、アンドリッチは『ドリナの橋』において、〔…〕民衆の生活をとおして、われわれに語っている。〔…〕
長いトルコの支配のもとに疲弊したボスニアに生まれ、20世紀の 2つの大戦を体験したアンドリッチは、その否定的な体験』によって、『この世の中の悪の存在に対して過敏な心をもつ。〔…〕「セルビアで、ここ何世紀か戦われてきた 2つの宗教のあいだの戦い――その実、宗教の仮面〔…〕に隠れての土地,権力,それぞれの人生観・世界観をめぐって戦われた大がかりな奇妙な戦い」に対して、冷徹な眼を向ける。アンドリッチは、偏狭な世界観による対立や憎しみのない、民族と民族,国民と国民,個人と個人の触れ合いの成就を願う。そしてそのことが、彼にあっては橋を見つめることを意味するのである。彼にとっては、橋は、人間と人間の結びつきの象徴である。〔…〕橋は、矛盾,対立,分離を取り除き、それらを克服しようとする人間の努力の表現として、彼の眼に映じたのである。』
栗原成郎「アンドリッチの人と文学」, in:『ドリナの橋』,第4版,pp.24-26.
ラホール城のアーラムギーリー門。現・パキスタン。ムガール帝国第6代
アウランゼブ(アーラムギール)帝の命で1674年建築。©Wikimedia.
【20】 モンゴルの残照――ムガール帝国
「ムガール」は、モンゴルを表わすペルシャ語「モゴール」から来ていますが他称で、王朝自身の自称は「ヒンドゥスタン」であったようです。しかし、創始者バーブルが、モンゴルの血筋を引く人であったことは確かです。バーブルは、チャガタイ汗国のハーンの娘を母とし、ティムール帝国の始祖ティムールの曾孫を父として、中央アジアのフェルガナ(現・ウズベキスタン)で生まれた。ティムールは、チャガタイ汗国の武将で、トルコ語化してイスラムに改宗したモンゴル人グループに属していました。したがって、バーブルは、父母ともにモンゴル人とモンゴル帝国にゆかり深い出自の人だと言えます。
バーブルは、1526年「第1次パーニパットの戦い」でデリー・スルタン朝を倒して北インドに侵入し建国。第3代・アクバル帝は、インダス全流域からベンガル湾に至る北インド領域を統一。アクバルは、ヒンドゥー教などイスラム以外の宗教に対して寛容で、1564年、イスラム法では異教徒に課することになっている人頭税(ジズヤ)を廃止しています。その他、もともと遊牧民・都市民を想定しているイスラム法を改革して、農業国に適した税制・行政への転換を図っています。
第5代・シャー・ジャハーンの治世〔1627-1658〕は、インド・イスラム文化の最盛期で、有名な「タージ・マハール」をはじめとする建築や美術工芸が今日まで残っています。
第6代・アウランゼブ帝は最大版図を実現し、南端を除く全インドを統一しました。その反面で、アウランゼブは熱心なイスラム教徒だったために、先代までの宗教融和策を撤回し、人頭税を復活、ヒンドゥー寺院を破壊するなど、そのため各地で反乱が起き、その鎮圧と南インド征服に生涯を費やしています。
アウランゼブの死後〔1707-〕は、各地の反乱で戦費がかさみ、帝室財政が枯渇。また廷臣・貴族の陰謀がくりかえされて歴代の君主は暗殺に倒れ、ムガール帝国は衰微に向かいます。18世紀半ばからは、イギリス・東インド会社も勢力を拡大して、領土を蚕食。他方で、ヒンドゥー教徒勢力の進出が、ムスリム貴族の支配を揺るがします。
以上、柄谷氏の本では具体的歴史記述が乏しいので、Wiki から補ってみました。
ファテープル・シクリは、ウッタルプラデシュ州にある都市遺跡。第3代・
アクバル帝は 1571-85年の間ここを首都として、壮麗な宮殿を営んだ。
ラージプート族(ヒンドゥー教徒)の王妃の名を冠せた帝の居城↑は、方形の
堀(プール)と中庭で囲まれ、ヒンドゥー寺院も備えられている。©Wikimedia.
インドに外から来て征服した『ムガールの支配者が出会った最大の困難は、〔…〕ヒンドゥー教が根強くあったことです。イスラム教は厳格な一神教であり、輪廻の観念やカースト制に根本的に敵対するものです。ところが』、というか、それゆえに、というか、アクバルら初期の『ムガールの支配者はイスラム教を強制しなかった〔…〕インド人の宗教や社会慣習には立ち入らなかった〔…〕。つまり、イスラム教より「帝国の原理」を優先させたのです。地租を払うかぎり、ヒンドゥー社会の宗教や社会慣習に干渉しなかった。
にもかかわらず、イスラム教は民衆のあいだに広がりました。荒松雄〔『ヒンドゥー教とイスラム教』〕は、多くの人がイスラム教に改宗した理由を2つ挙げています。1つは、神人合一の境地〔…〕を理想とする〔ギトン註――イスラム教の〕スーフィズムが、ヒンドゥー教の中世バクティの思想と実践に似ていた、〔…〕もう1つは、低いカースト(ヴァルナ)の人たちがすすんで集団的に改宗した〔…〕
改宗は、カースト制を解体させる方向には向かわなかった。〔…〕逆に、カースト制の強化という結果を招きました。それは、バラモン階層がムスリム支配への不満のはけ口を、カースト意識を一層強化するほうに向けたからだ、と荒松雄は推測しています。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.159-160.
「ヴァルナ」とは5つの身分階層:バラモン,クシャトリヤ,ヴァイシャ,シュードラ,および不可触賎民のこと。インド英語の「カースト」とは、インド固有の語では「ジャーティ」であり、4つ5つではなく、数えきれないほどたくさんの階層に分かれています。同位の階層が、地域ごとに異なる「ジャーティ」であったりもします。
このような複雑な身分秩序が、「アラーの前では万人平等」と唱えるイスラム《帝国》の支配下で、むしろ強化されたのは、どうしてなのか? 荒松雄『ヒンドゥー教とイスラム教』を読んでみたのですが、やはり納得できるような説明はありませんでした。
むしろ、イスラムに改宗したのは下級カーストの人々だった、という点も、著者荒氏は、自分の憶測にすぎないが、と断って書いています。柄谷氏は、下層カーストの人びとが、身分差別からの解放を求めて改宗した、といったことを考えているのだと思いますが、そう単純には言えないでしょう。
私の見るところでは、考慮すべき要素は3つあります。
① 「カースト」は、他の国のいわゆる身分制度のような・国家によって管理統制された秩序ではなく、ブッダ以前の時代からインド社会そのものに内在する社会構造だということです。
② 集団的束縛の強いヒンドゥー社会の特性から考えて、個人の改宗ということは考えられない。イスラムへの改宗は、カースト(ジャーティ)ごと、あるいは地域ぐるみで行なわれたにちがいない。荒氏は、そう推測しています。
バドシャーヒー・モスク。パキスタン、パンジャブ州、ラホール県。第6代君主
アウランゼブの命で 1671-73年に建設されたイスラム寺院。©Wikimedia.
ところで、ムガールの何世紀か前からインドに侵入してきたイスラム王朝勢力に対して、バラモンもクシャトリヤも、それぞれが多数の「カースト」に分かれていたために、結束して抵抗するということがまったくできなかった。もしそれができたら歴史は変っていただろう、と荒氏は述べています。
③ そして、イスラム教の “平等” とは、あくまでも「アラーの前での平等」であって、アラーを信じない人に対しては通用しない “平等” だということです。したがって、あるカースト(ジャーティ)がイスラムに改宗しても、他のジャーティが改宗しない以上、カーストからの解放など、ありえないのです。
じっさい、現代のパキスタンでもバングラデシュでも、ムスリムの最下層カーストの人びとが、掃除人以外の職業につけない、といった差別を受けて社会問題になっています。逆に、こうした実態から、もともと最下層カーストの人びとが進んでイスラムに改宗した、という憶測が生まれるのでしょう。しかし、彼らが最下層に落ちたのは、ムガール帝国からイギリスの支配に移った時に地位を失ったためだ、という歴史見解もあるのです。
そういうわけで、私はむしろ、ムガール帝国支配下でイスラムに改宗したのは、イスラム諸国と交易のあった海岸地方の商人や、ムガールの支配者に近い上層の人びと、そういった集団だったのではないかと推測します。彼らは、改宗による利益が大きかったと考えられるからです。これに対して、下層カーストの人びとは、たとえ改宗しても、それによってムガール支配者から恩恵を受けられるわけではない(ムガールは、ヒンドゥー教に寛容で、ヒンドゥーの支配層を差別しなかった)以上、何の利益も無いことになります。
いずれにせよ、ムガール帝国の下では、さまざまなカーストが、それぞれの利益をめざしてばらばらに改宗していった。そして、改宗に利益を認めない大部分のカーストは、カースト制度を固守した。改宗してムスリムとなった階層への差別意識から、カーストを厳格に守るようにもなった。そういったことが考えられます。荒氏は、つぎのように書いています:
『イスラムの浸透により、カースト=ヴァルナ制に貫かれていたヒンドゥー社会の一部が、〈改宗〉という事実によって切り崩されていった〔…〕その歴史的意義は大きい。しかし、ヒンドゥー社会の大部分においては、カースト=ヴァルナ制の秩序とその階層意識とは、そのまま温存されていった〔…〕一部では、ムスリム改宗者に対する〈再改宗〉〔の勧奨・強制?――ギトン註〕の動きさえ見られたという。』
荒松雄『ヒンドゥー教とイスラム教』,1977,岩波新書,p.138.
「他方、ヒンドゥー教がイスラム教と融合する〔…〕現象がありました。」その一つ、シーク教は、16世紀:ムガール帝国の初期に始まっています。アクバル帝が宗教融和策をとった時代です。シーク教は、のちにはムガール帝国に敵対するものになっていきます。おそらく、アウランゼブ帝以後の、厳格なイスラム教正統主義が、シーク教のような異端宗派を、反抗に追いこんだのでしょう。ただし、シーク教の場合、ムガールの「イスラム国家体制を、むしろイスラム教的な観点に立って批判するものでした。」
したがって、イギリスの支配が及ぶ以前のムガール帝国のもとでは、〔帝国とヒンドゥー教徒土侯[ラージプート族等]との政治的対立を除けば〕イスラム/ヒンドゥーの宗教的対立そのものは、主要な問題ではなかったと言えるかもしれません。その後、19世紀以来のイギリスの「分割統治」政策が、ヒンドゥー教,イスラム教,および融合宗教諸派の間の対立を激化させて今日に及んでいると言えます。(『帝国の構造』,p.160.)
北京,紫禁城(故宮)・太和殿。皇帝の即位式などの重要儀式が行われた。
入口の天安門から、まっすぐに宮城の奥へと延びる中央の石畳には、
進んでゆく龍が彫られている。©tabinodaiziten.com.
【21】 モンゴルの残照――清王朝
『明朝を征服して建国した満州族の清朝は、当然、元を受け継いでいます。〔…〕清朝は、満州人部族を統合するとともに、モンゴルをふくむ遊牧民世界全体を統べるハーンとして、他方で、中国の王朝としての正統性を持とうとしたのです。〔…〕
元と異なるのは、第1に、東南アジア・インドに繋がる海上の道が閉ざされたことです。このことは〔…〕すでに明の時代に始まっていました。〔…〕
明朝は、新たな北方の遊牧民の南下に直面して、海上交易を中止してしまった。むしろ中国沿岸は「倭寇」が席巻する場となった。〔…〕
第2に、陸上においても、清朝はチベット・モンゴルを版図に入れましたが、それ以上に拡大しなかった〔新疆[西域]も再征服した――ギトン註〕。全体として清朝は内閉的です。が、その分安定していました。元朝は〔…〕モンゴル帝国全体とたえず連動していたので、外での事態から影響を受けましたが、清朝の版図は中国周辺に限定されていたからです。〔…〕
清朝は、帝国の内部と周辺、そしてその外に対して、異なった統治政策をとりました。満州人,漢族やモンゴルは、内部に入れられます。〔…〕その外の「藩部」と呼ばれる領域に、チベットやウイグルなどが入れられた。〔…〕彼らはそれぞれ自治体制にありました。とくにチベットは、仏教を通して清朝に対する強い影響力をもっていました。〔★〕
〔…〕さらに、その外の周辺諸国に対しては、冊封や朝貢という外交関係をとりました。これも支配-服従という外見をもつが、実際には交易です。浜下武志は、〔…〕貿易を管理するシステムと見なし、それを「中華朝貢貿易システム」と名づけました〔『朝貢システムと近代アジア』〕。
〔…〕周辺部からの朝貢は多くの場合、互恵的というよりむしろ、清朝側の贈与によって成り立っていました。たとえば、琉球王国は〔…〕朝貢するたびに莫大なおみやげをもらった。〔…〕それによって周辺部〔ギトン註――との間〕に平和を築くことが、帝国の政策だったわけです。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.161,313(7),162.
註★「チベットの仏教」: 近世チベットは、中国・清と並んでアジアにおける学問の中心地の一つだった。当時中央アジアの王族(諸汗国のハーンなど)の子弟は、チベットに留学してサンスクリット語・チベット語の仏典を修めるのが、教養を高める唯一の道だった。近代日本の浄土真宗・本願寺派の僧たちが競ってチベットに留学したのは、たんに仏典の将来が目的ではなく、西洋哲学と並んで、東洋思想の源泉としてのチベット仏教学を尊崇したからである。
清王朝の朝貢貿易にかんする柄谷氏の叙述には、かなり問題があります。《帝国》が四方に恩恵を及ぼして平和を維持しようとする――などというのは、あくまでも《帝国》のタテマエ論理にすぎない。そんなキレイごとで歴史を理解することはできません。
浜下武志氏によれば、たとえば、琉球は清王朝にとって、日本との貿易中継点として大きな利益があったので、冊封関係の維持に努めたのです。当時、日本は銀が豊富で金/銀価格比が大きかったので、銀が不足しがちな清にとっては利益の多い貿易相手でした。ところが徳川幕府は鎖国政策をとって、長崎での貿易量も制限したので、清は、鹿児島・島津藩―琉球―清のルートと、対馬藩―朝鮮―清のルートを開拓して、貿易量を増やそうとしたのです。一方で島津藩に臣従しながら・他方で清の冊封も受けるという琉球の “二面外交” を、清は「見ぬふり」しながら利用していたわけです。同じことは、朝鮮王朝にも、対馬・島津の側にも言えます。
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!