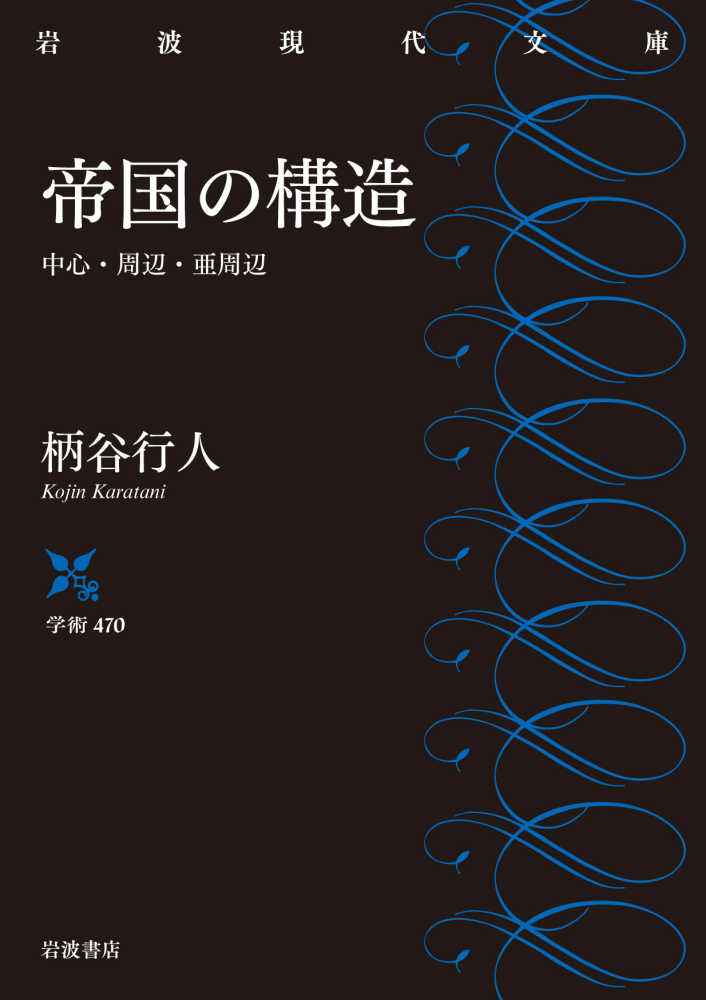天山山脈と羊の群れ。©ユーラシア旅行社.
【6】 「《帝国》の原理」――
官僚制支配と「徳治」の思想
「マルクス主義においては、国家に関して帝国が論じられることはありません。〔…〕古代の巨大な国家について論じられはしますが、〔…〕[東洋的専制国家]としてです。」(『帝国の構造』,岩波現代文庫,pp.85-86.)
これはマルクス主義に限らず、ウェーバーなどでも同様で、ヨーロッパの社会思想に共通する盲点と言えます。
「官僚制と常備軍は専制国家において生まれた。〔…〕王権が貴族(豪族)を圧倒するために、それらを必要としたからです。互酬的原理が強いとき、つまり豪族らの力が強いとき、王権は脆弱なままにとどまります。集権的な国家は」上意下達の可能な「官僚制と常備軍を不可欠とするのです。」
「東洋的専制国家」論の一面として、ウィットフォーゲルのように、大河流域の大規模な灌漑工事の必要が「東洋的専制国家」を生みだしたとする考え方もありますが、これももとはマルクスが言い出したことです。この考え方が、西洋人流の・とんでもない錯誤・偏見だということは、もう説明するまでもないでしょう。たとえば、黄河は、治水こそ歴代王朝にとって重大事でしたが、灌漑水源としてはまったく利用できない河です。エジプトのナイル河は、季節的に氾濫と減水を繰り返すのであって、人工灌漑は必要ない、また不可能です。モンゴル帝国のように、灌漑とは何の関係もない帝国もあります。ウィットフォーゲルの理論が通用するのは、メソポタミアの、それも限られた時代のことにすぎないのです。
「古代の専制国家をもたらしたのは、自然を支配する技術」ではなく、「人間を統治する技術です。」「官僚制も、そのような技術です。」(p.87.)
新疆,カシュガルのバザール。
「アジア的専制国家に対する誤解の一つは、専制君主を暴君とまちがえることです。専制国家では、大衆は〔…〕むしろ手厚く保護され」ます。「そのように民を扱うことが、王(皇帝)に支配の正当性を与える」。「アジア的専制国家」では、それが普遍的なイデオロギーだといってよい。(p.88.)
『家父長制的家産制〔=「専制国家」――ギトン註〕は、〔…〕強度に臣民の善意に依存せざるをえない』。かかる国家は、自分にとって『危険な特権諸身分の野望に対しては、大衆を動員することによってこれに対処する。〔…〕大衆神話が神聖化した理想は、〔ギトン註――ギリシャや西欧封建制社会のような〕英雄ではなくて、常に「善き」君主〔仁君――ギトン註〕であった。
したがって、家父長制的家産制は、〔…〕みずからを、臣民の「福祉」の保育者として正当化せざるをえないのである。それは、〔ギトン註――西欧封建制のような〕誓約された誠実という自由な戦友関係に発したものではなく、父と子の間の権威主義的関係にもとづいている。〔ウェーバー『支配の社会学』〕
西ヨーロッパでは、絶対主義王権においてはじめて、王が臣民を保有するという観念が出てきたのですが、そのような「福祉国家」の観念は、アジア的国家においてはありふれています。中国では漢王朝以後、専制国家の支配は儒教によって基礎づけられ〔…〕専制君主は、武力によってではなく、人徳によって統治する者(君子)と見なされる。すべての臣民を、官僚を通じて支配し、管理し、配慮し、面倒を見る。それが専制君主なのです。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.89-90.
「アジア的専制国家に関するもう一つの誤解は、それが統治のすみずみまで及ぶ強固な専制的体制だという見方」です。しかし、そのような強固な体制は、もしあっても、ごく短期間しか続かない。そして、通常の場合には、「王権を確保するために、宗教、姻戚関係、封による主従関係、官僚制などが用いられる。が、その結果逆に、神官・祭司、豪族、家産官僚、宦官などが、つぎつぎと王権に対抗する勢力となる。」そして王朝は崩壊するが、すぐにまた新たな王朝が興る。
しかし、王朝の絶え間ない興亡にもかかわらず、官僚制,常備軍などの統治機構は大きな変化なく繰り返されます。
これに関連して、「アジア的専制国家」の「永続性」は、基底にある「アジア的農業共同体」の停滞性のせいだ、という考え方があります。基底の「共同体」が、永久不変で発展性のないものなので、その上に乗っかった「国家」も変わりようがないのだ、というわけです。この偏見も、もとはと言えばマルクスが描いたアジア社会像です。
しかし、この見解は現在では大きく疑われています。そもそも、中国では、西欧中世のような、あるいはロシアのような「農業共同体」は、ひじょうに早い段階で、「春秋・戦国時代」あたりで崩壊してしまっている。それゆえにこそ、後世の王朝において、「均田制」(北魏~唐)のような、国家が農村の所有関係に強い規制を加える体制が可能になった。……このようなスキームが、中国史研究では主流になりつつあるのです。通時的に不変な「アジア的農業共同体」などはそもそも存在しない、というわけです。
水牛による水田の耕作。中央ジャワ,ケルバウ。©維基百科。
柄谷氏の場合には、「農業共同体」の存在自体は否定しないようですが、やはり、アジアの場合には国家の役割を強く見ています。
たとえば、「シュメールでは〔…〕国家が農業共同体を創り出した」。戦争で、他の都市国家を攻略して多数の捕虜を連行して来、灌漑工事を行なって、彼らに土地を割り当て、耕作させて徴税した、と。戦争捕虜と灌漑工事の代わりに、遊牧民の侵入による混乱・移住といった動因を考えれば、中国でも同様のことが言えるでしょう。
「専制国家は、賦役貢納を課すほかには、農業共同体の内部に干渉しなかった。そこには、一定の自治と相互扶助的なシステムが存在します。」これは、氏族社会の互酬システムの名残りのようにも見えるが、「ここでは、氏族社会にあった・上位組織に対する独立性が存在しません。」「ゆえに、共同体の自治を通じて、国家は共同体を支配することができる。これが、アジア的専制国家です。」
基底の共同体の不変性が社会の停滞をもたらしている、のではない。「不変的なのは、むしろ、このような専制国家の[構造]そのものです。それは、〔…〕官僚制と常備軍というシステムです。〔…〕真に永続的なのは、農業共同体〔…〕を上から統治する官僚制・常備軍などの国家装置です。農業共同体はむしろ、それに対応して、あるいは〔…〕対抗して形成されたのです。」(pp.91-92.)
とはいえ、柄谷氏の説明は、このままではまだ不十分な感じがします。が、ここでは論点の紹介にとどめ、のちほど第4章で、具体的歴史過程の叙述を見ながら、もう少し突っこんでみたいと思います。
【7】 「《帝国》の原理」――
「中心」「周辺」「亜周辺」
《帝国》には、「中心」-「周辺」-「亜周辺」という地政学的な構造が伴います。東アジア史で言えば、「中心」は「中華」、「周辺」は「東夷・南蛮・西戎・北狄」ということで分かりますが、「亜周辺」とは何でしょうか?
『周辺部では中心に従属しますが、彼ら〔古代ギリシャのポリス――ギトン註〕はそうではなかった。私は〔…〕選択的態度が可能な周辺部を、「亜周辺」と呼びます。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,p.95.
つまり、「中心」に近い「周辺」諸国は、《帝国》国家の軍事的・政治的圧力を受け続けるので、「中心」に政治的に従属し、「中心」の文明を選択の余地なく受け入れることになる。それに対して「亜周辺」は、こうした圧力を免れているので、「中心」の文明から、選択的に、必要と思うものを受け入れることができる。そして独自の文明を発展させることができる。‥‥
天山北路、キルギスの石人像。バラサグン遺跡・野外博物館。©西遊旅行。
ウィットフォーゲルが描くのは、このような図式です。そうすると、「亜周辺」とは、同心円状の図にすれば、「周辺」のさらに外側の世界、ということになるでしょう。ウィットフォーゲルが「亜周辺」に名指しているのは、ヨーロッパ(ギリシャ),日本,そしてロシアのキエフ公国です。ギリシャは、オリエントの諸《帝国》の「亜周辺」、日本は中華《帝国》の「亜周辺」、というわけです。ギリシャは地中海とエーゲ海で、日本は東シナ海で、いずれも「中心」とは海で隔てられています。
もちろん、このような図式的な理解を、じっさいの歴史に、まして現今の世界情勢にあてはめたら、とんでもない誤解のもとになります。「周辺」が「中心」の文明を受け入れる、という理解じたいが、そもそも問題で、何重にも注釈が必要でしょう。
たとえば、新羅、高麗、朝鮮(李朝)といった韓半島諸国は、名称の上では中国の諸制度をそのまま受け入れているように見えますが、制度の実体は、中国とはかなり異なるものです。同じことは、日本が受け入れた「律令制」の諸制度にも言えます。そうすると、「周辺」と「亜周辺」は、はっきり区別されるようなものではないことになります。たかだか程度の違いにすぎない。
「中華」にもっと近い諸国になると、ウィットフォーゲルの図式はいよいよ破綻します。匈奴,突厥,ウイグル,契丹,女真,モンゴル,チベットなどがありますが、これら「周辺」諸国は「中華帝国の外に帝国を築き、あるいは侵入して帝国を作った。〔…〕中華王朝から見た場合には周辺的ですが、中心に従属したわけではない。その逆です。彼らがむしろ[中心]となった」「彼らは中国の文化や制度に全面的に同化することはなく、むしろ草原にいたときの原理を保持しました。」たとえば、漢字を受け入れることなく、独自の文字を考案し使用しました。(p.253.)
「周辺は中心に従属する」などというのは、実際の歴史とは懸け離れた偏見にすぎないことになります。むしろ、「周辺は中心を侵略して中心を征服する」と言ったほうが、実際に近い。
同様のことは朝鮮王朝にも言えます。17世紀に女真族が中国を征服して清王朝を建てると、朝鮮では、清は「夷狄」であって中華ではない、いまや朝鮮こそが中華だ、という「小中華」イデオロギーが支配的になるのです。この場合には、「中心を征服」まではしないけれども、外面上は清に朝貢しながら、頭の中では自分のほうが「中心」です。
他方、ロシアについて言うと、ロシア(モスクワ)はモンゴル帝国に征服されてその一部となっています。のちにモンゴル帝国が瓦解して、その中から出てきたロシア帝国も、《帝国》を受け継ぐものです。これに対して、キエフ公国は「亜周辺」としてモンゴルに抵抗しましたが、けっきょく征服されています。そして、モンゴル帝国が無くなったあとも、その後継であるロシア帝国から隷従圧力を受け続けることになります(pp.252-253.)。こうなると、「亜周辺」だから独立性があるだとか、選択の自由があるなどとは言えなくなります。
「中心」-「周辺」-「亜周辺」という図式は、たしかに便利ですし、禁じ手にする必要はありませんが、じっさいの歴史や政治に適用するときには、よほど注意しないと、誤解や偏見の正当化として働いてしまいます。
「地政学」というものが一般に、そのようなマユツバなシロモノなのです。
天山北路、キルギスの石人像。バラサグン遺跡・野外博物館。
【8】 「《帝国》の原理」――
「近代世界システム」とは相容れない。
『「帝国の原理」とは何でしょうか。それは多数の部族や国家を、服従と保護という「交換」〔交換様式B――ギトン註〕によって統治するシステムです。』帝国は、征服した『相手を全面的に同化させたりしない。彼らが服従し貢納しさえすれば、そのままでよいのです。帝国はその版図を広げようとしますが、周辺には統治できない者がいます。たとえば、漢帝国にとって、遊牧民である匈奴〔…〕そのような周辺に対しては、外見上服属し朝貢する』ことを求め、それに応じなくとも『贈与や婚姻によって平和を保持するという政策をとったのです。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.97-98.
しかし、このような《帝国》は、「近代世界システム」の中では存立しえません。近代の「国民国家」(主権国家)には、《帝国》のような「統合の原理」が無いからです。
『永続性のある世界帝国を設立しうるのは、国民国家のような政治形態ではなく、』ローマ帝国のように『本質的に法に基づいた政治形態である。なぜなら、そこ〔帝国――ギトン註〕には〔…〕万人に等しく有効な立法という権威が存在するから、それによって〔…〕きわめて異質な民族集団も統合されうるからである。
国民国家は、このような統合の原理をもたない。』国民国家は、住民の同質性と、『政府に対する住民の積極的同意〔…〕とを前提としているからである。ネイションは、領土,民族,国家を歴史的に共有することにもとづく以上、帝国を建設することはできない。〔…〕
膨張が帝国主義の中心的政治理念である。膨張は〔…〕事業投機の領域から出た概念で、そこでは、19世紀に特徴的だった工業生産と経済取引とのたえざる拡大を意味していた。〔ハンナ・アーレント『全体主義の起源』2〕
〔…〕帝国主義はネーション=国家〔国民国家――ギトン註〕の拡大としてある〔…〕それは交換様式Cにもとづくものです。そして、他の国家にそれを強制します。〔…〕したがって、〔…〕外見上、自由・民主主義を奨励します。〔…〕
オスマン帝国にはまさに「帝国の原理」がありました。〔…〕オスマン王朝は住民をイスラム化しようとしなかった〔オスマン・トルコ支配下の東欧~ギリシャでは、住民はキリスト教徒のままだった――ギトン註〕。〔…〕国民国家の拡張としての帝国主義が、他民族に同質性を強要するのと対照的です。
オスマン帝国の解体、多数の民族の独立は、西欧諸国家の介入によってなされました。その時、西欧の諸国家は、諸民族を主権国家として帝国から独立させるのだと主張したのです。しかし、それによって経済的に支配しようとしたにすぎない。〔…〕「帝国主義」とは、「帝国」の原理無しに、ネーション=ステート〔国民国家――ギトン註〕が拡大し、他のネーションを支配することです。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.96-99.
天山北路、イーニン市のイリ河 。
【9】 「《帝国》の原理」――
ローマ教会と中世ヨーロッパ
《帝国》は一般に、堅固な専制国家として永続するものではありません。モンゴル帝国がそうであったように、完璧な統一体として続く期間は短いのです。比較的に変化なく続くのは官僚制,常備軍,万民法制などの支配機構とイデオロギーですが、その表面で、王朝などの政権実体は絶え間なく交替します。ある「帝国」が倒れれば、その混乱のなかから次の「帝国」が興ってくる。これが《帝国》の通常の歴史過程だと言ってよいのです。
『ローマ帝国の滅亡に関しては、謎はむしろ〔…〕なぜ滅亡したかではなく、なぜ帝国が再建されなかったかにこそあるのです。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,p.106.
↑この “謎” に対して、柄谷氏は答えを出していません。事実としては、ローマ帝国の西半分では、移住して来たゲルマン諸部族の持ちこんだ氏族的社会編成〔交換様式A〕が《帝国》の再建を妨げました。フランク王国,神聖ローマ帝国,いずれも「帝国」とは名ばかりで、地方領主の割拠・抗争が永く続きます。「皇帝」は、有力諸侯の選挙で選ばれる名目的な代表者にすぎませんでした。この状態が、近世に絶対主義王政が抬頭するまで続きます。
他方、東半分でも、《帝国》としての宗教・学問・文化に対する寛容が失われ、本来の「世界帝国」とは懸け離れたものになっていきます。まず、4世紀のコンスタンティウスⅡ世は、キリスト教(のちに異端とされたアリウス派)を採用して強制し、ギリシャ・ローマの伝統的な神々を禁止し、神殿を破壊しました。その後、テオドシウス帝は、キリスト教(アタナシウス正統派)を国教と定めて強制。そして、ユスティニアヌス帝は、「ネストリウス派を異端として追放するとともに、学問が異端の巣窟になる」として 529年「禁学令」を発布、ギリシャの学者たちはササン朝ペルシャに逃避し、プラトン以来の「アカデミアの伝統が絶えた。」(p.310.)こうして、東ローマ帝国は存続したものの、「もはや[帝国の原理]をもたない」単なる専制国家となり、支配領域も次第に縮小していきました(p.107.)。
しかしながら、西ヨーロッパで宗教的権力を持ったローマ教会は、ある意味でローマ帝国の伝統を引き継ぐ存在だった。「教会は、王・封建領主・都市が乱立する状態の下で、それらを統合する原理をもっていた。教会が帝国の形態を与えたわけです。」(pp.107-108.)
柄谷氏はこのように言うのですが、しかし、中世のローマ・カトリック教会は、宗教的にも文化的にもきわめて不寛容です。「《帝国》の原理」の継承者だなどとは、とうてい言えません。もっとも、⑤世界言語(ラテン語),⑩暦法(グレゴリオ暦),⑪紀年については、《帝国》の遺産を引き継ぐ面があったと言えます。(わずか 11分の3)
柄谷氏がローマ教会の《帝国》性にこだわるのは、アウグスティヌス→ライプニッツ→カント‥と引き継がれた《帝国》理念の発展(→カントの「永遠平和」「世界共和国」へ)に注目するからだと思います。
「イエス,パウロ,その他初期の教父」たちは、ローマ帝国など世俗の権力に対してネガティヴな見方をしていました。教父アウグスティヌスは、
「正義が無くなるとき、王国は大きな盗賊団以外の何であろうか。盗賊団も、小さな王国以外ではない。〔…〕首領の命令によって支配され、〔…〕掠奪品を分配するこの盗賊団という禍いは、〔…〕著しく増大して領土をつくり、住居を定め、諸国を占領し、諸民族を征服するとき、ますますおおっぴらに王国の名を僭称するのである。」〔『神の国』4巻4章〕
と書いています。しかし、「彼らは、帝国に抵抗したりはしなかった。」「悪しき者に逆らうな」「カエサルの物はカエサルに」という消極的服従の姿勢をとったのです。それというのも、当時のキリスト教団では、「神の国」の到来(最後の審判)は間近いと考えられていたからです。「神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」とイエスが言うように、悪者は放っておけ、まず自分が悔い改めよ。でないと、神の「審判」に間に合わないぞ、というわけです。
アウグスティヌス。6世紀頃のフレスコ画。バジリカ・
ディ・サン・ジョヴァンニ・イン・
ラテラーノ教会,ローマ市。©Wikimedia.
ところが、それから何百年か経過し、「終末がすぐには来ないことを認めた時点で、考えが変わります。ある意味で、その時に[キリスト教]が始まったとも言えます。」
この時点で、キリスト教会の首脳部は、次のように考えました。「神の国」は、すでに到来している。キリスト教会を中心として広がる世界が「神の国」だ。つまり、居直り説です。
しかし、居直るのはいいとしても、問題は、現実に存在する「ローマ帝国」をどう見なすかです。「ローマ帝国は神の国ではない」などと言えば迫害を招きます。そこで、当時、教会政治家として辣腕を発揮したミラノ主教アンブロシウスは、キリスト教を、皇帝にも優越するローマの国家宗教だと宣言しました。それは結局のところ、皇帝の支配に宗教的権威を与え、現実のローマ帝国の支配を、「神の国」の実現として正当化することになります。(pp.108-110.)
これを批判したのが、アウグスティヌスです。
『アウグスティヌスは、〔…〕ローマ帝国が栄えたのは、ローマ人の「道徳的卓越性」によってであり、それが滅んだのは〔『神の国』出版当時(410年)ローマ帝国はなお存したが、東西に分裂し混乱していた――ギトン註〕、彼らが道徳的に堕落したからだ、というのです。〔…〕帝国が栄えるのは「帝国の原理」を発揮しているかぎりであり、それが無くなれば滅んでしまう、ということです。〔…〕
帝国が形成されるまでに、実に悲惨な〔ギトン註――戦争と征服の〕過程があった。それは今もあり、将来にもある。その意味で、帝国は巨大な盗賊団にすぎない。〔…〕しかし、それは、人間が各地に散在していた氏族社会の段階から、相互に結びついてコスモポリスにいたる過程において避けられないことではないか。
神の国が形成されるとしても、それは現実的な社会の歴史の上においてのみ可能である。神の意志(摂理)は、突然の終末によって示されるのではなく、歴史的な過程を通して示されるのだ、というのがアウグスティヌスの見解です。〔…〕
地の国が「自己愛」に立脚する社会であるのに対して、神の国は「神への愛」ないしは隣人愛によって成立する社会です。〔…〕神の国は〔…〕ポリス(地の国)のような限界や境界をもたない、コスモポリスです。現実に諸国家が存在する一方で、神の国は、それらと重なり合いながら存在し、それらに徐々に浸透していく。
西ローマ帝国は滅んだけれども、ヨーロッパには、以上のような理念が残りました。「神の国」とは、具体的にいえば、ローマ教会を中心とする世界です。それが、政治的に四分五裂状態にあった西ヨーロッパを統合するものとして機能した。教会の存続が、その意味で「帝国」を保存させたのです。
西ヨーロッパが一定の同一的な輪郭を保ちえたのは、政治的な国家としてではなく、教会と法(自然法)によってです。その意味で、帝国はローマ教会として残ったのです。〔…〕
ヨーロッパでは、帝国の原理は国家ではなく、教会の側に残ったということができます。そして、これは、〔…〕近代の主権国家という観念を乗り越えようとした人たち〔たとえばカント――ギトン註〕が、明示的にであれ暗黙裡にであれ、つねに参照してきたものです。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.110,112-114.
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!