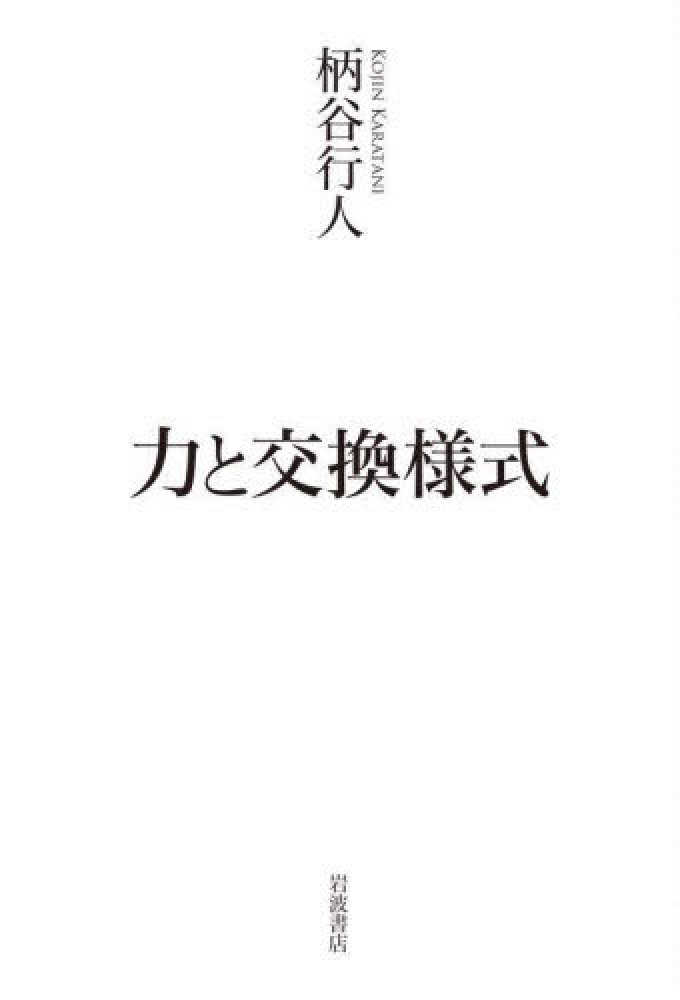サハリン北緯50度線の標示碑。1905-1945年、ロシア/ソ連と日本の国境だった。
【88】 「国家」から解放される未来はあるか?
議論は、「国際連合」の現状から出発します。「国連」の現状が理想からほど遠いことは明らかですが、カントの提唱した「諸国家連合」は、それとどのように異なるのか? そして、「諸国家連合」から「世界共和国」への道すじは? ……柄谷氏の議論を追って行きます。
『国際連合は、国際連盟よりははるかにましですが、結局、大国による支配を越えるものではありません。〔…〕
現在の国連は諸国家連邦ではありますが、実際には、米国のような強国が支配しています。つまり、国連が基づく原理は、実質的には交換様式Bなのです。〔…〕現在の国連は』カントの理念とは『ほど遠いものです。
カントが言う「世界共和国」は、国際連邦ないし世界政府のようなものとは異質です。それは、交換様式でいえばBやCではなくD、すなわち贈与の互酬Aを、高次元で回復することによってのみ可能です。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023(原2014),岩波現代文庫,pp.222,58-59.
つまり、「世界共和国」は、諸国家を支配する上級国家のようなものではない。歴史上で近い例を挙げれば、北米先住民イロコイ族の「イロコイ連邦」のような部族連合体が考えられます。「それは、贈与の互酬性、交換様式Aにもとづく世界システムなのです。」
大国のヘゲモニーや「支配従属」関係(交換様式B)とは異なる、部族連合のような水平的な結合。これを、「高次元で回復」するのが、「世界共和国」だ、と柄谷氏は言うのです。
アメリカ/メキシコ国境の壁。メキシコの写真家アレハンドロ・プリエトさんは
この写真で、2021年の Bird Photographer of the Year に選ばれた。
『カントは「世界共和国」という理念を提示した時、それを実現する第1歩として「諸国家連邦」の構築を説きました〔…〕
しかし、カントが「諸国家連邦」を唱えたのは、本来なすべきことの「消極的な代替物」としてではありません。諸国家の戦争状態を越えるというと、ひとは「諸民族合一国家」(世界国家)のようなものを考えてしまう。それは諸国家を上から実力によって統制するものです。それでは、ホッブズ〔絶対主義君主への主権譲渡――ギトン註〕やヘーゲル〔ヘゲモニー国家の支配による世界平和――ギトン註〕と同じ発想になってしまいます。
一方、カントがいう諸国家連邦という構想は、諸国家の自律性をとどめたままで、徐々に国家間の「自然状態」〔万国間の闘争状態――ギトン註〕を解消しようとするものです。だから、世界共和国への道は、「戦争を防止し、持続しながらたえず拡大する連合」しかない、というのです。』〔…〕
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,p.224.
つまり、「諸国家連合」は、…一気に「世界共和国」にはできないから、とりあえず前段階として連合を作ろう……というだけの、いわば「世界共和国」の代用品ではありません。「諸国家連合」という、諸国・諸国民の自律性を尊重する在り方が、そこから発展的に形成される「世界共和国」の性格にも影響を及ぼしてゆくのです。すなわち、ヘゲモニーによって征服し抑えるのではなく、結びついて拡大してゆくというやり方です。
『ホッブズがいたイギリス、スピノザがいたオランダは、当時の最先進国でありヘゲモニー国家〔覇権国家。今のアメリカのような。――ギトン註〕でした。彼らの考えは、近代の主権国家〔ネーション・ステート(国民国家)。ナショナリズムで団結した国家――ギトン註〕を前提しています。〔…〕
ところが、カントは、主権国家がそれぞれ煽るナショナリズムを、根絶すべき「妄想」として斥け〔…〕ているのです。
ある民族は他国よりも自国を愛するのである。各国の政府はこの妄想を歓迎する。〔…〕一方、理性はわれわれに法を与えて、本能は盲目だから〔…〕理性の格率によってとって代わらねばならない、と教えるのである。そうなるためには、ここに述べた国家の妄想〔ナショナリズム――ギトン註〕は根絶やしにされるべきであり、祖国愛と世界市民主義がそれにとって代わらなければならない。〔『カント全集』,15,人間学〕
〔…〕彼がここで言う祖国愛〔パトリオティズム。土地,住民,および特有の文化を「自己」としてそれに執着する意識。国家とは無関係――ギトン註〕は、近代国家のナショナリズムではなく、郷土愛のようなものです。コスモポリタニズムは〔…〕郷土愛とは両立します。コスモポリスは、多くの郷土が存在するような空間を意味する。〔…〕多数の郷土,言語,宗教を許容するものです。』
柄谷行人『帝国の構造』,pp.225-227.
「祖国愛」は、「ナショナリズム」とどこが違うのでしょうか? それはなぜ、コスモポリタニズム〔「世界市民」であること〕と両立するのでしょうか? ‥‥カントの考え方には、ライプニッツの影響を見てとることができます。ライプニッツの考え(モナド論)では、たとえばカトリックもルター派もカルヴィン派も、それどころかイスラム教も儒教も、ひとつの同じ宗教、同じ神を、異なるパースペクティヴから見ているにすぎない。人類には、「目に見えない唯一の教会」があるというのです(p.225)。また彼は、人類共通の普遍言語を考案しようと試みています。柄谷氏も、人工国際語(仲介言語)エスペラントに、たいへん好意的な論評を書いているのを見たことがあります。つまり、「世界市民」とは、民族の違いを無くそうとすることではなく、むしろ逆に、諸民族が、それぞれの相違を認め合うことにこそ、コスモポリタニズムがあるのです。地球上にヘゲモニーを得た国家と民族が、他の人びとを、みずからの言語,宗教,文化に同化させようとするならば、闘争状態がなくなることはありません。そうした圧迫に対して抵抗する「祖国愛」は、むしろコスモポリタンであり、正当なものです。
『カント〔…〕は、ルソーの市民革命が1国だけで考えられていることに対して批判的でした。
完全な意味での公民的組織を設定する問題は、諸国家のあいだに外的な合法的関係〔国家間の法秩序,条約,国際法,国家連合――ギトン註〕を創設する問題に従属するものであるから、後者の解決が実現しなければ、前者も解決され得ない。〔『世界公民的見地における一般史の構想』「第7命題」, in:『啓蒙とは何か 他4篇』,1950,岩波文庫,p.36. 〕
「完全な意味での公民的組織」とは、ルソー的な社会契約による国家〔理想的な市民国家――ギトン註〕です。が、それが成立するかどうかは他の国家、というより周囲の絶対主義的な王権国家との関係によって左右されるのです。〔…〕1国だけの市民革命は不可能です。〔…〕《それだから国内においてできる限り最善の公民的組織を設定するとともに、対外関係においても諸国家のあいだに協定と立法とを制定』しなければならない。『》〔op.cit.,pp.37-38.〕つまり、「諸国家連邦」の構想は、本来、市民革命を貫徹するためにこそ考えられたのです。』
柄谷行人『帝国の構造』,pp.228-229.
‥‥以上は、「国家連合(平和連合)」の話です。個々の国家の存在を前提として、その「連合」の必要性、「連合」のしかたを模索しています。が、そこから「世界共和国」へは、どうつながるのでしょうか?
『最後に、諸国家連合から世界共和国への進展において働く「力」について述べておきます。カントは、つぎのように言う。
連合制度〔諸国家連合――ギトン註〕は、しだいにすべての国家の上に広がり、そうして永遠平和へと導くことになろうが、』そ『の実現可能性は、おのずから証明されるのである。なぜなら、もし幸運にもある強力で啓蒙された民族が、1共和国を形成することができたら(共和国はその本性上、必然的に永遠平和を好む)、この共和国がほかの諸国家に対して連合的結合のかなめの役をはたすからで、〔…〕〔『世界平和のために』,1985,岩波文庫,p.45.〕』
柄谷行人『帝国の構造』,p.247.
戦争を好むのは君主であり、嫌うのは、戦争の被害を受ける臣民です。したがって、王政国家は戦争を好むが、共和国は「本性上必然的に」永遠平和を望む、とカントは言うのです。しかし、それにしても現実には、よほど強力な国が(市民革命によって)共和国になって「かなめ」の役を果たさないと、「諸国家連合」の形成は進展しません。
そこで問題となるのは、「強力な共和国」が、周辺の国々を「諸国家連合」に引き込んでゆく《力》は何か、ということです。現実の歴史がそうであったように、それが、軍事力や金銭の力(資本主義の経済力)であったなら、できあがった「連合」は、決して対等なものではありません。実質的には、大国がヘゲモニーによって支配しているにすぎず、たんに交換様式Bが国家間にまで拡大しただけ、ということになります。まして、そこから「世界国家」が形成されるとしたら、カントの提唱した理念とは真逆の、強権的な無敵の支配者となるでしょう。今日のアメリカのヘゲモニーは、その例であるかもしれません。
そこで、「世界共和国」を形成する《力》として柄谷氏が想定するのは、交換様式A、すなわち「贈与」の力です。ここまで来ると、柄谷氏の飛躍した論理に、付いていけないものを感じるかもしれません。しかし、めざす方向は、理解できるのではないでしょうか。
『が、国家以前の社会には、それら〔武力と経済力――ギトン註〕とは異質で圧倒的な力がありました。贈与の力です。それが交換様式Aを支える。このことは、交換様式Dがどんなものかを見るためのヒントになるはずです。交換様式Dは、交換様式Aの高次元での回復であるから、そこで働く力も一種の贈与の力だといえるでしょう(宗教ではそれを「愛の力」と呼ぶでしょうが)。〔…〕
諸国家連邦から世界共和国に至る過程で働く〔ギトン註――べき〕力は、贈与の力です。すなわち、武力や金銭の力ではなく、それらを贈与することがもたらす力です。〔…〕
戦争に負けて降伏した国は、武装解除され賠償金を払う。〔ギトン註――ホッブズの言う〕自然権の譲渡とは通常、そのような意味です。〔結果として、保護・服従の関係が生じる――ギトン註〕
一方、贈与はいわば勝者のほうが武装放棄することを意味します。〔…〕それはいかなる武力よりも強い。具体的にいえば、国際世論が震撼されるからです。これに対抗するためには、みずから贈与によって報いるほかない。贈与の連鎖的拡大によって創設される平和状態が、世界共和国です。それはカントが示したように、もっぱら「自然」によって〔つまり、人間の意志を超えて――ギトン註〕実現されるということができます。』
柄谷行人『帝国の構造』,pp.248-249.
↑最後の部分は、カントを越えて柄谷氏独自の見解になっているかもしれません。しかしそれは、交換様式論からの・すじの通った帰結であり、じっさいにそういうことが起きないとは、誰にも言えないでしょう。
ともあれ、「統制的理念」は “設計図” ではないのだから、あまり細部にこだわっても意味が無い。むしろ重要なのは、ある「統制的理念」にもとづいて、途上の現在においてどんな見解を持ち、どんな方向に努力するのか、ということでしょう。
私たちが「国家」の力を強めるのはどんな場合で、「資本」や「ネーション」を強めるのは、どんな場合か? 逆に、どんな行為がそれらを弱めるか? また、「贈与の力」は、どんな場合に働くか? 私たちは、世界中のどの国よりも「贈与の力」を発揮できる手段――「戦争」と軍備の放棄――を持っているのに、みすみすそれを反古にしていないでしょうか?
【89】 社会構成体史のスキーム
――「アソシエーション」という《交換様式》
柄谷氏の『ニュー・アソシエーショニスト宣言』には、つぎの図が掲げられています。
『哲学の起源』『力と交換様式』の4象限図と似ていますが、a と b の記号が逆になっています。それより重要なのは、d の位置に、「Ⅹ」でも「Aの高次元の回復」でもなく、「アソシエーション」と書かれていることです。アソシエーショニスト運動などの「ユートピアニズム」は、『力と交換様式』では「Aの回復」をめざす運動とされ、「D」とは認定されていませんでしたが、ここでは「D」(自由かつ平等)の位置に収まっています。説明は、次のようになっています:
『以上、交換にはこの3つの型〔互酬交換,強奪と再分配(国家),交易と資本主義――ギトン註〕がある。実は、さらに、もう1つの交換のタイプがあり、それがわれわれのいうアソシエーションや LETS である。それは、以上の3原理とは違った原理にもとづくものである。というのは、そこでの交換は、国家や資本と違って非搾取的であり、また、農業共同体と違って、その互酬性は自発的であり、かつ非排他的(開放的)であるから。』
柄谷行人『ニュー・アソシエーショニスト宣言』,2021,作品社,p.238.
『諸国家がその主権を譲渡することによって成立する世界共和国、〔…〕カントは「永遠平和」を実現するための国際連合を提唱しました。これは〔…〕たんなる平和論ではない。資本と国家を揚棄する過程の第1歩なのです。〔…〕
彼は、〔ギトン註――永久平和のための〕国家連合が人間の理性や道徳性によって実現されるとはまったく考えなかったのです。それをもたらすのは人間の「反社会的社会性」〔非社交的社交性――ギトン註〕、いいかえれば戦争、だとカントは考えたのです。〔…〕
人類はいま、緊急に解決せねばならない課題に直面しています。それは次の3つに集約できます。
1 戦争
2 環境破壊
3 経済的格差
これらは切り離せない問題です。〔…〕そしてこれらは、国家と資本の問題に帰着します。〔…〕
これらは、一国単位では考えることができない問題です。実際、そのためにグローバルな非国家組織やネットワークが数多く作り出されています。しかしそれらが有効に機能しないのは、結局は、諸国家の妨害に出会うからです。資本に対抗する各国の運動は、つねに国家によって分断されてしまいます。
南北直通列車の試運転(2007年5月17日 韓国・高城)。©AFP=時事.
韓国/北朝鮮 間の軍事境界線(38°線)非武装地帯〔写真・手前が韓国〕を越えて
北朝鮮の列車が同国側へ戻ってゆく。韓国・文在寅政権のもとで南北平和プロセス
の一環として鉄道線の復元がはかられたが、国連軍司令部が「制裁違反」との
判断を下したため、運転開始には至らなかった。
では、どのように国家に対抗すればよいのでしょうか。その内部から否定していくだけでは、国家を揚棄することはできない。国家は他の国家に対して存在するからです。われわれに可能なのは、各国で軍事的主権を徐々に国際連合に譲渡するように働きかけ、それによって国際連合を強化・再編成するということです。たとえば、日本の憲法第9条における戦争放棄とは、軍事的主権を国際連合に譲渡するものです。各国でこのように主権の放棄がなされる以外に、諸国家を揚棄する方法はありません。
各国における「下から」の運動は、諸国家を「上から」封じこめることによってのみ、分断をまぬかれます。「下から」と「上から」の運動の連係によって、新たな交換様式にもとづくグローバル・コミュニティ(アソシエーション)が徐々に実現される。もちろんその実現は容易ではないが、けっして絶望的ではありません。少なくとも、その道筋だけははっきりしているからです。』
柄谷行人『世界共和国へ』,2006,岩波新書,pp.182,220,224-225.
〈下から〉のアソシエーショニズムと、〈上から〉の「国際連合」によって、「国家と資本」――および「ネーション」――を挟み撃ちにし、それらの横暴を抑えて、現状の「三位一体」の覇権を崩していこうという発想です。したがって、「国連NGO」のような形で、「下からのD」と「上からのD」が連携してゆくことが重要になるでしょう。
ここで、別の面からの考察を見ましょう。柄谷氏がなぜ「世界共和国」にこだわるのか、「上からのD」がどうしてそれほどに重要なのかがわかります:
『普仏戦争〔1870年〕』は『世界史において最初の帝国主義戦争である。その時、資本・国家だけでなくネーションが重要な役割を果たすようになった。交換様式でいえば、ネーションはAの “低次元での” 回復〔想像上の回復――ギトン註〕である。ゆえにそれは国家(B)・資本(C)と共存すると同時に、それらに抗する何かをも持っている。政治的にそれを活用したのが、イタリアのファシズムやドイツのナチズム〔、日本では権藤成卿らの農本・反近代主義――ギトン註〕であった。今日〔…〕ポピュリズムと呼ばれるものにそれが残っている。
このように、資本=ネーション=国家が出現するとともに、「資本の揚棄」という問題も「国家の揚棄」という問題も、以前にもまして難しくなった。なぜなら、資本,ネーション,国家、すなわち交換様式C,A,Bが相互に助け合いつつ存続するからだ。したがって、それらを揚棄することを考えるとき、それらとは別の何かが不可欠となる。それがDにほかならない。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.291-292.
「C,A,Bが助け合いつつ存続する」というのは、たとえば、Aを回復する運動を進めると、容易にA=B=Cに取りこまれてファシズムや排外的ナショナリズムになってしまう事態を指しています。Aが復古的理念構想や政治的プログラムのかたちで唱えられる場合には、つねにそうした危険があります。それを防ぐには、ネーションを超える必要がある。「世界共和国」ないし「国際連合」、すなわち「上からのD」との連携ないし一体化が求められるゆえんです。
「永遠の謝罪」像。 江原道平昌「韓国自生植物園」2020年。©朝日新聞。
かつて「マルクス=レーニン主義」が進歩陣営の先頭に立っていたのは、共産党官僚の “詐欺” が上手だったからではありません。その時代の「マルクス=レーニン主義」が、ネーションを超える国際主義の色彩を帯びていたからです。
ただ、柄谷氏の言う「上からのD」としての「国際連合」が、いまある国連の改変によって辿り着くものなのか、それとも、世界戦争,環境危機の爆発といった・終末的破局によって国連が壊滅したあとで、新たな理念のもとに設立される第3のものなのかは、私は、なんとも言えないと思います。
他方、〈下から〉の「D」も、「アソシエーショニスト運動」だけで十分とは到底思えません。もっとさまざまな動きや試み――いわゆる「社会民主主義」政治の再評価も含めて――を綜合し、新たな「統制的理念」を創造する――というより、“向こうから来る” ものを逃さずキャッチする――努力が必要と思われます。その際には、人類が経験してきた宗教的な「D」,ブロッホが見出したような芸術的な「D」の予感も、おおいに寄与するにちがいない。
ただし、その「理念」はいかなる意味でも “設計図” ではないし、“目標” ですらないかもしれない。
その場合に、「アソシエーション」とは、いま行なわれている「アソシエーショニスト運動」に限らない・歴史的広がりをもった幅広い概念として考えてゆくことができるのかもしれません。
【90】 後記――柄谷さんは正しく述べていた......
このレヴューで私は、つぎの独自主張をしてきました:
①柄谷氏の「交換様式D」は、他の「交換様式」と同様に、物質的・経済的(および政治的)な交換の形態であって、たんなる想像上・観念上のものではない。他の「交換様式」と同様に、その「観念的な力」は、経済的・政治的な「ベース」から生じてくる。
②「交換様式D」は、「交換様式A」の高次元での回復であるというよりも、「原遊動性U」を高次元で回復するものである、と言うほうがよい。
――この2点を、私は柄谷理論の “修正” として折々に述べたのでした。ところが、“修正” の必要はなかった‥‥
じつは、柄谷氏自身が 2014年初版の『帝国の構造』で、この2点を、そっくりそのまま述べておられたことを最近知ったのです↓。文意はまったく明確ですから、あえて説明を加える必要もないでしょう。
『定住以前の遊動性を高次元で回復するもの、したがって国家と資本を超えるものを、私は交換様式Dと呼びます。それはたんなる理想主義ではありません。それは、交換様式A(互酬)がそうであったように、「抑圧されたものの回帰」として強迫的に到来します。いわば「神の命令」として。したがって、それは最初、普遍宗教という形をとってあらわれたのです。
しかし、交換様式そのものは宗教ではない。それはあくまで経済的な交換の形態です。交換様式Dにおいて、何が回帰するのか。定住によって失われた狩猟採集民の遊動性、すなわちそこに存する「自由の相互性」です。そして、それを回復させる衝迫は、歴史的にいつも存在し働いている、と私は考えています。それを経験的な実在として提示することはできませんが、少なくとも、理論的に考えることはできます。』
柄谷行人『帝国の構造』,pp.69-70.
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!