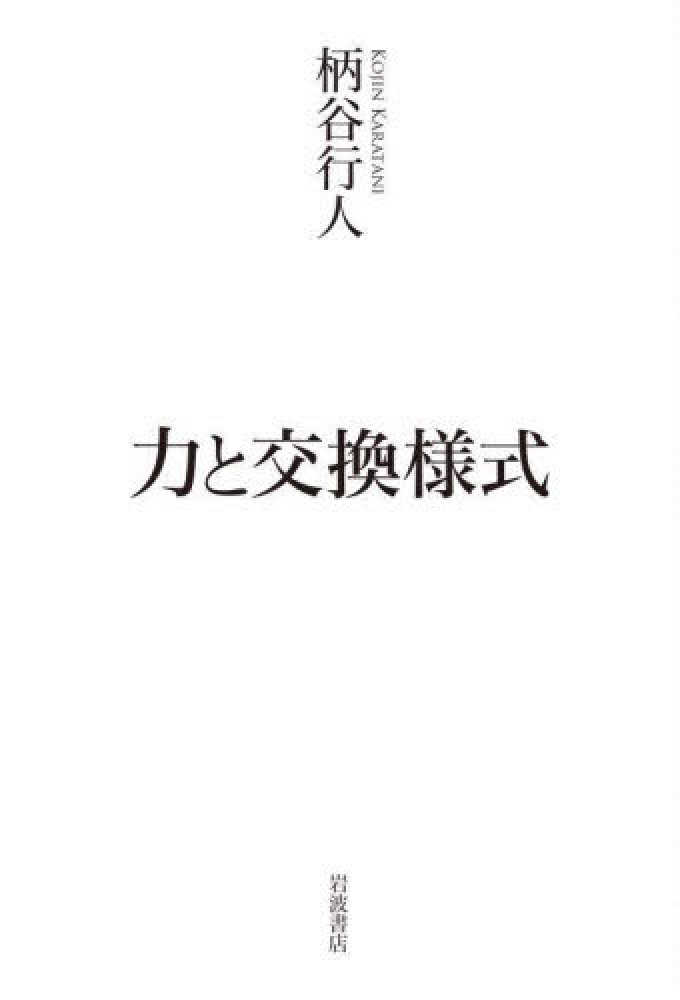インド・ブッダガヤの「大菩提寺」
【79】 「交換様式D」の先駆者たち
――ブッダと「宗教的観念の切断」
『中央アジアの草原地帯を原住地とした遊牧民のアーリア人〔…〕は、』北西インドに侵入・定住したあと、『前1000年頃からガンジス川流域に移動した。そこで〔ギトン註――先住民に対する〕アーリア人の支配体制を固めるために、バラモン(司祭者階層)を最上位とするカースト制を形成した。』この『身分秩序を支える宗教的イデオロギーがバラモン教であった。
しかし、』この社会『体制は、前7世紀頃から崩壊しはじめた。ガンジス川流域に、商工業の発展とともに 16の都市国家が生まれ、争うようになった〔…〕カーストでいえば、クシャトリヤ(政治・軍事階層)やヴァイシャ(商工業者)が力を持つようになったことを意味する。すなわち、カースト制とバラモン教がその権威を失いはじめたのである。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.183-184.
もっともその間、「バラモン教の内部でも、バラモンがたんに祭祀を司る役割だけになっていることを批判し」、内面的思索による真理の探究を進める動きが起きた。「宇宙の根源〔…〕、普遍的な真実、不滅なものを追求するウパニシャッド哲学が出現した。〔…〕宇宙の根源であるブラフマン(梵)と人間の本質であるアートマン(我)〔…〕が究極的に同一であることを認識すること(梵我一如)が真理の把握であり」、それによって「輪廻 りんね」と「業 ごう」から逃れて「解脱」に達することができると考えた。
ところが、その後、前8世紀以降に出現した思想家たちは、ウパニシャッドも含めたそのような思想的伝統を切断しはじめた。ちょうど、中国で「諸子百家」が輩出した時期と重なっている。インドでも、「唯物論者、不可知論者、運命論者、一切の道徳・宗教を否定する者などが出現した。」ブッダも、この動きに連なっている。仏教側では、マハーヴィーラ(ジャイナ教の祖と云われる)ら6人の自由思想家を「六師外道」と呼んでいるが、ブッダも、宗教的伝統を否定しその外部で思索したという意味では「外道 げどう」のひとりなのである。(柄谷,p.184)
さて、このあと柄谷氏の把握する「ブッダの思想」像が述べられるのですが、それは日本の仏教で言われていることとは大きく異なります。正反対と言ってもよいほどです。心して向かっていただきたいと思います。
手塚治虫『ブッダ』より。 .
上で述べたように、カーストを中心とする当時の古代的社会体制を支えていたのは、バラモン教とその枠内での哲学的世界像・死生観です。その核心に「輪廻」と「業」の体系があります。思想家たちは、「輪廻」と「業」の体系から脱却しようとして、人里離れた森林に隠棲し、衣食を断って、現存社会体制から無縁の「真理」の境地に達しようと努めました。しかし、「輪廻」からの「解脱」という目標じたいが、「輪廻」というバラモン教の宇宙観・タヒ生観を前提としています。そこでどんな「真理」を獲得しようと、伝統的思惟が前提にある以上、古代的社会体制を支えるものにしかならないのです。だからこそ、「真理」と合一したとされる者が人間社会に戻ってくると、「覚者」として尊敬され、多くのお布施や寄進が集まります。「覚者」を頂点として、カースト的社会体制が再生産されるのです。「解脱」によって現存社会体制と手を切ったかのように言いふらしながら、その実、社会体制を再生産している。それというのも、人間が他の人間すべてと手を切ることなど、できるわけがないからです。
ブッダが紆余曲折と彷徨ののちに悟ったのは、このようなことをいくら繰り返しても、「輪廻」と「業」の、つまり抑圧的な社会秩序の・しがらみから脱け出すことは無い。むしろ、他の人との関係でそれを強めてしまうということでした。そこで彼が実践しようと決意したのは、他の人間すべてとのつながり、生き物とのつながりを正面から認め、他者とのつながりにおいて自己を知ること。しかし、“他者と自己” というようなことも含めて、いっさいの哲学的思惟を否定し斥けること。なぜなら、いかなる哲学的思弁も、進めていけば必ず伝統的観念に達することになり、その呪縛から逃れるすべを奪ってしまうからです。こうしてブッダは、「輪廻」も「業」も否定したのです。
シャカ族の城主の王子であったブッダは、29歳の時に王宮を捨てて森林に入り、当時のバラモン修行者と同様に修業したが煩悩を超えられなかった。そこで苦行を放棄して放浪するうち、35歳の時にブッダガヤの菩提樹下で「悟り」を開き、人びとに説きはじめたと云われています。つまり、「王・祭司としての訓練を受けたが、それに満足できず放棄して放浪していたときに《啓示》を受けた」という経歴が、ゾロアスターと共通しています。(柄谷,p.185)
【80】 ブッダ:衝撃の「悟り」と「D」の開示
『ブッダの「悟り」は、「梵我一如」のような思弁的な事柄とは無縁であった。彼の思想は、〔…〕バラモン教あるいはウパニシャッド哲学を受け継ぐものではなかった。その逆に、彼は、業・輪廻・解脱というような・カースト制度を根拠づける〔…〕観念を斥けたのである。
インドラの網 https://nichigetu.b-tama.com/photo08.html
たとえば彼は、輪廻するとされる「自己」なるものの存在の同一性を疑った。』われわれは瞬間ごとに消滅し、別の存在になっている(「刹那滅」)のだと彼は言う。『そもそも、社会つまり他者・との関係なしに存在するような自己などは無い(「インドラの網」)。だからといって、彼は自己があるかどうかというような思弁的な問題に向かうこともなかった(「非有非無、非生滅非無生滅」)。彼の「悟り」は、バラモン的階級制度を否定する、倫理的な転換にあったというべきである。
輪廻からの解放は、思弁的問題ではなかった。それは社会体制を変え、平等・自由を実現するために不可欠であった。実際ブッダを支持したのは、抽象的な「苦」ではなく具体的に生存の「苦」を感じている女性、商人、シュードラ、不可触賎民であった。ブッダが説いた「慈悲」は具体的なものであった。また彼は〔ギトン註――開悟の後の布教においても〕国家に依存することなく遊動生活をし、自分らのアソシエーション(僧伽 サンガ)※を作ろうとしたのである。
生前において、ブッダの言葉と行為が、支配階層あるいは知識人層に影響を与えることはなかった。しかし、のちに、彼らによって受け入れられるようになるとともに、ブッダの言行は、バラモン教とウパニシャッド哲学の延長線上において解釈されるようになった。そのとき、仏教は思弁的・形而上学的な体系となった。しかし、それは、ブッダとは別のものだというべきである。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.185-186.
註※「山窩」と「僧伽」: 日本にも定住生活を拒否する社会集団「山窩」が戦後はじめまでいたことを(19)[【59】タイトル上]で触れたが、「山窩」の語源は「僧伽」ではないか。江戸時代の差別緊縛社会に統合されることを嫌った人びとが、おそらくは古くからあった遊動民集団に意識的に加入して、アソシエーションを形成したのが「山窩」の起源ではないだろうか。
その後インドでは、前4世紀末に侵入したアレクサンダーのギリシャ・マケドニア軍を駆逐したマウリヤ王朝の第3代アショカ王は、「インド全域に支配を広げたうえで、仏教を国家統治の原理として採用した〔…〕。インドに初めて諸国家を統合する[帝国]を造るためであった。」「その時、ブッダの創始した宗教は、〔…〕インドにおける帝国の宗教となった」。(柄谷,pp.186-187.)
つまり、ブッダが「啓示(開悟)」によって創始した交換様式Dの宗教は、彼の死後に知識階層による再解釈を受けてA,Bの要素を濃厚にし、ついでアショカ王による国教採用で、決定的に交換様式Bの宗教、すなわち「世界宗教」となったのです。以後、仏教は「北回り」「南回り」の各径路をたどって、「鎮護国家」の宗教として各国に受け入れられていったことは周知のとおりです。
敦煌莫高窟・第285窟、箜篌(ハープ)を弾く飛天。
https://avantdoublier.blogspot.com/2012/12/blog-post.html
『古代に各地で起こった普遍宗教的運動は、〔…〕次の点で共通している。それは、交換様式BとCに抗して、Aを “高次元” で回復するDの強迫的な到来である。』普遍宗教中の「D」は、外部の『BやCによって抑えこまれたり、自ら堕落し〔ギトン註――てB・C化し〕たりしたが、〔ギトン註――「D」の衝迫が〕完全に消えてしまうことはなかった。
Dの出現は、一度だけでなく、幾度もくりかえされる。それは多くの場合、普遍宗教の始祖に帰れというかたちをとる。たとえば、千年王国やさまざまな異端の運動がそうである。
しかし、産業資本主義が発展した社会段階では、Dがもたらす運動は、外見上宗教性を失った。』しかし、「科学的」と称する『社会主義の運動も、根本的に交換様式Dをめざすものであり、その意味で普遍宗教の性格を保持しているのである。
とはいえDは、それとして意識的に取り出せるものではない。「神の国」がそうであるように、「ここにある、あそこにある」と言えるようなものではない。またそれは、人間の意識的な企画によって実現されるものでもない。それは、いわば “向こうから来る” ものだ。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.187-188.
【81】 現代の世界宗教と「交換様式A・D」
『晩年のマルクスとエンゲルスはそれぞれ、『ユートピアから科学へ』で述べたのとは異なる観点から共産主義を見ようとした。〔…〕マルクスはその鍵を氏族社会に、エンゲルスはその鍵を原始キリスト教に見いだしたのである。〔…〕彼らがこの時考えたのは、事実上交換様式Dという問題であった。Dは、A・B・Cが経験的に実在するように見えるのに対して、たんに観念的・想像的なもののように見える。実際、それは宗教的・神学的な問題として扱われてきた。しかし、〔…〕Dが宗教的だというのは〔…〕正確ではない。なぜなら、いわゆる宗教には交換様式A・B・C・Dが同時に含まれているからだ。
今日世界宗教と見なされる諸宗教、諸宗派はすべて、交換様式Dに根ざしていると言ってよい。さもなければ各地に浸透する「世界宗教」たりえなかっただろうから。しかし、同時にそこにA・B・Cに由来する要素が〔…〕中心となっていることは確かである。いいかえればそこでは、Aが呪術(祈願=神強制)や相互扶助として、Bが教団組織の権力として、Cが経済的な動機として強く働いている。歴史的にそうであっただけでなく、現在もそうである。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.389-390.
「ソドムとゴモラから避難するロトと娘たち」
ヨース・デ・モンペルⅡ世 1581-1635 ©Wikimedia.
『旧約聖書』の「神」は、「多面的かつ矛盾をはらむものとして描かれている」。慈悲深いかと思えば嫉妬深く、子々孫々に至るまで祟りを及ぼすと、自ら宣言したりもする。「旧約聖書が重要なのは、神がDであると同時にA・B・Cとしてもあることを見逃さなかった」ことだ。「その姿勢は新約聖書にも受け継がれている。」(柄谷,pp.390-391.)
新約聖書に『描かれたイエスのふるまいを見ると、〔…〕BとCは一貫して厳しく斥けられているが、D〔ギトン註――が肯定されるの〕はいうまでもなく、Aも概して肯定されている。たとえばイエスは、病気を治 なお す、食べ物を創り出すなどの奇蹟を示し、また、共同体から排除された人たち〔徴税人,罪人,外国人など――ギトン註〕とも親しくつきあった。〔共同体の枠を超えるイエスの行動は、AではなくDと言うべきだろう――ギトン註〕
一方、彼は断固としてBとCを斥けた。政治的リーダーに祭り上げられそうになるとそれを避け、奇蹟を〔…〕見せてくれれば信じる、と迫られても決して乗らなかった。
ところが、歴史的に存在してきたキリスト教会の〔…〕“神” はむしろ国家権力の総元締め〔…〕であった。だからといって、そこにDが潜 ひそ んでいる可能性、また、今後においてそれが現れる可能性を否定することもできない。〔…〕
ゆえに、宗教一般を否定する必要はないし、そうすべきでもない。肝心なのは、それが交換様式から見て、どのように働いているかを見極めることである。その場合、交換様式Aから来る「力」に関しては、とくに注意が必要である。先ずそれは、「神強制」すなわち祈願や呪術につながる傾向がある。また、家族的な共同体に閉じこもることに結びつきがちである。そのため、宗教はしばしば前近代的迷信、あるいは「民衆のアヘン」として否定的に見られる。
しかし、交換様式A(互酬性)をたんに否定することはできない。それは人間にとって基礎的な在り方であるから。実際、晩年のマルクスはそれを「古代社会」に見いだし、共産主義を交換様式Aの “高次元” での回復と見なした。このとき、彼はそこに交換様式Dを見ていたといってよい。
一方、後期フロイトはそれを、無機的な原始状態を未来に回復※しようとする「反復」強迫として見出した。また、ブロッホは、それを “未意識” あるいは “希望” と呼んだ。〔…〕彼らはそこに、Dの到来を見たといってよい。
一方、BやCから来る観念的な力は、悪質であり強力である。それらは』現代においては『物神(資本)や怪獣(国家)なのだから。にもかかわらず、概してそれらは非宗教的なものだと考えられている。〔…〕非宗教的あるいは反宗教的と見える言説のなかにこそ、否定さるべき宗教性が見出されることが多い。たとえば、資本物神を無視したり嘲笑したりする人ほど、それに毒されていることが多いのだ。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.391-392.
註※「無機的な原始状態を未来に回復」: 「定住化」以前の「原始状態」を「無機的」と見ることの問題点は、(14)【45】で指摘した。むしろ、「原遊動Uの反復強迫」すなわち「超自我」の衝迫、と言うほうがよい。
「エリザベス女王(1世)に磁石の実験を披露するウィリアム・ギルバート」
アーネスト・ボード 1598 ©Wikimedia .
ここで柄谷氏が「非宗教的と見える……宗教性」と言っているのは、宗教団体のことではありません。自然科学・哲学・政治・経済にわたる現代のあらゆる言説のなかに潜む “隠れた宗教性” ―― “科学” の名のもとに主張される宗教性――のもつ危険を指摘しているのです。それは人を盲目にするからです。
『近世において、コペルニクスの地動説を支持して弾圧された科学者・哲学者らがこぞって、磁力を魔術として斥けた。つまりその時、磁力が現にあるのに、それを認めないことが “科学的” だと考えられたのである。それと同様に、今日の “科学的” な学者は、国家,資本,ネーションに存する “力” を斥ける〔見えないふりをする――ギトン註〕。つまり、“力” が働いているにもかかわらず、あたかもそれが無いかのように、その働きの結果だけを数学的に考察するのが “科学的” だと考えられているのである。』
柄谷行人『力と交換様式』,p.392.
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!