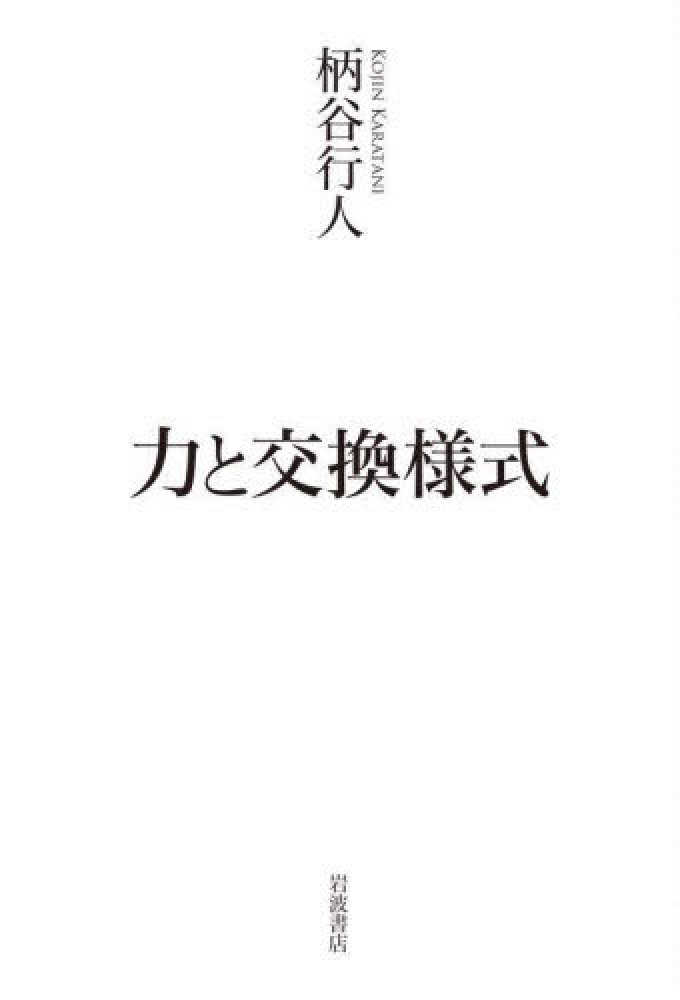メソポタミア最古の都市国家ウルクの遺構。現在は、乾燥化のために砂漠となって
いるが、都市国家当時は海辺の湿地だった。©SAC Andy Holmes (RAF)_MOD
【57】 「不平等よ、汝の名は国家なり」
前回の考察からすると、「狩猟定住」と「穀物定住」のあいだには大きな断絶があるように思われます。とくに、私たちの “島々の土地” に展開した先史をふりかえると、「縄文」と「弥生」という形で、生業・文化の大きく異なる集団が交替しているので、この断絶は大きく見えます。
これにたいして、「穀物定住」から、その後の「徴税国家」の形成に至る道は平坦であるように見えます。むしろ、スコットの筆致が示す勢いは、「徴税国家」の強制的な力によって人が集められ、「穀物定住」が成立したと言ってもよいほどです。なるほど、「徴税国家」が拡大し、また数多く族生と興亡を繰り返すようになる過程は、そのようなものだったでしょう。しかし、最初に「穀物定住」が地上に地歩を記した時から、最初の国家が成立する時までに 2000年ほどの時間が経過していることも事実なのです。
メソポタミア,エジプト,中国など以外の、最初から近くに「国家」のモデルができあがっている場合には、「2000年」の期間は、より短縮されます。日本の場合、弥生時代の初め(紀元前10世紀ないし紀元前4世紀)から「徴税国家」の成立(紀元後6~7世紀)まで、短く見れば 800年、どんなに長く見ても 1700年です。それにしても、「穀物定住」の始まりと「徴税国家」の成立は、同時ではありません。
「狩猟定住」時代の「自由・平等」と幸福な豊かさに感動し、「穀物定住」以後の過重な労働、「徴税国家」のもとでの不平等と奴隷的拘束を残念に思うとき、後者は、人びとが自然にそうなったとかそのように “発展” したのではなく、何らかの力に強制されて、望まざる境遇に陥れられたのだ――と考えたくなります。しかし、「国家」は――先史的な社会を、古代帝国や近代の西欧資本主義国が直接征服した場合を除いて――外からやってきた力ではなく、人類の “中から” 誕生したのです。
結局のところ、「穀物定住」から「徴税国家」への移行は、徐々に進行したと考えるほかはありません。「穀物定住」社会で、穀物の “徴税作物” としての特性に気づいた「首長・祭司」層が、これを生かせば自分たちはもっともっと有利になる、と考え、そういう方向に努力して、他の人びとを被支配者の地位に、場合によっては奴隷的境遇に落としめて、そうして少しずつ、“国家らしい” 形を整えていったのでしょう。
その過程で、すでに「呪術」として体系的に発展していた宗教が、人びとを従えるうえで大きな力を発揮したことは疑いありません。
そこで疑問として残るのは、「狩猟定住」時代の人びとにあった「自由・平等」の(観念的)力、「国家」の発生を抑え、「国家」の支配に抵抗する力は、どうなったのかということです。そうした抵抗力は、「穀物定住」に移行してもなお残っていたでしょう。弱まりはしたが、残っていた。「交換様式A」(互酬・贈与交換)は、「穀物定住」社会でも、また「国家」の下に包摂されて以後も、つづいてゆくからです。ただ、その抵抗力は、もはや狩猟採集民のように、支配をまったく受け付けないようなものではなかったでしょう。「徴税国家」時代ともなれば、「氏族」といえども「国家」に包摂され、「徴税」の重圧を受け入れつつも、そのもとで自分たち(「首長・祭司」層)の権益を主張してゆく。そういうものに変っていったのではないでしょうか。
キャッサバ。「コムギ国家」「イネ国家」があるのに
なぜ「キャッサバ国家」は誕生しなかったのか?
『最初期の国家で非エリート層にのしかかった負担〔…〕は相当に重かった。第1は、先にも指摘した〔ギトン註――穀物農業の〕重労働だ。一般に農業は、狩猟採集民と比べてはるかに手間がかかる。〔…〕人口圧がかかるか、なにかのかたちで強制されないかぎり、ほとんどの環境では、狩猟採集民が農業に移行する理由などない。
農業による第2の〔…〕負担は、密集からくる直接の疫学的影響だった。〔…〕最初期の国家の大半は、〔…〕流行病によって崩壊したとみてほぼ間違いない。しかも、もうひとつの疫病があった。穀物、〔ギトン註――治水灌漑工事や神殿建設の〕労働、徴兵というかたちで徴収される、税という名の国家の疫病だ。〔…〕
ほぼすべての古典的国家が穀物を基礎としていた〔…〕これは私の推測だが、集中的な生産、税額査定、収奪、地籍調査、保存、配給のすべてに適したものは穀物だけだったのだろう。〔…〕コムギは臣民を高密度に集中させるのに必要な農業生態を提供してくれる。
対照的に、キャッサバは塊茎が地中で育つ。ほとんど世話はいらないし、隠すのも容易〔…〕、地中に放っておいても腐らないので、向こう2年は食べられる〔…〕国家がキャッサバを欲しいと思えば、現地へ出向いて塊茎を一つひとつ掘り出さねばならない。〔…〕近代以前の「税務署員」の視点から作物を評価すれば、最も好ましいのは穀物、なかでも水稲で、〔…〕イモ類は最低ランクになるだろう。
こう考えてくると、国家の形成が可能となるのは、作物化された穀物が食生活を支配していて、替わるものがほとんどない場合ということになる。狩猟採集民、焼畑耕作民、海洋採集民などのように、生業がいくつかの食物網にまたがっているあいだは、国家が起こってくることは考えにくい。〔…〕
豆類はどうだろう。〔…〕障害となるのは、大半の豆類が無限成長性の作物で、生長しているかぎり実を摘みとることができる点だ。収穫期が決まっていないと、税務署員は困ってしまう。〔…〕
国家は、ひとたび確立されてからは、権力の基盤である農業生態学的環境を維持、増強、拡大していった。いわば「国家による景観の修正」だ。これには、〔…〕水路の補修、〔…〕掘削、耕作可能地への戦争捕虜の植民、耕作しない臣民への懲罰、焼畑や狩猟採集など課税対象とならない生業活動の禁止、さらには臣民の逃亡を予防する試みなどが含まれる。
〔…〕初期の国家が腐心したのは、課税可能な穀物を栽培する、見た目に分かりやすい、整然とした、ほぼ画一的な景観〔古代日本の条里制水田のような。――ギトン註〕をつくりだすことであり、その土地に大規模な人口を維持して、賦役や徴兵、そしてもちろん穀物生産に当たらせることだった。〔…〕
わたしは「国家らしさ」を制度的な連続体として捉えていて、』国家か、国家ではないか、『ではなく程度で判断するべきものだと思っている。ある政体に王と専任の行政スタッフがいて、社会的階級があり、記念碑的センターがあって、市が城壁で囲まれ、税の徴収と分配が行なわれていれば、〔…〕強い意味での「国家」になる〔明らかに国家と言える。――ギトン註〕。〔…〕
この本では国家を、税(穀物か労働力か正金かは問わない)の査定と徴収を専門とし、支配者に対して責任を負う役人階層を有する制度として考える。明確な分業(機織り、職人、聖職者、金属細工師、官吏、兵士、耕作者など)があって・高度に複合的かつ階層的な階級社会での行政権力の行使として国家を考える。〔…〕人によっては、〔…〕軍隊と防禦壁、巨大な祭祀センターないし宮殿があって、おそらくは王ないし女王がいるべきだと』いう、『もっと厳格な基準を適用するだろう〔…〕
初期国家の誕生を〔…〕領土があるということに加えて、特異的な国家装置である城壁、徴税、役人の存在を〔…〕重視してはどうだろうか。この基準で見れば、ウルクの「国家」は、紀元前3200年までには間違いなく確立されていたことになる。』
ジェームズ・C・スコット,立木勝・訳『反穀物の人類史』,2019,みすず書房,pp.19-22,111.
攻城と奴隷の捕獲。アッシリア? の画像石 メソポタミア初期国家の
人口増加の一部は、戦争による捕虜の連行だった。
スコットが挙げる「国家」のメルクマールのなかで、臣民の居住域を含む領域全体を囲む「城壁」は、なるほどメソポタミア、地中海岸、北インドと中国では認められるものの、日本や、世界の他の地域の初期国家にはありません。そこで、「徴税」・「役人(官僚組織)」・「階級分化(社会的分業)」が重要と考えられますが、これら3つは、たがいに結びあった現象です。徴税を実際に行なうには官僚組織が必要であり、専業的な官僚の供給源は、社会が階級分化してはじめて見いだされます。逆に、専業的な官僚はたいてい世襲され、それじたい特権階級を構成するようになります
『国家が興る』のに『必要なものは富』だが、『その富は、収奪と測定が可能な主要穀物と、それを育てるための、管理と動員が可能な人口というかたちをとる。
湿地など、非常に豊かだが多様性に富んだ地域は、移動性の人びとに生業の選択肢を数多く提供してくれるが、そうした選択肢は判別が難しく、多様なうえにそれぞれが一過性なので、国家をつくろうとしても、うまくいかない。』
ジェームズ・C・スコット,立木勝・訳『反穀物の人類史』,2019,みすず書房,p.22.
その意味では、初期の国家は、ヨーロッパ人の初期の植民者たちが新大陸アメリカで、原住民の「労働者をバラックに押し込ん」でこさえた「単作プランテーション」のようなものだと考えてよいのです。原住民たちは、豊かで多様な故郷の生業環境から切り離されて、バラックに住んで査定と管理を受けながら、ひたすら植民者のために利用されつくしたのです。(スコット,p.23.)
『初期の国家は、〔…〕さまざまな非自由労働』を『広範に用い』ていた。『女性を含む臣民を、富の一形態として家畜のように「管理」しようとしていた〔…〕多産と繁殖率の高さが奨励された〔…〕奴隷は犂をひかせる動物と同じ「生命ある道具」〔アリストテレスの言葉――ギトン註〕だった。〔…〕
中国で万里の長城が築かれたのは、蛮族を中に入れないためと同じくらい、中国人の納税者を外へ出さないためでもあった』
スコット,立木勝・訳『反穀物の人類史』,pp.24,26.
これは、日本の古代でも同様で、飛鳥・奈良時代の天皇や貴族は「百姓」の語を「おほみたから〔大御宝〕」と読んで臣民を尊びました。人としてではなく、あくまでも大切な宝物として珍重したのです。なお、「万里の長城」うんぬんの話は疑問ですが、古代都市(国家)一般の「城壁」(宮殿だけでなく、人民の居住地をも囲いこんでいる)について言うならば、たしかにそう言えるでしょう。
『メソポタミア沖積層の南部にあった湿地帯の生態系は、〔…〕富と町を生み出したが、国家が生まれるのはそれから 1000年以上も経ってからだった。湿地の生活の有り余るほどの多様性は、国家造りに望ましいものではなかった。
ナイル川デルタも、〔…〕人口は多く、生業資源は豊富だったのだが、国家の基盤とはならなかった。むしろ逆に、ここは国家に敵対し抵抗する地域だと見られていた。〔…〕初期のエジプト国家はナイルの上流で発生した。〔…〕デルタの人びと』は、『王朝としてのエジプトには属していなかったのだ。』
スコット,立木勝・訳『反穀物の人類史』,pp.118-119.
首枷をつけて運ばれる捕虜。アッシリア? の画像石。イラク国立博物館
『この時代〔最初の国家形成期――ギトン註〕のウルクが世界最大の都市だったことはほぼ確実だ。推定人口は 2万5000から 5万まで幅があるが、住民数が 200年で2倍になるなど、高い死亡率を考えれば、自然な人口増とは思えないほど増加している。〔…〕
ウルクの壁は 250ヘクタールの面積を囲い込んでいて、3000年近くあとの古代アテナイの2倍の大きさがある。〔…〕
国家が形成されたのが、沖積層に穀物とマンパワーを集中させ、それを支配、維持、拡大したからだとしたら、では、初期の国家はどうやってそうした人口 - 穀物モジュールを支配するようになったのか、〔…〕
耕作民が国家の臣民として集められた経緯の説明として説得力があるのは、気候変動だ。〔…〕紀元前3500-2500年の時期には海水レベルが急激に下がり、ユーフラテス川の水量が減少した〔…〕乾燥が進んだということは、河川〔デルタの支流――ギトン註〕が主流へと縮小し、残った水路の周辺に人々が急速に集まったこと、それと同時に、水を奪われた地域の土壌塩類化によって、耕作可能地が急激に減少したことを意味している。〔…〕人びとは衝撃的なほど集中し、それによって「都市化」が進んだ。灌漑が以前にもまして重要かつ労働集約的になり(たいていは揚水が必要になった)、掘削した運河〔ギトン註――の水〕へのアクセスは死活問題となった。〔…〕やがて、賦役や奴隷労働で掘削する網目状の運河システムが発達した。〔…〕
灌漑用水の不足は、水の豊かな場所にどんどん人を押し込め、〔…〕採集や狩猟などの多くを消滅ないし減少させた。〔…〕こうして、気候変動によって〔…〕都市化が強要され、人口の 90パーセントが 30ヘクタールほどの定住地に暮らすようになったことで、国家形成にとって理想的な 穀物 ‐ マンパワー・モジュールが強化された。〔…〕
これほどの数を維持できるのはここしかないという土壌に穀物とマンパワーが高い密度で集中したことで、収奪と階層化、そして不平等の可能性は最大化した。国家という形態は、この核となる地域を植民地化して生産基盤とすると、その規模を拡大し、強化し、ときにはインフラ(〔…〕運河など)を追加して、黄金の卵を産むガチョウを肥らせ、保護した。〔…〕こうした形態での強化は、エリート層のニッチ構築だったと考えることができるだろう。〔…〕
最初の官僚制国家が生まれる可能性が高いのは、こうした状況しかない。』
スコット,立木勝・訳『反穀物の人類史』,pp.113-114.
三内丸山遺跡。「大型竪穴建物」(上)と、その内部(下)。長方形プランの
一方の端に炉跡があり、内部構造は個人住居である竪穴建物と似る。集会場、
協働作業場、冬季の集団住居などと推測されているが、位階や権威を感じ
させる要素は無く、「三内丸山」住民の平等性を推定する根拠となっている
【58】 「原遊動U」への回帰:「交換様式A」
前節で「先史」がようやく終わりました。フロイトの「トーテムとタブー」以来、柄谷氏の引用する文献に遡って詳しく見てきました。「原遊動」時代から「穀物定住」→「国家」成立までは、マルクス/エンゲルスが「原始共産主義」を着想し、柄谷氏の「交換様式」論でも、「国家」以後の人類が無意識の「反復強迫」によって、繰り返し太古の「自由・平等」に立ち返ろうとする衝動を受けてきた、その元の時代です。人類の将来にかかわる「交換様式D」を理解するためには、ここでイメージをしっかり掴んでおく必要があると考えたわけです。
ちなみに、エルンスト・ブロッホの「希望」「未成のもの」〔⇒:(4),(6)〕とは、柄谷氏のいう立ち返りの衝動が、文学、童話、音楽、造形などのかたちで、間歇泉のように現出した痕跡にほかなりません。
このあとレヴューは、より本筋に戻って、歴史過程に関しては駆け足で、ピッチを上げたいと思います。
なお、この間に、縄文遺跡や古代文明への関心から拙文を読みはじめられた方もいらっしゃると思います。今後はやや古代から離れますが、先史・古代人の精神生活から、現代・将来にも有益な思想・教訓を、私たちは、どんなふうに構想することができるか? 現在のところ日本の思想家の最高峰といってよい柄谷行人を参照してみる‥‥そんな関心で読み続けていただけると幸いです。
さて、「狩猟定住」以後は「交換様式A」(互酬・贈与交換)の時代ですが、「交換様式A」じたいが、すでに過ぎ去った「原遊動U」――移動生活時代の原初的な「自由・平等」――へ立ち返ろうとする、あるいはその原則的エッセンスを保守維持しようとする衝動に由来する「力」であったと言えます。
その意味で、「定住」以後の人類にとって「原遊動U」は、現実の現在の活動に由来するものではなく、その「自由・平等」の慣習と観念は、多分に理想化された、文化伝統ともいうべきものだったのです。
クリストファー・ボームによれば、「定住化」以前の人間集団には、「平等化」の圧力が働いていたし、じっさいに「平等化」が実現していた。それとともに、相互に「自由」で「対等」な社会関係が支配していた。しかしそれは、“自然に” そうなっていたのではなくして、「社会的選択」すなわち進化の圧力によってそうなっていたのです。「自由・対等」とは、自己をも他者をも自由にしなければならないという「相互の縛り」(超自我)の結果でした。
「交換様式A」の社会――つまり「狩猟定住」以後――でも、基本的に同様の「相互の縛り」が働いており、むしろより強く働くようになっていたと言えます。ただし、「平等化」の「社会的選択」を支える条件は、もはや失われつつありました。大型猟獣を狩る機会は極端に減っていたからです。「平等化」の進化圧力は働かなくなり、「穀物定住」以後は、不平等な社会が成長して行きます。「自由・対等」は、相当に後代まで美徳とされていましたが、しだいにその内実は変質していきました。もはや「国家」に対抗してその支配を跳ね返すのではなく、むしろ国家の論理――交換様式B〔服従と保護の「交換」〕――を前提としつつ、不平等な社会のなかで他人に打ち克って、品位と「自律」を保持しつつ自分の意志を通す、そういうものになっていきました。武士、騎士のあいだで、狩りや弓矢の技 わざ などの「狩猟民」の活動が高貴なものとして尊ばれたのは、偶然ではありません。
「首長」「国家」以後の社会でも、「平等化」と「自由・対等」は、理想として生き続けることになります。その一つの現れが「交換様式A」だと言えるでしょう。
なお、世界の多くの場所で、人びとが「国家」の下に包摂されていったあとも、無視できない数の地域で、狩猟採集生活を続けた多くの人びとがいました。彼らは、たんに古い生活様式に固執したのではなく、「交換様式A」(互酬・贈与)など、「自由・平等」を維持する相互規制の倫理を厳格に守ったのです。そうした、ある意味で人類の “本性” を忠実に守りえた “正しい” 社会が、狩猟採集民として生き残ることができたと言えます。逆に、自然条件その他のおかげで狩猟採集民として生き残ることができた社会が、「交換様式A」などによって「自由・平等」を維持してきたと言ってもよいのです。
サンカ(山窩)。20世紀半ばまで日本にも、移動生活を送る人びとがいた。
柳田国男は、山窩を「原日本人」ないし縄文人と結びつけたが、憶測の
域を出ない。新河岸川南畑(現・埼玉県富士見市南畑)、1948年6月。
【59】 エルンスト・ブロッホ――
「太古からある・中断された道」の回復
『交換様式の観点から言えば、首長制社会は交換様式A、そしてそこから生じる力によって支えられている。この “力” は、定住化によって抑えられた原遊動性(U)の強迫的な回帰にもとづくものだ。そのため、Aを通して、原遊動性がある程度保持される。具体的に言えば、氏族社会・部族社会の人々は集団を形成しその中での規律に従いながらも、平等性と独立性(自由)を維持している。したがって、不満があれば出て行ってしまうし、また、首長といえども、失敗すれば解任されたり刹されたりする。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.123-124.
柄谷氏がここで「首長制社会」と言っているのは、おもに「狩猟定住」社会のことです。しかし、そこにはまだ「首長」はいませんでした。柄谷氏の叙述では、「狩猟定住」と「穀物定住」との相違――大きな、しかも重要な相違!――があいまいになっています。が、この箇所の行論では、おおむね「狩猟定住」について述べていると考えて大過ないでしょう。
『ブロッホは、未来の共産主義を、史的唯物論とは違って、「太古」からあり且つ中断されていた道を回復することだと考えた。〔…〕生産様式にもとづく史的唯物論では共産主義の必然性を示せないと考えていたからだ。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,p.387.
『たとえば、彼は、資本と国家を揚棄する可能性を「希望」と名づけた。この場合、希望は願望ではない。つまり、人の主観によって招来するものではない。「希望」とは、「中断された未成のもの」が、おのずから回帰することである。〔…〕
キリスト教にかぎらず「世界宗教」の根底にある「希望」は、〔…〕社会主義の中でこそ実現される、とブロッホは考えた。過去に中断されおしとどめられた「太古」の道が回復されることによって「未来」の道を開く。すなわち、「太古の道」が、向こうから到来する。
〔…〕共産主義は、資本主義の破綻によって必然的に生じるものではないし、また、たんに人間の認識と意志によって実現されるものでもない。そこには、人間の意志を越えた何かが働いている。神学であれば、それは、神の約束、あるいはイエスの再臨として語られるだろう。が、ブロッホは、未来の共産主義を、「太古」からあり且つ中断されていた道が回復されることだと考えた。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.380-382.
大峯・南奥駈道 東京志岳会 https://shigakukai.exblog.jp/240991463/
たとえば、「メールヒェン」とは、いつ・どこであったかも定かでない「太古」において・「未成」のまま中断されてしまった内実が、繰り返し人びとのもとに回帰する現れであって、それが「成る」ことを「おしとどめ」ている先史・から脱出し、神話と「説話」の呪縛から解き放たれることを志向しているのです。(ブロッホ『この時代の遺産』,p.179.)
『メールヒェンは、幸福を見出すために遙かな世界へ、叛逆的な未知のもののなかへ、圧迫からの解放に向かって、旅していくのだ。〔…〕
メールヒェンは、自分がそこへ追放されている民族的説話から脱したがっており、最初の「始め」のユートピアは、たんなる「太古」の先史的なものから脱したがっている。この「太古」とは、救いがたく過ぎ去り失跡してしまっているものか、さもなければ中断させられた未成の内実を内包したものかの、どちらかである。』
エルンスト・ブロッホ,池田浩士・訳『この時代の遺産』,水声社,2008,pp.176-177.
『ブロッホは共産主義の必然性を、キリスト教神学を手がかりにして考えると同時に、神学を斥けたのである。〔…〕
それはマルクス主義とは異なるものであった。が、マルクスとまったく無縁なわけではなかった。最晩年のマルクスは、ある意味で、共産主義を「太古からあり且つ中断されていた道」の回復として見ていたからだ。つまり、モーガンの『古代社会』を論じ、そこで、未来の共産主義を、アルカイックな社会の “高次元での回復” として見たのである。それは人間社会の歴史を、生産様式からではなく、交換様式から見ることであった。しかし、マルクス自身がそのことを自覚していなかった。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.387-388.
『定住以前の遊動的状態、つまり無機的な状態(U)〔…〕は定住化とともに失われる。このとき、無機的な状態に戻ろうとする「欲動」が生じた。フロイトはそれを「タヒの欲動」と呼び、快を求める欲動(快感原則)と区別したのである。〔…〕
つまり、フロイトがそこに見いだした「反復」強迫とは、〔…〕ブロッホがいう「未意識」に相当するものであった。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.386-387.
ブロッホの言う「太古からあり且つ中断されていた道」、すなわち太古の「自由・平等」を回復する道は、どのようにしたら、ふたたび開かれるのでしょうか? 柄谷氏によれば、それは人間の計画や意志や努力によって開かれるのではない。そこには、「人間の意志を超えた何かが働いている。」その・人間には予想しがたい「力」を解明するために、柄谷氏は、フロイトが発見した「反復強迫」という現象に手がかりを求めているわけです。
太古の「自由・平等」を回復しようとする「力」は、たしかに人間の「意識」を超えている。しかし、それは人間の無意識、衝動、「類」的記憶、ないし進化生物学的圧力、…そういったものに根拠をもっており、それゆえにそれは、宗教でも当為でもストーリーでも “弁証法的必然” でもなく、現実なのです。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!
Hans von Schrötter(1891-1965)