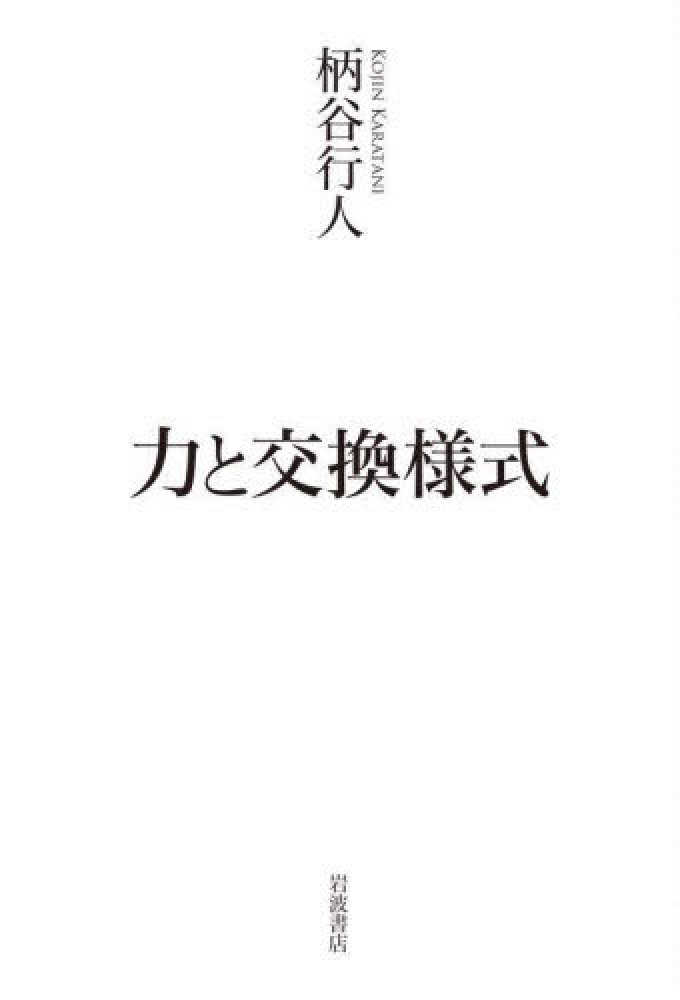墨子塑像。墨子紀念館。山東省、棗庄・滕州市。©劉軍_FOTOE.現代・大陸中国
では、墨子〔墨翟:c.470-c.390 BC〕は工匠であり先駆的科学者だったとして
(後ろに「墨子是一個労動者」と。)政治哲学を含む業績が見直されている
【76】 「交換様式D」の先駆者たち
――ソクラテスと「イソノミア」
ここで時間を少し巻き戻して、紀元前5世紀、インドのお釈迦さまと同時期に東西に現れた「D」の体現者:ソクラテスと墨子を扱います。
まずは西のソクラテスから。マックス・ウェーバーによれば、「預言者」とは、『旧約』の預言者や「黙示録のヨハネ」のような霊媒まがいの人ばかりではありません。ソクラテス、ブッダといった人びとも「預言者」なのです。
ソクラテスは、「黙示録のヨハネ」のように神の啓示を「幻視」したわけではないけれども、何か人間の意識を超えた巨きなものに動かされて行動したのは、『旧約』の預言者やイエスと異なりません。ギリシャ人は、このような「力」を「ダイモン」と呼びました。神ではないかもしれないが、人間でも理性でもない、人びとの外部にあって人を動かす魔的な存在、ということです。
『ソクラテスは、イオニアで自然哲学が栄えた時代にあった「イソノミア」(無支配)を、アテネにおいて、思想の形でとりもどそうとした哲学者である、〔…〕重要なのは、彼が自分の意志でそうしたのではなく、ダイモン(霊)のお告げに従ってそうした、ということだ。そのあげく、処刑された。その意味で、ソクラテスはむしろ、「神の委託を引き受けた」倫理的預言者であった、というべきである。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,p.180.
マックス・ウェーバーは、「預言者」を、「神の委託を受けてその意志を告知する媒介者」である「倫理的預言者」と、「模範的人間」として「みずからを範例として他の人びとに救済への道を指し示す」「模範的預言者」に分類した。前者は、イエス、ムハンマド等であり、彼らは「神の意志」を告知して、人びとが「倫理的義務」としてそれに服従することを要求します(柄谷,p.179.)。後者は、ブッダ、孔子、老子などであり、彼らが示すのは義務というよりは “お手本” であり、それに従うかどうかは選択の自由に委ねられているようにも見えます。が、じつは、その “選択” じたいが、コトバを超えた “お手本” の会得を必要とするのです。それをいわば “からだで” 解悟しないことには、入門さえ覚束ない難しさがあります。
もっとも、柄谷氏は、ウェーバーのこの分類を否定しており、ユダヤ以外の「預言者」は、「模範的預言者」であると同時に「倫理的預言者」でもあるとしています、したがって、以下では、この区別はとくに問題としないことにします。
『たしかに、イオニア〔エーゲ海を挟んでギリシャの対岸、現・トルコの西海岸――ギトン註〕の自然哲学者は、神話的・宗教的意味づけをすることなく、自然を説明しようとした。だが、それは彼らが宗教一般を否定したことを意味するものではない。擬人化されたオリンポスの神々を否定したとき、彼らは「唯一なる神=自然」という観念を見いだしていたと言える。
では、イオニアの自然哲学を受け継いだというべき・アテネのソクラテスはどうか。一見したところ彼も宗教的ではなかった。〔…〕が、彼の言動には霊媒的な面が垣間見える。たとえば、彼は「ダイモン」の声にしたがって行動した。議会には向かわず、広場に行って、人々と1対1で論議するようになったのは、そのため〔ギトン註――ダイモンの声に従ったため〕である。結果的に、彼はアテネのポリスに新たな「神」を持ちこんで伝統的な宗教を破壊したという廉 とが で処刑されたが、この嫌疑は必ずしも的外れではない。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.179-180.
ソクラテス裁判。
ところで、ソクラテスは、「交換様式D」の体現者としては、彼の言動のどんな点が注目されるでしょうか? 柄谷氏によれば、それはとりわけ「共同体からの個人の自立」を押し進めた点にあった、と言えます。前回見たように、イエスの場合には、「A」に対する無化の訴え(②)は、B,Cを強力に排撃したのと比べれば、それは教えの中心ではありませんでした。とくに「共同体」に対する強い攻撃はイエスには見られません。そこで、「D」のその局面に関しては、ソクラテスが重要になるのです。
ソクラテスは、「共同体からの個人の自立」について、直接それを訴えたり説教したりしたのではありません。彼は、「問答法」という間接的な方法によって、ひとりひとりが自覚せざるを得ないようにしてしまう、というやり方で遂行したのです。このようなやり方をした場合、イエスのように直ちに過激派として指弾されることはないかもしれませんが、けっきょく人びとの反感を買うことになるのは同じです。ソクラテスも、最後は「民会」に訴えられて、市民の大多数の投票によってタヒ刑に処せられました。
「共同体からの個人の自立」というソクラテスの考えは、イオニアで自然哲学とともに発生した《イソノミア(無支配)》の思想に淵源しています。これについては、柄谷氏の前著『哲学の起源』が詳しいので、本書とともに、そちらからも少し引用してみましょう。
『ギリシャの場合、多数の都市国家(ポリス)は、部族社会の様態のままにとどまった。〔…〕国家として統合されることはついになく、最終的にローマ帝国に従属するに至った。その意味でギリシャでは、多数の氏族・部族を越える「国家」が形成されなかった』
柄谷行人『力と交換様式』,p.200.
たとえば、ペルシャ帝国との戦争〔前492-前449〕では、アテネ・スパルタを中心とする諸都市の同盟を組んで戦いますが、そこで結成された「デロス同盟」は、戦勝後にアテネとスパルタの仲たがいのために分裂し、「ペロポネソス戦争」と呼ばれる都市間戦争に突入します。ギリシャ諸都市の「連邦」は、つねに内部紛争の火種をかかえたものであったのです。
『ギリシャ人はアジアの中心部(バビロニア,エジプトなど)から最先端の文明を受け入れたが、選択的にそうしただけであった。つまり、アジア的な官僚制国家を忌避し、いわばその「生産力」のみを摂取したのである。
したがって、ギリシャの「民主主義」は、進んだ文明段階から来たもの〔…〕ではない。それは、モーガンが指摘したように、そこに氏族社会が濃厚に残っていたからこそ可能となった。〔…〕
その結果ギリシャでは、氏族社会の痕を濃厚にとどめる多数の都市国家が形成され』た。『彼らの統合を妨げたのは氏族社会の軛 くびき である。たとえば、アテネでは、紀元前5世紀中頃の立法※によって、市民の両親から生まれた子でないかぎり市民権が与えられなくなった。〔…〕ゆえに、アテネはいかに強国になろうと、その規模を拡大できなかったのである。また、ギリシャ本土からの植民によって建設された各地の都市も、母市から独立したポリスとなった。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.200-201.
註※「前5世紀中頃アテネの立法」:前499年ペルシャ戦争に勝利したアテネでは、ペリクレスの執権のもとで、市民の直接民主制機関「民会」が国政最高機関の地位を確立するとともに、すべての公職が市民(クジ引き)に開放された。しかし同時に、このようにオールマイティな権限を持つ市民資格は、出自によって制限されるようにもなったのであろう。
シャルル=オギュスタン=ヴィクトル・ドエル『息子の死の床におけるペリクレス』
1851年。ラ・ロシェル美術館。©Wikimedia. .
『そのなかで注目すべき〔…〕はイオニアに移動した人々である。彼らはギリシャ本土とは違って、商業や手工業の発展による新たな社会を形成した。そこでは、氏族社会に固有の自由・平等の原理を維持しつつ、なお且つ、氏族的排他性を超えてポリスを形成する道が開かれた。
そして、ギリシャの自然哲学はイオニアに始まったのである。それを受け継いだのがアテネのソクラテスであった。』
柄谷行人『力と交換様式』,p.201.
【77】 イオニアの「イソノミア」と
アテネのデモクラシー
ここで、『哲学の起源』のほうに移ります。『力と交換様式』の 10年前に出たこの本では、イオニア植民諸都市について、「交換様式D」が実際に実現されていたかのように、かなり理想化して書かれています。しかし、それだけに古代イオニアの政治理念「イソノミア」とはどういうものなのか、具象的なイメージでつかむことができます。
そして、アテネでソクラテスが主張した「共同体からの個人の自立」とは、その継承にほかならないこと、また、それを主張するのに「問答法」という・あの奇妙なやり方を用いた理由も明らかになるでしょう。
『古代世界の各地に発生した都市国家は、相互の抗争を通じてアジア的な専制国家に帰結している。ギリシャでそうならなかったのは、〔…〕それを否定する原理があったからだ。それが、イオニアから来たイソノミアの観念である。〔…〕
イオニアの諸都市』は『氏族的伝統をもたない植民者たちによって形成された〔…〕そこでは、人々は血縁的なつながりや拘束から自由であった。それは、そこに生まれたというだけで個人がその “贈与” に対して報いなければならないというような、互酬原理から切れていたということである。〔…〕彼らはポリスに所属することを自発的に選んだ。ポリスはそのような盟約(社会契約)によって成立したのである。彼らの忠誠は血縁ではなく、盟約に向けられていた。
彼らの盟約は、アポロンのようなオリンポスの神々の下でなされた。〔…〕イオニアにおけるポリスの神々』は『古い氏族神ではなく、外来のオリンポスの神々であった〔…〕ギリシャにあってポリスの原理がまず確立されたのは、古い氏族社会が残存したところではなく、逆にそれがないような植民市においてであり、それが後にアテネやその他のポリスに波及していったのである。〔…〕
定住化とともに成立する氏族社会は、拡大するにつれて、その内部に深刻な不平等・対立を生みだす。それを解消する手段の1つが植民であった。〔…〕植民を通して、氏族社会に遊動性が回復されるといってもよい。〔…〕イオニアの諸都市において回復されたのは、氏族社会に先行するような遊動民のあり方である。〔…〕彼らが遊動性を回復したのは、広範囲の交易や手工業生産に従事することを通じてである。〔…〕
イオニアでは独立自営農民が主であり、大土地所有者はいなかった。その原因は使役可能な他者がいなかったことにある。土地を持たない者は、他人の土地で働くより、別の土地に移動したのである。〔…〕イオニアでは奴隷制生産に依拠することが無かった。大量の奴隷を獲得し、かつその反抗や逃亡を阻止するためには軍事的な国家でなければならないが、イオニアのポリスはそのような方向に進まなかった。〔…〕
イオニア古代都市エフェソス、アルテミス神殿の遺跡。 ©Wikimedia.
イオニア人の交易は、国家的ではなく、私的交易であった。それは商工業者のネットワークによってなされた。イオニアのポリスは、ある意味で、このような商工業者たちの評議会なのである。
国家による交易の独占がない場合、交易の利潤は平準化される。したがって、市場経済や交易がただちに格差をもたらすわけではない。アテネで貨幣経済によって階級分解が進んだ〔…〕ような・不平等や支配-被支配の関係は、イオニアには生じなかった。いいかえれば、イソノミア(無支配)が存在したのである。
もし、あるポリスの中に不平等や支配-被支配関係が生まれるならば、人は別の所に移動すればよい。その意味で、イソノミアは根本的に遊動性を前提しているのである。さらに〔…〕新たな遊動性をもたらしたのは商工業の発展である。
イオニアでは、交換様式Aおよび交換様式Bが交換様式Cによって越えられ、その上で、交換様式Aの根元にある遊動性が高次元で回復されたのである。それが交換様式D、すなわち自由であることが平等であるようなイソノミアである。
アテネのデモクラシーが現代の自由民主主義(議会制民主主義)につながっているとすれば、イオニアのイソノミアは、それを超えるようなシステムへの鍵となるはずである。』
柄谷行人『哲学の起源』,2012,岩波書店,pp.36-39,41-42.
↑この前著では、柄谷氏はイオニアの植民市社会を理想化しすぎているきらいもありますが、《イソノミア(無支配)》という「交換様式D」の一面を描いた概念図として読めば、解りやすいスケッチになっていると言えます。
そこで問題は、この《イソノミア》をアテネで実行しようとしたソクラテスへのつながりです。
『共同体に内属する状態では、真の意味での個人は存在しない。そこから出たときに初めて、ひとは個人となる。そのとき初めて「自己」が見出され、また「倫理」が問われるのである。』ところが、『アテネでは、そのような問題は存在しなかった。なぜなら、そこでは個人は氏族的段階以来の共同体から自立していなかったからである。
一方、さまざまな共同体から出てきた植民者からなるイオニアでは、最初から「個人」が存在した。イオニアのポリスは、そのような個人の「社会契約」によって成立した。ここでは、個人は伝統的な共同体からは自立していたが、自ら選んだポリスに対しては忠実であった。』そこでは、ポリスへの所属は『個人の意志によるので、そこに生まれたという運命によってではない。だからまた、そのポリスが不平等である〔ギトン註――不公平だと感じる〕ならば、人はそこを出たのである。イソノミアは、このようなポリスにおいてのみ可能な原理である。』
柄谷行人『哲学の起源』,2012,岩波書店,pp.57-58,41-42.
『ソクラテスとアルキビアデス』
1813-1816 Christoffer Wilhelm Eckersberg
「ソクラテスが人びとの眼に、アテネの社会規範に対して最も挑戦的な存在」だと思われたのは、彼が、アテネ市民として、つまり「公人」として「生きることの価値を否定した」からである。
ソクラテスは、裁判での『弁明』において、「ほんとうに正義のために戦おうとする者は、私人としてあることが必要であって、公人として行動すべきではない」、しかもこれは、彼の「ダイモン(霊)」が命ずるところなのだと言う(柄谷『哲学の起源』,p.184.)。この言は、ひとかどの市民として、誇りを持って政治や裁判に参与している市民たちの自尊心を、深く傷つけるものでした。そして、心底から憤らせたのです。なぜなら、被告人であるソクラテスがそう言うことは、君たちのしている政治活動、また現に今やっている私の裁判は、正義に叶うものではない、正義に反することを君たちはしているんだぞ! と言うに等しかったからです。
「ほんとうに正義のために戦うことは、公人としてではできない」――そこまでソクラテスが言い切るとき、彼は、市民たちが誇るアテネの民主主義制度を否定し、市民たちの公務参加の「徳」を侮辱した、と市民らは感じた。「ソクラテスは、民会や法廷で活躍し権力を得ることを、価値とは見なさなかった。」(柄谷『哲学の起源』,p.185-186.)
ふだんからソクラテスは、一般のアテネ市民のように民会へ行って弁論を闘わせたり、政治権力を求めたりはしなかったのです。彼は、「民会に行くかわりに、アゴラ〔広場,市場〕に行った」。
『アゴラには、決して公人とはなりえないような人々、すなわち外国人,女性,奴隷がいた。民会にデモクラシーがあるとすれば、アゴラにはイソノミアがある。つまり、アテネでは、アゴラにしかイソノミアはありえなかったと言ってもよい。ゆえに、もっぱらアゴラで活動することによって、彼はそうと知らずにイオニア的な思想を回復させたのである。』
柄谷行人『哲学の起源』,2012,岩波書店,p.198.
アゴラでのソクラテスの活動とは、言うまでもなく、そこにいる市民の誰彼をつかまえて「問答」をすることですが、彼の問答とは、意見の違う者どうしが甲論乙駁する通常の問答(議会での民主的議論)とは違います。ソクラテス自身は、あたかも自分の意見が無いかのようにふるまい、ただただ相手の意見に賛成して、それを延長して行き、挙句の果てに相手の最初の意見と正反対の帰結に持って行ってしまうのです。これをやられた市民たちは、バカにされたと思って激怒しました。ディオゲネス・ラエルティオスの『ギリシャ哲学者列伝』には、市民たちはソクラテスを殴ったり、髪を引っぱったり、足蹴にしたりしたが、彼はじっと堪えたと書かれています。
しかし、ソクラテス自身は、バカにするためにやっていたのでは勿論なく、彼らが自ら自覚するようにするために、こうしたやり方を用いたのです。それというのも、彼が人びとに理解させようとしていたのは、人びとが自ら発見する以外には伝えようのないことがらだったからです。
『アルキビアデスを快楽の抱擁から引きはがすソクラテス』
1791 Jean-Baptiste Regnault, Musée du Louvre.
『ソクラテスが開示したのは、公人や私人、自由民や奴隷という区別を越えて存在するような「徳」である。この「徳」は、外から教えられるような知識や技術ではない。各人が、公人でも私人でもない「自己」〔つまり、自立した「個人」――ギトン註〕であることを悟ることによってしか得られない。〔…〕自覚は、それを妨げている虚偽の前提を破ることによってのみ可能である。〔…〕
ソクラテスの問答法は、相手がもつ虚偽の前提を論破し自己撞着に追いこむが、〔…〕相手が「自覚」に達するかどうかは分からない。〔…〕したがって、この問答には〔…〕命の危険がともなう。〔…〕
しかし、〔…〕ソクラテスが考えていたのは、あくまでポリスの問題、すなわち政治の問題であった。それは公人と私人の二重世界を廃棄することである。ただ、それは一人ひとりの自覚という契機なしにありえない、と彼は考えたのである。そのとき、公人でも私人でもない「自己」が問われるのである。
ソクラテスはデモクラシーに対して批判的であった。〔…〕アテネの人々はソロンの改革以来、イオニア的なイソノミアの精神に触発されてきたが、現実には、イソノミアの堕落した形態であるデモクラシー(多数派支配)にとどまっていた。それは、公人と私人の分割、精神労働と肉体労働の分割をけっして越えることはなかった。そのなかでソクラテスは、デモクラシーが前提とする公人と私人という二重世界を解体しようとした。それは、イソノミアを回復することにほかならない。
ソクラテスはそのことを、そうと意識することなしに行なった。すなわち、ダイモンの指令に従って行なったのである。その結果、彼は貴族派に嫌われただけでなく、民主派によって告訴された。』
柄谷行人『哲学の起源』,2012,岩波書店,pp.199-201,216.
【78】 「交換様式D」の先駆者たち
――抹消された思想家「墨子」
『多数の都市国家が争った春秋戦国時代〔前8-前3世紀〕に、諸子百家と呼ばれる自由思想家たちが輩出した。彼らは各国にその思想を説いて回った。それはこの時期どこでも、〔…〕氏族的共同体の伝統に依拠してやっていけなくなり、新たな思想が必要とされたからだ。〔…〕
諸子百家のなかで私が特筆しておきたいのは、墨子である。〔…〕ここで、墨子が説いた 10個のキー・コンセプト(『墨家十論』)のなかから、2つを取り上げておこう。
まず、1つは「兼愛」である。〔…〕墨子によれば、孔子の言う 仁 は差別的である。〔…〕それは家族や長たる者を大切にする「偏愛」でしかない。これは、交換様式で言えば、堕落したAである。また、孔子の言う 仁 は、国家の政策として実現されるべきものだ。すなわち、それはBとつながる。ゆえに、孔子の思想は国家と直結するものであり、官吏をめざす者にとって不可欠な学となった。
それに対して、墨子の言う「兼愛」は、博愛というよりもむしろ、恵まれない者への愛を説くものだ。これは、交換様式Aの高次元での回復である。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.181-182.
墨子の考案した兵器の復元「藉車」。3人以上で操作し、炭火を投擲する。
柄谷氏が引用書目とする『墨子十論』は、全5部からなる書『墨子』の第2部の通称で、そこに「兼愛」「非攻」が収められています。なお、第3部は、論理学・幾何学・光学、第5部は、土木・冶金・兵器工学,守城術,戦術論,政治制度論を扱っています。
「兼愛」の交換様式に関する柄谷氏の説明↑には、私は異議があります。「兼愛」は、柄谷氏が述べるような・「交換様式A」つまり「互酬交換」の回復なのだとしたら、「兼愛」を向けられた「恵まれない者」は、「お返し」をする義務を負うことになります。物質的に「お返し」をすることができなければ、労力で返す、それもできなければ、服従するほかはないでしょう。墨子の「兼愛」が、そのようなものだとしたら、AどころかBにもなりかねない(じつは、それこそが、Aが氏族社会の階級分化を止められない理由です)。孔子の仁以上にタテの支配を正当化することになります。
しかし、「兼愛」は、そのようなものではない。「互酬・贈与」ではなく、イエスの説く無差別な「隣人愛」に近いものでしょう。それは端的に、「Dの到来」と言うべきです。強いて「回帰」と言うなら、「原遊動Uの回帰」です。その意味で「Aの高次元での回帰」と云うのであれば、そう言っても間違えではない。が、紛らわしいです。「高次元」と言うだけでは、「A」そのままの再現とどこが違うのか分からないからです。
『「兼愛交利」とは、〔…〕墨子が唱えた倫理説。儒教批判を含んでいる。
墨子は、「天下の利益」は平等から生まれ、「天下の損害」は差別から起こるという前提に立ち、孔子による・仁にもとづく愛は、家族や長たる者のみを強調する差別的な愛(別愛)、限定的な愛(偏愛)であるとして批判し、自他の別なく全ての人を平等に、公平に隔たりなく愛すべきであるという博愛主義を唱えた。これが「兼 ひろ く愛する」、すなわち「兼愛」である。
兼愛は、結果的に互いの福利を増進することとなるのであり、そのことを「交利」と呼んでいる。こうして墨子は、互いに互いの利益を考え、実践することから道徳が成り立つことを説いた。』
Wiki:「兼愛交利」 .
以上が「兼愛」。単に精神的な「愛」だけではなく、「交利」、つまり物質的な利益の供与を含んでいると考えられます。これは「原遊動」状態には無かったことであり、「A」も、そのような普遍的で一方的な援助ではありませんでした。「交利」は、「D」を「高次元」のものとする一つの要素だと言えるでしょう。
墨子紀念館。守城設備の復元。
↓つぎは、「非攻」。
『もう1つ、墨子が掲げた重要な観念は「非攻」である。〔…〕反戦・平和を説くものである。墨子は言う。「人ひとりを刹せばタヒ刑なのに、なぜ百万人を刹した将軍が勲章をもらうのか」。しかし、〔…〕墨子は自衛のための戦争を斥けなかった。むしろ、積極的に軍事組織を作ったのである。また、防衛のための軍事技術も開発した。しかし、〔…〕墨子の言う「非攻」は単なる自衛ではない。それは、軍事的に無力な者を護り助けることをもっぱら意味する。いいかえれば、「非攻」とは、Bを拒絶することである。〔…〕
「墨家」〔墨子の創始した学派――ギトン註〕は、戦国時代において〔ギトン註――儒家とならぶ〕大きな存在となった。〔…〕まさにそれゆえに、秦の始皇帝によって、儒家とともに徹底的に弾圧されたのである。そのとき、法家の韓非子が唱えた法治主義が支配的な国家思想となった。〔…〕漢王朝では、儒家が復活し〔…〕法家と結びつき、国家的なイデオロギーを形成し』たが、反国家的な「墨家」が復活することは無かった。『墨家は秦以来、完全に斥けられたままであった。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.182-183.
「非攻」は、キリスト教的な・理念的な平和主義とは異なって、現実的な政策志向であり、それに基づく諸知識の体系だということが分かります。柄谷氏が「非攻」に注目するのは、現代国際政治への関心からです。柄谷氏は、「国際連合」の・ある部分――とりわけ、国連に集約される非国家的な国際運動――を、「D」の現れと見て注目しているのです。これは後ほど、該当の箇所で述べるでしょう。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!