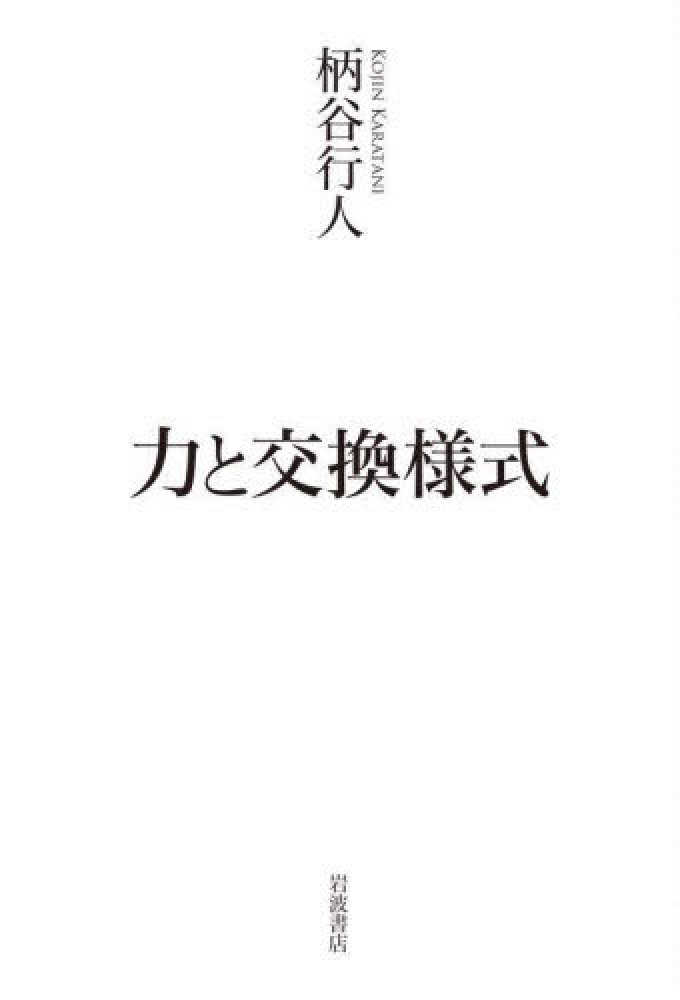そのころ、ある安息日に、イエスは麦畑の中を通られた。すると弟子たちは、
空腹であったので、穂を摘んで食べはじめた。〔マタイ12:1〕©まこっつ
https://www.pixiv.net/artworks/119335582
【63】 「交換様式A」と「D」――麦畑のイエス教団
ここで道草を喰って、福音書の一節を引いてみます。
1 ある安息日に、イエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは麦の穂を摘み、手でもんで食べた。 2 ファリサイ派のある人々が、「なぜ、安息日にしてはならないことを、あなたたちはするのか」と言った。 3 イエスはお答えになった。「ダビデが、自分も供の者たちも空腹だったときに何をしたか、読んだことがないのか。 4 神の家〔神殿――ギトン註〕に入り、ただ祭司のほかにはだれも食べてはならない供えのパンを取って食べ、供の者たちにも与えたではないか。」 5 そして、彼らに言われた。「人の子〔イエスの自称――ギトン註〕は安息日の主である。」
〔ルカによる福音書(新共同訳)6:1-5〕
他の福音書を見ると、『ルカ伝』にないイエスの言葉もありますから、追加しておきましょう:
27 そして更に言われた。「安息日は、人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。」
〔マルコによる福音書(新共同訳)2:27〕
7 「もし、[わたし〔神――ギトン註〕が求めるのは憐れみであって、いけにえではない]〔旧約ホセア書6:6〕という言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪のない人たちをとがめなかったであろう。」
〔マタイによる福音書(新共同訳)12:7〕
イエスの弟子たちは、通りがかりの麦畑――ちょうど稔りの季節だったのでしょう――から麦の穂を勝手に摘んで、モミを揉んで落としただけでムシャムシャと食べ始めました。それを見とがめたパリサイ人 びと がイエスの弟子たちを非難し、イエスがそれに反論しているわけですが、咎めた理由も、イエスの反論も、私たちの常識とは少しズレています。
他人の麦畑に入って、勝手に取って食べているのですから、私たちの常識ではドロボーですが、当時のユダヤの法では許されていたようにも考えられます。『旧約』の「申命記」には、次のようにあります:
25 隣人のぶどう畑に入るときは、思う存分満足するまでぶどうを食べてもよいが、籠に入れてはならない。 26 隣人の麦畑に入るときは、手で穂を摘んでもよいが、その麦畑で鎌を使ってはならない。
〔申命記(新共同訳)23:25-26〕
つまり、たくさん取って籠に入れて持ち去ったり、鎌を使って大量に刈り取ったらドロボーだが(「十戒」には、「盗んではならない」とあります)、その場で食べるぶんには、好きなだけ取ってよい。「思う存分満足するまで食べてもよい」とは、すごいですね。マルクスは『ゴータ綱領批判』に、共産主義のスローガンとして、
『能力に応じて働き、必要に応じて受け取る』
と書いていますが、『旧約』の法慣習は、それに近いとさえ言えます。空腹な人や、自分の畑を持たない貧民、流民には有難い法律です。
このような法慣習は、氏族社会の「交換様式A」が、「穀物定住」以後も残っていたのだと見ることができます。
とはいっても、‥‥『申命記』は、モーセの時代に書かれたとされる古い慣習法(「律法」)で、その時代はたしかに、国家成立以前の「氏族社会」でした。しかしその後、ユダヤ人(ヘブライ人)は「ダヴィデ王国」を建国したものの「ユダ王国」と「イスラエル王国」に分裂、それぞれがアッシリアとバビロニアに征服されたあと、ペルシャ帝国の下で、ようやく自治を認められる、といった苦難ののち、イエスの時代には、ローマ帝国の支配を受けていました。つまり、イエスの時代のユダヤは、「国家」成立後の・「国家」の支配下にあったわけです。ということは、『申命記』の慣習法〔※〕も、じっさいには形骸化していたのではないかと想像されるのです。
というのは、パリサイ人は、ほんとうは「人の畑の作物を盗むな!」と言いたかったのでしょうけれども、あえてそうは言わずに、論争になるのを見越して、「安息日」を盾にとって攻撃した――と見ることができるからです。「盗みだ」などと言えば、相手は『旧約』の律法をよく知っているイエス教団ですから、「申命記に、こう書いてあるのを知らないのか?」などと反論されて恥をかかされるに決まっている。だから、先回りして、「安息日」違反に引っかけようとした。そう見ることができます。
註※「『申命記』の慣習法」:じつは、もう一つ問題があります。『申命記』には「隣人のぶどう畑」「隣人の麦畑」と書いてあります。しかし、イエスたちはガリラヤからやってきた「よそ者」なのですから、「隣人の」ではなく、まったく赤の他人の畑を荒らしているのです。
『申命記』の規定は、やはり「共同体」の中での互酬性・相互扶助の精神に基づくものなのでしょう。「共同体」内の貧民や困窮者には許されていても、同じことを「よそ者」がやったらドロボーになってしまいます。そういうことからすると、「入るときは」と2度くりかえしているのも意味があるかもしれません。正当な理由があって「入るとき」に限る。畑を荒らす目的で入るのはダメだ、とも読めるからです。正当な理由があって「入るとき」とは、たとえば、畑の持ち主に頼まれたとき、収穫の手伝いに雇われたとき、などが考えられます。それにしても、収穫して籠に入れたぶん、鎌で刈り取ったぶんから取ってはいけない、としているわけです。
しかし、もしパリサイ人が、その点を根拠に、「おまえらはヨソ者じゃないか。おまえらがやっていることはドロボーだ!」とでも非難しようものなら、イエスは、「主の御前では、すべての人は隣人である」「すべて、聖書を信じる者は隣人である」「隣人どうし、助け合い、愛し合わなければならない」などと、滔々と自説を展開することでしょう。群衆が集まって来て、聞きほれるかもしれません。パリサイ人は、イエス教団の盗賊の実態をあばくつもりが、かえって布教集会を開催させてしまうことになります。だからあえて、ドロボーだとは言わなかったのです。「安息日」に引っかけて、煩瑣な律法問題に持ちこんだほうがパリサイ人には有利だし、一般の人には何の話だか分かりません。だから、そうしたのです。〔註終り〕
イエス教団の教義は、氏族時代の古い教義のエッセンスを単純化して主張し、「交換様式A」の原則を、どこまでも貫くことを要求した。そう考えることができます。「ダビデが、自分も供の者たちも空腹だった時に、〔…〕神殿に入り、〔…〕誰も食べてはならない供えのパンを取って食べ、供の者たちにも与えたではないか」「安息日は人のためにある。人が安息日のためにあるのではない」「神が求めるのは憐れみであって、いけにえではない」――つまり、イエスとパリサイ人のあいだの本当の争点は、「安息日」違反かどうかではなく、いっさいの社会的な拘束を無視してでも、神の前の実質的「平等」、遊動的な「自由」、血縁・地縁にかかわりのない「友愛」を貫くかどうか、ということだったと言えます。
「実質的平等」とは、能力のある者も、ない者も、必要なだけのものを手に入れることができる。全体が困窮しているときには、誰もが同じように欠乏を背負う。全体が豊かなときには、誰もが裕福である。そういう状態をいいます。
つまり、イエスの主張は、「国家」を超えているだけでなく、「氏族社会」ないし「共同体の掟」をも超えているのです。そうしたイエス教団の主張と行動は、「国家」と「共同体」の秩序を破壊する過激なものと見られるほかはない。しかし、柄谷氏の言う「交換様式D」とは、このような・氏族社会よりもさらに太古にあったであろう「未成の道」が、強迫的に復活することなのです。
「能力に応じて働き、必要に応じて受け取る」 というのは、「共産主義」経済の原理を表す標語ですが、これは、ある意味で狩猟採集社会の原理でもあります。ただし、狩猟採集社会の実体は、『ゴータ綱領批判』の「共産主義」とは大きく異なる点があります。狩猟採集社会は「共産」ではなく、そこには個人の「所有」があるからです。
その「所有」とは、私たちの知っている近代的「所有」ーーマルクス主義者たちの「私有」イメージはこれに近いーーとは異なったものです。しかし、共産主義の「共有」――つまり「私有財産の廃止」――とも、異なります。それをひとことで言えば、個人個人の「実質的に平等」な所有であり、常に平等化のために分配・再分配させる圧力に晒された所有です。
マルクスは、『ゴータ綱領批判』のような「定式」とは別に、たとえば『資本論』の「本源的蓄積」の節〔Ⅰ,24-7〕では、このような・平等な「個人的所有」について、資本主義を超克した後に現れる経済体制として述べているのです。このような「個人的所有」の平等性は、集団全体が、周囲の生態環境を「共同占有」(占取 besitzen)しているという事実に基づいています。「平等化」の圧力は、この「共同占有」という・個人の「所有」を成り立たせている本質的前提から発しています。
しかし、『資本論』で述べられた・この「個人的所有」の構想は、その後の共産主義・社会主義の公式においては生かされないままになってしまいました。が、マルクスはこの考えかけの構想を、忘れることなく温めていたことが、晩年の「古代社会ノート」には表れています。この点は、すでに触れていますので、ここでは繰り返しません。
【64】 「交換様式B」――神聖王権の成立
本題に戻りましょう。「氏族社会」の互酬的な「交換様式A」から、「国家」に自発的に服従する「交換様式B」への移行、ないしは、「国家」が「氏族社会」の抵抗を制圧して自らの支配下に組み込んでしまう過程が、問題になっていました。結論を先取りしていえば、それは、「遠隔地交易」と「世界宗教」によって、すなわち、「国家」が世界交通を支配するとともに、王の支配が宗教的次元を伴なった時に成就されたのです。
Gaston Goor
『国家の起源は、首長制を超えるような変化が生じたことにある。では、いかにしてそれがありえたのか。
史的唯物論では、それを生産様式(生産力と生産関係)から説明しようとするが、うまくいかない。なぜなら、国家の成立は、生産様式だけでは説明できない何か、つまり、経済的というより、観念的・宗教的と見える次元と絡んでいるからだ。それは、経済的な次元だけでは説明できない。〔…〕
社会人類学者A・M・ホカートは、』氏族社会の「首長」から国家の王へと飛躍する『この一歩を、「聖なる王権」という観念に見いだした。彼は、言語学者がとってきた比較歴史学的方法を採用して、ヨーロッパから太平洋におよぶ地域の君主制度を分析した。〔…〕たとえば、ヨーロッパの戴冠式と、フィジーの部族内における首長の即位式を比較分析することによって、そこに共通する、王が一度タヒに、神として復活する儀式を見いだした。ここからホカートは、君主制度は「聖なる王権」に由来する、と結論した。それは、国家という「統治機関の発明〔発生――ギトン註〕」にほかならない。
自分の手では何もせず、ただ単に存在するだけで離れた所から自分の環境に力を及ぼす――そういういわば太陽のごとき人物を考え出したことは、人類の歴史の中でもっとも重要なことの一つである。それは統治機関の発明にほかならない。太陽=人間という教義が君主制に与えた形態〔…〕の異常なる存続とそれらの驚くべき生命力が示唆することは、〔…〕君主体制にはわれわれがいまだに理解できない心理学的価値があるということである。〔A・M・ホカート,橋本和也・訳『王権』,2012,岩波文庫.〕
〔…〕人間の統治〔人間を「統治する」ということ――ギトン註〕を可能にする力は、人間から来るのではないし、また、近接的な物理的力によるのでもない。「離れた所から自分の環境に及ぼす力」とは、まさに “遠隔的” な力である。いいかえれば、霊的な力である。〔…〕
聖なる王権が民衆にとって「大きな魅力」となったのは、それが単に服従と奉仕を要求するだけではなく〔…〕保護・救済を与えると考えられたからだ。このとき生じたのは、被支配者が支配者に服従することによって保護・救済を得るというタイプの「交換」、すなわち交換様式Bである。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.117-120.
しかし、初期の「国家」は、メソポタミア初期の都市国家がそうであったように短命であり、また、しばしば首長制社会に逆戻りしました。たとえば、エドモンド・リーチによれば、北ビルマのカチン族は山地で移動性の焼畑農業を営む人びとですが、その社会は、世襲の首長が支配する統合的な「グムサ社会」と、世襲的階級差をもたない小集団分散型の「グムラオ社会」の2種類からなっており、この2つは「振り子のように交替している」というのです(関本照夫・訳『高地ビルマの政治体系』,1995,弘文堂)(柄谷,p.121)。
Kachin tribe depiction, 1900s. 池田光穂/さくらインターネット .
もっとも、柄谷氏によるリーチの読み方は図式的すぎるようです。リーチが「交替している」と言うのは、「グムサ社会」が「グムラオ社会」に変化し「グムラオ社会」は「グムサ社会」に変化する循環運動をしているという意味ではありません。「グムサ」「グムラオ」は、カチン族がもつ両極端の政治理念であり、社会秩序のモデルであって、個々の地域集団や成員は、両モデルのあいだを揺れ動いているのです。(⇒:池田光穂webpages)
たとえば、現在の日本の社会体制は、憲法だけを見れば「民主主義社会」に見えます。しかし、他方で現実を見て、世襲的特権が支配する利権社会だと批判する人たちもいます。彼らは、民主主義社会に変えていくことが理想だと思っています。逆に、権利ばかりを主張する「民主主義」は宜しくない。もっと縁故情実や家格といったものを見直すべきだと主張する人たちもいます。そこへ西洋の人類学者が調査に来て、「日本人の社会には、民主主義社会と縁故利権社会の2種類があって、両者は循環変化している」と言ったら、どうでしょうか?「バカを言え!」と怒鳴りたくなりませんか? カチン族の場合も、実像はそのようなものではないかと思います。
そういうわけで、「首長制社会に逆戻り」は図式的すぎる理解です。しかし、一応「国家」は成立しても、なお首長制の要素が残っていて、安定してはいない。そういう言い方はできると思います。
これを、交換様式の観点でいうと、首長制に後戻りしないような・安定した「国家」となるためには、交換様式Bが成立するだけでは足りないのです。柄谷氏によれば、Bに加えて交換様式Cの発展が必要だったというのです。
交換様式Cの発展、とくに異なる地域・部族とのあいだの「遠隔地交易」が拡大するとともに、「国家」は、他の「国家」や諸部族を服属させて「帝国」(世界帝国)となります。もっともこれは、かならずしも領土に組み込んで直接支配するわけではなく、権威による遠隔的な支配の側面が大きい。中国(唐王朝)でいえば、北方の突厥やベトナム,朝鮮諸国,倭国を組み込んだ「冊封体制」がそれにあたります。「帝国」の神聖王権は、「世界宗教」を成立させて、圏域内のあらゆる人間に遠隔的な「力」を及ぼす「太陽=人間」を現出させます。柄谷氏によれば、バビロニアのハンムラビ王、エジプトのファラオ・アメンホテプⅣ世(イクナトン)が、そのような「神聖王」です。中国でも、儒教・道教の「天」の思想が、そのような宗教的役割を果たしました。皇帝は「天子」であり、「天」の命令を受けて世界を治めているのです。(倭国王権の意識はそれ以上で、「天皇」とはもともと、天の最高神を指す道教の用語でした。)
「帝国」の神聖王権――交換様式B――は、交換様式Aが生じさせる “復讐の無限の連鎖” を禁止し、「首長・祭司」層を抑圧することによって、首長制を抑えこんだのです。そうした「世界宗教」と「万民法」が、部族の違いを超えた世界「帝国」の支配を可能にしました。首長制に後戻りすることのない「国家」が成立したのは、この時です。
まとめて言えば、「帝国」とその下での交換様式Cの発展が「世界宗教」を生み出し、「世界宗教」の裏付けを得た「神聖王権」が交換様式Aを抑えこんで、もはや首長制に後戻りしない交換様式B、すなわち専制帝国「国家」を成立させた。私たちはこれを、「国家」の《確立》と呼ぶことができるでしょう。じつは、これこそが、ホッブズの「主権者国家」にほかならないのです。
イクナトン王,王妃ネフェルティティと2人の王女。太陽神アテンから
触手のようなものが放射し、イクナトン夫妻は祭具?を捧げ持って礼拝
している。エジプト第18王朝、紀元前14世紀。王墓の墓石。©Wikimedia
『国家の成立〔確立――ギトン註〕にとって必要なのは、〔…〕いわば “自発的に服従する奴隷”、つまり、臣民(subject)である。〔…〕それは、支配することと自発的に服従すること、あるいは収奪されることと保護されることの「交換」である。そのとき、支配する側にも相手〔臣民――ギトン註〕を保護する義務が生じる。そこに、交換様式Aとは異なるが一種の互酬性(相互性)が存在する〔…〕交換様式Bが確立されるのは、そのときである。〔…〕
しかし、後述するように、自発的な隷従はむしろ、交換様式Cが発展した段階で生じた』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.124-127.
↑ここで言う「交換様式Cが発展した段階」とは、「世界帝国」「世界宗教」の段階です。それについては、↓後掲の引用で明らかになります。「世界宗教」という裏付けをもった「世界帝国」が成立してはじめて、臣民が自発的に国家に服従するという・ホッブズ流の「主権者国家」が誕生するのです。
こうして《確立》された「国家」の下では、「農耕に従事する者のみならず、それを指揮する者もまた、“自発的に服従する奴隷” であった」。「それを典型的に示すのは、〔…〕官僚制である。」(柄谷,p.126)
『官僚制は上意下達のシステムであり、互酬原理が強い社会では成り立たない。〔ギトン註――互酬性社会では、〕人々は独立心が強く、上の命令に服従させられることを嫌うからだ。それを進んで引き受けたのが官僚である。したがって、官僚は隷従的である。しかし、たんなる奴隷ではない。奴隷はもし隙 すき があれば逃亡するだろうが、官僚は積極的に王の命令に従うからだ。その意味で、官僚は “自発的に服従する奴隷” すなわち臣民である。たとえば、マックス・ウェーバーは、エジプトの官僚は事実上ファラオの奴隷であったと言う〔『支配の社会学』,Ⅰ,創文社.〕。〔…〕
武官についても同様のことが言える。国家の軍隊は王にたいして忠実な兵士からなっていた。それは部族社会にはありえなかったタイプである。それは奴隷軍人制と呼ばれるが、いわゆる奴隷ではなく、武官(軍官)であった。したがって、農耕民が積極的に隷従しただけでなく、それを統治する者、すなわち文武官僚も王に仕える servant であった。このようにして、交換様式Bが確立されたのである。〔…〕
このような交換様式Bの確立のもとで、A〔…〕はBの下に抑えこまれた。しかし、消滅してしまったわけではない。たとえば、それは、農業共同体として存続したと言える。そこでは、部族社会にあったような平等性・連帯性が残った。にもかかわらず、それは根本的に国家に従属するものである。Aにあった個人の独立性・遊動性が斥けられたので、個人は共同体に従属する存在となった。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.126-127,
金銅製龍頭 製作年代6世紀。福岡県宗像市沖ノ島・5号祭祀遺跡出土。
「海の道むなかた館」展示。 「龍頭」は、竿の先につけて幡や天蓋を
吊り下げる金具(右下図)。この龍頭は 6世紀中頃の中国・東魏の様式。
朝鮮半島からの舶載品と思われる。宗像は、海部(海人)の根拠地だった
とされ、沖ノ島の祭祀場址と、陸地の古墳から、ペルシャのガラス器,
3世紀中国の銅鏡,新羅の純金製指輪,百済圏の大刀飾り,
新羅・百済の金銅製馬具,飾履など、多数の交易品が出土している。
『国家の成立、すなわちBの発展が生じるためには、同時に、Cの発展、すなわち、交易の発展が必要である。しかし、〔…〕
一般に、農業の発展とともに国家が生じ、交易が発展したと考えられているが、〔…〕交易あるいは貨幣経済は〔…〕共同体と共同体の「間」、あるいは国家と国家の「間」にとどまり、その内部に浸透するものとはならなかった。つまり、交換様式Cは農耕共同体の内部には浸透しなかった、〔…〕そして、交易を担ったのは、〔ギトン註――農耕民ではなく〕遊牧民ないし漁民である。彼らは遊牧や漁を行なうと同時に、交易にも従事してきた。』
柄谷行人『力と交換様式』,p.135.
たとえば、地中海域最初の商業民族であるフェニキア人は、もともと漁民であったといわれています。また、日本古代に海上交易を担った「海人・海部」は、漁業に特化した部族です。
しかし、「国家」成立以後の遠隔地交易の発展は、「国家」との強い結びつきのもとで展開しました。「海人・海部」も、ヤマト王権との結びつきのもとで、朝鮮半島との交易を担ったのです。
『地中海における遠隔地交易を発展させたのは、フェニキアに代表されるように、元漁民が形成した国家である。こうして、古代オリエントにおいて、国家と交易、いいかえれば、交換様式BとCが結びついた。それによって創り出されたのが、古代の領域国家あるいは「帝国」である。〔…〕
〔ギトン註――遊牧民と並んで〕交易の担い手となったもう一つの例は、漁民である。〔…〕貝が貨幣にされたことも、漁民の活動を示すと言える。彼らも、フェニキア人がそうであるように、貿易活動を通して、海洋国家を形成するにいたった。〔…〕
交換様式Cの拡大について考えてみよう。それは、具体的には貨幣経済の広がりである。〔…〕国家が貨幣を作り出したわけではない。貨幣の力は、共同体や国家を越えて通用する「信用」にある。国家が行なったのは、それを保証することである。〔…〕
貴金属は持ち運びが困難であり、その分量〔含有量――ギトン註〕も見分けがたい。したがって、〔…〕貴金属〔…〕が貨幣として使われる時には、国家による保証が必要であった。〔…〕したがって、貴金属が貨幣として用いられるようになったのは、国家が確立した段階以後だと言ってよい。〔…〕
国家が貨幣発行に関与するようになったのは、それが利益をもたらすからでもあった。それ〔金属貨幣――ギトン註〕によって、財や労働を調達できたし、貨幣の普及により税の徴収が楽になるという利点があった。特に古代帝国〔オリエントの――ギトン註〕の段階では、兵士への支払いに硬貨が使われた。ゆえに、貴金属が貨幣となったことは、国家の確立・拡大と切り離せない。いいかえれば、交換様式Cの発展はBのそれと切り離せないのである。〔…〕
フェニキアの商船。紀元2世紀の石棺上のレリーフ。©Wikimedia.
貨幣に諸物と交換しうる「力」を付与するのは、国家ではなく、そこ〔金属片――ギトン註〕に付着した “何か”、つまり貨幣物神である。ただ、国家の保証がなければ、それは貨幣として機能しない※。その意味で、貨幣経済、そして貨幣の増殖としての資本の活動が成立するのは、国家の下においてである。〔…〕
たんに貨幣を貯め込むだけでなく、売買を通してそれを蓄積し〔蓄積を増大させ――ギトン註〕ようとする「絶対的な致富衝動」、あるいは営利的な精神は、古代から存在するとしても、〔…〕それが肯定的に見られるようになったのは、近世ヨーロッパにおける商人資本主義の段階〔16世紀?~――ギトン註〕である。
古代の領域国家では、「致富衝動」が存在したとしても、それが守銭奴や資本家を広汎に生みだすことはなかった。交易を通して貨幣を増殖しようとする欲動は、〔ギトン註――近代以前においては〕国家によってもたらされたと言うべきである。〔…〕個人の「致富衝動」〔…〕は、国家による交易の活動の拡大と利潤の獲得に付随してあらわれたものである。そもそも、限られた範囲内での市場交易は、利潤をもたらさないからだ。そして、大きな利潤をもたらす遠距離交易は、国家によってしかなしえない。〔…〕
古代国家において重要であったのは、管理交易、すなわち、国家によって遠隔地との間においてなされる交易である。それも一種の利益を動機と』してはいたが、主要な目的は『「王の威信」を拡大することにあった。その意味で、対外交易を推進し、結果的に領域国家や帝国を築く原動力となったのは、「聖なる王権」である。つまり、その「力」が、一方で王の威信を無限に拡張する衝動をもたらすと同時に、他方で「私的な致富衝動」を抑制したのである。
私的交易者は小規模であり、その利潤も少なかった。それに対して、遠隔地交易に従事したのは商人ではなく、国家官僚ないしそれに準じる者である。そこから巨大な利益が得られたが、〔…〕彼らが交易に勤 いそ しんだのは、「利潤動機」ではなく「身分動機」によってであった。〔…〕彼らが求めたのは、先ず、身分とそれに伴う権力である。
カール・ポランニーによれば、交易が身分動機によってなされるとき、名誉ある行為とみなされ、たんに利潤動機から交易を行なうことは蔑まれた。(ポランニー『人間の経済』,Ⅰ.)〔…〕
古代世界で交易が拡大したことは、Cの発展というより、むしろBの発展に貢献したというべきである。それによって、都市国家を越えた領域国家、さらにそれを越えた「帝国」が出現したのだ。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.136-141,402(4).
註※「金属貨幣は、国家の保証がなければ機能しない」: 議論の余地ある判断。しかし、この難問には深入りせず、柄谷氏のテーゼとして受け入れてレヴューを進めたい。
博多港に寄港した復元遣唐使船。2010年。©ぱちょび CC BY-SA 3.0
かくして、「世界帝国」「世界宗教」「遠隔地交易」「主権者国家」の、いわば “四位一体” が成立した時に、交換様式Bは、交換様式Aを完全に抑えこみ、交換様式Aの優越する「氏族社会」にはもはや後戻りしないだけの地歩を固めることとなるのです。その実年代は、地中海~中東地域ではかなり早かったようで、柄谷氏は「ハンムラビ法典」〔前18世紀〕を挙げています。それは疑問があるとしても、遅くとも東ローマ帝国(ユスティニアヌス法典 紀元529年)までには完成したと見てよいでしょう。中国ではやや遅く、宋朝〔960年~〕の「天子独裁制(皇帝専制)」までに確立すると見られます。これら “文明の中心部” に対して、“周辺部” であるアルプス以北のヨーロッパや日本では “四位一体” の成立はずっと遅く、西欧は近世の「絶対王政」(王権神授説)〔英16世紀~,仏17世紀~〕、日本では幕藩体制〔17世紀~〕ないし明治維新によって初めて交換様式Bの絶対的優位が確立したと考えてよいと思います。
しかし、近世の場合には、確立した交換様式Bのもとで交換様式Cが大発展して、交換様式Aが従属化して残る農業共同体を蚕食し、資本主義の《本源的蓄積》過程を押し進めることとなるのです。
「世界帝国」と「世界宗教」については、もう少し述べておかなければならないことがあります。ひとつは、「帝国」は宗教とともに「法」を生みだしていることです。それは、「氏族社会」の慣習法を超えた成文法である国家法、すなわち「万民法」です。それによって、「国家」の支配は盤石 ばんじゃく を得ることとなります。
もうひとつは、「帝国」の「世界宗教」に対抗して、被支配種族や境界的な遊動民のなかから「普遍宗教」が発生してきます。ユダヤ教、キリスト教、仏教などがそれです。それらはいずれも、「交換様式D」の噴出として開始されます。
次回は、そのへんから始めたいと思います。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!