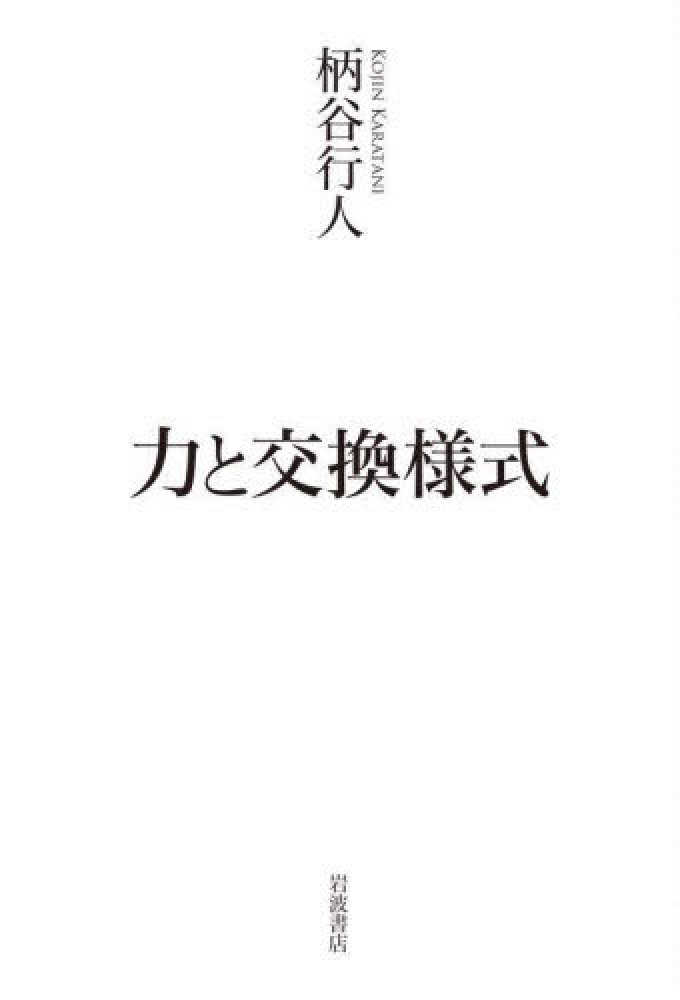漢代の画像石(拓本) 狩猟と農耕
成都市郊出土 重慶市博物館・四川省博物館蔵
【54】 《原遊動》から「狩猟定住」→「穀物定住」へ
前回からしつこく繰り返していますが、遊動生活を送っていた人類が、「定住」生活へ、そしてさらには「国家」の支配に従属した定住民の緊縛生活へと変遷してゆくプロセスは、まず、狩猟採集生活のままで「定住」し、数千年のちに初めて「穀物」農業に専従する農耕「定住」民となり、ついで、ないし同時に、「国家」の支配に従属して租税を負担するようになる――という過程をたどりました。第2段階の「定住」は、「国家」の発生ないし外来「国家」への服属と同時か、やや先立って起きていますが、それほど隔たってはいません。それというのも、「穀物」は、専制国家のための作物と言ってもよいほど、徴税に適した作物だからです。
この第1段階の定住を「狩猟定住」、固定耕地での穀物作に専念するようになってからの定住を「穀物定住」と呼ぶことができるでしょう。
以上のプロセスを、ボーム,スコット,柄谷氏の叙述から整理して図式化すると、次のようになります。
「ヤンガー・ドリアス」は、最後の氷期(氷河期)のあとで、短期間、氷期に近い寒冷期が訪れた「寒の戻り」の時期です。ただし、東アジアだけは例外的に「ヤンガー・ドリアス」亜氷期がありませんでした。この間、温暖な気候が続いたことが、中国・長江流域でのイネの作物化――が起きたのは亜氷期より後ですが――に関係しているかもしれません。
図の中央のS字形の色分けは、曲線の左が、人類総人口中の「定住」民の割合、右が移動生活者の割合を表しています。「バンド→氏族→メガバンド→部族」といった集団の種別と階梯、また【原遊動】【交換様式A/B】等の柄谷理論については、次節以下であらためて説明します。
【55】 マルセル・モース――
「贈与交換」の発見
『ここで重要なのは、定住化とともに「交換」が始まった、ということである。もちろん、それ以前に遊動的狩猟採集民も交換をした。しかし、その場合、交換は臨時的なものであった。〔…〕また互いに移動していたため、交換の相手も固定していなかった。しかるに、定住後には、交換が不可欠で切実なものとなった。その地域で取得できないものがあるからだ。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,p.64.
遊動民どうしの交換が「臨時的なもの」で「交換の相手も固定していなかった」との柄谷氏の推論には疑問があります。「遊動」と言っても、通常は一定の狭い地域の中でキャンプ地を変えて移動しているのであって、大陸や太平洋をまたにかけて大移動する、というようなことは通常はないはずです。狩猟採集生活には、特定の地域の気候等の諸条件、該地域の動植物の特性に関する知識が欠かせません。草木の稔りの時期、鳥、魚群や獲物の「渡り」の時期などの環境条件を熟知していればこそ、安定した狩猟採取が行なえるのです。移動狩猟民が見馴れた地域から離れることは、危険を伴います。これまでとは環境条件の異なる場所への移動を試みるのは、気候変動など、環境の急変のために、今いる地域ではもうやっていけなくなった、という場合なのではないでしょうか? そういった場合に初めて、より良い条件を求めて新しい土地への冒険的な移住が行なわれるのだと思います。
だとすれば、一定の地域の産物との交換を求めて、他の地域から定期的に交易の “キャラバン” がやってきて、移動民どうしで小規模な交換を行なう――といったことはありうると思うのです。
とはいえ、そうした “交易する移動生活民” が、一定の場所に「定住」するようになれば、他地域との交換・交易が、より盛んになっただろうことは、十分に想定できます。いつでも、その場所に行けば集落があって、そこにはこちらにはない物資がある、とわかっていれば、交易に訪れる “キャラバン” は増えるでしょう。“キャラバン” を送り出す地域が増えれば、それだけ様々な物資が集まって、交換の利益と誘因は飛躍的に高まると思われます。
ただ、その場合でも、柄谷氏が、そもそもの「定住」の初めに、交換 “開始” の画期を置いている点は疑問です。「定住」と言っても、狩猟採集民のままでの「狩猟定住」の場合には、さまざまな生態系の交錯点を選んで定住している以上、諸種の物資を自前で取得できるはずだからです。本格的に、自前で生産できない物資の需要が高まるのは、むしろ「穀物定住」に移った段階だろうと思われます。
「狩猟定住」の好例と思われる「三内丸山遺跡」の場合にも、この十数年の発掘調査成果の展示を見ると、陸奥湾の魚類を中心とする域内産物の消費が圧倒的に多く、黒曜石、ヒスイ等・他地域からの産物の流入は目立つものの、割合的にはそれほど多くはないのです。10年以上前、復元建物群が建ち上がった頃には、北海道方面から持ちこまれたと思われる大型海獣の骨が出土して注目されましたが、それも割合的にはたいしたものではありません。
黒曜石製石槍とヒスイ製大珠。紀元前3300-2200年。三内丸山遺跡。
黒曜石は北海道,長野県等で、ヒスイは新潟県で産出する。
『その場合、交換は先ず、互酬交換(A)として始まったと言ってよい。マルセル・モースが述べたように、それは、「贈与せよ」「贈与を受け取れ」「贈与にお返しせよ」という強制、しかも霊による強制を伴なう。つまり、交換には、何らかの観念的な力が不可欠なのだ。
さらに交換が商品交換(C)となるためには、それまでなかった観念的な力、つまりマルクスがいう “物神” が不可欠となる。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.64-65.
しかし、ここでモースが言う「交換」とは、個人間の物々交換のようなものではなく、集団と集団のあいだ――柄谷氏の言い方では「共同体のあいだ」――のやりとりなのです。首長や “貴族” どうしで「交換」しているように見えても、それは彼らが代表する集団どうしのやりとりにほかならない。相手の集団が欲しがる物資を「贈与」しあうだけではなく、たがいに・自集団が持っている価値ある物資を破壊して見せ、その気前良さを競う競争(ポトラッチ)も行なわれます。より多くのものを破壊した集団が勝利し、他の集団を服属させて、集団間の階層化が生じます。物資を「贈与」しあう場合も同様で、より多くを与えた集団が優位に立ち、他の集団の上に立つことになると思われます。
モースが言う「交換」とは、《集団間》の交換であって、わたしたちが「互酬」「贈与」というとイメージするような、《集団内》の個人間の相互扶助や「贈り物」「お返し」といったものではないのです。
『これらの給付がいわば自発的であり、見た目には自由で見返りを求めない給付としてなされているにもかかわらず、それがじつは強制力にもとづき、利害関心にもとづいてなされているということである。〔…〕
お互いに義務を負い、交換を行ない、契約を交わすのは、個人ではなく集団である。契約当事者となるのは、権利義務の主体となる資格が認められた集団である。ある場合には集団どうしが実地に相対することによってなされ、別の場合にはそれぞれの首長を仲立ちとしてなされ』る。『これらの集団が交換するのは財や富だけではない。〔…〕交換されるのは何よりも、礼儀作法にかなったふるまいであり、饗宴であり、儀礼であり、軍務であり、女性であり、子どもであり、踊りであり、祝祭であり、祭市である。〔…〕
これらの給付と反対給付は、贈り物やプレゼントという、どちらかといえば自発的なかたちで行なわれるのだが、にもかかわらずそれは、実際のところはまったく義務によってなされている。』
マルセル・モース,森山工・訳『贈与論・他2篇』,2014,岩波文庫,pp.60,67-68.
Marcel Mauss (1872-1950)
モースに遡って読んでみると、どうも彼の言う「給付」「交換」というのは、日常的な、あるいは経済的な意味をあまりもたないのではないか? という疑問が湧きます。たとえば、《集団間》の「交換」的給付のひとつである「祭市」の開催は、その市場 いちば での (おそらく個人間の)「物の取引き」を伴なうと言うのです。経済的には、こちらの個人間の「交換」のほうが、重要な意味をもつはずです。
柄谷氏のいう「交換様式」とは、それが社会の根幹を形づくるようなものだとすれば、たとえ形式は儀礼として行なわれても、実質において経済的に機能するだけの量と質が伴わなければならないと思うのですが。。。
もちろん、モースを離れて言えば、古い社会ほど商品交換・交易の比重は低く、《集団間》でも、集団内部の個人間でも、「贈与・お返し」の交換や相互扶助の慣習が生きていたということは、誰もが認めることでしょう。また、モースの言うような・《集団間》の儀礼としての「祭市」などの催しも、贈与交換や物々交換の行なわれる機会を定期的に提供するものとして把えれば、その社会経済的意義をよりよく理解できるかもしれません。
そのようにして、ゆるく・幅広く考えれば、柄谷氏の「交換様式A」は、卓見として受け入れることができます。しかし、モースの意味に――贈与・お返しを強制する「霊」を含めて――それを狭く把えるのは、たいへんに疑問です。
ともかく、広い意味での「贈与・互酬」交換――交換様式A――にしろ、異なる物資を携えた個人が市場で出会って交換するような「交換様式C」の交換にしろ、それらが《集団間》で経済的意味をもつほどの量で行なわれるようになったのは、「狩猟定住」の段階ではなく、より後の「穀物定住」の段階だったと考えられるのです。
【56】 バンド→氏族→部族…と「呪術」宗教の発生
『進化心理学者ロビン・ダンバーが提起した〔…〕「時間収支」の仮説。1日の生活は、「摂食・移動・休息」、そして集団(の絆)を維持するための「社交」からなる。それらのための時間をどう配分するかが、時間収支である。とくに重要なのは、社交のための時間である。
類人猿の段階では、それはグルーミング(毛づくろい)であった。それが、幸福感、満足感を与える脳内物質エンドルフィンをもたらす。人類においては、グルーミングに代わるものとして、集団における笑い,歌,踊り、さらに、言語が生まれた、とダンバーは言う。
彼の考えでは集団の巨大化は、以下のような階層化によってなされる。
1 家族
2 野営集団=バンド(移動をともにするユニット)
30-50人
3 氏族(共同体) 150人程度
4 内婚的共同体(メガバンド。この内部で婚姻がなされる)
5 民族言語共同体(部族)
このなかで、氏族とは、一定のテリトリー、あるいは特別な資源(永続的な水源や聖なる場所)へのアクセス権を共有する集団の在りようである。これは気のおけない、互恵的な集団であるが、150人が限度である。それがダンバー数(150)と呼ばれる。それは遊動的な社会から、定住的な未開社会、〔…〕〔ギトン註――歴史時代の〕村落、軍隊、地域教会、政治組織に至るまで共通している。それ〔150人という人数――ギトン註〕が人の社会の基礎単位であるようだ。
彼の考えでは、集団が拡大するとその維持が難しくなる。たとえば、摂食のための移動・労働などに時間をとられるようになると、社交のための時間が不足する。すると、集団が崩壊してしまう。また、集団を広げつつそれを維持するためには、社交を集約し効率化しなければならない。それを果たすのが祭式であり、また宗教である。
ダンバーの考察は、遊動的狩猟採集民が定住した時に生じた問題をを考えるのに、ヒントを与えてくれる。たとえば、つぎのように推測することができる。
遊動的バンドは 30-50名ほどである。このことは、現在残っている遊動的狩猟採集民にもあてはまる。
定住して人口が増大しても、この規模が保持される。そして、複数の集落による共同体を形成するようになる。その共同体の規模は 150名程度である。さらに、それらの共同体の集まりからなる共同体(内婚的共同体)が形成される。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.65-67.
つまり、柄谷氏は、「定住」開始後の狩猟採集民も、遊動時代と同じ「バンド」規模の集落を形成し、人口が増えても、やはり 30-50人規模の集落に分散する、そして、複数の「バンド」規模集落が連携して、「氏族」のまとまりを持つと考えています。しかし、これは縄文集落遺跡の発掘結果と一致しません。
たとえば、↓こちらに図示した埼玉県嵐山町「行免司遺跡」では、多い時には 20軒、100人以上、つまり「氏族」規模に近い人数が、1か所で「環状集落」をつくって集住していたのです。
嵐山町最初の定住集落遺跡「志賀・金平遺跡」(紀元前5000年頃)は、同時に存在した住居は 2,3軒、わずか 10-15人程度の小さな集落でした。この人数は、「バンド」の規模に達しません。
環状集落「行免司遺跡」では、最盛期である8期(縄文中期末。紀元前2300年頃)には 38軒の住居跡が検出されています。1軒に 5人から 8人程度が暮らしていたとされます。8期は、住居も広く 7-8坪程度だと言いますから、1軒平均 7人とすれば、計算上は 266人となります。38軒全部が同時に存在したわけではないので、その約半分としても、130人程度という数が得られます。「氏族」に近い規模の人口が集住していたことになります。
柄谷氏の描く先史社会像は、基礎集団「バンド」から最高位の「民族言語共同体」まで樹状組織図のようにきれいに整った系統図式で、たしかにわかりやすいけれども、実像として受け入れることはできないと思います。このようなものは、「国家」の支配に包摂されてはじめて成立するものでしょう。遺跡の発掘によって得られたデータにも合致しません。
しかし、「ダンバー数」150人という数は、心理学として根拠のあるものならば、先史社会にも何らかの痕跡を残していてよい。その意味で、「150人」を、「狩猟定住」段階の集落人口の上限と見てはどうでしょうか。じっさい、人口150人を越える縄文集落遺跡は、いまのところ見つかっていないようです。
ともかく、常識で考えても、130-150人もの人数がいっしょに暮らすようになれば、さまざまな揉めごとが起きるようになることは容易に想像できます。
『問題は、〔…〕集団の拡大から生じる危機が、いかにして克服されたのかということである。ダンバーが分けた5段階において、最も大きな危機をもたらし、したがってまた、最も大きな変化をもたらしたのは、段階2から3への移行である。〔…〕それが示すのは、定住によって生じた危機の深化である。ダンバーの考えでは、この危機はグルーミングの人間版としての、祭式や宗教によって克服される。』
柄谷行人『力と交換様式』,p.67.
ここでの柄谷氏の考察を図式化してまとめますと: 労働の加重。→「社交」への時間配分が減って、集団の維持に危機が訪れる。→アニミズムに代わる、新たな宗教・祭式が必要になり、宗教が変容する。→危機は克服され、集団は維持拡大される。――となります。
『この危機が宗教によって超えられたように見えるとしても、そのとき “宗教” がそれ自体変わった〔…〕定住とともに新たな「交換」の問題が生じ、それが宗教の変容をもたらした〔…〕具体的に言うと、定住後は蓄積が可能になるため、放置すれば格差・不平等が生じる。そこで、狩猟採集による全生産物が一旦集団によって所有され、各人に再分配されるというシステムが作られた。それはまた、そのような役割を果たす者として首長が生まれたということでもある。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.67-68.
しかし、ボームと柄谷氏が言うような・セントリックでシステマチックな平等分配の機構があったとは思えません。柄谷氏は、「首長」という “管理人” が出現して、「狩猟採集による全生産物が一旦集団によって所有され、各人に再分配されるというシステム」が作られたと言うのですが、このような想定は、考古学的証拠とも現存の狩猟採集民族の実態とも矛盾します。
ばかりでなく、柄谷氏自身の論理とも矛盾するように思われます。こうした “専業管理人” は、容易に権力者となりうるからです。狩猟採集社会は「定住」後も平等だったという氏自身の想定と矛盾するのです。全生産物を一手に占めて「分配」の役割を握った人が、無私無欲な全能神のように、一人ひとりの事情を正確に見極め、全体の利益をはかって、平等な分配を行なう、などということは、決して起こりうるものではありません。人間心理の特質に反するからです。フロイトが明らかにしたように、いかなる人間も、つねに無意識の欲動に動かされて生きているのです。
柄谷氏は、「放置すれば格差・不平等が生じる」と言います。なるほど、そういう観念は、資本主義であればもちろん、おしなべて「国家」支配の下にある歴史社会では “常識” かもしれません。しかし、ボームによれば、先史の狩猟採集社会では、人びとに・いわば本能として「平等化」がビルド・インされているのです。氷河期の移動生活から、初期の「狩猟定住」にわたる社会では、人びとのあいだに「平等化」の圧力がつねに働いており、各自の「所有物」を分配しあうことがむしろ “常識” であり常態だったと想定することが可能だと思います。
現存の狩猟採集民族に関する知見から推せば、先史でも「狩猟定住」の当初から、個人の私有財産はあったと考えてよい。「全生産物が一旦集団によって所有される」体制があったなどと、根拠もなく想定する必要はありません。たとえば、「三内丸山遺跡」では、個人の竪穴住居跡から、大量に貯蔵されたクリが出土しています。倉庫とされる掘立柱建物跡はあるものの、それらは、「大人の墓場」のすぐ隣に集中しています。倉庫ではなく、「もがり場」かもしれませんから、これをもって「集団的所有」の証拠とすることはできません。もっとも、大型魚類などは、集団的に消費されたかもしれません。石器・骨器・土器などの製造・加工も、集団で行なわれた可能性は高いでしょう。
しかし、鍵のかからない家に住み、猟・漁や採集のために不在になることが多い「狩猟定住」の “むら” では、村人のすべての財産は公開状態で、誰が何をどれだけ持っているかを全員が知っていたと考えられます。「平等化」の圧力(超自我)のもとで、個人の財産を互いに再分配する機会が頻繁に設けられていたにちがいありません。日常的な「おすそ分け」のような個人間の贈与だけでなく、集団の行事として、みんなで神様に「お供え」をし、欲しい人が供物の「もらい下げ」を受けるといった形で、集団的な贈与が行なわれることもあったでしょう。贈与だけでなく、財産を投棄する機会(ポトラッチ)が定期的にあったでしょう。というのは、ヒスイ珠などの貴重品は、個人の住居でも墓でもなく、部落共有の「捨て場」から出土しているのです。「三内丸山遺跡」では、個人の死とともに、その人の財産は投棄されたと推定されていますが、あるいは生前にも投棄の機会があったかもしれません。
このような「狩猟定住」集落は、「威信財」というものが存在しえない社会だったと言えます。「穀物定住」以後、日本でいえば弥生・古墳時代には、勾玉、剣、銅鏡などの「威信財」が、重要な政治的役割を果たしました。それは、階層分化し、支配者と被支配者のいる社会の徴表と言えます。ところが、縄文集落では、せっかく手に入れた宝物は、かんたんに捨てられたり贈与されたりしてしまう。そうやって価値あるものを手放す思い切りの良さ、気前良さこそが、宝物よりずっと大切な “人望” をもたらすと考えられている。そのような社会では、「威信財」は存立しません。だから、「三内丸山」ほか縄文の墓には、副葬品がないのです。
このように、《集団内》の「贈与交換」は、「狩猟定住」の最初から行われていたと考えてよい。
三内丸山遺跡。土壙墓の列。この区域には、
大人の墓とみられる土壙が集中して発見された。
『宗教に関していうと、遊動的な段階では、人々は素朴なアニミズム(アニマティズム)をもっていた。〔…〕死者・祖先神への信仰はなかった。それが始まったのは、定住の結果生じた危機によってである。〔…〕そのとき、死者との「交換」が始まった。タヒ者を弔うことは “贈与” することであり、それは当然、タヒ者に返礼〔ごリヤク――ギトン註〕を強いるものである。こうして、互酬交換が宗教を変えた。〔…〕初期的なアニミズムから、呪術や先祖崇拝への発展をもたらした、〔…〕そこから、そのような任務を果たす祭司が生まれた。このようにして、氏族社会が形成されたのである。』
柄谷行人『力と交換様式』,p.68.
『ウェーバーによれば、「呪術」とは、神仏などの超越的な諸力に対して人間が何らかの呪的〔「まじない」的――ギトン註〕な手段をもって作用を及ぼし、これに人間に役立つ働きを強制することができるという観念と、それに基づく行為(神強制)をいう。感性的に認知可能なものと超感性的な力とを直結させるこのような観念は、しかし、神的なものについての思惟が合理化し体系化されるにつれて破綻して衰退してゆき、やがて、彼岸と此岸とを峻別し、人間はもっぱら神仏の超越的な力に服してただ祈願・供儀・崇拝(神奉仕)を行えるのみであるとする観念が、優勢になってくる。概念的にはこれが「呪術」から「宗教」への移行であり、本来はこのプロセスが脱呪術化と呼ばれるものである。』
廣松渉・他編『岩波 哲学・思想事典』,1998,「脱呪術化」.
「呪術」とは、端的に言えば、「ごリヤク」を求めて「お供え」をするという「交換」行為であり、人間が神を強制して、自分の都合に合わせて事態を動かさせること(神強制)です。人間はひたすら神に祈るだけであり、神が世界をどう動かすかは神次第、人間が影響を与えることはできない・という、西洋人(とくにプロテスタント)の考える “本来の宗教” とは、対極にあるとされました。神道は、典型的な「呪術」といってよいでしょう。
しかし、「定住」以前の・遊動生活を送っていた人類は、自然の事物はそれぞれ「霊」を持って活動しているという・単純なアニミズムを信じていたにすぎないと考えられます。そこから変化して、「呪術」宗教という特別な世界観を抱くようになったのは、「定住」が原因だったと、柄谷氏は言うのです。
ただ、問題は、はじめの「狩猟定住」の段階でそうなったと考えるか、それとも、「穀物定住」に移行した時に初めて、そのような “発展” を強いられたと考えるかです。柄谷氏は、「狩猟定住」の段階ですでに「呪術」「祖先崇拝」が始まったと考えています。氏がそう考えるのは、「呪術」「祖先崇拝」は、人間と神のあいだ、人間と祖先とのあいだの「交換」であり、「交換様式A」(贈与交換)の一局面だと考えるからでしょう。
しかし他面で、アニミズムが「呪術」「祖先崇拝」に変容し、より完備した祭式と思考体系を備えるようになったのは、それを必要とする人間社会の側の条件があったからです。ダンバーによれば、それは、「時間収支」の中での労働時間の比重が増して、集団を維持するために必須の「社交」時間が減ってしまうという危機を克服するためでした。宗教の祭式の力によって、長時間の「社交」に代わるだけの心理的効果を短時間に実現し、人びとの気分を一新して、また明日からの労働に向かう活力を引き出したわけです。だとすれば、穀物耕作に多大の専業労働力を注ぎ込まなければならなくなる「穀物定住」への移行期こそが、宗教が変容する画期としてふさわしいと言えないでしょうか?
また、専業の「祭司」の発生という点から言っても、それは、「穀物」生産力の飛躍的上昇によって「首長」が発生する「穀物定住」開始期と同時だったと見るほうが、論理的に分かりやすいと言えます。
三内丸山遺跡。復元された竪穴住居。縄文住居は、ながらく、弥生と同じ
茅葺きと考えられ、各地の遺跡でそのように復元され展示されてきた。
ところが最近は疑問視されている。左は土葺き、右は樹皮葺きで復元。
現存するサハリン,シベリアの狩猟民に倣ったこれらの住居のほうが、
案外、真実に近いのかもしれない。
くりかえしますと、柄谷氏は、「贈与交換」の開始、「呪術」「祖先崇拝」宗教への変容、および、祭司・首長の発生を、「定住の開始」、すなわち「狩猟定住」の開始と同時だったとしていますが、これはたいへんに疑問です。
たしかに、「贈与交換」(交換様式A)は、「狩猟定住」の開始とともに始まったと見て問題ないでしょう。遊動時代からあった「平等化」の圧力のもとで、「定住」と集落規模の拡大(「氏族」規模まで)によって生じた・社会関係の複雑化にもかかわらず、「自由・対等」と「平等」分配の原則を維持するために、やや複雑な「贈与交換」の慣習が作られていったのでしょう。
しかし、「呪術」宗教と「祖先崇拝」、それらを司 つかさど る専業の「祭司」が発生したのは、もっと後代の、「穀物定住」・穀作専業への移行期だったと考えられます。
同時に、穀作専業への移行によって、生産物の貯蔵ははるかに容易になり、集落の生産物をまとめて貯蔵する倉庫や、その分配と消費を司 つかさど る「首長」が発生したと考えてよい。「首長」は、穀物畑/水田の整備や灌漑工事などの作業を指揮監督する役割も持ったはずです。ただし、「首長」のような専業管理人が分配を行なう場合、「分配」は平等に行なわれるとは限らないことに注意する必要があります。特定の人間が「分配」の決定権を持つことによって、その者の血縁者や縁のある者に有利な分配が行なわれるようになるのは、むしろ自然な成り行きだと考えられます。こうして、集団内に階層分化が兆 きざ すことになります。
それでも、「穀物定住」以後においても、「氏族」内部で階層分化が進行していった後も、「贈与交換」は《集団内》で行なわれ続けました。「贈与交換」じたいは、《集団内》の完全な平等を保証するものでは必ずしもないからです。
したがって、「呪術」宗教と「祭司」の発生、《集団内》の集権的な分配と「首長」の発生は、「穀物定住」の開始とともに始まったと考えたほうがよいのです。
まとめますと:
「定住化」以前の遊動生活の段階では、人びとは、バンド(30-50人)以下の規模で集まり、キャンプを張って滞在しては、環境の変化に応じて移動を繰り返していました。人びとにとっての常識は、アニミズムであり、また「自由・平等」でした。「自由・平等」を維持できない集団は、自然の脅威の前に亡びるほかはないからです。
さいごの「亜氷期」が終った温暖・湿潤化の好条件のなかで、「狩猟定住」が始まりました。「氏族」(150人程度)を上限とする規模の大集落が出現し、人びとは、狩猟、漁撈、半栽培を伴なう採集、移動農耕など、さまざまな生業を往き来しました。人びとのアニミズムも高度な体系をもつようになり、環状列石、もがり場、木製列柱など、天体の動きや動植物・魚類の移動に深い理解を示すようになっています。しかし、「呪術」宗教も「祖先崇拝」も、まだ発生していません。集団内では「贈与交換」や、宝物の投棄が行なわれ(交換様式A)、遊動生活時代以来の「自由・平等」が、相互の規制と分配慣習によって維持されました。
「穀物定住」、穀物耕作への専業化によって、労働時間が増加し、「社交」時間の不足を補うために、宗教が変容し、「呪術」「祖先崇拝」の祭式が発達し、専業の「祭司」が発生します。同時に、貯蔵が容易になった大量の生産物:「穀物」の管理・分配とその生産をつかさどる「首長」が発生します。しかし、「首長」による分配は、集団内に階層分化をもたらすことになります。かつて、遊動生活時代の人類に作用していた「平等化」の進化圧力は、もはや条件を失っていたのです。「自由・平等」は、しだいに現実から乖離した倫理ないし理想となっていきます。
以上は、「国家」の出現に先立つ変遷の大まかなスケッチです。そこで、今回最初に掲げた概念図を修正して示すと、次のようになります:
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!