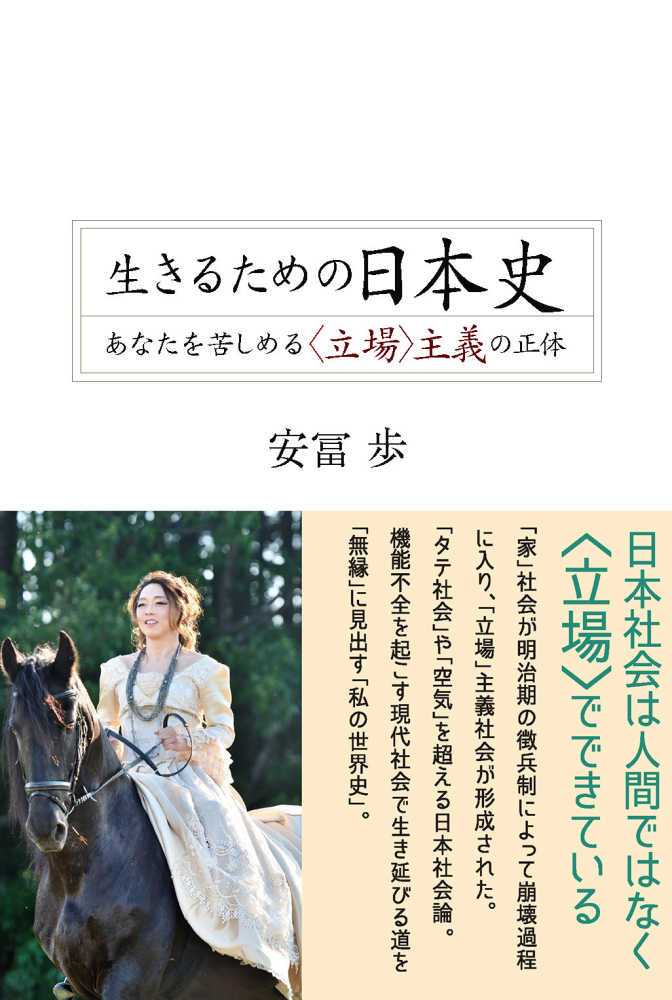村上水軍の根拠地とルイス・フロイス 香川元太郎・画/村上海賊ミュージアム
「その島には日本最大の海賊が住んでおり、大きな城を構え、多数の部下、領地、
船舶を有し、船はたえず獲物を襲っていた」と宣教師フロイスは記している。
【52】中間まとめ――画期としての南北朝
前回は、中学の社会科や高校の日本史とリンクする話もあったので、なじみ深く読んでいただけたかと思います。しかし、それだけに “流れ” が複雑になって、頭の中が整理しきれないかもしれません。ここで、平安~戦国までの主要な社会史項目を、年代順に整理してみると、つぎのようになります:
- 10世紀前半 平将門・藤原純友の乱 律令体制の動揺 平安
- 10世紀後半~12世紀 徴税請負→商業・海運・金融業の勃興
- 11世紀後半~13世紀前半 「荘園公領制」の成立 院政~
- 12世紀~13世紀初め 「神人供御人制」の成立 鎌倉初め
- 13世紀後半~14世紀 勧進聖·遊行僧/悪党·海賊の活躍 鎌倉
- 14世紀 転換期:神仏·天皇の権威凋落、経済の世俗化 南北朝
- 15世紀~16世紀 重商主義:寺院金融、自治都市 室町戦国
平安時代中ごろの「将門・純友の乱」で火がついた律令体制の動揺は、徴税を実際に請負うことのできる民間の商人・金融業者の活動を活発にさせ、その結果として、院政時代から鎌倉時代初期にかけて、「荘園公領制」「神人供御人制」という2つのしくみを成立させます。こうして、古代の律令体制に代わる中世の社会体制ができあがり、内部に激動をはらみながらも、朝廷と幕府に分裂ぎみの国家統治体制を支えてゆくことになります。
ところが、非農業民を中心とする商人・海民・宗教者の活動は、「神人供御人制」の枠をはみ出してさらに展開し、鎌倉中期以降は、時衆などの「遊行(ゆぎょう)僧」集団と「勧進聖(かんじんひじり)」の活動が幕府を動揺させ、他方で、「悪党」「海賊」などといわれる一種の冒険商人の暴力的自力活動を、朝廷も幕府も抑えきれなくなります。
14世紀、つまり、鎌倉時代末期から「南北朝」までの時代が、大きな《転換期》になります。
《転換》の意味は2つあります。〔①〕ひとつは、朝廷・幕府のような統治権力が、非農業民を中心とする商人や遍歴宗教者のアナーキーな活動を、あくまで鎮圧し抑え込もうとするのか、それとも、むしろ彼らを政権の基盤に取り込んでいくのか、という路線問題です。
北条執権家の鎌倉幕府の内部には、この路線対立があったのですが、けっきょく結論が出ないうちに、鎌倉幕府は滅亡してしまいます。
《建武政権》を握った後醍醐天皇は、むしろ「悪党」「海賊」まで含めて、このアナーキーな連中と提携し、政権の基盤とする強烈な意志で独裁親政を進めようとしました。北朝方の保守的な天皇・公家からすれば、後醍醐は、とんでもない革命陰謀家であり強権ファシストだったのです。
しかし、「南北合体」後の室町幕府は、将軍足利義満以後、金融業者である「酒屋・土倉」「悪党」「海賊」などを懐柔しつつ政権基盤に取り込む路線(重商主義)に踏み切ります。そして彼らの力を借りて対・中国貿易を行ない、また「河原者」を重用して、外来文化の影響のもとに、能・狂言、建築・造園などに華麗な室町文化を開花させるのです。
戦国大名による「楽市楽座令」、南蛮貿易などの重商主義政策は、その延長線上にあると言ってよいと思います。
しかし、「南北朝」の分裂騒乱は、〔②〕それまでは絶対的に信じられていた天皇の権威の失墜、それとともに、神仏すべての権威の低下という結果をもたらしました。これが、《転換》のもう一つの意味です。
このことは、宗教者に対してはもちろん、商人・金融業者、手工業「職能民」、芸能民、海民に対しても重大な影響をもたらさずにいません。というのは、鎌倉時代までの商人・金融業者、職人らは、「悪党」と非難された人びともふくめて、みな何らかの意味で天皇・神仏の権威につながり、聖なる権威を背景にして活動していたからです。
《転換》の結果をひとことで言えば、彼らの社会的地位・活動の《世俗化》でした。
一方で、「酒屋・土倉」などの金融業者は、もう神仏を恐れる必要もなくなって、純粋に自分の経済的利益を追い求めるようになります。彼らに対する社会一般の風当たりが強くなるのは当然のなりゆきですが、世間の指弾は弱者に向けられがちです。その意味で、もっとも深刻な影響をこうむったのは、「河原者」「遊女」「非人」など、遍歴職能民のなかでも最も権力から遠い人びとでした。
彼らはかつて、通常の平民とは異なる「異形(いぎょう)の者」として特別視されつつも、神仏につながる神聖な民として尊重されてもいました。しかし、いまやマジカルな美しい装いは剝げ落ちて、あからさまな蔑視だけが向けられるようになったのです。
【53】勧進聖と禅僧――鎌倉時代の資本主義
『鎌倉時代、西大寺流の律宗が叡尊、忍性によってさかんになり、鎌倉中期、この流派の律僧が活発な活動をしています。』
網野善彦『日本の歴史をよみなおす(全)』,2005,ちくま学芸文庫, pp.74-75.
「律宗」は、奈良時代に唐から来朝した鑑真が伝えた宗派で、戒律の研究と実践を主たる活動としますが、平安時代には天台宗、真言宗に押されて教勢は衰微していました。鎌倉時代になると、新義律宗3派による革新運動が起き、なかでも叡尊らの「西大寺流」は、真言密教を加味し、「勧進」や、非人の救済をはじめとする盛んな実践活動によって、鎌倉新仏教の諸宗派に劣らない広範な民衆信仰を集めたのです。西大寺流律宗は、叡尊が住持する奈良「西大寺」とともに、忍性が開いた鎌倉「極楽寺」を拠点としていました。
鎌倉時代に「律僧」と呼ばれ、「勧進聖」として全国を回って寄付金を集めたのは、もっぱらこの「西大寺流」に属する僧たちでした。
当時、寺社の建築や修繕は、世間から集めた寄付金や寄付の米を原資としました。この寄付集めの活動が、「勧進」と呼ばれます。「勧進」は本来、勧進聖が辻に立って募金を呼びかけたり、徒歩で家々を回ってお願いして集めていたのですが、時代が下るにつれ、東大寺のような大寺社が「勧進職」を設けて、彼らの地位を保証するようになります。こうして権威・権力とむすびついた勧進聖は、もっと効率的でラクなやり方をするようになります。
すなわち、辻に立つ代わりに関所を設けて、寄付名目で通行税を取る。あるいは、1軒につきいくらと決めて「棟別銭」を徴収する。つまり、税金と変わらなくなるのです。
さらに、あつめた銭・米は、国司、官司、公家などに融資して利息を取る。神仏のものを貸し与えるのですから、返済も利殖も確実です。そればかりか、これを元手に中国に「唐船」を出して貿易し、巨額の利益を稼ぐことも行われました。
つまり、「勧進聖」は、事実上、巨大な企業家であったのです。
『律僧はただ勧進をするというだけではなくて、手工業者、職人を組織していたと考えられます。
たとえば、叡尊の場合、中国から渡ってきた宋人の石工に、般若寺を建てる時の石塔をつくらせていますし、忍性も石工と深いかかわり〔…〕鋳物師との関係もあったようで、律僧はこうした職人を動員して寺社の修造を推進〔…〕そうした工事の請負人だったともいえます。
また当時、中国大陸とのあいだにはさかんに「唐船」が往来し、貿易が行われていました。〔…〕「唐船」に乗って、貿易商人として出かけた人も、律僧が非常に多かったと思うのです。13世紀の後半から 14世紀にかけて、このような貿易船が中国に行く場合、かならず勧進聖が乗っており、その利益で寺社の修造をやることになっていました。ですから律僧は勧進によって集められたものを資本として運用する企業家であり、また貿易商人』でもあった。
網野善彦『日本の歴史をよみなおす(全)』,2005,ちくま学芸文庫, pp.75-76.
律僧と同じことは、禅僧の一部にも言えました。勧進聖として「唐船」に乗った人には禅僧もおり、中国から水墨画などの文物や芸能、茶道、素麺、築庭の技術を持ち帰ったことが記録されていますが、文物だけで利益目的の貿易をしなかったとは思えません。たとえば、「唐船」は、船を安定させるためのバラストとして大量の銅銭を船倉に積んでいました。当時日本では貨幣を鋳造しておらず、流通したのはもっぱら宋銭でしたから、日本に帰国したらバラストを放出するだけで、巨額の利益になったのです。
『日本の社会では、商業や金融にたずさわる人びとには古代から僧侶が多かったのですが、この時期〔13-14世紀――ギトン註〕になると、〔…〕浄土宗、時宗、禅宗、律宗、さらには山臥の系統の僧侶が、金融や商業、廻船に従事している事例を、非常に顕著に見ることができます。』
網野善彦『日本の歴史をよみなおす(全)』,2005,ちくま学芸文庫, p.344.
丹波国穴生観音堂に逗留する一遍と時衆の一行 『一遍上人絵伝』
【54】遊行集団と一遍―― “原初への回帰” の思想
『「身命を山野にすて、居住を風雲にまかせて」遍歴する遊行(ゆぎょう)、信・不信、浄・不浄を問わず広くすべての人びとに名号札(みょうごうふだ)〔受け取るだけで極楽往生が決定するという――ギトン註〕を賦(くば)る賦算。そして念仏するよろこびを身体そのものの躍動によって表現する踊念仏。これが一遍の思想・宗教のおのずからなる行動であり、その特質を端的に示している〔…〕
遊行の開始当初は数人であった一遍の一行は、やがて十数人から数十人の大集団にふくれ上がっていく。この遊行はもとより単純な旅行ではなく、〔…〕縄文時代に遡りうるきわめて原始的で粗末な衣をまとった姿に、すべてを捨て去り切ったことを端的に示す、自覚的な乞食僧の集団の修業・伝道の旅であったが、こうした集団の移動が九州・四国・本州の全域にわたって〔…〕可能になったのは〔…〕こうした旅人たちの宿泊を広域的に支えた施設のネットワークが実際に形成されていたことをよく示している。』
網野善彦『日本中世に何が起きたか』,2017,角川文庫, pp.213-214.
「受け取るだけで往生が決定する名号札」とは、ルターを怒らせたカトリックの「免罪符」も顔負けのシロモノですが、「免罪符」は高価で販売されたのに対し、一遍の「名号札」はタダで誰にでも配布したという点が、とにかくすごいと言わざるをえないのです。
その「名号札」には、「決定往生六十万人」と、配布の目標が書かれていました。13世紀における日本の人口は 500-600万人ほどでしたから(⇒:近代以前の日本の人口統計)、「60万人」という目標の巨きさが知れますが、けっして非現実的な数字でないことも解ります。このような目標を「一遍が掲げ得たのは、13世紀後半という時期が、すでに特定の個人がそれだけ膨大な数の人びとと接触〔…〕を考えうるだけの条件をつくり出していたから」だと言えます。それだけの交通路の発達があっただけでなく、不特定多数の人の集まる場が、各地に簇生していたのです。『一遍上人絵伝』に描かれているだけでも、各地の著名な寺院、各国の「一宮(いちのみや)」、各所の「市庭」「津」「泊(とまり)」などがあります。
「踊念仏」も、こちらの最初の絵に見るように、京都の古谷道場、近江の関寺、相模・片瀬の地蔵堂では、舞台小屋を仮設し、見物の桟敷まで作って、多数の観衆を集めた「芸能」として行われています。
『遊行、賦算、踊念仏のいずれもが、不特定の多様な人びとが数多く往反し、群集する場の存在を前提としていたのであり、〔…〕一遍の宗教は、まさしく都市ないし都市的な場に生きる人びと、形成されつつある都市民を背景に生み出され、そうした場と人びとを前提とした方法によって〔…〕布教されたのである。』
網野善彦『日本中世に何が起きたか』,2017,角川文庫, pp.216-217.
他方、「信・不信」「浄・不浄」を区別することなく、どんな人も無差別に救い上げるという一遍の思想は、やはり不特定者が行き交う都市の思想であり、商工業者ともかかわりのある宗教だと、網野氏は述べています(op.cit.,p.167)。たしかに、安定した定住農民よりも、明日の生死さえ知れない・移動する都市民にこそ、この教えはふさわしい。
一遍の宗教は、社会の底辺にいる「乞食」や「非人」たちから強く支持されており、遊行の過程で多数の女性が、その遊行衆に加わっています。かつての「聖性」と “神通力” が色あせ、しだいに隔離され底辺に押し込められようとしていた・これらの人びとの心を、一遍の「無差別」の教えがつかんだことは、十分に想像できるでしょう。そしてそれは、商工業者など「無縁の場」に集まる人びと一般に、多かれ少なかれあてはまることでした。
北条時宗の従者に追い払われる一遍と時衆 『一遍上人絵伝』小袋坂木戸の場
一遍の宗教は、底辺の民衆や特定の階層に限定されず、貴族にも武士にも、神官や僧侶にも、広く支持者を見出していました。とは言っても、貴族や、大寺社の僧侶、上層の武家のあいだからは、一遍と時衆に対する激烈な批判も巻き起こっていたのです。執権北条時宗が、時衆を乞食と同一視して、鎌倉への入場を禁止し追い散らしたのも(⇒:(13) の最初の絵を参照)、そうした激しい嫌悪の現れだったと言えます。
『こういう動きを我慢ならないと考えている勢力も当然あったのです。大寺社の僧侶や貴族、武家、とくに「農本主義」的な路線に立つ人びとは、〔…〕真っ向から非難を加えます。この見方は『天狗草紙』という絵巻や『野守鏡』という歌論書によってはっきりわかりますが、穢れた女性たちを加えて集団をなして遊行をし、「非人」を従えていることをきびしく批判しています。』
網野善彦『日本の歴史をよみなおす(全)』,2005,ちくま学芸文庫, pp.358-359.
『その〔ギトン註――『天狗草紙』と『野守鏡』の〕作者たちは一遍が男女一緒に遊行しているということに対して口をきわめて非難をしていますが、踊念仏に対して「まるで野馬のように肩を揺すって、男女とも根も隠すところなく踊りまくる」と〔…〕
穢(けが)れているものも、穢れていないものも、善人も悪人もすべてを救うという一遍の教えに対する非常にきびしい批判〔…〕』
網野善彦『日本中世に何が起きたか』,2017,角川文庫, pp.168-169.
貴族・武士・僧侶の上層部、統治者を自負する人びとから一遍と時衆に向けられた激しい非難は、彼らの思想・行動のうち、何をターゲットにしていたのか。――悪人も、「穢(けが)れた者」も、信心のない者も、誰もが往生できるという教え、女性も非人もまったく差別しない布教方法、こうした一遍の「無差別」の教えこそが、彼らをいらだたせたのだと思います。
そのことは、「穢れ」と「祓(はら)い」、「信心」と「不信心」、「善」と「悪」、「男」と「女」、‥‥そういった区別によって成り立っていた社会の価値と秩序が、混迷し、危殆に瀕していたことを示すものです。古い秩序の維持を図ろうとする人びとは、それらを完全に否定しようとするかに見える一遍の教えと行動に、おそろしい危機感を抱いたのではないでしょうか。
逆にいえば、一遍の思想と行動は、激しい社会変動の中で重大な疑問を突き付けられた従来の価値を、いったんすべて否定し、 “原初” の状態に巻き戻そうとする志向を持っていたのです。一遍らが、もっとも原始的な「網衣(あみぎぬ)」を身にまとい、舞踏によるオルギーの興奮から陰部をも顕わして全裸になることを厭わなかったのは、まさに、“原初への回帰” の衝動ではなかったでしょうか?
(ちなみに、前回の4枚目:『職人歌合(うたあわせ)』の絵を見ると、「博奕打(ばくちうち)」が全裸で描かれています。当時、全裸には、習俗的か宗教的か、何かの意味があったと考えざるをえないのです。)
『「念仏する時ハ、頭をふり、肩をゆりておどる事、野馬のごとし、さはがしき事、山猿にことならず、男女根をかくすことなく、食物をつかみくひ」と時衆を罵倒〔…〕する『天狗草紙』、「よろづ(万)いつは(偽)りてすべからずとて、はだかになれども、見苦しき所をもかくさず、偏に狂人のごとくにして、にくしと思ふ人をば、はゞかる所なく放言して、これをゆかしく、たふと(尊)き正直のいたりなり」とする一遍の徒をののしる『野守鏡』』
網野善彦『増補 無縁・公界・楽』,1996,平凡社ライブラリー, p.151.
【55】「悪党・海賊」と「重商主義」vs 豊臣・徳川の「農本主義」
『一遍上人絵伝』の一場面に、尾張國甚目寺(現在、名古屋市の北西に接する名鉄津島線沿い)で、2人の「徳人」(裕福な人)が、一遍の一行に食料の施業〔お布施,差し入れ〕を行なう景があります。
寺の外垣に沿って、犬神人(いぬじにん)〔非人のリーダー〕に率いられた「非人」の群れが、寺の中の時衆を警護するように居並び、「徳人」のひとりは、本堂の前でひざまずき、中の一遍と時衆に、何事か申し出ている。高足駄をはき、団扇(うちわ)を持った・もうひとりの「徳人」が、威風堂々と肩をそびやかして、本堂に向って歩いており、後ろに、乳飲み児を抱いた女、巻いた茣蓙(ござ)を提げた女(少年?)、長柄(ながえ)傘をかつぐ男を従えています。「徳人」の妻子と付き人に見えます(↓下に拡大画像あり)。そのあとから、飯を入れた桶や桝(ます)を頭に載せた女たちと、食物と食器類のはいった唐櫃(からびつ)を担ぐ男たちが続きます。
『一遍上人絵伝』尾張甚目寺の場
『一遍上人絵伝』尾張甚目寺の場 生垣、犬神人(矢印)と非人
『一遍上人絵伝』尾張甚目寺の場 飯を運ぶ女たち
『一遍上人絵伝』尾張甚目寺の場 食器類?を運ぶ男たち
この2人の「徳人」が特異なのは、彼らの髪型です。当時、成年の男は髷(まげ)を結い、女は髪を伸ばして垂らすのが常例でした。日本中世の社会は、“短髪、スーツにネクタイ” のドレス・コードがどこでも厳格に守られているようなもので、服装や髪型は、出身階層や職業を正確に表していたのです。
しかし、このドレス・コードからはみ出ている人びとがいました。「非人」「乞食」「博奕打(ばくちうち)」など、いわば「境界外」の人びとで、蓬髪〔結っていない長髪〕や童形(どうぎょう)の髪〔ポニーテールのように後ろにまとめる〕をしていました。この「甚目寺の場」の2人の「徳人」は童形、「長柄傘の男」は蓬髪の姿なのです。
この「徳人」たちは、当時のコトバで言えば「異形(いぎょう)」の集団であったと言えます。
『一遍上人絵伝』尾張甚目寺の場 徳人B(矢印)と妻子、付き人
『一遍上人絵伝』尾張甚目寺の場 徳人A(矢印)と時僧たち
付された絵詞(えことば)によると、一遍たちは甚目寺で「七日の行法」を始めたが、食糧がなく、「力尽きて」しまった。その時、近くの「津」の「宿」にいた「徳人」たちの夢枕に毘沙門天が立って、一遍に供養することを命じたので、「徳人」たちは食事を用意して訪れたと云います。
さらに、絵詞(えことば)によると、このあと一遍らは、美濃・尾張を巡回して遊行したが、「処々の悪党」が札を立てて一遍の一行や、彼らに詣でる人びとを迫害しないよう命じた。「同心せざらむ者におきては、戒めを加うべし」と威嚇もまじえて布告したので、「よりて三年があいだ、海道をすすめ給うに、昼夜に」平穏に遊行することができ、難儀がなかったと云うのです。(当時、伊勢湾の海岸線は、岐阜近くまで入り込んでいて、濃尾平野は水郷のような状態でした。この地方の遊行は、まさに「海道」の旅だったのです。)
『つまり所々の悪党たちが高札(こうさつ)を立てて、一遍の布教にいっさい妨害をしてはならないと定めたので、なんの妨げもなく三年間、一遍は活動できたというのです。世の中から〔…〕山賊・海賊と扱われた悪党たち自身が一遍を擁護し、その布教を積極的に支持したというわけですが、』
網野善彦『日本の歴史をよみなおす(全)』,2005,ちくま学芸文庫, p.133.
絵巻の文脈からすれば、これは、甚目寺を訪れた「2人の徳人」のおかげで、こうなったと考えなければならない。つまり、「異形」の2名の「徳人」は、「所々の悪党たち」に威令をきかせ、遊行者の保護を命ずることのできる人びとであったことになります。絵巻の構図からすると、彼らは、「非人」集団とも、つながりがあったかもしれない。
『当時「悪党」といわれた集団は、童形の人びとや非人、さらには博奕打ときわめて近接しており、〔…〕一遍の布教はまさしく、悪党・童姿の人びとや非人に支えられながらおこなわれていった』
網野善彦『日本の歴史をよみなおす(全)』,2005,ちくま学芸文庫, p.133.
『当時の美濃・尾張の状況、その古地形からみて、この「悪党」の中に、河海にかかわりを持つ「海賊」のいたことは確実といってよいが、〔…〕「悪党」たちは自らの実力で、「海道」の交通路を管理し、高札を立てて自らの定めた禁制を実力で三年間も実現しているのである。まさしくこれは流通・交通路の自立的なネットワークであり、この時期の「悪党」「海賊」はまさしくこのようにそれを担った人びとととらえなくてはならない。
事実『峯相記』〔14-15世紀,播磨國を中心とする地誌――ギトン註〕の悪党も海賊を広く含み、播磨・但馬・丹波・因幡・伯耆にわたる広域的な縄張りの中で、〔…〕事前・事後の賄賂を受けとり、訴訟を請負って、「追捕犯籍・苅田苅畠、打入奪取」などの実力を行使して、それを執行したのであり、1315年、兵庫関に乱入して守護使と合戦した「悪党」もまた、巨倉(おぐら)池〔京都市伏見区から宇治市にまたがって存在した湖――ギトン註〕、淀川から大阪湾一帯の流通路に分布する山僧を中心とした広域的な組織であった。〔…〕
この時期の「悪党」「海賊」は、神人・供御人制の枠組をこえて流通・交通路のネットワークを自律的に管理する、商業・金融・交通に深く関わった人びとととらえることができよう。』
網野善彦『日本中世に何が起きたか』,2017,角川文庫, pp.224-225.
朝廷の「神人・供御人」制が形を整えたのは 13世紀初めでしたが、この 13世紀後半になると、早くもこの制度は、ほころびを見せ始めます。制度の枠におさまらない新しいタイプの商人・金融業者、闘争をも辞さない実力で遍歴営業活動を行なうアナーキーな「無縁」の人びとが続出してきたからです。
『13世紀以後の社会の発展は、たちまちその〔「神人供御人制」の――ギトン註〕枠をのりこえ、この制度を動揺させ、形骸化していった。新たな商工業者、金融業者、交通運輸業者、倉庫業者たちが広範に出現してくる〔…〕都市ないし都市的な場は、まさしくその中で姿を現わしてきたのである。「有徳人」「徳人」とよばれたのはこうした人びとで、〔…〕
〔ギトン註――『一遍上人絵伝』甚目寺の場の「徳人」の〕この「非人」にも通ずる「童形」の髪型、高足駄、団扇などの「異形」は、〔…〕未開で荒々しい野生が新たな都市的な風潮と結びついた、13世紀後半から 14世紀にかけての特有の風俗であった。』
網野善彦『日本中世に何が起きたか』,2017,角川文庫, p.222.
すでに 12世紀の段階で、朝廷の徴税令書が金融業者のあいだを流通して「為替手形」の役割をしていましたが、13世紀後半になると、「割符(わりふ)」とよばれる本格的な手形が流通しはじめます。
『13世紀後半以降の為替手形の流通が、どのような組織の力で保証されていたのかは、大きな問題です。当然、不渡手形、「違い割符」の出る場合もありえますが、このような場合や、手形をめぐる紛争がおこったとき、だれがどういう方法で保証し解決してくれたのかという問題です。
この時代の公権力は、〔…〕手形の流通についてはほとんど保証していません。京都の王朝政府も、鎌倉幕府も、荘園や御家人の所領など、土地問題についての訴訟は非常に熱心にとりあげ、その解決のための手続きも整備しています。〔…〕
ところが、銭の貸借や商業・流通関係の訴訟は、〔…〕制度があまり整っていない部門であり、〔…〕重要視されていなかった〔…〕
これは古代以来のことで、国家の「農本主義」がここによく現れているのですが、11世紀までは国制の外にあった神人、寄人たちは、自立的な金融・流通のネットワークをつくり、裁判も自分たちでやり、判決を自らの実力、武力で執行していたのです。』
網野善彦『日本の歴史をよみなおす(全)』,2005,ちくま学芸文庫, pp.346-347.
つまり、朝廷が何もしてくれないので、「神人」「寄人」と呼ばれた初期の商人・金融業者は、自分たちのネットワークで権力的に解決し、従わない者には武力で制裁(リンチ)を加えていたのです。これが、平安中期、11世紀までの状態でした。
しかし、これは、王朝の外で別の権力ができあがって跋扈してゆくことになりますから、朝廷にとってゆゆしい問題です。院政期の朝廷が「神人・供御人」制を公的制度として作り、12世紀から 13世紀初めまでに軌道に乗せたのは、このアナーキー状態を何とかしなければならないと考えたからです。しかし、それでもやはり、手形の流通や、不渡りの処理、商業紛争の裁定と執行、‥‥といった問題には、朝廷はタッチしようとしなかったし、幕府も不熱心でした。これでは、商業部門のアナーキーを解消することはできません。商人・金融業者は、結局やはり自分たちで独自権力を持って解決するほかはないので、そこで、「神人・供御人」制の枠からはみ出すような、新たなタイプの、より武力的でアナーキーな人びとが出て来ざるをえなかったのです。
それが、「悪党」「海賊」と呼ばれた人びとにほかなりません。
『13世紀後半から 14世紀にかけて、〔…〕金融・商業の組織や、廻船のネットワークは、前よりもずっと規模が大きく、また濃密になってゆきます。供御人、神人、寄人の組織は、さらに広域的に広がり、緊密の度合も強くなって、公権力の枠をこえて独自な動きを強めていかざるをえなくなってきます。
こうして、交通路、流通路を管理する人びとの組織の新しい活動がこの時期に目立ってくるのですが、このような人びとの動きが、権力の側から悪党・海賊といわれたのだと思います。〔…〕
これらの悪党や海賊の実態は、「海の領主」、「山の領主」のような、交通路にかかわりを持つ武装勢力をはじめ、商業・金融にたずさわる比叡山の山僧や山臥などであったことがわかっています。このように、交通路の安全や手形の流通を保証する商人や金融業者のネットワークは、13世紀後半から 14世紀にかけて、悪党・海賊によって保証されていたと考えられます。
〔…〕もともとは「遊手浮食の輩」などといわれ、博奕などにもたずさわっていた人びとですが、このころの悪党・海賊は広域的な組織を持っており、何かもめ事がおこると、賄賂、礼銭をとり、訴訟を請負って、トラブルを自力で〔つまり、暴力と実力で――ギトン註〕解決しています。〔…〕
この組織の中には女性もいたことは確実で、〔…〕遊女がかかわっていたことも考えられます。〔…〕
13世紀後半から 14世紀にかけて、幕府は執拗なまでに悪党・海賊禁圧令をくり返しくり返し発しています。』
網野善彦『日本の歴史をよみなおす(全)』,2005,ちくま学芸文庫, pp.348-350.
しかし、いくら禁圧しても効果のないことが判ってくると、幕府の中にも、むしろ、ただ禁止するよりも統制下に入れて、彼らのネットワークを利用して交通路や廻船流通を幕府が支配する方向で考える人びとが出てきました。彼ら「御内人(みうちにん)」は、積極的に金融業者と結んで、所領経営にも金融業者を代官に任命して上がりを増やしたり、全国の「津」「泊」を北条家の所領にして、廻船の上前をはねたり、といった流通支配政策に積極的に乗り出します。
「元寇」後になると、この「御内人」の勢力が大きくなって、商業・金融を蔑視する従来型の「農本主義」御家人勢力と激しく対立し、「霜月騒動」(1285年)が起きています。
さらに 14 世紀に入ると、鎌倉政権内の混乱に乗じて倒幕の陰謀を進める後醍醐天皇は、律僧、神人・供御人、非人など「無縁」の勢力と積極的に手を組むだけでなく、北条氏の禁圧策に反発する「悪党」「海賊」の武力に応援を求め、京都の流通・金融業者である「酒屋」「土倉」に対しても、支配下に入れて優遇するとともに、財政基盤として利用しようと図るのです。
たとえば、楠木正成の出自については諸説ありますが、河内の「悪党」で、金剛山で水銀鉱山を採掘し、交通路を押さえる武装商人であったとする説も有力です。そして、正成を後醍醐天皇に結びつけたのは、西大寺流の「律僧」文観でした。後醍醐方に「非人」を動員したのも文観だと言われています。(網野善彦・他『日本中世史像の再検討』,1988,山川出版社, pp.30,39.)
『悪党、海賊を積極的に組織し、時には非人の武力も動員することを辞さないで、商工業を発展させて、商業や金融に権力の基盤を置こうとする政治勢力――仮に、〔…〕重商主義といっておきますが、〔…〕これに対して、あくまでも田畠の所領、そこから年貢をとることを基本に置いて、「農は天下の本」〔…〕という方向できっちりとした政治を行なおうとする農本主義が対立する。』
網野善彦『日本中世に何が起きたか』,2017,角川文庫, p.171.
中世の人びとの言う「悪党」「悪僧」「悪人」といった語の「悪」は、「善・悪」の「悪」という意味よりも、「制御できない魔力のように人をとらえてしまう力」に対する恐れのニュアンスが強いのです。平治の乱で活躍する「悪源太義平(あくげんた・よしひら)」のように、強い武将の尊称としても、「悪」の語は用いられています。日本人がこれまで知らなかった貨幣経済の急激な隆盛のなかで、貨幣の抗しがたい魔力を象徴する語として、商業・金融にかかわる人びとに「悪」の語が冠せられたのではないでしょうか。
『13世紀から 14世紀にかけての時期は、銭貨の本格的浸透に伴う人間関係のあり方の大きな変化、それ以前の神仏の権威の低下という、自然と社会の関係の転換に伴い、この「悪」をめぐって、政治的・思想的にきびしい緊張関係が生まれた。政治的には「悪党」・「海賊」を徹底的に禁圧し、商業・金融を抑制しようとする「農本主義」的政治路線と、むしろ商人、金融業者と積極的に結びついて流通路を支配し、悪党・海賊もそのために動員することを辞さない「重商主義」的路線との間の鋭い対立がつづくが、〔…〕
この「悪」の問題と正面から向かいあった思想家たちが、鎌倉仏教の祖師となっていった〔親鸞の「悪人正機説」など――ギトン註〕〔…〕
16,17世紀、百姓は農業に従事していればよいという「農本主義」を建前とした世俗権力〔「太閤検地」と「刀狩り」、徳川の「士農工商」「石高制」――ギトン註〕と、都市民に主として支えられた宗教勢力との正面からの衝突、後者の敗退という動きの中で、商人、金融業者の俗人化と社会的地位の低下が進行してゆく』
網野善彦『日本中世に何が起きたか』,2017,角川文庫, pp.248-249,251.
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらは自撮り写真帖⇒:
ギトンの Galerie de Tableau