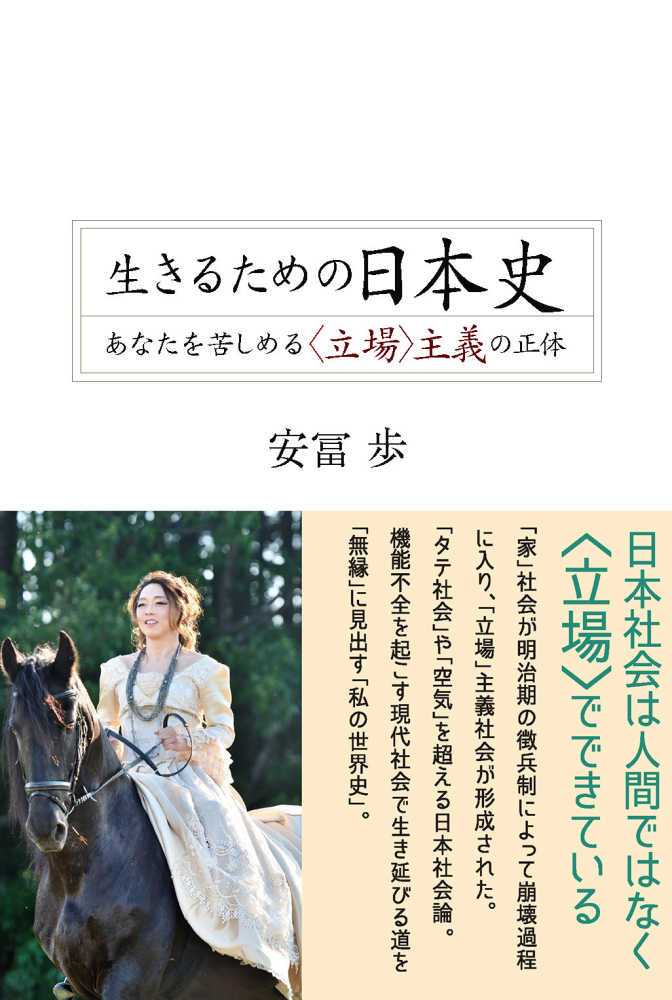佐久の踊り念仏 『一遍上人絵伝』東博本
1279年、一遍は、鎌倉幕府御家人・大井太郎光長の招きで、
弟子らを伴なって信濃國佐久郡の光長の館を訪れた。
【44】「一揆」と「アジール」――「無縁」の社会史
ここでおさらいしますと、勝俣鎮夫氏が注目したのは、非日常的・一時的に人びとが身を寄せようとする「無縁」でした。その人びとは、農民にしろ、武士や幕府の役人にしろ、大寺院の衆徒にしろ、いつもは「有縁」の世界の人であり、定住農業社会の一員でした。「縁」のしがらみにひたっていたのでは、どうしても突破することができない極限的な困難に逢着した時、彼らは一時的に、非日常的な「無縁」の世界に移行し、一時的に「無縁」の人となって、問題を解決しようとするのでした。その世界では、中世の社会を支配した主従と依附の「縁」は切れ、「自由」「平等」「自立」の原理が支配した、というのです。
その場合、一時的にもせよ「有縁」の世界を離れ、それら「無縁」の原理を身に帯びるためには、「縁」を断ち切ったと思える根拠がなければなりません。それが、たとえば「一揆」農民が駈け入る「山林」のような、「無縁の地」であったのです。彼らがふだん暮らしている定住農業社会の外側には、広漠とした「無縁」の世界が広がっている――当時の人びとには、そういう観念があったと言えます。
それならば、その「無縁」の世界のほうに生活の本拠をもっている人がいれば、その人にとっては、「無縁」は一時的・非日常的ではなく、恒常的かつ日常的な生活原理なのではないか。
この点に注目したのが、網野善彦氏だったと言えます。
「山林」、河と海、道路、それら交通路の結節点にできる「津泊〔みなと〕」「市(いち)」「宿」……そうした「無縁」の世界に生活の本拠をもつ人と言えば、いわゆる「漂泊の民」――遍歴職人、行商人、遍歴・遊行僧(ゆぎょうそう)、旅芸人、遊女、さらに、乞食、非人といった、移動生活をする人びとが浮かびます。「海人(あま)」「山人」といった非農業民も、定住農民を主な対象とした国家・領主の支配システム――「農本主義」体制――から逸脱しているという意味では、「無縁」の民にふくめて考えられるでしょう。
ただ、これらの人びとに関しては、定住農民の場合とはちがって、極端に文字史料が少ないのです。平安中期以前に関しては、ほぼ皆無と言ってよいでしょう。「海民」に関しては、じつは膨大な資料が、奥能登など今は辺地となっている・かつての海上商業の根拠地に残されているのですが、それらが “発掘” されて研究の対象となったのは、網野氏以後と言ってよいのです。
そこで網野氏は、「非定住民」に断片的にふれた史料を多数集めて比較したり、間接的な史料から推定したり、といった操作を駆使して、従来の日本史ではおもてに現れなかった「無縁」の領域に光を当てようとしました。想像力をおおいに働かせなければ、何も解明できないことになります。従来扱われてこなかった・中世特有の特殊な語の意味も解明したうえで、史料を解読しなければなりません。いきおい、「史料から確実に言えることだけを言う」という従来の歴史学とは異なるスタイルをとらざるを得ないので、『無縁・公界・楽』が世に出た 1970年代には、「網野歴史学」に対する学界の風当たりは激しかったのです。とくに日本共産党員や “革新” 陣営の学者たち・大学院生たちのなかには、悪意に満ちた「偏見」を向ける者さえ見られました。
アジール: チャールズ・フォスター「逃れの町」
この本の中で網野氏が最初に注目しているのは、江戸時代の「駈け込み寺」のような “アジール” です。いわば、「無縁」原理が、狭い領域に閉じ込められて、その中でだけ許されているような場所――日本中世の言葉でいえば、「無縁所」です。
離婚を求める女性の「駆け込み寺」としては、鎌倉の「東慶寺」が有名ですが、ほかにも幾つかあります。犯罪を犯した人の「駆け込み寺」もありました(⇒:[ヤマレコ]相模大山(2) 日向の「浄発願寺」)。しかし、戦国時代以前には、このような「駆け込み寺」や、「駆け込み」の可能な場所は、各地に非常にたくさんあったのです。「浄発願寺」は、重罪人までは保護することができませんでしたが、戦国時代の「駆け込み寺」は、犯罪の種類を問わない。殺人でも強盗でも、そこに駆け込んで一心に仏に帰依すれば、捕吏に引き渡されることはなかったのです。
また、戦国時代までの「駆け込み寺」やアジールには、「奴婢」や「下人」、つまり奴隷も駆け込むことができました。『安寿と厨子王』という昔話はご存知でしょう。森鷗外の小説のもとになった講談によると: 人さらいに騙されて「山椒大夫」の奴婢にされた厨子王は、丹後の「国分寺」に逃げこみ、そこにいた「遍歴の聖(ひじり)」にかくまわれて、追手を逃れることができました。これは中世末の話です。
しかし、徳川幕府は、それらの「無縁所」を圧迫して可能な限り壊滅させ、残された「東慶寺」等に対しても、しだいに制限を強めていきました。とくに「享保の改革」以後に、制限は厳しくなっています。
そうすると、そこから想像力を働かせると、もともと古い時代には、「無縁」の場所はもっと広範に存在していたにちがいない――と考えてみることができます。
旧石器時代や縄文時代には、所有権も主従関係もありませんから、すべてが「無縁の場」であったろう。古代社会になっても、たとえば「班田収授」というのがあって、すべての平民男子に同じ面積の田を支給する、というのが建前だった。「班田収授」が曲がりなりにも実施されていたとすれば、当時の人びとにとっては、もともと土地所有権というものはなかったと考えなければならない。そして、「全員が平等」ということに対する抵抗もなかった。つまり、無主・無縁の世界が広がっていたことになります。(網野善彦『増補 無縁・公界・楽』,1996,平凡社ライブラリー, pp.234-251.)
しかし、その後「荘園」が広がって、日本じゅうの田畑に領主がいて年貢を取り立てる中世――「荘園公領制」の時代になると、「無縁の地」は、山林・河・海・道路といった、誰のものでもない無主無人の地に制限されるようになります。そして、そうした「無縁の地」と、田畑があって領主がいるふつうの土地との・「境界」に本拠を持つ「遍歴の民」や「海民」「山人」は、「無縁」の人びととして特別視されるようになるのです。
そのような、「農本主義」の支配が及ばない非農業民は、朝廷や歴代幕府のような権力者にとっては、たいへんに厄介な存在です。なんとかして支配下に取り込みたい。また、彼らの勝手な行動を制限していこうとする。こうした歴代の支配者の努力の結果として、「無縁の場」は潰されて次第に少なくなり、「無縁」の人びとは減って、江戸時代には「無縁」の原理は、ごくわずかの「駆け込み寺」に残されるだけとなったわけです。
かつては自由に遍歴していた「遊女」も、公認された遊郭に閉じ込められ、「非人」は被差別部落に押し込められました。それらは江戸時代には、実際上はともかく公式には、アジールの機能を喪失しています。
【45】「無縁」「公界」「楽」――8つの特徴
それでは、中世には盛んだったという、網野氏の言う「無縁」の原理とは、具体的にどんなものだったのでしょうか?
じつは、室町末~戦国時代になると、幕府、守護大名などが、市場(いちば)や「無縁寺」の特権を認めて与えた文書が、たくさん残されるようになります。中世の市場の多くは、河原や、港、街道の結節点に設けられ、代表的な「無縁の場」でした。大名などの権力者としては、それらの「無縁の場」が従来から持っていた特権を認めてやるかわりに、支配下に取り込み、その特権も、しだいに制限していこうと努めたのです。織田信長ら戦国大名の「楽市・楽座令」は、その頂点に立つものでした。
「楽(らく)」とは、当時のコトバで「無縁」を意味しました。また、同じことが、場合によっては「公界(くがい)」とも呼ばれています。
しかし、そうした取り込みのおかげで、「無縁の場」のようすを伝える多くの文書が残されることになりました。網野氏にしたがって、これらの “特許状” を中心とする文書に現れた「無縁の場」の特徴をまとめると、つぎのようになります:
(1) 不入権
大名の家臣や領主の役人が、逮捕や財物検索のために入って来ることを、禁止しています。「駆け込み寺」の場合にはハッキリしていますが、ふつうの市場でも、「理不尽の使入るべからず」といった規定をしばしば設けています。市場内に家臣の武士が居住することを禁じた条項も見られます。この場合には、「不入」の延長であるだけでなく、大名としては、主従関係を堅持すべき家臣が、市場の人びとと縁を結んで「無縁」原理に “汚染” されることを、防止しようとしたと見ることができます。
(2) 年貢・課役の免除
市場などの敷地に対する課税、取引税、市場に住む人の人頭税や諸役など、いっさいの租税・地代の賦課を禁止するのが、「無縁所」「公界」「楽市場」に与えられる特権の通例でした。
ただ、次節で述べるように、前代から引きつづいている多くの「無縁所」や「無縁」の人びとが、朝廷の「供御人(くごにん)」、寺社の「神人(じにん)」「寄人(よりうど)」として、それらの権威にもとづいて諸特権を認められていました。その場合、彼らが朝廷などに納める「公事(くじ)」〔特産品など〕は、彼らの「無縁」としての「聖性」を基礎づけるものにほかなりません。天皇や神仏の権威によって、彼らは他の幕府、大名、領主に対する一切の税・役を拒否する特権を保持したのです。
(3) 自由通行権の保証
『周防の禅昌寺、尾張の雲興寺、自治都市博多、美濃の加納・楽市場など〔…〕無縁・公界・楽の場に住む人々は、自由通行権(戦国大名の場合には、分国内通行権)を保証されていた。〔…〕楽市場の住人が通行税の免除、路次の安全通行を社会的に保証されていたこと〔…〕このような無縁・公界の場に来住する人々が、それ自身、公界者・無縁の人々であり、そうした人々は〔…〕、無縁の人々として、このような自由通行を保証されていたとみる』
網野善彦『増補 無縁・公界・楽』,1996,平凡社ライブラリー, pp.111-112.
つまり、大名などが「楽市場令」によって自由通行権を認めたのは、当時、大名が認める以前から、「無縁寺」や、市場の住人には、社会の慣習として「自由通行権」があり、彼らは特別な人間として、関所の通過税を免除され、通行の安全を保証されるという社会的な了解があった。戦国大名は、それをあたかも自分が与える特権であるかのように “特許状” に書き込んだのだ、と言うのです。
じっさい、自由通行権を認められた人びとのなかには、古くから朝廷の「供御人」といった地位に基いて、諸税・関渡津料を免除されてきた者もいます。彼らの起源をたどってゆくと、中世前期(鎌倉時代)の「供御人」に行きつくでしょう。そうした、自由通行権を保証された商人や遍歴職人が、市場や、市場をもつ寺内地に定住するようになったので、戦国時代には、市場そのものが、そこに関係する人すべてを「公界者」「無縁」の者と認めさせ、自由通行権を保証する「場の特質」をもつようになった、と網野氏は言うのです。
「洛中洛外図屏風」
(4) 平和領域
『無縁・公界・楽の場は〔…〕「敵味方の沙汰に及ば」ぬ「平和領域」であった。〔…〕〔ギトン註――そこに出入りする〕三昧聖(ひじり)・勧進(かんじん)上人・禅律僧・山伏をはじめ、連歌師・茶人・桂女(かつらめ)等々、商工民をも含む広義の「芸能民」は、みな平和の使者たりうる「平和」な集団であった。世俗での争い、戦闘――「闘諍喧𠵅(けんか)」「殺害刃傷」〔…〕、さらには訴訟もここには及んでこない。』
網野善彦『増補 無縁・公界・楽』,1996,平凡社ライブラリー, p.113.
つまり、市場でも、他の「無縁所」でも、戦闘は禁じられました。市場で仇討ちをしているテレビの時代劇は、とんでもない間違えです。これは、「楽市令」が出されるまでもなく、商業取引の場を成立させるために必須の、最低限の掟であることが明らかです。
そればかりでなく、万が一、ケンカや刃傷沙汰が起きて被害が出てしまったとしても、後日その復讐をしたり、訴訟に訴えることはできなかったのです。中世には、道路、市場などの「開かれた場」では、そこで起きたことはその場限りとする、という不文律があったと考えられます。神聖な場であり「平和領域」であるとは、そういう意味なのです。
「誰が悪い」ではなく、とにかくケンカはあってはならない――それが「神の平和」の意味です。仇討ちなど、とんでもない。
また、当国の者か、他国の者かを問い質したり、敵味方を判別することも、市場では禁じられました。どこの国の者でも、やってきて商売ができる。それが鉄則でした。
『罪人の駈入り〔…〕も認められたのである。』
網野善彦『増補 無縁・公界・楽』,1996,平凡社ライブラリー, pp.113-114.
市場は、駆け込み寺と同様に、逃げ込んだ犯人を追いかけて行くことができない場所とされていたのです。
映画「山椒大夫」
(5) 私的隷属からの解放
「無縁寺」にしろ市場にしろ、下人や所従が逃げこめば、主人は連れ戻すことができないとされました。「いかなる奉公人でも吟味しない」とされ、荘園から逃亡した百姓の「走り入り」の場とされたのです。
逆に、主(ぬし)持ちの武士が、主との関係を保ったまま市場内に移住しようとする場合、市場は拒否することができました。
『これらの文言は、私的な主従関係、隷属関係が無縁・公界・楽の場には及び難いことを明らかに示している。〔…〕
〔ギトン註――市場の人びと、つまり〕公界者・公界往来人は、大名、主人の私的な保護をうけない人々、私的な主従、隷属関係から自由な人々であった。主人面をして手をかけようとするもの〔庇護してやろうと言う者――ギトン註〕を、断乎として拒否するこうした人々の行動は、戦国期、なお社会的に認められ、支えられていたのである。』
網野善彦『増補 無縁・公界・楽』,1996,平凡社ライブラリー, pp.114-115.
つまり、このような「無縁」の世界の「掟」は、市場など「無縁所」を守る人々が、強い自立心をもって主従関係を拒否し、権力者の誘惑にも脅しにも屈しない態度で支えていなければ、決して維持できるものではありません。「楽市楽座令」は織田や豊臣の先進的な政策によって導入された、などというのは、まったくありえないことなのです。
(6) 貸借関係の消滅
『借銭・借米が無縁・公界・楽の場では破棄された』
網野善彦『増補 無縁・公界・楽』,1996,平凡社ライブラリー, p.115.
市場や「無縁寺」などに来て、貸金や貸米の取り立てをすることはできませんでした。滞納した年貢の取り立ても同じです。事実上、市場の商人は、金を借りても返さないでよい、ともとれる規定です。ところが、次のような「掟」もあるのです:
『そして同じ原理から、無縁・公界・楽の場が徳政を免許〔免除――ギトン註〕されていたことも、〔…〕こうした場に特有の属性とみなくてはならない。』
網野善彦『増補 無縁・公界・楽』,1996,平凡社ライブラリー, p.115.
つまり、市場には徳政令が及ばないのです。徳政令が及ぶ・及ばないが問題になるということは、「借銭・借米」とは逆に、市場の商人が外部の人に貸した貸金・貸米は有効で、取り立てできたことになります。しかも、徳政令が発令されたって関係ない。利息の最後の一毛まで搾り取れるのです。こんな手前勝手な「掟」があるでしょうか?!
網野氏は「同じ原理で」と言っていますが、私には、これはまったく理解できません。
もしかすると、網野氏の解釈がおかしいのではないか?‥とも思うので、少し考えてみます。市場の商人(お寺の坊さんでも同じ)が借りた貸借は「破棄され」、貸した場合は有効である。もしそうだとすると、坊さんにも商人にも、カネや米を貸す人はいなくなるでしょう。坊さんはそれでいいかもしれません。お布施をもらえばよいのです。坊さんは借金をするな、ということでいいでしょう。
商人は、それでは困るのではないでしょうか?……ひとつの解釈は、市場という場では、取り立てのような、紛争になりかねないことをするな、という意味だと考えることです。つまり、借金が「破棄」されるわけではなく、その場では取り立てができないだけ、と考えればよい。そもそも、商人は金の貸し借りができなくなったらアウトですから、「あいつに貸したら、返ってこなかった」という評判が立たないようにするためには、どんな掟があろうと、自分からキチンと返すでしょう。
そういう信義が前提ならば、「徳政令が及ばない」というのも理解できます。徳政令があろうと何があろうと、借りたものはきちんと返す、これが市場商人である――ということなら、その市場は繁栄するにちがいありません。
以上は、あくまでも私の解釈です。史料的根拠があるわけではないので、ほんとうにそう考えてよいのかどうか、わかりません。この疑問は疑問のままにしておくほかありません。
ところで、坊さんの場合ですが、当時、お寺や神社が行なった貸金を「祠堂銭」と言います。お布施や寄付を集めてきて原資にして、それを貸して利息を取って増やすのです。そうやって増やした資金は、本堂や祭殿の修理とか、神仏のためにだけ使う。坊さんの贅沢には使わない。そういう信頼が、当時の社会にはあったようです。「祠堂銭」には徳政令が及ばない、というのも、そういうことなら理解できます。神仏のものを借りておきながら、返さなかったら、それこそバチがあたる‥
ちなみに、「祠堂銭」は、当時のふつうの貸金よりも利子が安かったと言われています。どのくらいだったのかはわかりません。当時は高利が当たり前でしたから、安いと言ってもねえ。。。
Parrish Maxfiels (1870-1966): Air castles, 1904.
(7) 連座制の否定
当時、「無縁」以外の一般社会では、犯人の家族を処罰する「連座」、犯人の近所の人や犯人の家主を処罰する「縁座」は、ごくふつうのことでした。しかし、市場では、犯人一人を処罰せよと決められていて、連座・縁座は禁止でした。喧嘩口論、放火、火事の火元責任などの連・縁座禁止規定の史料が残っています。
「無縁」の場を構成した人びとの、個人としての「自立」の現れであるように思います。
(1) の「不入権」に対応して、内部の秩序維持のための処罰は、自治としてやっていたこともわかります。
(8) 老若の組織
以前に (10)【38】で、日根野荘入山田村の村民自治は、村の成年男子全員が年齢階梯で「老(おとな)」「中老」「若衆(わかしゅう)」に分かれて、それぞれ仕事を分担し、重要な問題は成年男子全員の「寄合(よりあい)」で決める、という平等主義的な組織を見ました。
各種「無縁の場」の自治も、基本的に、これと同じだったようです。ただ、たとえば、自治都市の場合ですと、少数の大商人だけで自治組織を作って町全体を運営していたり、その自治組織の中も、年齢順ではなく、富裕度の順に発言権が大きかったなど、そういった傾向があります。意志決定方法も、多数決であったのかどうか、わかりません。
職種ごとの「職人」組織の場合には、年功・熟練度の順になっていたと思われます。「遊女」なども同様ですが、上臈(じょうろう)の権限がひじょうに強かったかもしれません。「駆け込み寺」に駆け込んだ女性たちのあいだにも、かなり厳しい階梯序列があったと言われています。
「一揆」のような非日常的・一時的集団でなく、日常的・恒常的組織になると、やはり、完全に平等な民主制というのは難しいのかもしれません。それでも、当時の幕府、大名、領主の独裁体制や、朝廷・公家の硬直したヒエラルキー体制と比べれば、「無縁の場」の平等性・民主性の程度は、かけはなれて大きかったと言わなければなりません。
【46】中世人の理想
『以上、無縁・公界・楽の場、及び人の特徴をまとめてみたが、このすべての点がそのままに実現されたとすれば、これは驚くべき理想的な世界といわなくてはならない。俗権力も介入できず、諸役は免許、自由な通行が保証され、私的隷属や貸借関係からの自由、世俗の争い・戦争に関わりなく平和で、相互に平等な場、あるいは集団。まさしくこれは「理想郷」であり、〔…〕
もとより、戦国、織豊期の現実はきびしく、このような理想郷がそのまま存在したわけではない。〔…〕俗権力は、無縁・公界・楽の場や集団を、極力狭く限定し、枠をはめ、包みこもうとしており、その圧力は、深刻な内部の矛盾をよびおこしていた。それだけではない、こうした世界の一部は体制から排除され、差別の中に閉じこめられようとしていたのである。餓死・野たれ死と、自由な境涯とは、背中合せの現実であった。
とはいえ、〔…〕さきの諸特徴を現実化し、理想郷をつくり出そうとする強靭な志向は、「有主」の原理の否応のない浸透と、そこに基礎をおく強大な権力の圧力にも屈することなく、自らを必死で貫徹しようとしていた。それは、こうした場を、当時の人々が「楽」「公界」と名付けたという事実そのものに、端的に現われている。』
網野善彦『増補 無縁・公界・楽』,1996,平凡社ライブラリー, pp.118-119.
「楽」とは「十楽」のことであり、当時の仏教用語で「極楽浄土」の 10の楽しみを意味しました。(源信『往生要集』)
「公界」も仏教用語であり、本来は、「俗界の縁を断ち切って修業を行なう場」を意味しました。しかし、当時この言葉は、「私」に対する「公」「世間」をさすコトバとして、一般に広く用いられてもいました。
『そしてまた「公」なことは当然「公正」なことでなければならず、また秘されるべきことではなく、〔…〕さらに進んで、「公正」ということが、一方につながれない「自由」なことを意味する場合』
網野善彦『増補 無縁・公界・楽』,1996,平凡社ライブラリー, p.295.
‥‥があったと言います。当時の用例として、「人ニモ不仕〔つかえず〕ノ公界モノ」というのがあります。「公界寺」とは、特定の檀那の保護を受けない無私公正な寺というニュアンスで、「無縁所」である寺院を意味しました。
『「公界」は〔…〕私的な縁の一切を断ち切る強い意志を秘めている。「理想郷」をめざす志向に抑圧を加えようとする力に対し、これを断固拒否する姿勢を示す表現として「公界」は最も適当だったといえよう。』
網野善彦『増補 無縁・公界・楽』,1996,平凡社ライブラリー, p.121.
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらは自撮り写真帖⇒:
ギトンの Galerie de Tableau