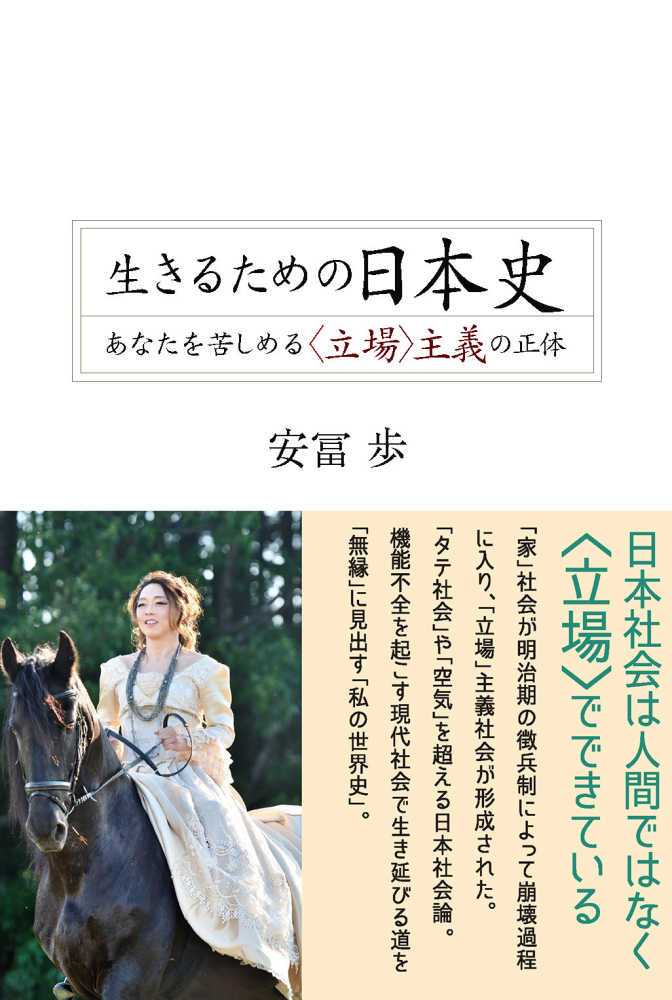村を襲う守護大名の軍勢 宮下実・絵,勝俣鎮夫・文『戦国時代の村の生活』
村の若い女を担いで拉致してゆく侍たち、奥では、村人を強制して米俵を
運び出させている。家々に火が付けられ、抵抗する若衆が槍で突かれている。
【41】 寺社衆徒の「一揆」
前回見たように、中世の日本は厳しい身分制社会であり、しかも江戸時代とは違って身分による力関係も主従関係も流動的で、さまざまな権威、権力、武力が激しくせめぎ合う、内乱が常態化した社会でした。
それは最下層の農民も例外ではなく、農民は、自分たちの生活を守るために「惣村」に結集し、外に対しては武装して戦い、内に対しては連座・死刑をふくむ厳しい統制をしいたのです。社会は上から下まで、主従と姻戚の「縁」によって、がんじがらめに縛りつけられていました。
「一揆」という、日本中世に特有な集団結成方法は、このような格差と「縁」のきづなでがんじがらめになった日常から、一時的にもせよ人びとが離脱し、なにものにも屈従しない「自立性」と、成員間の完全な「平等性」のもとで、人びとが突き当たった極限的な困難を乗り越えるために結ばれました。多くの場合に、「一揆」は最後の手段でした。
特定の目的のための非日常的・一時的結合――という点に、「一揆」の特質があります。
さて、「衆議」→「多数決」による決定→「一味神水」という手続きをへて成立した「一揆」集団は、参加者全員によって、決定事項の実施に移ります。その内容はさまざまですが、重要な点は、全員によって行われることです。農民の「一揆」が領主に直訴する場合も、寺院の僧徒が朝廷に訴え出る場合も、代表者が行くのではなく、「一味神水」をした参加者全員が、集団で押しかけました。つまり、多数決で反対に投票した参加者も、全体の決定に従って “心を一つにして” 全員で実行するのです。なぜなら、「一揆」の衆決は “神の意志” だからです。
決定に反することは許されません。「じつは私は反対したんです」などと後から言えば、「諸人(もろびと)の嘲(あざけり)」の的になりました〔鎌倉幕府「御成敗式目・起請文」〕。なぜなら、「一揆」の衆決は “神の意志” だからです。
文字を書けない農民のレベルでの「一揆」が、どの程度古くからあるのかは、記録が残らないので分かりません。文書が残っているかぎりで最も古いのは、寺院の僧徒の「一揆」です。僧徒の場合を見ましょう。
『院政時代、専制君主として権勢をふるった白河法皇が、「賀茂川の水、双六(すごろく)の賽(さい)、山法師(やまぼうし)、是(これ)ぞ朕が心に随(したが)わぬ者」と嘆いた話は有名である。』
勝俣鎮夫『一揆』,1982,岩波新書, p.41.
「賀茂川の水」とは洪水、「山法師」とは比叡山の僧徒のことですが、大寺の僧徒による「列参強訴」は、この院政期を頂点としつつも平安時代から室町時代までつづいた現象であり、比叡山延暦寺、園城寺、奈良興福寺、東大寺などにかぎらず、地方の大社寺も強訴の主体として猛威をふるいました。当時の人びとは、日常的に神罰、仏罰の存在を信じていましたから、俗界で権勢をふるう地位にある者も、神意とされた僧徒の強訴要求の前には無力でした。白河法皇など、院政の独裁者たちも、強訴の要求に対しては、「理非にかかわりなく、それが強訴であるというだけで認めてしまうのが一般的であった」のです。
『列参強訴の前に、かならず〔…〕衆徒の集会がひらかれた。〔…〕寺院全体の意志を形成する場合、満寺集会という衆徒全員が出席する集会が開催されたのである。〔…〕
この強訴の衆徒集団の様子は、法螺貝が吹きならされ、鉦や鼓が打ちならされ、数千の衆徒の放声や怒号があたりにひびき、道筋では喧嘩や乱暴狼藉がおこなわれ、これが定まったふるまいとされていた。』
勝俣鎮夫『一揆』,1982,岩波新書, pp.46,50.
延暦寺の場合には日吉神社の神輿(みこし)をかつぎ、興福寺の場合には春日神社の神木を先頭に立てて、怒涛のように押し寄せたのです。強訴による刑事責任はいっさい追及されないという特権的な慣習が、鎌倉時代にはできあがっていました。逆に、強訴を阻もうとした武士は、強訴側の要求によってしばしば処罰されました。
日吉大社・東本宮 比叡山の地主神・大山咋神と、延暦寺・天台宗習合の
山王権現を祀る。1095年以来、延暦寺の衆徒と日吉神社の神人は、日吉社の
神輿をかついで朝廷に強訴を繰り返し、室町時代末までに 40数回にわたった。
『列参強訴という形態は、当時の寺社勢力にとって〔…〕正当な手段とされていたのである。』
勝俣鎮夫『一揆』,1982,岩波新書, p.49.
寺社は、強訴という手段も、その要求じたいも、「理非にかかわりなく」強訴であるがゆえに認められるべきである、と考えていました。道理として正しいかどうかということよりも、多数の者が「全員同心」したのだから、したがって “神意” なのだから、認められなければならない――という主張であったのです。
1198年に興福寺の満寺衆徒が、寺領に対する国司の横暴を指弾し、その流罪を要求して朝廷へ強訴を行ないました。興福寺が、その強訴の正当性を幕府に説明した「牒状」には、要約つぎのように書かれています。
『一般原則として国家の刑罰の法にしたがうのは当然である。しかし、この原則も〔…〕例外がありうるのである。およそ三千人の衆徒が同心した訴状を提出しているのに、』朝廷がそれを認めず、流罪の決定をしないのは不当である。だから当寺は強訴に訴えたのだ。『多数の考え方のちがう人びとが全員同心して、満寺三千衆徒一味同心という状態がつくられたということは、〔…〕この主張が「理の窮み」であるからで、おそらく春日神社の神が、われわれ衆徒にその意志を託したものといえよう。〔…〕
ここに明瞭に、〔…〕一揆が〔…〕通常の理非の世界をこえた「理」をつくりあげることができるという主張を読みとることができる。』
勝俣鎮夫『一揆』,1982,岩波新書, p.45.
つまり、「一揆」の「一味同心」に現れた神意は、国家の通常の法(律令など)を超える正当性をもつ、と彼らは考えたのです。あまりにも乱暴な主張だと思うでしょうか?‥しかし、「国家の法をこえる神意の正当性」とは、ヨーロッパの中世に、憲法や「法の支配」の原則を生み出した・あの精神に似ていないでしょうか? 衆徒の行動は、乱暴狼藉のような現象が目につくのもたしかですが、その一方で、「衆議」にあたって、いっさいの「縁」も忖度も断ち切って公平な意見を述べなければならないとされたことや、一山の衆徒全員が平等の資格で表決したことなど、“神意” にふさわしい公正さを追求する面があったことを見る必要があります。
「一味同心」「一揆」の作法を、寺法に規定するにあたって、まず、個々の僧による実力行使や、役人へのワイロによって解決しようとすることを、厳しく禁止した例もあります(p.49)。また、多くの寺で、「一揆」強訴は最後の手段であり、通常の訴訟などの手段を尽くしても解決しない場合に初めて、執るべきものとされたのです。
【42】「一揆」「逃散」「無縁」
次に、農民の場合を見ましょう。
『荘園領主に対する荘民の一揆である荘家の一揆の場合、〔…〕まず合法的な手続きをふんだ訴訟、そこで要求がみたされない場合、荘民が一味神水し一揆を結んで強訴をおこなう。ここでなお要求が貫徹しない場合、実力行使として、荘民が荘外へ逃亡して荘園からの収入をとめる逃散(ちょうさん)がおこなわれる。この過程は、強訴をへず、一揆から逃散という形と二本立でおこなわれた。』
勝俣鎮夫『一揆』,1982,岩波新書, p.54.
「逃散」は、かつて平安時代までは、文字どおり流亡して流民になったり、他の荘園に移ってしまったのですが、鎌倉・室町時代になると、あらかじめ「山小屋」を作っておいて、一時的に山の中などに隠れ、領主が折れてくるのを待っている、――という一種のストライキとして行われることが多くなります。
ところで、寺社の「一揆」の場合と同様に、農民も、理非を議論するまでもなく「一揆」が成立したこと自体によって、要求は当然に正当である、という主張をします。たとえば、1442年に山城国上久世荘の「名主百姓等一同」が、用水路修理費用の負担を求めて領主・東寺に提出した訴状では‥‥
『荘内の百姓が列参強訴しているのであるから、たとえそれが過大な要求であっても領主がその要求を認めるのが当然であると主張している〔…〕
ここでもまた、一同列参の強訴は理非にかかわりなく認められるべきものという、一揆にもとづく列参強訴の力の論理が正面にかかげられている。』
勝俣鎮夫『一揆』,1982,岩波新書, p.57.
過大な要求であっても認めるのが当然、‥‥まして我々の言い分は、自分で溝を掘って今年の作は支障なく行なうから、費用は持ってほしいということで、けっして過大な要求ではない、まったく忠実そのものではないか、と主張するのです。
逃散した農民の家。ササを立てて囲んで、「山林不入地」を主張している。
宮下実・絵『戦国時代の村の生活』
『荘園の農民は、不作の時や、戦争で田畑があらされたとき、一揆を結んで年貢をへらしてもらうことを領主に要求しました。〔…〕それでも領主が要求をみとめない時は、みんなで、村をすて、山にこもる逃散(ちょうさん)ということをしました。
当時、山は山の神様が支配する神聖な場所とされており、領主が強制的に、山に逃げこんだ人びとをよびもどせなかったからです。
また逃散する人びとは、その留守ちゅう、自分の家の財産や田畑の作物が、領主の役人にうばわれたり、家にのこされた妻や子が人質にとられるのを防ぐため、家のまわりや田畑を竹や柴〔サカキなど霊力のある常緑樹の枝――ギトン註〕でかこみました。これは、かこまれた場所が神聖な山林になったことを示すために行なったもので、領主の役人もこれをどけて入ると山の神の罰(ばち)があたると考え、なかなか立入れなかったのです。
この逃散によって、領主は思いどおりの年貢をとれなくなり、たいてい降参して、一揆の要求をみとめたのです。〔…〕
10月1日 領主様が年貢をまけてくれないので、お父さんも兄さんも家のまわりをササでかこって、山へこもってしまった。お母さんが、お父さんたちは領主様が降参するまで帰ってこない、といった。外に出られないので、家の中で、こまをまわしたりして遊んだ。領主様の家来たちがやってきたけれど、ササの中には入れなくて、いろいろ悪口を言っただけで帰っていった。』
勝俣鎮夫『戦国時代の村の生活』,1988,岩波書店, pp.54,28-29.
「逃散」は、中世の農民にとっては有効な手段でした。「日根野荘」でも、九条政基の日記を見ると、政基の手下の代官を罷免するように村人に要求され、応じなかったところ「逃散」をされたという記述があります。不作や戦乱による加地子(年貢)の減免などは、領主が現地にいて見ていれば、農民が本当に苦しいのかどうかはわかりますから、「一揆」に訴えるまでもなく認めていたのではないでしょうか。
「一揆」「逃散」がその力を発揮するのは、代官や荘官の罷免を要求したり、新たな租税の賦課を拒んだりといった、領主のいわば “経営事項” へ介入しようとする場合だったと思われます。これらは、領主側から見れば越権行為に思われたでしょうし、なかなか応じなかったと考えられます。
「逃散」という農民の抵抗手段を有効にしている “秘密” が、「山林」の聖性であったということも分かります。寺院僧徒の強訴は、神仏の力を背景にして要求を押し通したのですが、「惣村」農民の場合には、「山の神」の聖性、聖なる領域としての「山林」の特性を、抵抗の根拠としたわけです。
『「山林」は、主人のもとから逃亡した下人(げにん)(奴隷)や犯罪人が駆け入る例からも知られるように、「聖なる場」としての性格をもつアジールとして存在していた〔…〕
農民たちは、一般的には、逃散〔…〕の後なお領主側の追及を受けたため、〔…〕領主側が追及できない場とされていた「山林」へ逃げこんだのである。このように逃散して山林に逃げこむのが慣習となっていたため、逃散のことを「山林に交わる」というようになった〔…〕
逃散した百姓の関心は、逃散中の屋敷、家財、田畠の保全に集中したと思われる。〔…〕
中世後期、15,16世紀の荘園や村落の百姓の逃散に関する史料には、「篠を引く」という語が登場する。〔…〕「ささを引く」〔…〕「篠をかける」「柴を引く」と表現している例もみられる。これらの言葉は、この時代、東は遠江から西は播磨まで広範囲にみられ、〔…〕逃散と同義語として使用されているから、百姓たちが逃散のまえに篠を引いて〔…〕逃散するという作法が慣習として存在していたことが知られる。
〔…〕おそらく、篠または柴を対象〔家や田畑〕のまわりにつきさして垣のように引きめぐらしたのがその具体的形態であったと思われる。〔…〕
1563年、戦国大名今川氏がつぎのような法令をだしている。
百姓たちが自分の家や田畑などに篠を懸け、逃散しその篠を懸けたところを、ここは山林不入地であると号して、領主側の強制執行を行なわせず、近辺を徘徊しているようなことがあっても、〔…〕あきらめることなく、〔…〕きちんと年貢をとらなくてはいけない。
〔…〕百姓たちの意識としては、山林不入地にする目的で篠が懸けられたことが確認される。山林は聖地であり、アジール=不入地であったのであり、百姓たちは「篠を引く」行為によって、〔…〕一時的にせよ、一定の効力をもつ聖なる地、領主権力などの力がおよばない不入地にすることに成功したのである。』
勝俣鎮夫『一揆』,1982,岩波新書, pp.134,137-138,141,147-148.
『「篠を懸」けた場所が「山林不入地」といわれたことは、山林が聖地であり、アジールであったことをよく物語っている。〔…〕
山林は下人・所従の逃げ籠る場でもあった。
〔…〕ある種の山林そのものが、少なくとも中世前期、さらには古代末期、「無縁」の場としての性格を持ち、アジールの機能を果たしていた〔…〕同様の性格をもつ場としては、当然、河、海もあげることができよう。』
網野善彦『増補 無縁・公界・楽』,1996,平凡社ライブラリー, pp.305,127,129.
雪遊び 宮下実・絵『戦国時代の村の生活』
山林は「無縁の場」である――とは、どういうことでしょうか? 荘民が「逃散」して山林に籠った場合、荘園領主の側からも、それは一時的にもせよ、領主と荘民の「縁を切る」行為と考えられたのです。今のコトバで言えば、親子の縁を切る、勘当する、ということです。もう主人でもない、家来でもない。そんなら勝手にしろ‥‥と言いたいところですが、領主としては、収穫する人がいなくなって年貢が取れなくなっては堪らない。やむなく、「親子の縁を戻そうよ」と、頭を下げて呼び戻すことになります。
つまり、山林は、そこに入ると俗世の「縁」が切れる「無縁の場」であったのです。
『1503年、日根野荘の西方(にしかた)の百姓たちは領主〔九条政基――ギトン註〕の段銭(たんせん)賦課を拒否し、篠を引いて領主側の役人の立入を禁じ、自分たちも政基のもとへ出入りしなかった』
勝俣鎮夫『一揆』,1982,岩波新書, p.140.
この場合は、村を囲うように、あるいは村の入口に「篠を引い」て、村全体を「聖域化」し、領主側の者を完全に閉め出したわけです。ところが、翌年、村が属する和泉国の守護大名細川氏と、となりの紀伊国・根来寺(ねごろでら)との間で、また戦争が始まりました。根来寺の僧兵は鉄砲隊も擁して強力で、国境を越えた「日根野荘」一帯までも勢力圏に収めていたので、以前からこの周辺は、両勢力が衝突するたびに、戦場になっていたのです。そこで西方の百姓たちは、「篠を引い」ているにもかかわらず、政基に申状(もうしじょう)を送って保護を求めてきました。政基に武力はありませんが、朝廷の最上級の家柄ですから、うまく根回しをすれば、戦場にならないように取り計らうことができます。
それにしても、政基から見れば、西方の百姓のお願いは、ムシのいい話です。
『政基は、その日記に、「西方百姓は、篠を引いて年貢などの課役をいっさい納入していないのに、このような申状を提出することは、まったく理解できない。〔…〕篠を引きながら、領主に保護を求める〔…〕矛盾した行為は不可解で、返事を出すべきかどうか思案にくれるが、篠を引いている以上返事を出す必要はない」と記している。
この記事から考えると、この篠を引く行為は、領主側からも、領主-領民関係を断ち切った行為、年貢などの収納・納入関係、領主の支配・保護関係〔…〕が消滅したものと認識されていることがわかる。もちろん、〔…〕百姓側は、そのことを目的に〔「篠引き」を――ギトン註〕行なったことは確かである。』
勝俣鎮夫『一揆』,1982,岩波新書, p.140.
【43】「無縁」としての子ども、「無縁の場」としての河
『村の公的な役割・仕事は成年の男子にわりあてられ、老人・女性・子どもはこの世界から除かれて〔…〕いました。〔…〕
子どもも「7歳までは神のうち」という諺があるように、他人の山の木の果物をとって食べても許されるなど、大人の社会の厳しい掟などがおしつけられない、独自の世界に生きるものとして自由に生きていたのです。子どもはまだ正式のこの現実の社会のメンバーとは認められず、まだ半分は生まれる前の世界の人間と考えられていたのです。〔…〕来日した宣教師は、〔…〕「日本の子どもは半分はだかで、親からかわいがられることも少なく、あまり楽しみもあたえられずに育てられている」とのべているのは、大人の世話をうけないかわりに干渉もされない当時の子どもたちのありかたをよく示していると言えるでしょう。
子どもたちは村の行事に、よく主役として登場しました。子どもには〔…〕神様が宿りやすいという考え方にもとづいた〔…〕大人の期待からそういう役割をはたしたのでした。〔…〕5月5日の石合戦がその年の豊作か凶作を占う行事であったのは、〔…〕神様の意志を示す〔…〕子どもの役割をよくあらわしています。
〔…〕この時代の竹馬は、枝や葉のついたほうきのような形をした竹にまたがって遊ぶものでした。この遊びも〔ギトン註――霊力のある竹の枝葉で地面をなでて〕地面の神様を鎮める〔…〕神様と関係のある行為でした。〔…〕
5月5日の端午の節句は、もともとは中国の風習が伝わったもの〔…〕日本人の生活慣習とむすびついてさまざまな行事や風習がつくられていきました。〔…〕屋根にショウブをさす菖蒲葺、ショウブでおたがいにたたきあう菖蒲たたきもそのひとつです。〔…〕刀のような形をして強い香りのするショウブには悪霊をおいはらう力があると考えられた〔…〕
この日には、子どもたちが石を投げてあらそう石合戦も行われました。この石を投げる飛礫(つぶて)の風習は古くからありました〔…〕子どもたちが川をはさんで二組にわかれて行われました。そして飛礫が神様の意向を示すものであるとの考えから、農村では、その勝負によってその年の豊作・凶作をうらなうたいせつな行事となりました。そのため、〔…〕たんなる遊びではなくて、しんけんにたたかわれ、大人もその勝負に大きな関心をもっていました。〔…〕
5月5日 きょうはお節句だ。石合戦の日だ。ぼくたちはみんなで力いっぱい石を投げたのに、となり村の子の石の力が強かったので、負けてしまった。』
勝俣鎮夫『戦国時代の村の生活』,1988,岩波書店, pp.49,52.
流出した用水「樋」を引き上げる作業 宮下実・絵『戦国時代の村の生活』
中世の「惣村」では、溜池や用水溝など、水田灌漑施設の造成、修築は、村人の共同作業で行なわれました。「日根野荘」のある和泉国をはじめとする瀬戸内海沿岸は降水量が乏しいので、灌漑施設はとくに重要でした。
「日根野荘」には、多くの小規模な溜池が造られていたほか、犬鳴川の上流に「樋(とい)」を設けて水を取り入れ、用水溝で各村の水田まで水を引いていました。この用水溝は、現在でも「入山田村」の用水路として使われています。
ところが、この年の梅雨の洪水で、「入山田村」が設けていた2個の「樋」が流され、下流の「上郷(かみごう)長滝荘(ながたきのしょう)」まで流れて行ってしまったのです。「入山田村」の村民たちは、「樋」を取り戻すために、川伝いにおそるおそる下流へ出かけて行ったところ‥‥
『樋がふたつ流れついた上郷・長滝荘の人びとが総出で応援にかけつけ、総勢 400人以上の人びとが力を合わせて樋を引き上げる作業をしました。
この上郷や長滝荘は、領主もことなり、入山田村とは政治的に敵味方に分かれていましたが、このような場合、村々が連帯して、農民たちの共同作業が行われました。入山田村の人びとは、これに感謝して、とぼしい村の費用で、応援にきた人々にお酒をのませたり、ご飯を食べさせたりして、もてなしました。〔…〕
6月15日 おとといからの大雨で、川から水を引く樋が、川下に流されてしまった。雨がやむと、村じゅうの男の人たちが、大あわてで樋を引きあげに行った。いつもは仲の悪い川下の村の人たちも、どんどん集まってきて手伝ってくれた。河原で、みんなでお酒をのんだり、ごはんをたいたりして、にぎやかだった。みんなの気持が一つになっていくようで、とてもたのしかった。』
勝俣鎮夫『戦国時代の村の生活』,1988,岩波書店, pp.53,12-13.
前の節で書いたように、「日根野荘」は、和泉国の境界内なのに、となりの紀伊国の根来寺(ねごろじ)の勢力圏下にあったため、和泉国の大名・細川家とのあいだで戦闘が絶えなかったのです。細川家が支配する下流の村々とも、「日根野荘」の村々は戦争状態だったと言えます。
絵本の文だけ読むと、農民同士が仲良くするのは当たり前、のように思って読み過ごしてしまいますが、私はむしろ、だいじな用水「樋」が敵の村の領域に流れこんでしまったのに、よく取り合いの暴力沙汰にならなかったもんだ、と思いました。話し合いの結果、協力したのではなく、雨がやむと同時に、下流の村々からも河原に駆けつけて、当たり前のように共同作業が成立していることが、私を驚かせます。
しかも、共同で作業するだけでなく、共同で食事をしています。古代・中世には、日本でも他の民族でも、共同の飲食――「共餐」は、たがいに社会的絆(きづな)を結んだり、絆を確かめ合うための重要な儀式でした。どうして、そんなことが成立したのか? お百姓さんは人がいい、というだけでは説明できないことです。
しかし、これには理由がありました。「樋」が設置されていた上流には「大井関神社」という大社があって、そこに分水堰があり、境内を通って用水路が「日根野荘」に達していました。「大井関神社」の祭礼には、守護方も根来寺方も休戦し、祭礼の馬を出し、競馬や射弓をともに行なうのが慣例になっていました。
「大井関神社」は、少なくとも祭礼の日には、敵対関係が切れ、闘争が禁止される「平和領域」――「アジールの場」になっていたのです。
しかも、網野善彦氏によれば、「河」は、「山林」、海、道路などとともに「無縁の地」であり、アジールの機能をもっていました(網野善彦『増補 無縁・公界・楽』,平凡社ライブラリー, pp.129,160.)。 川は、古くから「境界」として、「賽(さい)の神」「境(い)の神」の宿る場であり、「賽の河原」であったのです。河原は、無主の地として、旅人や流浪の人びとが気兼ねなく休める場所であり、中世になると、「市」が立ったり「宿」ができたり、遊女や旅芸人、遍歴の僧から、葬送・屠殺に従事する人びと、非人、乞食に至るまでの「無縁」の人びとが住みつく「無縁の地」でした。
「市(いち)町・野山・浦浜・道路」などは「平和領域」であり、そこでは「闘諍」が禁止されるとともに、万一「闘諍」が起きてしまった場合には、その場かぎりですませ、後で報復や犯人捜索などをしてはならないとされていました。河原も、同じでした(op.cit., pp.159-160.)。
「河」にかかる橋、渡(わたし)も、古来多くの伝説で彩られた「聖なる場」であったのです。
「日根野荘」の用水「樋」が流失したさいに、敵同士の関係にある村のあいだで、即座に共同が成立したのは、「河」の「無縁」性、アジール性のためではなかったか、と私は想像するのです。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらは自撮り写真帖⇒:
ギトンの Galerie de Tableau