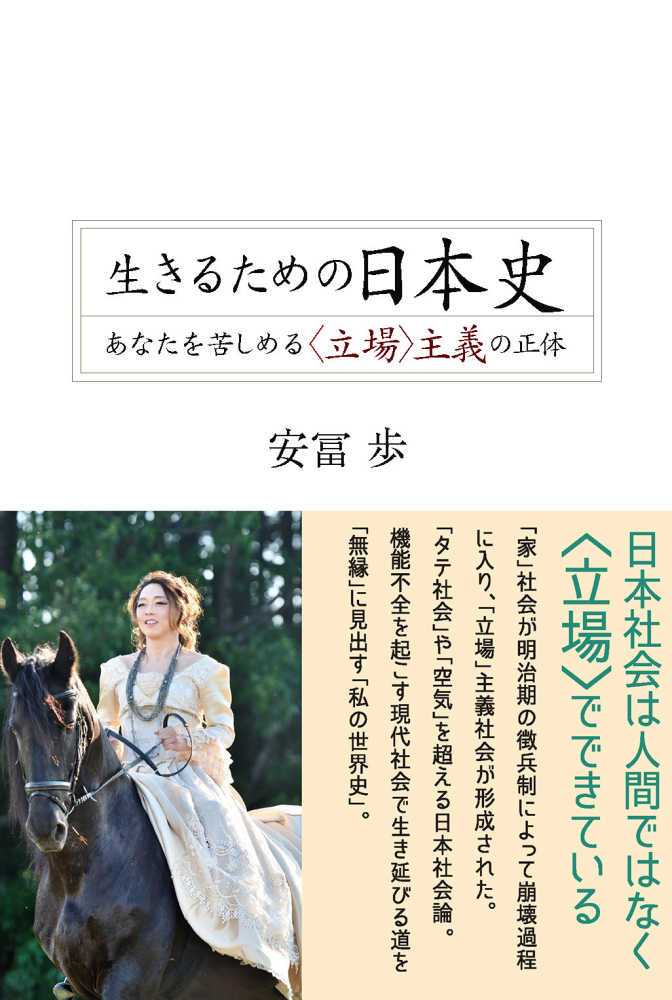毛沢東主席から『楚辞集註』を贈られる田中角栄首相 1972年9月27日 北京,中南海.
【23】「立場主義」の拡散――昭和戦前から戦後へ
安富さんの本↑の「第3章」に入ります。前回は、夏目漱石の小説『明暗』に出現した「立場」の頻度と意味内容を分析した結果、現在に近い意味での「立場」の使用が、この大正時代には成立しているようだ、と見ることができました。
しかし、「立場」という語が、雑誌や新聞で広く使われるようになるのは、もう少し後であったと考えられます。『明暗』に「立場」の用例が多いのは、当時の一般的な使用の反映である以上に、日本の言論と思想をリードした漱石の創造力というか洞察力によるところが大きいと思われます。『明暗』じたいが広く読まれることによって、「立場」の使用、また「立場」という考え方の拡散に寄与しただろうことは、無視できません。
↓下のグラフは、各種の雑誌記事索引(記事タイトルの集成)を網羅したデータベースである『ざっさくプラス』によって、1910年以前から 1985年までの「立場」という語(類義語を含まない)の年ごと頻度を集計したものです。
これを見ると、1910年代の使用頻度はまだ微々たるもので、その後、20年代から戦中にかけて増加していきます。終戦前後の谷は、雑誌の出版じたいが困難になったためです。そして、戦後の米軍占領時代に急激なピークを迎えます。
占領時代といえば、太宰治『斜陽』〔1947年〕に描かれているように、華族、士族、旧「上流階級」の没落が顕著でした。しだいに形骸化しつつも、戦前に「家」主義が強固に残存していたのは、もっぱらこの階級が「家」主義を建前としていたからです。戦後の「民主化」のもとで、旧「上流階級」の「家」の解体が進むなか、「個人主義」と「個人」の尊重を人びとは謳歌していると、戦後の日本国民は思っていました。しかし、台頭したのは「個人」ではなく「立場」だったのではないか? 上のグラフは、そのことを強く示唆しています。
なお、グラフに載せられている朝鮮語雑誌の集計から、戦前は朝鮮語でも「立場 ipchang」という語が頻繁に使われ、戦後(韓国)にも少し残っていくことがわかります。すでに (4) で『朝鮮語辞典』から予想されていたことですが、雑誌記事タイトルからも裏付けられました。
しかし、ここですぐに戦後に入ってしまうと、戦中における「立場」の意味の展開が抜け落ちてしまいます。漱石の時代に成立した「立場」の意味は、あくまでも「家」との関係を強く残していました。ところが、戦後にいわば「黄金時代」を迎える「立場主義」の舞台は、「家」よりも、会社や官庁などの、もっと公的な組織なのです。2つの時代の中間には戦争があって、戦争が「立場主義」の変容に与えた影響は、決して無視できないのです。
【24】沖縄戦から、戦後の「立場主義」黄金時代へ
太平洋の日本軍を壊滅させた米軍が沖縄本島に上陸したのは 1945年4月1日でした。日本軍は予め沖縄にも多数の兵員を送り込んでおり、本島全体が戦場になるほどの激しい戦闘が米軍と日本軍守備隊のあいだで行なわれました。
東京帝大出身の渡辺研一は、歩兵小隊長として沖縄に派遣された兵士のひとりで、45年5月27日に本島与那原(よなばる)付近(島尻郡南風原町)で戦死しています。
『最初から兵糧不足の沖縄守備隊ですが、戦時中に編成された部隊は人数だけは多くてもまともな武器は無く、粗製乱造の小銃と手榴弾だけの装備でした。当然海空の支援を受けた重装備の米軍との戦力差は甚だしく、この日一度だけの戦闘で壊滅状態となりました。しかし正しく死守と言う言葉の通り、兵士が退却することなく戦闘を継続したので米軍は後退し、退路を遮断されずに済んだので司令部は予定通り南部に移動することが出来ました。』
「5月27日、65年前の沖縄で」『地球見聞録』
そして、南端部の戦闘で、「ひめゆり隊」の最期に象徴される悲劇的自滅を遂げることになります。
沖縄戦跡 中頭郡西原町 棚原陣地壕(陸軍歩兵部隊)跡
渡辺の小隊は、「武器集積場の警備、壕掘り、木材の伐り出し」等を任務とする後方部隊で、もともと戦闘を任務とする部隊ではなく、群馬県高崎市で部隊編成をして以来、戦闘訓練をまったく受けることなく派遣され、沖縄では他の部隊が戦闘訓練と築城に専念できるようあらゆる雑用を引き受けていたのです。ところが、米軍上陸後、前線の部隊が次々に潰滅するなかで、後方の諸部隊が前線に出されることになります。
渡辺隊は、5月22日に与那原方面への移動を命ぜられ、23日に目的地である 87高地に接近しますが、米軍の機銃掃射を受けて後退、手前の丘に別の部隊が掘った退避壕に入り、この丘に布陣しようとします。しかし、ここは、すぐ近くの 55高地に拠る米軍から見下ろせる位置にあり、25日は終日、迫撃砲と機関銃の攻撃を受けています。渡辺隊の武器は小銃と手榴弾だけですから、まったく反撃できない一方的な攻撃にさらされ、戦闘というより虐殺です。
26日は早朝から豪雨でしたが、砲撃はいよいよ激しくなり、米軍歩兵の進撃も開始されました。
『渡辺隊は〔…〕歩哨を残して壕内で待機していたところ、血だるまになった歩哨が山頂から転がり落ちてきて敵の進撃を伝えました。渡辺中尉は〔…〕南方の神里部落にいる砲兵隊に支援を依頼しましたが、「既に当日の割り当て分 10発を撃っているので射撃はできない」との返事でした。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.162.
やむなく、渡辺隊は壕を出て山頂へ向かい、進撃して来る米軍歩兵に応戦しようとしますが、丘を登っている途中で、後方に回り込んだ米兵の機銃掃射を浴びて、渡辺と部下1名が戦死しています。
『隊長を失いながらも渡辺隊は小銃と手榴弾のみで反撃し、優勢な敵を撃退しました。しかし〔…〕米軍は、さらに激しい迫撃砲による攻撃を続行しました。〔…〕渡辺隊は後退することなく戦線を保持していましたが、日没になって〔…〕無傷の者はほんのわずかであり、弾薬も撃ち尽くしてしまったものが多く、まさに死守の状況でした。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.162.
渡辺が派遣される前に内地の兵営から家族にあてた手紙が残っており、その中に「立場」という語が出てきます。
『「〔…〕時機はいよいよ迫りつつあります。〔…〕その時の来ない中に、言ふべきことは言って置きたいと思ひます。然し、いざペンをとってみると今更乍ら申すことのないのに気がつきます。」
〔…〕明らかに。彼は「書きたいけれど、〔検閲があるので――ギトン註〕ここには書けない」と言っているのです。〔…〕
「今の私は強くあらねばなりません。寂しい、悲しいといふやうな感情を振り捨てて与へられた使命に進まねばならぬ立場にあるのです。ただ一切を忘れて戦って戦って戦ひ抜きたいと思ひます。〔…〕」
〔…〕この手紙がすごいのは、〔…〕検閲の目をくぐり抜けて、自分の思いを正確に表現しているところです。〔…〕「寂しい、悲しいといふやうな感情を振り捨てて」〔…という〕一文によって彼が、どれほど寂しくて悲しかったか、どれほど奥さんのもとに帰りたかったかということが読みとれます。そして、その思いを直接に表現することすら、許されない立場にあったのだということも』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.163-164.
日本軍の組織に所属する兵士である自分は兵士の「立場」にあり、兵営の外にいる家族もまた、戦時の日本社会にいる以上、「銃後」の「立場」にいる。渡辺は、そう言っているのです。「立場」上、渡辺は「寂しい、悲しい」などと手紙に書くことはできないし、家族も、渡辺がほんとうの気持を伝えてくると期待することはできない。ともに、「感情を振り捨てて与へられた使命に進まねばならぬ立場」にあるのです。
自分の「立場」に忠実に行動することが、ほとんど習性のようになってしまった日本人ばかりが編成する軍隊であったからこそ、渡辺隊をはじめとする沖縄守備隊は、歩哨が血だるまになって落ちてきても、隊長が戦死しても、弾薬が尽きても、決して後退することなく陣地を「死守」したのです。また、友軍を守るよりも、「1日 10発」という割り当てられた作戦計画を「死守」すべき「立場」にあったからこそ、砲兵隊は援護射撃を拒否したのです。これは、石原莞爾らが軍の秩序を無視して「満州事変」を敢行したのとはまったく逆の事態であり、石原は、自国と自軍のこのような行く末をまったく予期することなく、引き金を引いてしまったのだ、と言うことができます。
兵士が自分の家族に書く手紙を軍が検閲するのは、本来は、軍の機密を守るためです。部隊が今どこにいて、どこに向かっているか、どんな装備を持っているか、敵に知られてしまえば、作戦は不可能になります。しかし、日本軍の検閲は、その必要を超えて、極限的に広範な束縛を兵士に課していました。勇ましい兵士という・期待される兵士像を演じて書かなければならない。弱音を吐いたり、軍の方針に沿わないことを書いてはならない。兵士には、ほとんど道徳的な規律が課せられ、しかも、日本人ならば当然に守るべきことだと信じられていました。個々の兵士は、それを自分の「立場」として意識し、「死守」したのです。
前回、夏目漱石の『明暗』で見たように、「立場主義」は当初、「家」の中での家族の自己主張として始まり、「家」の延長である「会社」組織や「階級」といった一般社会に広がっていきました。しかし、当時の日本の社会は、原子のような個人から成り立つ市民社会ではありませんでした。人びとは「家」から外に出ても、「家」の母斑を色濃く引きずっていました。いわば、日本の社会全体が、「家」化された村的社会といったものでした。そのなかで、軍組織に所属する兵士の「立場」、兵士の「立場」・役割を支援すべき「銃後」家族の「立場」が意識されたのです。
沖縄戦跡 糸満市伊敷 轟壕(トドロンガマ) 住民の避難壕だったが、
陸軍が武力で住民を追い立てて占拠し、陣地として使用した。
『日本の軍国主義というものは、軍隊や軍事力をおびた連中が日本の政治を云々するとか、そういうところに本質があるわけではないと、私は思います。このような立場に置かれた人が、そうせざるを得ないと誰もが考え、とにかくそのとおりに歯を食いしばって頑張っていくという、そこに日本の軍国主義の本質があったと考えています。
その観点に立つなら、戦後日本こそは、そういう意味での微分化された軍国主義が社会の隅々まで浸透していった時代だということになります。おそらく、若者も含めた今の人々も、立場上やむを得なかったら、渡辺さんと同じように戦い抜くに違いありません。そうじゃない人は少数派だろうし、そうじゃない人は非常に嫌われます。
つまり、日本社会は戦時中以上に、強い立場主義の世の中になっているということです。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.166-167.
『戦後になって、立場主義のエートスは工場生産の方に向けられました。立場を守るために必死で役を果たせば、給料が倍々に増えていったりします。みんな家を買えるし、息子を大学に入れることができるようになった。このとてつもない成功をもたらした戦後の経済発展の段階こそは、立場主義の黄金時代です。かくて立場主義が、私たちの骨の髄に浸透していきました。
その立場主義のイデオロギーが頂点に達したのが 80年代末、ジャパン・アズ・ナンバーワンの時代ではないでしょうか。その頂点で、立場を守るために必死に働く銀行員たちによってバブルが引き起こされ、立場主義は崩壊の一歩を踏み出したと、私は思っています。
立場主義は、戦後に完成したと思ったらすぐに崩壊し始めている〔…〕日本史を特徴づける、数世紀にわたる家の盛衰と比べると、ずいぶんアッサリしていますから、立場は家の崩壊期に出現したその変形にすぎないのだろう、と考えています。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.154.
中国の農村
【25】中国から見た「立場主義」
『日本軍が徴兵をするのは簡単で、赤紙一枚で個人を呼び出していたわけですが、中国ではそうはいきませんでした。』国民党政府は国民党政府で、共産党は共産党で、必要な兵員の数を、『自分たちが実効支配している地域ごとに割り振っていきます。たとえばそれを村ごとに割り振るのですが、そもそも「村」というものが何なのかがよく分からない。
日本の場合だと、〔…〕中世期に村同士が血みどろの戦いをしてそれぞれの人的物的境界を決めていった〔…〕かくて近代以前から、村の境界線も、どの家がどの村に属するのかも、誰が家のメンバーかも、明確に決まっていた。
ところが中国の村はそんな歴史を経ていないので、ある村の村人は誰かとなると、〔…〕どっちだかわからないという人もたくさん出てくるのです。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.168.
ちょっと安富さんが正確でないところを補っておきますと、日本で「赤紙一枚」で呼び出せるのは「召集」の場合です。これは、すでに徴兵検査をして、検査の結果の「甲種合格」とか「乙種」「丙種」という分類に応じて、2年間兵営に入れて訓練したうえで「予備役」という名目で自宅に帰しておいた人や、「後備役」として自宅待機させておいた人を呼び出すのですから、ハガキ1枚で呼び出せるのは、軍から見れば当たり前なのです。つまり、戦前の日本では、すべての成年男子は兵士として名簿に載っているわけで、そのうち、徴兵検査を受けて間もない若者や、身体頑健な者を呼び出して編成しているのが、現役の軍隊なのです。
ところが、中国(1945年以前)の場合には、まず、国家統一的な「徴兵検査」というものがありません。村の土地も、村人も、境目があいまいで、そんなところに「兵隊を何人出せ」と割り振っても、誰が行けばよいのか分からない。そもそも、行きたい人などいないから、みな「私は、そちらの村の住民じゃありませんよ」と言って忌避してしまう。
しかも、華北の村は流動が激しくて、日本の村のように「中核的な家が何百年も続いている」などということはありません。これは、すごく古い時代から‥、少なくとも「明(みん)」の時代から、そうなのです。紀元前から、諸子百家が国々を渡り歩いて、自分たちを取り立ててくれる君主を探したり、塩や鉄をあきなう商人が中国全土を股にかけたり‥、といった例がいくらでも見いだせます。加えて、戦乱や水害で、ある地域の人口が減って、ほとんどいなくなってしまう、ということがよく起きました。そうなると歴代の王朝政府は移民を奨励し、各地から新しい居住者がどんどん集まって来て、村も土地も新参者のものになってしまいます。
こういう状態ですから、徴兵の割り振りをされた村当局は、応召する人員を確保するのにたいへん苦労したのです。
『それでどうするかというと、軍隊に行く係の人を雇ってあったりするわけです。そこらへんのゴロツキを日頃からお金を出して雇っておいて、軍隊から召集がかかったら、その人たちを行かせる。彼らは軍隊に行っても、〔…〕隙を見て脱走する。そしてまた別の村に行って軍隊に行く仕事を請け負う。そうやって応召を職業にしている人たちがいました。
さらには、農民がよそ者を拉致して、応召させる、という事件も頻発しました。もっとすごいこともあって、国民党の兵隊を、地元住民が拉致して、徴兵に応召するための人数(壮丁)として軍隊に出した、というのです。〔…〕
これが、1930年代に日本軍と戦っていた中国軍の背後にいた人々の構図です。日本の立場主義との距離は、想像を絶します。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.170-171.
中国の農村
『人間の社会的自由といえば、基本的には移動の自由と職業選択の自由が一番大事なところです。そんなものは何千年も前から、中国にはあります。〔…〕そういう意味では強烈な自由の伝統があります。あまりにも個人が自由でバラバラなので、それを宗族とか廟会とか結社とか、いろんな形でネットワーク的に接続していくわけです。中国は、そういった日本とはまったく違う伝統の上に立つ社会なんです。
日本人で〔…〕赤紙が来たら、誰かを誘拐して代わりに行かせるなんてことは、想像もつかない。私たち日本人は〔…〕どんなに反立場主義を貫いたところで立場主義者なのです。それくらい深く、私たちの生き方とか感覚のべースに入り込んでいるということを理解してほしいと思います。
中国がよく、日本の軍国主義が復活する、と騒ぐのは〔…〕、こういう伝統の国から見れば、そう見えるということです。日本人の方にそんなつもりはまったくないけれど、いったん国がそっちの方向に流れていって徴兵とか海外派兵とか始まってしまったら、「しょうがないな。立場上やむを得ないから」と言って命懸けで熱心に中国人を撃ち殺す、くらいは平気でやるのではないでしょうか。
日本人には、「しょうがないです、私だってやりたくないけど、立場上やむを得ないんです」という強烈な倫理があり、これは時に反社会的行為を正当化します。〔…〕やる気はなくてもそちらに転がっていったら何をするかわからないわけです。これは、政府がどんなに抑え込もうとしても、人々が好き勝手にやるので困っている中国のような国から見ると、怖い。軍国主義の国に見える。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.178-179.
【26】田中角栄と日本型福祉国家、「家主義」の潰滅
戦後日本の総理大臣の最終学歴を一覧にすると、つぎのようになります。
0 鈴木貫太郎(在任 1945.4.-8.17.) 海軍大学校
0 東久邇宮稔彦(在任 8.17.-10.9.) 陸軍大学校
1 幣原喜重郎(在任 45.10.-46.5.) 東京帝大法科大(現・法学部)
2 吉田茂(在任 46.5.-47.5.,48.10.-54.12.) 東京帝大法科大(現・法学部)
3 片山哲(在任 47.5.-48.3.) 東京帝大法科大(現・法学部)
4 芦田均(在任 48.3.-10.) 東京帝大法科大(現・法学部)
5 鳩山一郎(在任 54.12.-56.12. ) 東京帝大法科大(現・法学部)
6 石橋湛山(在任 56.12.-57.2.) 早稲田大学文学科(大学院宗教研究科)
7 岸信介(在任 57.2.-60.7.) 東京帝大法学部
8 池田勇人(在任 60.7.-64.11.) 京都帝大法学部
9 佐藤栄作(在任 64.11.-72.7.) 東京帝大法学部
10 田中角栄(在任 72.7.-74.12.) 中央工学校土木科
11 三木武夫(在任 74.12.-76.12.) 明治大学法学部
12 福田赳夫(在任 76.12.-78.12.) 東京帝大法学部
13 大平正芳(在任 78.12.-80.6.) 東京商科大学
14 鈴木善幸(在任 80.7.-82.11.) 水産講習所
15 中曾根康弘(在任 82.11.-87.11.) 東京帝大法学部
16 竹下登(在任 87.11.-89.6.) 早稲田大学商学部
17 宇野宗佑(在任 89.6.-8.) 神戸商業大学
18 海部俊樹(在任 89.8.-91.11.) 早稲田大学院法学研究科
19 宮澤喜一(在任 91.11.-93.8.) 東京帝大法学部
20 細川護熙(在任 93.8.-94.4.) 上智大学法学部
21 羽田孜(在任 94.4.-6.) 成城大学経済学部
22 村山富市(在任 94.6.-96.1.) 明治大学専門部政経科
23 橋本龍太郎(在任 96.1.-98.7.) 慶應義塾大学法学部
24 小渕恵三(在任 98.7.-2000.4.) 早稲田大学院政治学研究科
25 森喜朗(在任 00.4.-01.4.) 早稲田大学第二商学部
26 小泉純一郎(在任 01.4.-06.9.) 慶應義塾大学経済学部
27 安倍晋三(在任 06.9.-07.9.,12.12.-20.9.) 成城大学法学部
28 福田康夫(在任 07.9.-.08.9) 早稲田大学政経学部
29 麻生太郎(在任 08.9.-09.9.) 学習院大学政経学部
30 鳩山由紀夫(在任 09.9.-10.6.) スタンフォード大学院工学部
31 菅直人(在任 10.6.-11.9.) 東京工業大学理学部
32 野田佳彦(在任 11.9.-12.12.) 早稲田大学政経学部
33 菅義偉(在任 20.9.-21.10.) 法政大学法学部政治学科
34 岸田文雄(在任 21.10.-22.11.?) 早稲田大学法学部
これを見ると、戦後、幣原喜重郎から佐藤栄作までの 30年ちかくは、「東京帝国大学法学部卒業」が、日本の首相にほとんど必須の肩書であったことが分かります。池田勇人は京都帝大ですが、東京帝大に準ずると考えてよいでしょう。例外は、早稲田・文学部卒・院修了の石橋湛山ですが、石橋は戦前に「植民地大国主義」反対の論陣を張った反骨ジャーナリストだった人です。就任1か月足らずで自宅の風呂場で転倒したケガで辞任していますが、石橋の在任がもっと長ければ、戦後の歴史が変っていたのはまちがえありません。石橋の後に就任したのは東京帝大卒・官僚上がりの岸信介ですから。
「東京帝大法学部卒」が戦後 30年間の政界を支配したのは、ひとつには、侵略戦争に対する反省のためだったと思います。戦争は軍部のせいだ、軍部が悪い→官僚は良い、という “常識” が支配し、日本の政界に強い影響を及ぼしたアメリカのエスタブリッシュメントが、その認定を支持したのです。その意味での “初代首相” といえる幣原喜重郎は、戦前に外務大臣として「幣原平和外交」を展開しましたが、幣原のその軍縮外交・対欧米協調政策を攻撃することによって、軍部と政界右派が台頭した経緯がありました。幣原は、戦前デモクラシーの復活として、国民の歓呼に迎えられたのです。
「東京帝大法学部卒」の政権独占時代の最後が佐藤栄作だというのも象徴的です。佐藤は、「非核三原則」を提唱し、沖縄返還を実現し、ノーベル平和賞まで獲得していますが、沖縄返還協定の裏にはアメリカとの密約があって、以後現在に至るまでの米軍への従属状態をもたらしています。「非核三原則」も、事実はいまだ不明ですが、米軍基地内への核兵器持ち込みを容認していると批判されました。佐藤は、「戦後30年レジーム」の華々しい頂点をめざして、けっきょく失墜したと言うべきでしょうか? 佐藤の次は、専門学校土木科卒の田中角栄が就任しています。
田中以後、細川護熙までの 20年間は、「東京帝大法学部卒」の首相と、そうでない首相(たち)が交代で執権する時代がつづいています。細川の先代宮澤喜一を最後に、「東京帝大法学部卒」の首相はいなくなりました。そればかりか、「東京大学法学部卒」という首相もいない。そもそも、「東京大学法学部卒」は日本の首相に一人もいないということに、私は注目したいと思います。戦後に「帝国」が取れた後の東大卒業生は、依然として高級官僚の供給源ではあったが、政界のエリートになった者はいない、ということです。政界と官界が分離した、と言うべきでしょうか?
東京大学法学部
以上の観察を踏まえたうえで、安富さんの考察を読んでみたいと思います。
『田中角栄の出現以前と以降とでは、日本の政治構造に明確な違いがあります。〔…〕
田中角栄の出現以前と以降で総理大臣の学歴に大きな違いがある、ということは、〔…〕このあたりで社会構造が大きく変わったことを反映しているのだと考えます。いわゆる東京のエスタブリッシュメント、都会の官僚とかエリート層を中心とした保守本流、その圧倒的権威だけでは選挙に勝てなくなった。だからどうしても、田中角栄に代表される勢力を重視せざるを得なくなった。つまりは、田舎の代表です。
田中角栄の出現によって、東京を中心としたエリート層と、田舎を中心とした田中派に代表されるような政治家が、票と公共事業や補助金とを交換する体制ができたのだと考えます。しかも、この交換に貢献した官僚には、該当する事業に付随する天下り先を作る。
かくして、財政支出によって田舎で巨大な公共事業をして、それに伴って発生する様々な団体に官僚を天下りさせてあげる、そのかわり票を自民党に集めるという、あの構造が成立したのです。これが田中政治というものの本質だと考えます。
〔…〕
この田中システム、つまり都市エスタブリッシュメントと田舎との交換体制――からはみ出すのが、都市の労働者層です。その支持を得たのが社会党です。保守本流、田中派、社会党が、それぞれ3分の1を得た、とざっくり考えればよいのではないでしょうか。〔…〕労働者があまりに激化してはこまるので、この層にもかなりの配分がなされした。かくて財政支出がどんどん膨らんでいきます。
〔…〕こういう構造が体制に組み込まれたままで、経済成長のスピードが遅くなったり止まったりすると、国債ばかりが増えるようになります。これがバブル崩壊以降の、「失われた30年」の本質だと思います。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.181-184.
高度成長期の後半から――池田首相以後でしょうか?――顕著になった、日本の社会経済政策の変化は、教科書では、「福祉国家になったのだ」とまとめられています。しかし、「福祉国家」とは言っても、戦前アメリカのニューディールや、戦後の北欧諸国と比べると、かなり違う特徴をもっています。なによりも、公共事業や、企業向け補助金による「バラまき」の部分が非常に大きい。所得再分配のための給付、つまり狭義の「社会福祉」は、控えめにしか行われないし、そのなかでも、社会保険の比重が高いのです。国民健康保険や国民年金は、所得の再分配というより国民に強制する貯蓄でして、19世紀ドイツ帝国のビスマルク政権が始めた政策です。労働者から吸い上げた保険料を原資にして、労働者層の過激化を防ぐことに主眼があるのです。
『日本型福祉国家は、〔…〕保守本流と田中派との利益交換によるものであって、社会民主主義的な福祉社会とは違うということです。
〔…〕
自民党は福祉政策そのものは抑制して〔…〕福祉政策ではなく公共投資や中小企業、流通業の保護・規制などの経済政策によって地方での雇用供給に力を注いだ。〔…〕日本型福祉国家が雇用に力点をおいたのは、〔ギトン註――都市「大企業労使連合」の〕自由主義戦略と〔地方の〕保守主義戦略の独自な結合のしかたに由来する〔…〕
日本の保守主義は、福祉国家を地域や家庭の伝統的秩序に敵対するものと考えていた。したがって、地方を基盤とする〔ギトン註――自民党〕政治家たちは、以前にもまして、大量の公共事業や保護・規制による保守地盤の培養をはかった。その結果、〔…〕大企業労使連合〔大企業経営者+大企業労働者――ギトン註〕が官僚制の支援を受けてつくりだす経済成長の果実を、狭義の福祉政策を通してではなく、公共事業や、各種の保護・規制による雇用創出を通じて〔ギトン註――田舎の中小企業や農家に〕再分配するしくみができあがっていった。
(宮本太郎『福祉国家という戦略』,1999,法律文化社,pp.27-28,276-277)』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.186-188.
ここで、安富さんが強調する重要点は、「家」制度の潰滅との関係です。「家」は、戦中・戦後を通じて、都市の「上流階級」では、旧階級自体の没落とともに解体していましたが、地方では、崩壊しかけの状態で、高度成長期を通じて命脈を保っていました。それはもはや「家」の形骸にすぎなかったのですが、崩壊に瀕すれば瀕するほど、地方の保守勢力は、この基盤を守ろうと努め、それが国の保守政治に大きな影響力を持ったのです。
『例えば、どうして日本型福祉社会は直接給付ではなかったのか。それは直接給付にすると女性にも配らないといけないからです。お父さんにもお母さんにも、子供にも給付することになります。そうすると、お母さんや子供がお父さんの言うことを聞かなくなります。だからお父さんに渡したい。そうするには、公共事業をやってお父さんに働きに来てもらう』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.185.
あるいは、営農援助やらコメの減反やら、さまざまな補助金を農家に落として、戸主に渡す。さまざまな保護・規制による利権を地方の土建業に与えて雇用を増やし、そこにお父さんが働きに来る。家の農業は母ちゃん爺ちゃんに任せられるように、機械化資金を農協から融資する。
『日本型福祉社会を作り出したのは田中角栄だと思いますが、かくしてお父さんをサポートする田中角栄システムは、個人給付ではなくて家給付です。崩壊しつつある家制度を守るために、田中角栄システムは生まれたのです。〔…〕
家制度が危機に瀕した時に、お父さん方が公共事業にたくさん出て行って、メンツをかけて家を何とか守ろうとした。そのために田中派は、田舎にたくさんお金を落としました。
民主党の衆議院議員〔…〕石井紘基〔2002年、自宅庭先で暗殺された――ギトン註〕は、〔…〕こういう構造が日本経済を瀕死に追い込んでいる、〔…〕利権に多くの人が群がっている。〔…〕田舎というのは、補助金に頼らずに暮らしているのは学校の先生と農協の職員と公務員しかいない、と指摘していました。〔…〕
田中派を代表とする政治家に投票していたのは、主として滅びゆく家主義者だったと思います。拡大していく立場主義〔都会の大企業経営者と大企業労働者――ギトン註〕と、滅びゆく家主義〔地方の保守層:農家や中小企業――ギトン註〕の妥協点が田中システムでした。立場主義の中核を担ってきたエリートと彼らが結託して自由民主党を支え、中途半端な立場主義者たる都市労働者は社会党に行った、〔…〕こうして現代日本の社会構造が生み出されたのです。
〔…〕そうするとどうなるかといえば、〔ギトン註――公共事業や補助金バラマキで〕国債がどんどん増えます。あまりにも増えすぎて困った。どうするかというと、今度は田舎を切る。〔…〕つまりは田中派を切るということですね。これが小泉純一郎政権の「骨太の改革」の正体です。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.185-189.
次回は「第3章」の後半、小泉政権の「新自由主義」からです。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらは自撮り写真帖⇒:
ギトンの Galerie de Tableau