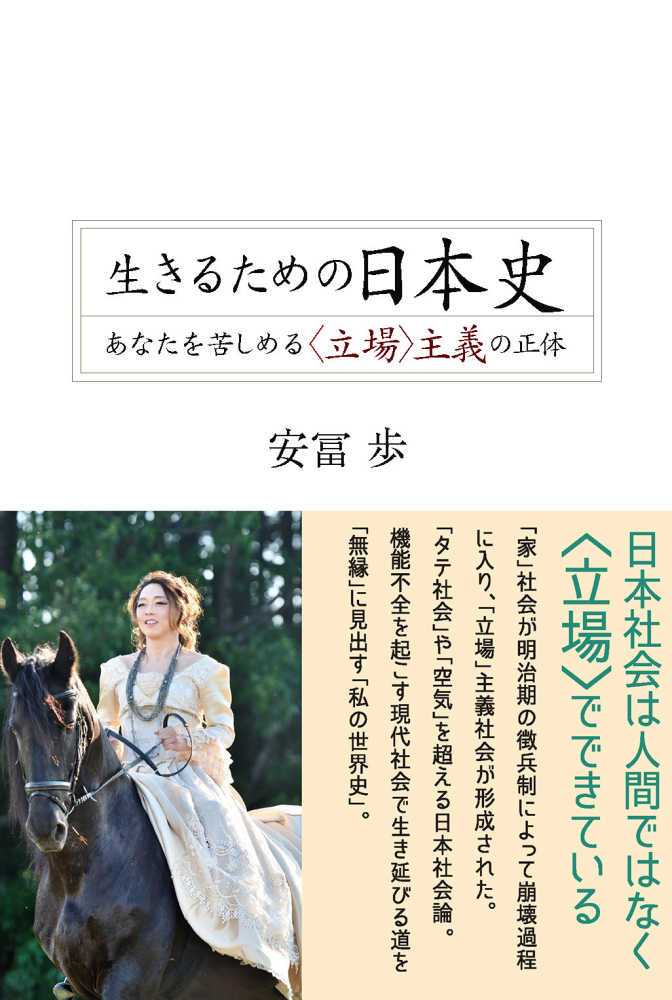安冨 歩 『一月万冊』清水有高(右)と。
【5】3・11から 10年たって、‥
このテーマ・シリーズ《新書日本史》に賭ける思いを、あらためて自己認識するために、安冨歩さんの『生きるための日本史』を読んでいます。今回は「第1章」の前半分のレヴュー。
福島の3・11原発事故が起きた時に、当時官房長官だった枝野幸男さんが、「この事故は想定外だ」ということを、テレビで何度も言っていました。この発言に対して私たちは、「想定しないのが悪いじゃないか」「最低の言い訳に聞こえる」と、強い異和感で受け止め、ツイッターなどで、そう言って批判してもいました。
現在から回顧すれば、3・11事故を防げなかったのは、ざっくり言えば「自民党のせい」です。科学的には「想定」できていたことを無視して、政治家と電力会社経営陣の安上がりな「想定」に置き換えて済ませていたために惨事をもたらした、ということが広く知られています。執権するまで、国の原子力政策に口を出すこともできなかった民主党にも、枝野さんにも罪がないことは明らかです。
しかし、いまここで気づくのは、枝野さんの発言にも、私たちの当時のツイートにも、何度も現れていた「想定」という言葉の危うさです。これらの発言の前提には、「人間は、いかなる原発事故の発生も、あらかじめ科学的に想定し、カバーすることができる。」という、およそありえない傲慢な “信仰” があるようにも思われるからです。いや‥、「いかなる」は言い過ぎかもしれません。しかし、原因が地震や津波であれば、それらは日本では起きやすい自然災害であり、過去にどんな規模・強度の地震や津波があったかは、よく研究されていて、私たちは知っているのです。「東日本大震災」は、十分にその「想定」の範囲内でした。にもかかわらず、私たちの「社会」は、極限的な事故の発生を防げなかった。「政権交代」という・私たちの民主主義の輝かしい機能が発揮された直後であったのに、できなかったのです。このことの持つ意味は、くりかえし問うてみる必要があります。
ここで、現代の私たちがふつうに思いつくのは、私たちの科学的な能力がまだまだ不十分で、極限の災害が起きることまで「想定」できていなかった、あるいは、科学的な「予測」「想定」はできていたのに、私たちの社会のしくみが、それを受け入れなかった、という問題設定です。この前半の問題意識――「私たちの知識も科学も、原子力を安全に扱うには不十分だ」――からは、科学がもっと発達するまで、原子力発電はやめるべきだ、という結論が出てきます。3・11の直後に私が考えていたのも、そういう議論の筋でした。しかし、その後の反原発世論の方向は、上の後半の意識へ移行していきました。じつは、津波の高さも、振動の強度も、科学的に予測する報告書が事前に出ていたのに、東電の経営者たちも、国の原発規制機関も、それを無視していた。3・11は、彼らの過失が引き起こした人災であり、彼らは処罰されなければならない、という方向です。
現在でも、事故原発から出た放射能汚染水を、あの手この手でごまかしながら太平洋に垂れ流しを強行しようとしている電力会社と規制機関と自民党政府に非難が集中するのは、当然のことです。いきおい、3・11に関する世論が全体として、「科学的には予測できていたのに、経営者と政治家がジャマをした」「人災だった」、という方向に行くのは、自然な流れなのかもしれません。しかし、それだけでよいのか?
たとえば、……津波の高さは予測されていたのに、それをカバーする防波堤の建造を怠っていた、というのは事実でしょう。しかし、防波堤を越えた海水が原発建屋に侵入すると何が起きるか?、‥予備電源で何とかなると思うか、それとも炉心溶融まで行くと思うか、という「因果の予測」――その強度は、大出裕章さんのような意識的な科学者と、「原子力村」のぬるま湯に浸かった科学者や経営陣とでは、大きく異なるのではないか? その「ぬるま湯」は、単に過失があるとか、金と地位の保持に馴れきって科学者の良心を忘れている、というようなことだけだろうか? むしろ、「科学」ないし「科学的予測」ということ自体の孕む問題群が、そこに胚胎されてはいないだろうか?
そういうわけで、「科学的には予測できたのに、それを無視した経営者と政治家と “原子力村学者” が事故を引き起こした」という現在の議論の方向に水を差すつもりは毛頭ないのですが、……ここではそれを超えて、「科学的予測」「想定」ということの孕む問題群を探ってみたいのです。
【6】「ソリューション」という まやかしの罠
もし原子力発電の利用を今後も続けるのであれば、自然災害や人為による事故の「予測」「想定」ということをやめるわけにはいきません。
逆に、原発をやめたとしても、それですべてが解決するわけではありません。原発をすべて廃棄して、ウランの精錬や放射性元素の製造をすべて禁止して、原子力利用ですでに出てしまった放射性廃棄物も、全部何とか処理できたとしても、ほかの産業や公害や交通については、「科学的予測」をやめるわけにはいかない。人間が科学を応用して産業経済活動を続ける限り、「予測」と「想定」は不可欠であり、それなしにはどんな事故も防ぐことができません。たとえば、昨年起きた熱海土石流災害が良い例でしょう。
この「予測」と「想定」もまた、科学によって行われます。すくなくとも、ある「予測」が正しいか否かの最終的な判定は「科学」によらなければならない、という暗黙の了解が、私たちの時代と社会にはあります。どんどん廃土が積み上げられていって、なんだか崩れそうだ、怖い、という住民の「不安感」を役所に言っても、それは単に「気がする」だけだ、規制して欲しかったら科学的なデータを持って来なさい、と言われて、追い返されてしまう。
自然科学や工学による「予測」が困難な分野に対しては、「経済学」とか「地政学」とか、その他もろもろのイデオロギーが「科学」の代わりをしています。それらの「予測」の正確さ――当たるか当たらないか――は、自然科学よりもはるかに危ういものです。「社会科学」という言葉がありますが、私は「社会科学」の「科学」は、比喩以上の意味ではないと思っています。「歴史科学」「人間科学」などということになると、もっとあやふやです。それでもなおかつ、あらゆる分野について、「科学的」なもの、「科学」みたいに見えるものが、正しさの基準になると信じられている。‥‥それが、私たちの時代と社会――の病理――なのです。
『私が〔…〕お伝えしたいと思っている一番大切なことは、「予測は不可能だ」ということです。〔…〕世界がどんなに複雑であろうとも、これを適切に抽象化して、こういうふうになっているんだよという奇麗な図式を描いて理解すれば、これから起こることが予測できたり、あるいは問題の解決方法(=ソリューション)がわかったりするという考え、これは根本的に間違っている、と私は信じます。
ところが、現代社会の〔…〕政策とか方策とかいったものは、基本的にこの図式〔予測やソリューションを与える図式――ギトン註〕に基いています。ある事態があったら、〔…〕その論理や構造を把握すれば予測が可能となり、また、原因を解明すれば問題の発生そのものを防ぐことができる〔…〕政府の経済政策なども、こういう考え方で立案されます。
〔…〕図式化で何かが解決できる、などと考えたとしたら、それは狂気としか思えない。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.23-24.
もちろん、「図式化」が常に間違った判断を出すわけではありません。しかし、「図式化」が通用するためには、さまざまな《条件》が必要です。
『図式が成り立つためには、さまざまな条件が必要です。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.24.
つまり、「図式化」には大きな制約があるのです。まず、もっとも根本的な制約から話を始めましょう。
【7】ラッセルのパラドックス
あらゆる科学は、「論理」によってできあがっています。科学者がある理論を思いついた最初の段階では、情緒あふれる直感や、神秘的なインスピレーションによって導かれる場合もあるでしょう。しかし、それが論文の形になって完成されたときには、その骨格を支えるものは「論理」です。なぜなら、他人にも理解されて受け入れられるには、「論理」によるほかないからです。“神秘” をそのまま書いても、本人にしか理解できません。小説として人々を楽しませたり、宗教の経典として信奉されることはあっても、「科学」として理解されることはありません。
バートランド・ラッセル〔1872-1970〕は、あらゆる自然科学の基礎である――と彼が信じる――数学を、「論理学」によって基礎づけ、究極的には人間のすべての英知を理性的「論理」によって、一点の綻びもない整合的な体系として仕上げることができると考えました。
『少年ラッセルは、〔…〕世界や物事は論理的にきちんと考えることができて、合理的に解決するという方法によって進んで行く以外に人間が正しく生きることはできないという信念をいだいていた〔…〕
ラッセルが最初に取り組んだ研究は、数学の厳密化でした。〔…〕まずは厳密な論理学を構成し、その厳密な論理学によって数学をどう基礎づけられるか。……まあ、そういうことを考えたんです。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.25.
こうして、ラッセルがホワイトヘッドと共著で書き上げたのが、『プリンキピア・マテマティカ』〔1911-13〕という大判3巻の大著です。この本は、もっとも基礎にある「論理学」から「数学基礎論」までですが、その上にある「数学」の全体が、諸定理と証明でつながった一貫した体系であることは、当時は自明のことでした(その後、ゲーデルらによって、その体系には綻びのあることが発見されるのですが)。数学から先についても、数学が物理学を基礎づけ、物理学が化学を基礎づけ、化学が生理学と生物学を基礎づける、‥‥というように、一貫した「論理」の体系になっていることが、すでに多くの哲学者によって指摘されていました。
そして、ラッセル自身はさらにその先まで‥‥、現状の「社会科学」が、自然科学とは一線を画しているかのように見えるのは、単に、今の時代がまだ熟していないためだ、とラッセルはあるエッセイで書いています。「社会」に関しては、いまはまだ中世の魔女狩りの時代がつづいているのであって、将来においては必ずその誤りは正され、「社会」も「自然」と何ら区別なく、科学的に探究されるようになるだろう…。かつて私などは、――ラッセルの死後ですが――このエッセイを読んで、大いに啓発されたものです。英語版のそのエッセイには、魔女の処刑の絵まで挿絵として載っていました。
ところが、ラッセルの考えた壮大な体系は、じつにその最底辺の「論理学」の部分に、どうすることもできない「論理」の破綻――不可避の矛盾――が蔵されていることが、まもなく明らかになりました。この矛盾を全面的な形で剔抉したのはゲーデルの「不完全性定理」〔1931〕ですが、同じことは、ラッセル自身が、よりシンプルな形で、すでに指摘していました。
天才の悲しさ、と言ったらよいのでしょうか? ラッセルの鋭敏な頭脳と、一点の妥協も許さない厳密さは、自らの理論がはらむ致命的欠点をも自ら発見し、そこから眼をそらすことさえ自己に禁じたのでした。
この「ラッセルのパラドックス」を、安富さんにしたがってひとことで言うと、どんなに壮大で精緻な論理体系も、そのどこかに「自己言及的なものがあると、そこに矛盾が生じてしまう」ということです。論理体系が論理体系として「完全」であるためには、「自己言及」を禁じることはできませんから、けっきょく、あらゆる「完全」な論理体系は「不完全」である、不可避的に破綻する‥ということになります。
これをうんと分かりやすく説明すると、「クレタ島のパラドックス」↓が、非常に単純な例になります。
『「クレタ人は嘘つきだ。」
と、あるクレタ人が言った。』
これは、「自己言及」の例として有名なものです。クレタ島は、ギリシャのエーゲ海にある島。クレタ人は、そこの住民です。ここでは、「嘘つき」とは、ウソしか言わない人のことだと考えてください。故・安倍晋三氏だって、たまにはウソでないことも言うわけですから、ウソしか言わない人など実際にはありえないのですが、これは例ですから、「噓つき」とはそういう人だと思ってください。また、クレタ人は、全員が正直者か、全員が嘘つきか、のどちらかだとします。
そうすると、もしこのクレタ人の言うことが本当だとしたら、クレタ人はウソしか言わないことになる。→このクレタ人もウソしか言わない。ところが彼は本当のことを言ったはずだった。これは矛盾。もしもこのクレタ人の言がウソならば、クレタ人は正直者だということになる。→このクレタ人も正直者だ。ところが、彼はウソを言ったはずだった。これも矛盾。けっきょく、何をどう考えても矛盾してしまい、論理ではにっちもさっちも行かなくなってしまいます。
もっとも、ラッセルは、このパラドックスを回避する方法も考えました。「世界」全体をまるのまま論理体系にしようとするのでなく、さまざまなカテゴリーによって「階層化」するという工夫です。これを「タイプ理論」というそうです。
たとえば、「クレタ島」の場合ならば、「あるクレタ人」という個人が、「クレタ人」全体という集団について言及するから、おかしなことになるのです。個人のレベルと集団のレベルとを分け、ある「階層」の要素が、異なる「階層」の要素に言及することを禁じれば、このような矛盾は起きません。個人は誰それ個人のことだけを考えろ。「日本人は、どうだ」とか「韓国人ガァァ𠆢𠆢𠆢」とか言うのは、まかりならん! 「子は怪力乱神を語らず」――分をわきまえろ、というわけです。しかし、ラッセルの当初の構想ではオールマイティーだったはずの「人間の論理」に対して、これはずいぶんと窮屈な制約になります。
『論理学を成り立たせるには、何らかの制限を設けて工夫をしないといけない、ということです。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.27.
そうやって「階層化」して思考に制限を設けたり、もっと端的に、「自己言及」が生じそうなときには、そっちへ行かないように回り道をしたりすれば、それ以外の場面では、あたかも論理整合性がオールマイティーな判断基準であるかのように、あいかわらず信じて、諸問題を「科学的」に処理してゆくことも、できるように見えます。しかし、そうやっているうちに、さらに生じてくる大きな問題は、「論理的思考」が正しいということは、どうして言えるのか?‥という根本的な疑問です。そもそも人間は、「論理」とか「合理的思考」というものを、いったいどこから獲得したのか? 誰からもらったかわからないようなものを、われわれは、どうして「正しい」と信じて使うことなどできようか?!。。。
西洋の哲学者がみな有神論者でキリスト教徒だった時代には、話はかんたんでした。カントなどは、人間に悟性の枠組みを与えたのは神様だ、神から授かったものであるがゆえに、人間の論理は正しい、と正面から断言しています(『純粋理性批判』)。しかし、神にも仏にも頼らないですべてを「合理的思考」で説明しようとするラッセルが、こんなことを言うわけにはいきません。
個々の人間の知識は、それぞれの経験に根差した主観的なものであるのに、そこから客観的な論理的知識が成立しうるのは、どうしてなのか?
『知識というものは本質的に主観的なものです。そこから科学的知識のようなもの、あるいはそこまでいかなくても、日常的な生活を可能にする客観性は、どうやって成立するのでしょうか。〔…〕
ラッセルの基本的な正当化の原理は、生物の進化にあります。〔…〕
「知識」というものは、〔…〕その根を、〔…〕言語化されない動物の行動のなかにおろしている。〔…〕論理的に基礎的な諸仮定〔人、物、それらの運動や因果関係を知ることができるための、5つの推論の要請。↓下記※参照〕は、動物がある種の匂いをもったものは食べられると期待する、といった習性を始点としており、そこからの長く続いた洗練の到達点である。それゆえ、われわれは科学的推理の要請(基本仮定)を〔…〕ある意味では知っており、ある意味では知らない。 (B. Russel: Human Knowledge, Routledge:Oxford, 2009, p.5)
〔…〕ラッセルは、我々の個人的な知識が何らかの客観性に到達しうる基盤は、動物の習性の進化した形態である我々の習性を、歴史の発展のなかで洗練させたものだ、と言っている〔…。しかし、〕進化の過程や文化の発展も、神の存在と同じくらい、神秘的な現象であるように私には思えます。
進化の過程で生き延びるという形で我々の知性が検証されていることが、我々が真理に接近できる最大の根拠だ、〔…〕』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.28-30.
※:ラッセルの「5箇条の要請」:①準永続性の要請〔同一地点で近い時刻には、似たものが存在するはずだ。→人、物、自己、等々の存在を信じる理由〕、②分離可能な因果の線の要請〔多くの現象をメンバーとする・ひとつづきの「系列」を構成することができる。→一つの物の運動ないし因果的変化として認識される〕、③因果の線のなかでの時間空間的連続性の要請〔念力やテレパシーの否定。離れた2点間で因果関係があるなら、両点をつなぐ連続的な因果系列が存在する〕、④一つの中心のまわりに配列した相似構造の共通の因果的起源の要請〔多数の人の網膜に、よく似た花火の像が生じるならば、中心点で打ち上げられた花火を皆が見ているのだと推論する〕、⑤アナロジーの要請〔人が直接感じることのできない、他人の感覚や、他人のなかにある精神の存在を、自己のアナロジーによって信じることができる〕 (安冨歩,pp.272-276.)
【8】お天気から津波災害まで、この世界のすべては「非線形」。
人間の持つ「理性」の特性、真理に接近しうる「合理性」の根拠を、人間の動物としての行動や習性、‥いわば “本能” のなかに求めるという傾向は、ラッセルのみならず、戦後の英米を中心とする哲学、言語学では、広く見られるものです。しかし、そこでは、安富さんのように、「進化」を、人間精神の正しさの根拠として援用するだけではなく、むしろ、人間の思考に刻印された「ゆがみ」を、そこから発見しようとする関心が見られます。たとえば、人間とチンパンジーを比べた場合、人間にとっては「上」と「下」、「前」と「後ろ」が基本的な対立概念であるのに対し、「右」と「左」は、しばしば混同されるほど等価です。ところが、樹上での生活が長かったチンパンジーにとっては、むしろ、「上」と「下」が等価なのです。⇒:ジョージ・レイコフ『認知意味論』
また、安富さんも指摘するように、前節の註※に書いたラッセルの「5箇条の要請」に現れた人間の合理的思考の「基礎的仮定」――いわば「公理」――にも、特有の「ゆがみ」が見られます。それは、「近傍」と「連続性」に対して、もっぱら関心を集中しようとすることです。
ここでクローズアップされるのは、人間の合理的・数学的思考は、「線形システム」と相性が良いのに、自然界の現象も人間社会の現象も、その大部分は「非線形システム」だという現実です。
「線形システム」とは、(連立)一次方程式や、一階線形常微分方程式で表すことのできる系です。たとえば、高校の物理で習う・もっともかんたんな方程式に、「フックの法則」:
ε = k・σ
というのがあります。バネを σ グラムの錘(おもり)で引っ張ると、バネは ε センチメートル伸びる。引っ張る力を2倍の 2σ グラムにすると、伸びる長さも2倍の 2ε センチメートルになる。この世界の出来事がすべて、このように簡単な関係になっていれば、すべては予測可能になります。それこそ、バートランド・ラッセルが夢見たような “科学万能のユートピア” が現出するでしょう。
しかし、バネの場合にしてからが、↑この法則が通用するのは、錘があまり重くない時だけです。引っ張る力が、ある限界を超えると、バネは伸び切った状態になり、さらに無理やり力を大きくしてゆくと、バネは破断してしまいます。その場合の σ と ε の関係をグラフにすると、たとえば↓下のようなギザギザの形になります。
しかし、このグラフは一例でして、いつでも同じになるわけではありません。力の加わり方が、ほんの少し変わるだけで、グラフの形は大きく変化しますから、じっさいにどのようになるかは予測困難です。これはたとえば、防波堤に津波が押し寄せたときに防波堤がどう変形したり破断したりするか、ということにも言えます。自然現象がどんな災害を引き起こすかという予測は、非常に難しい。難しい理由の多くは、自然現象が「非線形」であることによるのです。
『線形というのは簡単に言えば、原因があって結果があるという関係が明白であるときに、その原因を二倍にすれば結果も二倍になる、というようなことです。これが成り立たないと、大抵の予測や事前の制御は成り立ちません。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.31.
「非線形」の現象にはさまざまのものがありますが、いずれも、原因から結果を予想することが容易でない、のが特徴です。なかには、同じ原因から、その時々で大きく異なる、ランダムな結果が生じるように見える現象があります。こういうものは「カオス」と呼ばれます。「なかには」と言いましたが、自然界の「カオス」は非常に多い。むしろ「カオス」でない現象が、めずらしいくらいです。
たとえば、地球大気の運動、つまり気象現象は、「カオス」の典型だと言われています。どおりで、お天気予報が当たらないわけです。むしろ、最近少しずつ予報の精度が上がってきたのが、驚異的なくらいです。
「カオス」といえども、基本になる関係自体は――「非線形」とはいえ――方程式で記述されます。つまり、決定論なのです。だから、「決定論的カオス」とも言います。ところが、じっさいに起きる現象は、ランダムな結果を生じているように見える。これは、“原因” つまり初期状態を正確に測定することが困難であるために、初期状態の・ちょっとの違いが引き起こす・結果の大きなブレが、あたかもデタラメな、ランダムな結果を生じているように見せるのだ‥‥
↑じつは、この説明は、私がこのあたりを集中的に読書した当時の本では、このように書かれていた、ということです。ところが、現在では、「決定論的カオス」の研究はもっと進展しているようです。安富さんの本を見ると、「カオス」のランダムさは、測定の誤差が拡大してランダムに見える‥というような生やさしいものではない。現象の極微な “もとの” 部分で、非決定論的なランダムな現象が起きている、その微小な「揺らぎ」が、「非線形」系のふるまいによって拡大されて、大波のようにランダムな激動を引き起こしてしまう。。。 現在では、そのような説明が有力になっているようです。
しかし、私の↑この要約は、文学的で、あまり正確ではないかもしれません。安富さんの記述を引用して、「決定論的カオス」をもっと正確に述べましょう。次回は、そこから始めます。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらは自撮り写真帖⇒:
ギトンの Galerie de Tableau