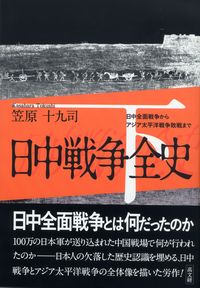笠原十九司『日中戦争全史・下』 高文研, 2017.
本書は、「日華事変」(1937年)から1945年敗戦までの「日中戦争」の全過程、および日本の「対華21ヵ条要求」(1915年)以来の「前史」を一著に収めた通史として、唯一のものではないかと思う。歴史的考察を欠いた通俗的な「戦史」は論外としても、これまでの日本史学者による研究は、⑴「前史」と、⑵対米開戦までの「日中戦史」ないし中国侵略と、⑶それ以後の「太平洋戦争」を、それぞれまったく別個の視点で扱ってきた。
しかし、この時代を生きた人々の記憶としては、日本人にとっても中国人にとっても、「日華事変」以前の「満州事変」、あるいはそれ以前から、1945年敗戦までの約20年間が、(中国人にとっては、さらに ⑷「国共内戦」・「朝鮮戦争」までが)ひとつの「時代」、ひとつの「戦争」として記憶されていたと思う。
"3つの時期"を統一的に把握する視点が欠けていた結果として、戦後のアカデミックな歴史認識は、2つの点で不十分なものとなった。①日本の中国大陸空爆の史的位置づけ。とくに、日本内地に対する米軍の「戦略爆撃」との対応関係・関連性。②対米開戦(1941年12月)以後も中国大陸で継続された戦争の過程と性格。
①の把握の不十分さは、「日中戦争」「アジア太平洋戦争」全部にわたって貫かれた日本海軍の“主導的”役割を見落とす結果となった。陸軍だけが、アジア侵略と無謀な対米戦争の”元凶”であり、海軍は戦争の拡大に反対した”善玉”だという、まったく誤った歴史認識を生み出すこととなった。
②については、もっぱら元兵士の体験記等によって扱われてきた。が、それらは個々の局面を明らかにするにとどまり、日本帝国と連合軍の全戦争過程のなかで、中国戦場にどういう役割が課せられたか、日本敗戦に向かってどのような効果を及ぼしたか、等々を総体的に俯瞰するには不十分であった。
本書下巻は、約3分の2を割いて、①②の総体的把握をめざしている。
【7】「日中戦争」の4つの段階
まず、これまでの日中戦争の経過を、ざっとおさらいしておこう。
『日本軍が国民政府軍との「正面戦場」における戦闘により拡大した占領地を4つの段階に区分して表示した。〔…〕
第1段階は〔…〕1937年後半の〔…〕戦闘により占領した区域で、華北と上海・南京中心の長江下流域である。
第2段階は〔…〕、国民政府の壊滅をめざした1938年の大作戦により占領した華北南部と華中の長江中流域の国民政府の政治・経済基盤になっていた地域である。〔…〕国民政府は長江上流の重慶を抗戦首都にして屈服せず、日本の大作戦は挫折したのだった。
第3段階が、〔…〕〔1939年~41年の〕作戦と戦闘により占領した地域であるが、重慶政府への陸上からの進撃は、艦船の遡行できる宜昌までで、それから奥への地上からの進攻は、三峡渓谷といわれる急峻な地形に阻まれて不可能であった。そのため、〔…〕空からの重慶爆撃を大々的にかつ長期にわたり敢行したのである。
第3段階では華中における正面戦場はほとんど拡大していない。〔…〕〔中国共産党軍の〕百団作戦を契機に後方戦場における八路軍・抗日ゲリラとの戦闘に大兵力を投入しなければならなくなったからである。
第4段階〔1942年以後。日米戦争開始後〕の戦場と戦闘〔…〕、それまでの日中戦争とはまったく性格を異にし、日本軍は、華南のアメリカ軍航空基地の破壊と占領ならびに〔…〕中国大陸縦断鉄道の占領をめざして、中国軍(国民政府軍)とアメリカ空軍との同盟軍を相手に大陸打通作戦(1944年4月~45年2月)を展開した。〔…〕日中戦争の性格が、アメリカ空軍の日本本土爆撃を防衛するための戦闘に変化したのである。
〔…〕日本軍の広大な占領地は、〔…〕鉄道間の奥地は、〔共産党軍、国民党ゲリラ、地方軍閥によって〕解放されて広大な抗日根拠地となっていた〔…〕
日本軍が正面戦場で〔…〕国民政府軍を敗退させ、占領地を拡大しても、共産党軍が占領地の内側から武力解放して〔…〕、日本軍の占領〔…〕を「無」に帰してしまったのである。〔…〕
日本軍は、後方戦場〔抗日根拠地・ゲリラ地区との戦闘〕のために、〔…〕占領した広大な地域に膨大な数の部隊を常時駐屯させなければならなかった。〔…〕アジア太平洋戦争に突入して以後も、膨大な数の日本軍を後方戦場のために張りつけておかねばならなかったのである。
日本は、1941年夏の段階で、〔「満州国」駐屯の関東軍以外に〕約85万人にものぼる日本軍を中国大陸に投入していた。〔…〕陸軍は〔…〕最大時にはおよそ100万の大軍を中国大陸に釘づけにせざるを得ない状況に陥っていた。』
『日中戦争全史』下巻, pp.136-137,139-140.
【8】 重慶爆撃
陸軍が対ゲリラ「治安戦」の泥沼で呻吟していたのとは対照的に、海軍は、中国戦線に航空部隊を投入して、戦闘機の開発改良の”実験台”として利用し(その成果が「零式艦上戦闘機(ゼロ戦)」の開発)、わずかな犠牲によって、「日中戦争」から最大限の利益を得ていた。
『謀略により大山事件をおこして日中戦争を全面化したのは海軍であったが、〔…〕海軍の最大の関心と目標は、日中戦争を利用して〔…〕海軍の軍備拡張と戦闘力強化を実現することにあった。とくに対米航空決戦に勝利できる海軍航空隊の軍備と戦闘力の充実をめざして、中国空軍を相手に実戦訓練を重ね、〔…〕戦闘機の開発を重ねてきた〔…〕
海軍の主要な戦闘は、艦隊と航空部隊によるものであり、陸軍とは〔…〕まったく負担と犠牲が異なった。』
『日中戦争全史』下巻, pp.140-141.
「日中戦争」が開始された 1937年8月から、対米開戦直前の 41年9月までの4年間、海軍航空隊は、
『ほぼ連日にわたり、中国全土の都市・鉄道・軍事施設などへの爆撃をおこなった。走行中の列車への爆弾投下、あるいは駅舎・艦船・船舶の爆撃は、アメリカの駆逐艦や艦船にみたてての、格好の爆撃訓練の目標になった。
消費した航空燃料(ガソリン)の総計は、天文学的な量にたっしたと思われるが、潤沢な日中戦争臨時軍事費から、それこそ〝湯水のごとく〟使用しても、軍事機密として、どこからもチェックされなかった。』
『日中戦争全史』下巻, pp.140-141.
海軍による・このガソリン大量消費が、米国をして「対日石油禁輸措置」を制裁手段に選ばせた理由であり、「禁輸措置」を受けた日本政府・軍部が、「石油の備蓄があるうちに、対英米開戦をしなければならない」として、見込みのない世界戦争の開戦に踏み切った原因だった。
中国国民政府の抗日首都・重慶に対する空爆は、1938年12月、陸軍飛行団と海軍航空隊の共同作戦として開始されたが、しだいに大規模化するとともに海軍航空隊の主導する作戦に移行していった。
『蒋介石は〔…〕重慶国民政府を設立し、四川省の重慶・成都から雲南省の昆明にかけて抗日戦争の大後方として西南建設をすすめ、長期抗戦の基盤とした。』
『日中戦争全史』下巻, pp.121-122.
昆明からは、国境を越えてビルマ、インド領方面へ「ビルマ・ルート」が延びており、国民政府への英米の支援物資が運ばれる補給路となっていた。
『日本軍は中支那派遣軍を中心に重慶政府を降伏させるために何度か大作戦を試みたが、ことごとく失敗した〔…〕
そこで、地上戦の手詰まり状況を打開するために考えついたのが空からの爆撃であった。
〔…〕純粋に空爆のみによって、重慶の首都機能を徹底的に破壊し、蒋介石政権に降伏を強いる作戦が考え出されたのである。〔…〕重慶の都市と住民を標的にして無差別爆撃をおこない、中国国民の抗戦継続意志の破壊をめざした本格的な戦略爆撃であった。
重慶爆撃のなかでも、一日の犠牲がもっとも大きかったのは、1939年5月3日と4日の2日間にわたっておこなわれた大爆撃で、中国では「五三・五四大空襲」として記憶されている。
日本海軍航空隊は、村落・民家焼却のため、焼夷弾を使用するようになっていた。5月4日の重慶爆撃は焼夷弾投下によって発生した夜間の火災のために多くの犠牲者を出したのである。
5月3日、4日の爆撃の惨状は、重慶に駐在していたアメリカの「タイム」特派員セオドア・ホワイトがスクープし、〔…〕「タイム」や「ライフ」に大きく掲載され、アメリカ国民の対日経済制裁要求の世論を強めた。』
『日中戦争全史』下巻, pp.143-146.
「重慶爆撃」が、史上最初の本格的な「戦略爆撃」であったことは重要だ。「戦略爆撃」とは、相手国の生活機能を麻痺させ、相手国民の抗戦意欲を奪うことを目的として、もっぱら民間人と民家、都市、産業基盤などを目標に行われる空爆である。「真珠湾攻撃」のように、基地・軍事施設と戦力に直接打撃を与える作戦とは、発想が異なっている。
当然のことながら、「戦略爆撃」は、基地や軍隊に対する攻撃よりもはるかに広汎で甚大な被害をもたらす。多数の非戦闘員・民間人が犠牲になる点で、凶悪な戦争手段だと言える。戦時国際法においては、攻撃は戦闘員を目標として、相手の攻撃力を縮減するための必要最小限のものでなければならないとしている。「戦略爆撃」は、国際法に反する違法な戦争遂行であり、「人道に対する罪」に該当する戦争犯罪なのである。
その「戦略爆撃」の典型として、しばしば言及されるのが、米軍の日本内地に対する「大空襲」であり、広島、長崎への原爆投下である。しかし、「戦略爆撃」を作戦として人類最初に立案し実行したのは、米軍ではなく、日本海軍であった。米軍は、日本が中国に対しておこなった「戦略爆撃」を学んで、当の日本に対して加えたにすぎない。「東京大空襲」も、日本各地に落とされた「焼夷弾」も、米軍は、たんに日本の残虐行為をマネしたのであって、日本にとってはブーメランだったと言わなければならない。
【8-1】 百一号作戦
日本海軍が「重慶爆撃」を集中的に行なった作戦として、「百一号」作戦と「百二号」作戦がある。
『百一号作戦は、1940年5月17日より9月5日まで3ヵ月にわたり〔…〕おこなわれた重慶爆撃である。』
『日中戦争全史』下巻, p.146.
海軍の艦船は、長江の武漢と重慶のあいだにある急流の大渓谷「三峡」に阻まれて、重慶には進軍することができなかった。「三峡」の沿岸には、当時は車道も無かったから、地上部隊が通過することもできなかった。日本軍は、武漢占領後は、ここから爆撃機を発進させて重慶を空爆したが、爆撃機を護衛するための戦闘機の発信基地としては、武漢は遠すぎた。そこで、40年6月に、武漢の270キロ上流の宜昌を占領し、ここに戦闘機の発進基地を建設した。
こうして、迎え撃つ中国空軍機を排除しながら、「百一号」作戦による重慶空爆が実施された。
『当時の日本政府は、海軍大将の米内光政内閣であった。〔…〕米内内閣のもと、海軍航空部隊を最大規模に動員して百一号作戦を遂行した背景には、ヨーロッパにおけるドイツ空軍のイギリス空爆作戦があった。』
『日中戦争全史』下巻, p.149.
40年6月にパリを占領したヒトラーは、(日本の重慶爆撃開始に遅れること2ヵ月)7月からイギリス本土空襲を開始した。ロンドンに、65日間にわたる夜間爆撃を加え、12月には焼夷弾を投下して1500か所の火災を発生させた。
日本の重慶爆撃と、ヒトラーのイギリス空爆は、洋の東西で競い合うように並行して行われた「戦略爆撃」であった。
『日本海軍は、〔…〕航空部隊を総動員して、「重慶定期便」を呼号しながら、連日のように重慶にたいして無差別爆撃をおこなった。〔…〕重慶市の徹底破壊を目標にして、市街地を東端から順次A・B・C・D・E地区と〔…〕区分し、各航空隊がそれぞれの区域を担当して、すきまなく徹底的に爆撃した。海軍航空隊はこれを絨毯爆撃作戦と称した。さらに、重慶市民に〔…〕恐怖心を与えることを企図して夜間空襲も行なった。』
『日中戦争全史』下巻, p.150.
【8-2】 百二号作戦
1941年7月27日~8月31日、海軍航空隊は、武漢、宜昌の航空基地から、重慶ほか四川省要所にたいする集中的な爆撃をおこなった。日本海軍の陸上攻撃機のほとんど全機を動員し、重慶市街にたいしては絨毯爆撃をおこなった。
並行して、占領した仏印ハノイから出撃して、雲南省昆明と「ビルマルート」も空爆した。
しかし、海軍は、すでに「百一号作戦」の結果から、これだけの空爆をしても蒋介石国民政府が降伏しないことは予想していた。むしろ、「百二号作戦」の目的は、別にあった:
『航空艦隊の全機を中国基地に進出させ、〔…〕、アジア太平洋戦争開戦に備えて「一通り訓練を行う」というのが百二号作戦の目的であった〔…〕
アジア太平洋戦争開戦に備えた海軍航空隊の最後の実戦演習であったという性格が強い。
それは百数十機からなる零戦と中攻機〔「中攻」とは、「九六式」及び「一式陸上攻撃機」の略称。海軍の爆撃機であるが、急降下爆撃ができない欠点があった――ギトン註〕を数ヶ所の基地から離陸させ、空中において大編隊を編成し、一糸乱れぬ指揮系統のもとに重慶爆撃を敢行するという訓練である。これは太平洋上の何隻かの航空母艦や何ヵ所かの陸上基地から飛び立った戦闘機や爆撃機が空中で集合して大編隊を組むという〔…〕、真珠湾攻撃やフィリピン攻撃を想定していたことは言うまでもない。』
『日中戦争全史』下巻, pp.184,187-188.
【9】 ブーメランとしての日本内地爆撃
米軍の初めての日本内地空襲は、開戦4か月後の 1942年4月18日、東京から横須賀までの東京湾岸、名古屋・四日市、和歌山、神戸、新潟に対しておこなわれた。ドゥーリトル少佐指揮下のB25爆撃機16機は、太平洋上の航空母艦から発進して低空で接近したために、日本軍のレーダーは捕捉することができず、爆弾が落ち始めてから空襲警報を鳴らすありさまであった。もちろん、迎撃も間に合わなかった。
この日の『大本営機密戦争日誌』は、「帝都空襲せられて上下驚駭す」と記している。
『政府と軍部の指導者たちが受けた衝撃は大きかった。
〔…〕海軍航空隊は1937年8月15日に南京渡洋爆撃を強行、中国政府と国民に対して心理的打撃を与えることを意図したが、ドゥーリトル隊の日本本土奇襲によって、日本はまったく逆の立場に立たされて「驚駭〔恐れ驚く〕」したのである。〔…〕緒戦の勝利に酔っていた日本軍部指導者たちは面子をつぶされたため、〔…〕「彼らをして神州を侵すことを恐れさせる必要があるという敵愾心が大本営陸軍部内に漲った。このため、〔…〕陸軍作戦指導の本幹を覆すような作戦指導に傾斜していくのであった。」〔防衛庁戦史室『戦史叢書・大本営陸軍部⑷』〕』
『日中戦争全史』下巻, pp.272-273.
「驚駭」のあまり、日本陸軍の作戦指導は、まったく誤った方向へそれてゆくことになったのだ。これこそ、「ドゥーリトル空襲」がもたらした・連合国にとっての最大の成果だったと言わねばならないだろう。
はじめて受けた”本土空襲”に対して、効果的な対策は、米艦隊の動向察知をふくむ内地防衛体制の強化であっただろう。ところが、陸軍首脳部が考えた”対策”は、まったく違っていた。敵の航空機が今後二度と「神州」に来ることのないように、敵航空基地を攻撃して”殲滅”してしまえ、というのである。また、アジア・太平洋全域の戦線を拡大して、本土に飛来できるような距離には敵基地を造らせない、というのだ。当時、参謀本部員だった井本熊男は、戦後に回想して、↓こう述べている。
『「戦争指導の中枢にある人達〔…〕の理想的概念は、わが勢力圏を拡張して、敵の航空兵力を日本本土〔…〕に手の届かぬ距離に押しやることであって、〔…〕敵航空勢力をして今後帝都に一指も触れさせてはならぬという考えが濃厚であった。これは戦理を超越した考え方である」』
『日中戦争全史』下巻, p.273.
内地空襲を受けたことによって、守勢に転ずるどころか、かえっていよいよ不可能な「勢力圏拡張」に狂奔するというのだから、まさに「戦理を超越」した狂気の策というほかはない。
こうして、ドゥーリトル空襲の衝撃は、具体的には2つの方向で、日本陸軍の作戦指導を狂わせてゆく。
ひとつは、「ミッドウェイ海戦」である。当初、海軍・連合艦隊(山本五十六長官)が立てた「ミッドウェイ作戦」の目的は、ミッドウェイ島を攻略してアメリカ艦隊(空母機動部隊)を誘い出し、捕捉撃滅するというものだった。これ自体、敵艦隊の行動を予測するリスクが大きく、勝利は疑問であり、陸軍は、実施に消極的であった。
ところが、ドゥーリトル空襲によって「勢力圏拡張」に狂奔しはじめた陸軍は、一転して「ミッドウェイ作戦」を支持しただけでなく、海軍の計画を越えて作戦を拡張した。すなわち、海軍が米艦隊を”壊滅させる”のと同時に、陸軍はミッドウェイ島に上陸・占領して、「ミッドウェイ島を基地として日本の哨戒線(米軍の襲撃にそなえて艦船や航空機で警戒するライン)を前進させることに主眼がおかれるようになった。」(下巻, p.274.)
こうして作戦は、①米機動部隊の撃滅、②ミッドウェイ島の攻略・占領――という「二兎を追う」ものとなり、どちらに主眼があるのかあいまいであり、兵力は分散しがちとなった。アメリカは、暗号電文の解読などから日本の企図を察知し、ミッドウェイ島付近に機動部隊を配置して迎え討った。
その結果、「ミッドウェイ海戦(1942年6月)」で日本側は、海軍の主力航空母艦4隻を撃沈され、艦載機全機と熟練した搭乗員多数を失うという全面的敗退に終った。「ミッドウェイ」をさかいに、日米間の海空戦力比は逆転した。
ドゥーリトルショックの・もう一つの結果は、陸軍が中国大陸での戦争目的を反転させてしまったことである。
たまたま、中国の南昌に不時着したドゥーリトル隊の一機を捕獲した日本軍は、捕虜にした搭乗員から、爆撃後の各機は、浙江省などの中国軍の飛行場に着陸する計画であったことを聴き出した。そこで、中国にある国民政府軍の飛行場を破壊する作戦が立てられた。
まずは、不時着機が着陸する予定だった浙江省一帯の飛行場を破壊すべく、「浙贛(せっかん)作戦」が実施された。その後、米軍の日本内地空襲が激化していったのに対応して、中国華中・華南の航空基地を目標とする・より広範囲な「大陸打通作戦(1944年1月~45年5月)」が着手された。
これらは、「本土防衛」目的の作戦としては、まったく無意味な労苦というほかはなかった。米軍機が中国の飛行場を使って日本「本土」を空襲するというのは、たまたま捕まえた一機の”証言”を都合よく解釈した妄想であった。
「大陸打通作戦」が 45年5月下旬に中止されたのは、この頃になると米軍はマリアナ諸島に航空基地を建設して、ここから日本内地を空襲するようになり(44年11月24日~)、のちにはさらに接近して、硫黄島から出撃するようになったため、中国での航空基地撃滅戦が無駄であることは、誰の目にも明らかになったからであった。
じっさいには、中国大陸の航空基地を、米軍はもっぱら台湾・沖縄を空襲するために利用した。日本軍は、「神州」防衛に血まなこになって、まったく無関係な基地を破壊するために、莫大な戦力と将兵の生命を浪費していたのである。
【10】 「浙贛作戦」
「浙贛(せっかん)作戦」は、1942年5月中旬に開始され、浙江省の中国軍飛行場を破壊し、同年9月末に終了した。支那派遣軍は、準備していたすべての作戦の中止を命ぜられ、総兵力18万を、この作戦に投入することとなった。当然に、現地指揮官からは、これでは国民政府を圧迫することもできず、敵を泳がせてしまう、との不満が出たが、内地の陸軍中央は意に介しなかった。「議論すれば水掛け論になるから、黙って従え」と言うのであった。
もはや、中国政府の“殲滅”は、戦争目的ではなくなっていた。対米開戦後・半年もたたぬうちに、日本軍部は中国との戦争を放棄していたのだ。中国で勝利することなどは念頭になく、日本内地、とくに天皇のいる帝都を死守することが至上目的となっていた。すなわち、
『日中戦争が〔…〕国民政府軍と共産党軍の覆滅をはかる戦争であったのが、〔…〕米軍機が日本本土を空襲するのを防禦するための戦争へと180度転換したことを意味している。〔…〕
参謀本部は、東京の天皇の身に米軍機空襲の危険がおよばないようにするのを最優先に考えて、〔…〕現実的には無意味な作戦を実施させたのである。』
『日中戦争全史』下巻, pp.276-279.
この作戦は、実施時期にも配慮がなかった。前半は中国の梅雨期で、しかもこの年は60年来の豪雨に見舞われた。後半は炎熱下の行軍で兵士は体力を消耗した。しかも、弾薬も食料も、補給は途絶えた。東南アジア、太平洋方面への戦線拡大で、もはや中国の派遣軍に補給する余裕は無かったのだ。中国は「兵站基地」と位置づけられ、現地から収奪した物資は、現地の日本軍には回らず、ひたすら日本内地と他戦場へ送られた。
『各部隊は食料を「現地自活」つまり、現地住民からの掠奪によって何とか食いつないでいる、というのである。総兵力約18万の日本軍が、連日、行軍・作戦中の食糧をすべて現地の住民や畑作物からの掠奪によったというのであるから、作戦戦場で中国民衆が被った損失総額は膨大なものとなった。
澤田司令官〔第13軍〕の陣中日記は「〔…〕同師団の栄養失調患者多数にて反転作戦〔退却のこと〕にも支障あらんか憂慮しあり」と記している。〔第13軍所属〕第22師団では食糧補給がまったくないために、兵士に食べるものがなく、栄養失調にかかって、歩行困難な兵士が多数〔…〕撤退も困難であるというのである。』
『日中戦争全史』下巻, pp.278-279.
「浙贛(せっかん)作戦」期間中の第13軍の損害は、戦死・戦病死の合計が 1284名、戦傷2767名、戦病〔戦地で病に倒れること〕1万1812名であった。日本軍のこうむった主要な損耗は、敵との交戦による損害ではなく、飢餓による戦病と餓死だったのだ。この状況は、このあとの「大陸打通作戦」でも繰り返され、敗戦に至るまで中国の日本軍の常態となった。
「浙贛作戦」では、細菌戦と毒ガス戦も、これまでにない規模で行われた。弾薬などの通常兵器が乏しくなったために、これらの特殊戦術に頼ろうとしたのだ。
とくに、細菌戦は、前後の他の作戦では見ない規模で遂行された。参謀本部の作戦課長服部卓四郎と作戦班長辻政信の意向によるものだった。この2人は、関東軍参謀だった当時、防疫給水部(731部隊)の石井四郎隊長と親しくなっていたのだ。
中国の現地軍指揮官らは、細菌戦に反対であった。第13軍澤田司令官は、「日支関係に百年の痕を残す。〔…〕山中、田舎の百姓を犠牲にして何の理かあらん」と陣中日誌に記している。しかし、辻政信中佐が南京の支那派遣軍総司令部に来て実施を督励した。石井隊長は前線司令部まで出かけて、細菌戦の実施要領を指導した。
『浙贛作戦の戦場において、関東軍防疫給水部(731部隊)の指導下に、〔…〕地上と飛行機から病原体を大規模に散布した。この時使用されたのはコレラ菌が中心で、1万人以上の被害者が出た。〔…〕1700人以上が死亡した。』
『日中戦争全史』下巻, p.282.
しかし、それらの犠牲者は、患者も死者も、すべてが日本兵だった! 中国軍は速やかに撤退したので、罹患しなかったのだ。(民間中国人も、罹患する前に避難したのであろう)。なぜ日本兵が犠牲になったかと言えば、参謀部も現地司令部も、細菌戦の実施を厳重機密としたために、兵士は細菌戦の実施を知らなかったのだ!
『まともに戦闘できなくなった日本軍とは対照的に、連合軍の一員となったことで戦意の高まった中国国民政府軍の抵抗は頑強になり、〔…〕日本軍が飛行場を破壊しても、中国側は民衆の人海戦術で、たちまち修復できたし、何よりも米軍は、ブルドーザーやダンプカーなどの〔…〕機械化部隊によって、別の場所に新しく飛行場を造成できたのである。』
『日中戦争全史』下巻, p.279.
こうして、対米開戦後の中国戦場では、どんな意味でも無駄な浪費でしかない作戦が、陸軍幹部の指導の下に続けられていった。したがって、もうここで「日中戦争史」の叙述を終りにしてもよいくらいなのだが、なおもう1回レヴューをつづけたい。というのは、「大陸打通作戦」の実態、ソ連参戦を予想した「防衛体制」の欺瞞的な構築、敗戦とともに約300万人の大陸植民者を犠牲にすることが予定されていたこと、そして何よりも、無条件降伏に踏み切った理由は何だったのか、……まだまだ論ずべき問題はたくさんあるのだから。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらは自撮り写真帖⇒:
ギトンの Galerie de Tableau
.