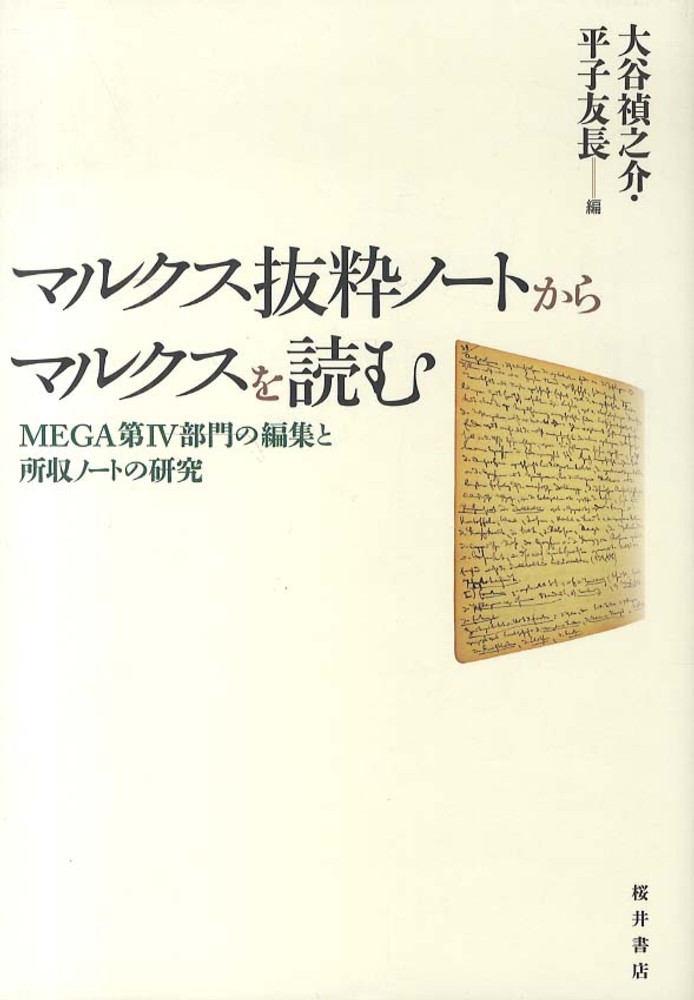Karl Marx: Exzerpte aus J. B. Jukes: The student’s manual of geology.
S. 294. In: MEGA IV/26, S. 575 (© BBAW)
ジュークス『学生のための地質学便覧』からのマルクスの抜粋ノート。
原書の図版(三葉虫,アンモナイト化石など)をていねいに書写している。
斎藤幸平氏が⇒:『人新生の資本論』の中でもふれているように、1867年に『資本論』第1巻を公刊したあと、マルクスが、その死に至るまで自然科学の研究に専心していた事実は、今日ではよく知られるようになった。マルクスは、『資本論』の完成をほったらかしにして、趣味の科学研究に耽っていたのだろうか? そう主張する説もないではない。が、死までの20年余りの期間に作成された膨大な自然科学研究ノートが、アムステルダムの「国際ME研究所」から出版され、その全貌が明らかになりつつあるいま、彼の自然科学研究は、遂に未完に終ったものの、『資本論』の完成には必須の・壮大なプロジェクトの一環だった、という結論に、専門研究者たちの見方は傾いている。
しかし、“『資本論』の完成に必須の自然科学研究”と一口に言っても、「抜粋ノート」の公刊がまだ続いている現状で、想定できる方向は、いくつかあるだろう。
ひとつは、第3巻に収録が予定されていた「地代論」を執筆補充するためであったという想定だ。そう考えている研究者が、もっとも多いかもしれない。しかし、「地代論」のためにしては、マルクスの“研究”――というより、マルクスは、化学反応式や鉱物の結晶構造を一から“学習”しているのだ――はあまりにも広汎すぎる。そこで、第二に、マルクスは、エンゲルスが遺稿『自然の弁証法』で展開したような、自然科学と社会科学を有機的につないだ科学論と、その上に立った一種の社会経済哲学を構想していたのではないか? という想定がありうることになる。↑上記の『マルクス抜粋ノートからマルクスを読む』に収録されたグリーゼ論文の見方は、これに近い。
そして、斎藤幸平氏らの想定が、その次に来る。“自然科学”といっても、マルクスが精読している諸著は、もっぱら、化学、農芸化学、地質学、鉱物学といったもので、“科学哲学”ならば中心になるはずの物理や天文学は含まれていない。マルクスの関心は、農業生産、農芸化学と、それらの最新理論を理解するための基礎化学に向けられている。人類の誕生に先立つ“自然の歴史 natural history”に関する地質学・古生物学への関心が、それに加わっている。つまり、マルクスの研究目的は、単なる農業生産と「地代論」の枠を超えて、ひろく《人間と自然との物質代謝》の歴史的変遷を解明して、『資本論』の理論的枠組みを大幅に拡充することにあった、ということになる。もしそうだとしたら、マルクスがもう少し長く生きていれば、20世紀の歴史を大きく塗り変えたであろう“革命的エコロジー”が誕生していたことになる。この想定は、現在までに公刊された「抜粋ノート」の実態を、もっともよくふまえていると言えるだろう。
「人類の誕生に先立つ“自然の歴史”」すなわち「自然史 natural history」が、マルクス・エンゲルスの構想した“人類社会史”の・不可欠の半面をなしていた――ということは、二人が探求の出発点として書いた草稿『ドイツ・イデオロギー』の↓次の部分からも伺える。彼らが、その時点で、地質学・自然科学方面の考察を省いたのは、当時彼らにはその方面の素養がなかったからである。しかしいま、すでに『資本論』第1巻を世に問うて、“社会経済”プロパーについては一通りの考察を終えた地点に立って見れば、いまや、もう一つの半面である“自然史”についても、あらためて基礎からの考察を積み上げていかなければ、『資本論』の体系は、片ちんばな偏頗なものになってしまうと感じられたであろう。
「歴史にとっての、第一前提を確定すること。それはつまり、『歴史を創る』ことができるためには、人間たちが生活できていなければならないという前提である。生活しているからには、何はおいても最低限、飲食、住居、被服、その他若干のものがそこに含まれている。それゆえ、第一の歴史的行為は、これらの欲求を充足させる手段を創出すること、つまり、物質的生活そのものの生産である。
地質学的、水理学的、等々の諸関係。人間の身体。欲求、労働。
このことは、しかも、歴史全般の根本条件ともいうべき歴史的行為であって、〔…〕」
(廣松渉・他訳『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,岩波文庫,pp.51-53. 斜体は加筆部分。黒字はエンゲルスの筆跡、青字はマルクスの筆跡。)
「人間史全般の第一の前提は、いうまでもなく、生きた人間諸個人の生存である。これらの諸個人が自らを動物から区別することになる第一の歴史的行為は、彼らが思考するということではなく、彼らが自らの生活手段を生産し始めるということである。第一に確定されるべき構成要件は、それゆえ、これら諸個人の身体組織と、それによって与えられる身体以外の自然に対する関係である。われわれは、ここではもちろん、人間そのものの肉体的特質についても、また人間が眼前に見出す自然的諸条件、すなわち地質学的、山水誌的、風土的その他の諸関係、についても、立ち入ることはできない。〔…〕歴史記述はすべて、この自然的基礎ならびにそれが歴史の行程の中で人間の営為によってこうむる変容から、出発しなければならない。」
(廣松渉・他訳『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,岩波文庫,pp.25-26. 下線部は抹消された部分。斜体は加筆部分。)
なお、『マルクス抜粋ノートからマルクスを読む』は、ここで取り上げるグリーゼ論文↓以外にも、内外(日本、中国、ヨーロッパ)の研究者による有用な論考を集めており、マルクスに関心をもつ読者なら、書棚に1冊置いておきたいレファレンス本だ。残念ながら、アマゾン傘下でもほかのメディアでも、現在はすべての古書店に在庫がない。しかし、将来再版される可能性はあるので、「ほしい本」に登録しておかれることをお勧めする。
アネリーゼ・グリーゼ Anneliese Griese「マルクスの『化学諸草稿』と地質学・鉱物学・農芸化学抜粋――マルクスの抜粋を科学史のなかに位置づける」
in:大谷禎之介,平子友長・編著『マルクス抜粋ノートからマルクスを読む――MEGA第Ⅳ部門の編集と所収ノートの研究』,2013,桜井書店,pp.261-281.
【1】 『地質学マニュアル』から最も多く抜粋
2011年に刊行された『MEGA』第Ⅳ部門第26巻は、地質学・化学・農芸化学関連の多数の書籍からのマルクスの抜粋と草稿を収録している。さまざまな性格のテクストを多数含んでいるが、なかでも、印刷された第26巻で 500ページを超える最大のテクストは、1872年エディンバラで出版された『学生のための地質学便覧』第3版からの抜粋である。著者ジョゼフ・ジュークス [Joseph Beete Jukes , 1811 – 1869]は、ケンブリッジ大学で地質学を学び、1839-40年にカナダ・ニューファンドランド島、42-46年に、ジャワ島,トレス海峡諸島(ニューギニアとオーストラリアの間),オーストラリア東海岸およびグレイト・バリア・リーフを調査し、当時まだよく知られていなかったオーストラリア大陸の地質構造と土壌特性の概略を明らかにした。イギリスにもどったジュークスは、政府の命で北ウエールズ炭田を調査し、50年からはアイルランドの地質調査に従事した。
『便覧』は 1857年に初版刊行、多年にわたって学生、研究者の指針となったが、第3版は、ジュークス死後に、ギーキ[Archibald Geikie]らが最新の知見を入れて大幅に変更拡充したもの。
ジュークスによれば、地質学[Geologie]者の任務は、なによりもまず、ゲオグノジー[Geognosie]にある。すなわち、
「地球の表面にあるさまざまな岩石および鉱物を、さしあたってそれらの発生の歴史は考慮せずに、長い時間をかけて調査し、その結果を良心的に記述することである。
〔…〕そのような独自の任務が遂行されたことによって、驚くべき結果がもたらされた。すなわち、一見したところなんの秩序も規則もないように見える岩石や鉱物の世界は、秩序と調和によって支配されているということ、地殻は規則的に配列された岩石群からなっていて、これらの岩石群は、順を追って、あるいは〔…〕つぎつぎに継起したもろもろの長大な時期のあいだに生成した、ということである。」
(『マルクス抜粋ノートからマルクスを読む』,p.263.)
ただし、時期の順序を特定するには、鉱物学だけでは不可能で、古生物学(化石による時期の特定)が必要である、と。
ジュークスとギーキによるこの書物は、マルクスに対して、かつてスミスの『諸国民の富』が国民経済学に関して果したのに匹敵する役割を、地質学について果たしたと言える。「この書物をマルクスは、ほかのどんな自然科学の著作にも見られないほど徹底して研究した。」
「この書がはっきりとわからせてくれるのは、地質学の中心には大地の歴史性という理念があって、この理念を基礎づけるためにさまざまの専門的学問分野の協働を必要とする〔…〕、ということである。」
(『マルクス抜粋ノートからマルクスを読む』,p.264.)
「マルクスは、岩石を形成し地表を変えるような諸力が扱われる第2部、いわゆる動的地質学[Dynamische Geologie]から始める。それに続くのは第3部、化石の研究に専念する古生物学である。そのあとでようやく、肉眼岩石学と記載岩石学の両辺を含む第1部、いわゆるゲオグノジーまたは岩石学がきて、最後に層序学または一連の堆積岩列の形成史を扱う第4部になる。第4部のうちの残りの約90ページからはひとつの抜粋もない。マルクスは、かなり唐突に抜粋作業を打ち切っているのである。」(a.a.O.)
この“学習”順序は、地質学の初学者としてはまったく一般的なコースに思われる。最初に火山の噴火や造山運動、マグマの冷却による岩石の生成といった、一般に興味のわくトピックスを追っていき、関心が高まったところで基本にもどって、地質学・岩石学の基礎的な方法論をじっくりと学んでいく。これは、博物館を見て回る場合でも同じだろう。最初から岩石の種類の体系や特徴を忍耐強く学ぼうとする初学者などはおるまい。
しかし、マルクスが、さいごに堆積岩の層序に関する部分に進んで、その中途で突然、抜粋を――したがっておそらく読書そのものを、中断してしまった、という点は興味を惹く。彼は、そこで何らかのインスピレーションを得たのではないか? この点は、著者グリーゼ自身が、この論文の結論部分で指摘することになる。
「この抜粋はまず間違いなく、『化学諸草稿』〔『MEGA』Ⅳ-31巻収録のノート――ギトン註〕よりも前に作成された。」
(『マルクス抜粋ノートからマルクスを読む』,pp.264-265.)
つまり、マルクスは最初に地質学を“学習”し、そこで化学の再履修(古い教科書には無かった化学反応式など)の必要を感じて、化学の教科書類に向かった、ということがわかる。
「化学は鉱物学と地質学にとっての不可欠な基礎なのだ、――マルクスは抜粋のさいの研究のなかで、まさにこの事実を把握したのである。とくにマルクスが肉眼岩石学について書きとめた文章には、このことがはっきりと刻み込まれている。」(『マルクス抜粋ノートからマルクスを読む』,p.265.)
IMES: Marx-Engels-Gesamtausgabe (国際ME研究所編『マルクス・エンゲルス全集 {新MEGA]』)
【2】 “50の手習い”。中学生の参考書で鉱物学を習う。
ジュークスとギーキの『便覧』以外で、特に注目に値する抜粋は、シェードラー『自然論』およびジョンストン『農芸化学と地質学の初歩』からのものである。これらは、『便覧』からの抜粋よりもはるかに少量で、『便覧』が、本の全体から抜粋されているのとは異なって、特定の章節からのみ抜粋している。
「シェードラーの著作とジョンストンの著作からの抜粋は、全部合わせても 50印刷ページそこそこしかなく、おそらく1878年4月から5月末までに作成された」(『マルクス抜粋ノートからマルクスを読む』,p.267.)
シェードラーは専門科学の研究者ではなく、啓蒙教育家だったが、『自然論』は、ギムナジウムと実科中学校での「授業のさいの手引き」として書かれ、「物理学」「天文学」「化学」「鉱物学」「「植物学」「動物学」の諸篇からなっていた。つまり、当時の自然科学の全分野にわたる平易な解説書で、じっさいに著者の生前に 22版に達するほど広く読まれていた。
シェードラーが著述家として成功をおさめたのは、リービヒの後押しがあったからだった。シェードラーは大学卒業後の3年間、ギーセンでリービヒの助手を務めており、リービヒはその後出版された弟子の著作を、世間に対して推奨したのだった。(pp.267-268)
中・東欧の古い教育制度では、中等教育(現在の日本の中学+高校)は、ラテン語・ギリシャ語を中心とする「ギムナジウム」と、英語や数学・理科をふくむ近代教育の「実科学校 Realschule」に分かれていた。大学に進学するには「ギムナジウム」を出なければならず、マルクスとエンゲルスも「ギムナジウム」に通っている。したがって、彼らが学校で理科を習う機会は、ほとんどなかっただろう。だからマルクスは、50歳を過ぎてから、中学生用の参考書に取りくんで“自然科学”を一から学習する必要があったのだ。
『自然論』の「鉱物学」編は、鉱物だけでなく、岩石や、地質学にわたる内容も含んでいる。マルクスがここから抄録した時期は、ジュークスの『地質学便覧』にとりかかるより前だった。中学校から大学へ、という順序に従って、独学を進めていたのだ。
「マルクスは、『鉱物学』篇の主な内容を細部にわたって採録した。」
(『マルクス抜粋ノートからマルクスを読む』,p.269.)
マルクスは、「鉱物学」篇から、まず「一定の化学組成と結晶系によって特徴づけられる」「単純な鉱物」の記述と分類を抄録した。つづいて、「鉱物混合体」すなわち岩石についての説明、その「成層・生起・形成についての説明、ゲオグノジーと地質学の説明に向かう。」 シェードラーの説明は、単純ないし均質な鉱物から混合鉱物へ、単純な岩石から「混合された不均質な岩石」へ、要素の分類と生成から、より包括的な構造体の形成の論理へ、最終的には「地殻が形成されてきた順序」の概観へと、体系的に展開されている。(p.269)
しかし、ここで私たちは、著者が指摘していない・一つの疑問にぶつかってしまう。“地質学というものは――化学,農学もそうだが――はたして、書物を独学するだけで習得できるものだろうか?”という疑問だ。古典派経済学のようなものなら、マルクスのように哲学の素養があれば、“書物からの習得”も可能だろう。しかし、“哲学的なアタマ”は、自然科学にも通用するだろうか? という疑問がある。加えて、標本の観察も、露頭の臨検もしたことがない者に、上っつらでない地質学の理解が可能か? という根本的な疑問がある。
マルクスが、そうした“専門家の手ほどき”を受けなかったと断定するのは、早すぎるかもしれない。彼には、エンゲルスを通じて連絡のとれる化学、地質学の専門家が何人もいた。“手ほどき”を受けようと思えば受けられたはずだ。しかし、問題は、現代のマルクス研究者たちが、そうしたことにまったく関心を示さないことにある。地質学を理解するための「臨検・観察」の重要性、自然科学を学習するうえでの「実験」の重要性、‥そうしたことをマルクスが、意識していたかどうか? ――これは、どうしても検証しておかなければならないテーマであるはずだ。
【3】 ジョンストンから、《物質代謝の亀裂 metabolic rift》を学ぶ。
ジョンストンからの抜粋は、『農芸化学と地質学の初歩』第7版(1856年)からのものである。この書物はマルクスの興味を強く惹いたらしく、彼は「シェードラーの抜粋を一時中断し、しばしジョンストンに全力を注いだ。」(p.270)
ジョンストン(James Finlay Weir Johnston 1796-1855)は、スコットランドの農芸化学・地質学者。単なる啓蒙家ではなく、自分の専門領域での代表的研究者だった。スウェーデンのベルセリウスのもとで化学を学び、1832年に英国・ダラム大学が設立されると、化学・鉱物学の主任教授に任命された。『農芸化学と地質学の初歩』は第6版までに、ヨーロッパの多くの言語に翻訳されて普及した。
かつてマルクスは、『資本論』起草前の 1850年代に、ジョンストンを「イギリスのリービヒ」と呼んで称揚し、その農業経済論を熱心に読んで抄録を作っていた(『ロンドン・ノート』収録)。その時のテーマは農業生産力の発展可能性、つまりリカードの「収穫逓減則」への反論根拠をジョンストンに求めたのだった。(⇒:【経済論レヴュー】 斎藤幸平『大洪水の前に』(4)――穀物法廃止とグアノ戦争【13】【14】)
「『農場経営者は土地そのものの性格を変えることができる。』〔…〕『適当な時期に、適切な物質を適当量土壌に投入するならば、彼は土地の肥沃さをおそらく永遠に保つことができる。』
〔…〕リービッヒもジョンストンも〔…〕化学と技術学を用いた改良による将来の農業生産性の増大を確信していたのだ。〔…〕こうして、農業における改良の自然的限界を強調するリカードーやマルサスに対して、マルクスは農業の近代化による収穫逓増を信じるようになっていったのである。
〔…〕化学肥料によって、休耕も輪作もなしに、そして、土壌ごとの特性も関係なしに〔変更し、改良して〕、市場でもっとも有利に販売することのできる作物を最大限に育てること〔…〕が、19世紀の農業革命の目指すところであった。」
斎藤幸平『大洪水の前に』,pp.177-178,184.
しかし、『資本論』第1巻刊行後の現段階では、マルクスは、“農業生産力発展”といった外面的な結論部分に眼を奪われることなく、より基本的な、農業にとっての自然科学の重要性、…生産と《自然》との関係――という科学者ジョンストンのおおもとの思考に焦点をあてているのだ。というのは、科学は、農業の生産性を増大させるばかりではない、そうした「生産力至上」農業による土地と《自然》の荒廃を解明してゆくこともまた、科学に課せられた大きな役割だからだ。
「ジョンストンは緒論で、農業の実務を完全なものにしていくためにはもろもろの科学を援用することが必要不可欠だ、と強調する。実務家は自分の仕事と〔…〕化学、地質学、化学的生理学との連関を知っておく必要があるのだ、と彼は言う。〔…〕
10ページにもみたないジョンストンからの抜粋は、主として〔…〕農業にたいする地質学の直接的関係を論じている2つの章からのものである。〔…〕この関係がマルクスにとっての内容的な重点であったことは明らかである。」
(『マルクス抜粋ノートからマルクスを読む』,p.271.)
グリーゼによると、『農芸化学と地質学の初歩』は、第1~4章で、植物の化学的組成、植物の成長に重要な生化学過程の特殊性を述べ、第5~8章では、土壌の種類と区別を記述し、各種類をそれぞれの地質学的前提条件から説明している。つづいて、第9章は、さまざまな土壌の生理学的・化学的特質についての詳細な説明、また、「土壌の性質と自然植生のあいだの直接的な関連性」についての詳論。第10章以下では、土壌改良のさまざまな方式について述べている。
そうすると、マルクスが抜粋した「2つの章」とは、5~8章に含まれる部分だろうか?
「シェードラーおよびジョンストンからの抜粋に特徴的〔…〕のは、おそらくあとで読み直した時に書き込んだと思われるマルクスの手になる多数の欄外書込みが見られることである。そうした欄外書込みがあるのは、なかでも、テキストのうち土壌の性質ないし土壌の豊度の諸問題が論じられている箇所である。」
(『マルクス抜粋ノートからマルクスを読む』,p.278.)
【4】 地質層序学からのインスピレーション
さて、論文の結論部分で、著者グリーゼは、地質学文献からのマルクスの抜粋は、地質学そのものの研究よりも、その方法論を、社会経済学、とりわけ「史的唯物論」の構想に役立てるためだったという考察を述べている。
これは無理な推論だと私は思う。自然科学の“論理を借りるため”にしては、マルクスの“学習”はあまりにも念が入っているからだ。しかも、地質学の論理は、「史的唯物論」とは、似て非なるものだ。表面的に比べる人は似ていると思うが、詳しく理解すれば、まったく違うことがわかる。地質学を熟読したマルクスに、それが分らなかったはずはない、と思うのである。
「マルクスは自分の時代の自然科学のなかに、社会理論の研究にとっての方法的な範例を見ていた。〔…〕
マルクスによる自然科学研究の一つの中心的テーマは、地質学における発展の考え方であり、また、この考え方をはっきりと示すもろもろの地層[geologische Formation]のあいだの関連という概念である。〔…〕
マルクスはすでに 1851年に、ジョンストンの『農芸化学と地質学の講義』からの抜粋で、地表のなかのさまざまな層(あるいは層のつらなり)が互いのあいだでつねに同じ相対的な位置を占めており、それらの層の空間的な重なり合いからそれらの相対的な年代がわかる、ということを示唆する記述を書きとめている。〔…〕ジョンストンは地層[geologische Formation]という概念を用いており、〔…〕
このようにしてマルクスは〔…〕地層の連続[Formationsfolge]という概念〔…〕をはじめて理解する。」
(『マルクス抜粋ノートからマルクスを読む』,pp.278-279.)
しかし、ここで注意しなければならないのは、「地層」の層序と、「史的唯物論」つまり「社会構成体」の“層序”とは、まったく論理の性質が異なるということである。類似は、表面的なものにすぎない。両者をイコールで結べるのは、せいぜい比喩としてである。社会の歴史を「地層」のアナロジーで理解しようとするならば、悪名高い「社会的ダーウィニズム」よりもひどいコジツケに陥ってしまうことになる。
まず第一に、「地層」の各層は、互いのあいだに形成の関連性を持たない。それぞれの層は、それぞれの時期に、他の層とはまったく無関係に形成される。たとえば、砂岩の層の上に泥岩の層が形成されるのは、以前の時期に砂岩が形成されたから、今は泥岩が形成される――などという因果関係は存在しない。砂岩が“発展”して泥岩になるでもない。各層は、それぞれの時期の気候、陸水、海流、地殻変動などの条件によって、砂が積もったり、泥が積もったりした結果であって、原因は完全に外在的なのだ。砂岩→泥岩、というような内在的発展要因はありえない。
第二に、地層の層序は、現在の上下関係が、形成の時間的順序を表しているとは限らない。地層は、しばしば地殻変動によって反転するし、異なる地層や岩塊(スコリア)の陥入・攪乱はめずらしくない。だからこそ、マルクスが『資本論Ⅰ』刊行以後に熟読したジュークス『地質学便覧』には、地層の「時期の順序を特定するには、鉱物学だけでは不可能で、古生物学(化石による時期の特定)が必要である」と書いてあるのだ。(↑前記【1】参照)
もしもマルクスが、地層の層序にヒントを得て「史的唯物論」を構想したのだとすると、たとえば、原始共産主義社会が、資本主義の「陥入」によっていきなり資本主義社会になり、そのあと封建制に退行し、さらに奴隷制社会に退行してゆく‥‥というようなしっちゃかめっちゃかを考えなくてはなるまい。「継起的発展」どころではないのである。
しかし、逆に言えば、マルクスは、そのような“逆転的変異”をも説明できるような自由度の高い社会変遷の論理を、地質学から学び取っていた……のかもしれない。
「『MEGA』Ⅳ-26巻収録の〔…1870年以後・晩年の地質学等抜粋ノートでは〕マルクスは、〔…〕とりわけジュークス/ギーキ、ジョンストン、シェードラーにかかわって、〔…〕地殻は、どのような過程を経て現在の姿にたどりついたのか、さまざまな地層はなにによって互いに区別されるのか、それらは互いにどのように関連しあっているのか、という問題を検討している。〔…〕
1881年2-3月に書かれた〔…〕ザスーリチへの手紙の諸草稿〔…〕のなかでは、繰り返して、歴史的な構成体の連続と地層の連続とが対比されている。
地質学上の地層概念が、マルクスの思考における社会構成体という新たなカテゴリーにとって本質的な意味を持っているという推定〔…〕」
(『マルクス抜粋ノートからマルクスを読む』,pp.279-280.)
さらに著者は言う。「地層の連続」に最初に注目したのはヘーゲルであった、と。しかし、「地層」の層序に対するヘーゲルの理解は、地層が「内的・必然的連関」に貫かれている、そこに「普遍的法則」がある、という錯誤にみちた異常な思い込みなのだ。もしも、著者の言うようにマルクスが、ヘーゲルのこの偏執狂的勘違いを引き継いだのだとしたら、「史的唯物論」は、錯誤の上に錯誤を積み重ねた虚構の建造物だということになってしまう。もちろん私はそうは思わない。
「ヘーゲルの『自然哲学』を考慮に入れる必要がある。〔…〕地層の連続という地質学的概念についてヘーゲルは、『〔…〕この連続[Folge]のなかにはなにかもっと根深いものがある』と述べている。『過程の意味と精神は、これらの地層の内的関連、必然的な連関である。……地層のこの連続の普遍的法則こそが、認識されねばならず、……この法則が重要なのである。』」
(『マルクス抜粋ノートからマルクスを読む』,p.280.)
繰り返そう。マルクスの地質学研究は、社会科学へのアナロジーなどではなく、地質学そのものの理解が目的であった。それは、『資本論』構想の半面である《人間と自然との物質代謝》論を構築する努力の一環であった。
ところで、この記事を書き終えて他の人のブログを見ていたら、↓次のような一句が眼にとまった:
「自分の考察したい分野はほかの分野を見てよくわかるというのはよくあることだ。」
たしかに、それはマルクスにもあっただろう。地質学の読書からも、社会経済の考察について、いつも何らかの示唆を得ていたに違いない。それは否定できないことだ。もちろん、ヘーゲルのような“大まちがえの大風呂敷”は排除したうえでのこととして。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらは自撮り写真帖⇒:
ギトンの Galerie de Tableau