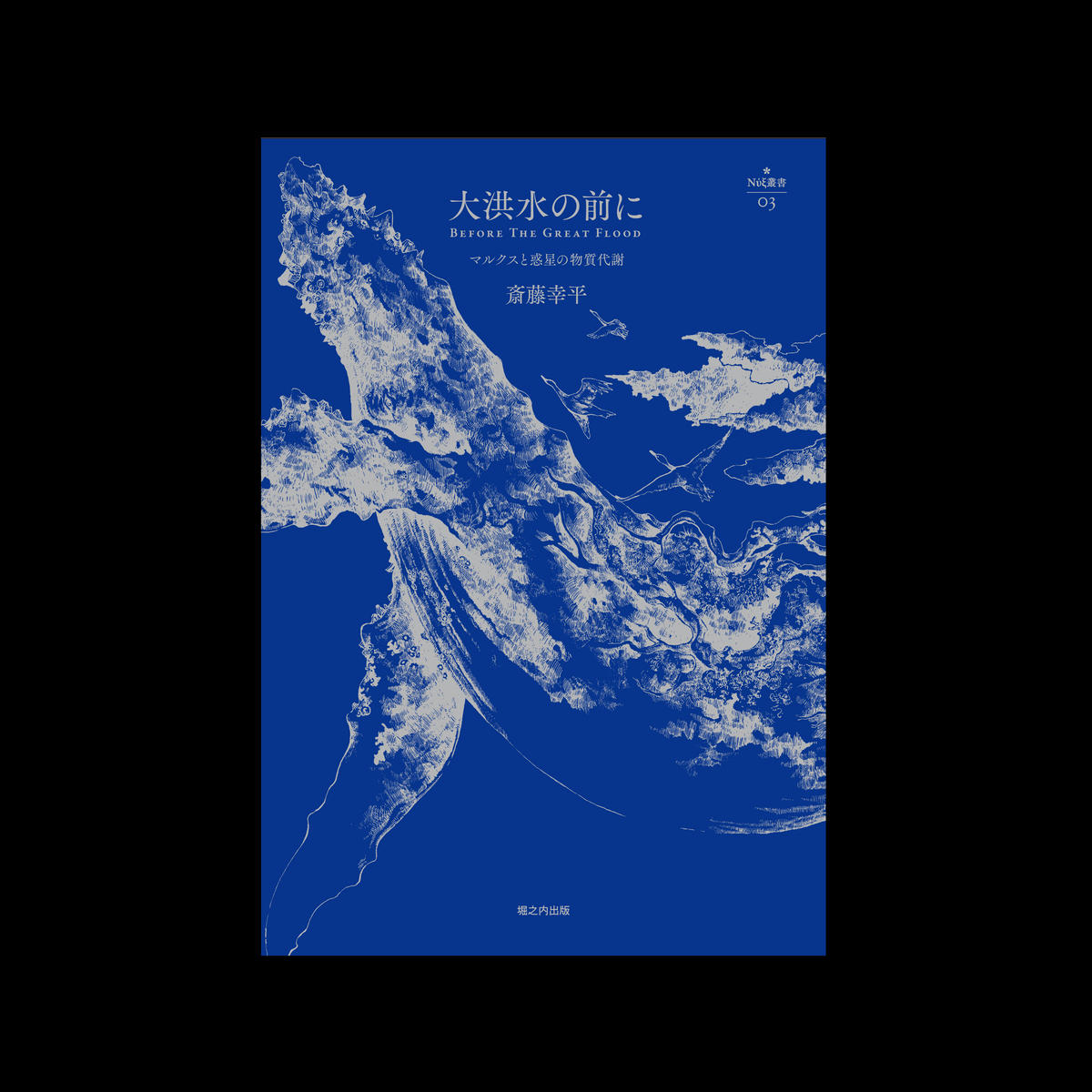〔18〕 「利潤率低下」論争
今回は、第6章、第7章を駆け足でダイジェストします。
第6章「利潤率、弾力性、自然」では、『資本論』の
有名な論争点「利潤率の 傾向的低下(法則)」を扱っています。
『資本論』が言う「利潤」とは、大企業の役員報酬、内部留保といった
ものとイコールではありません。それらも含みますが、新規設備投資
や借入金の利子支払も「利潤」の一部です。一国の経済全体でいえば、
経済成長の”増分”、昨年の国民純生産額よりも今年の国民純生産額が
増えた分が、「利潤」にほぼイコールです。つまり、
資本家が”もうけ”を自分のポッケにいれる‥というイメージとは少し
違うのです。拡大再生産をするための追加費用は「利潤」の中から
出さなくてはなりません。
”ある時に資本家が手持ちの資金で原料を買い、労働者を雇って
生産を開始し、できた製品を市場で売って、資金を回収する”
という『資本論』第1巻の生産モデルをイメージする必要があります。
現実世界の企業は、一期の途中で次期のための設備投資をしたり
原料を買い入れたり給料を払ったりしますから、もっと複雑です。
『資本論』はあくまでも経済学モデルです。
そのモデルで、期末に回収した資金(貨幣額)から期首の資金額を
引いた残りが、「剰余価値」すなわち「利潤」です。
「利潤」を資本家が飲み代や海外バカンスに全部費消してしまえば
次期の生産は今期と同じ規模で「単純再生産」、「利潤」の一部を
次期生産に投入すれば「拡大再生産」です。
「利潤」を M,原料・燃料や設備費用すなわち「不変資本」を C,賃金すなわち「可変資本」を V,とすると、「利潤率」 r は、↓左の式で与えられます。分子と分母を V で割ると、↓右の式が得られます。
(C/V) は「資本の有機的構成」[要するに、賃金に対して、機械設備コストの割合]、 (M/V) は「剰余価値率(搾取率)」です。いま、「剰余価値率」を一定とすると、「有機的構成」が大きくなる(高度化する)にしたがって、「利潤率」は低下していきます。資本主義が発展して技術革新が進めば、「有機的構成」はどうしても大きくなりますから、「利潤率」は低下してゆく運命だ!‥‥おそろしく乱暴な理解ですが、これが「利潤率の傾向的低下」法則と言われるものです。
しかし、「搾取率が一定」なんて、とうてい受け入れられる仮定ではないでしょう。資本家は、賃金をつねに生活費の最低水準に切り下げて、「利潤」増大を図る‥というのが『資本論』の一貫した仮定なのですから、イノベーションで生産性が上がれば、賃金はどんどん切り下げられて「搾取率」は大きくなるにきまっている‥‥そういう反論が起きます。私が大学で習った「マルクス経済学」の教科書は、「剰余価値率を 1 とすると」 と常に仮定していて、なぜ 1 (1対1)なのかの説明はどこにもなかったので(講義でも、無かった)、「マルクス経済学」は信用できないと確信してしまいましたw。単位取得はあきらめて、翌年は、ケインズ派の近代経済学と公共経済学に乗り換えましたです。それでも、大塚流の経済史は好きでしたし、『資本論』も、ずっとあとで置塩信雄氏の本を読んで「信頼」を回復して読み直すのですが‥。
いま、↑上の右側の式で考えると、分母の「有機的構成」と分子の「剰余価値率」が同じ速度で増大した場合には、‥(「+1」が分母の足を引っ張るので)「利潤率」は増大します。「利潤率」が下がるには、「剰余価値率」の増大は、「有機的構成」よりもよほどゆっくりと進まねばならない……そうなるという証明が、『資本論』にはあるのだろうか?!
ただ、こういう数式の議論には、ひとつの前提があります。マルクスは、「利潤率の傾向的低下」を、資本主義経済の「法則」として主張しているのだ、という前提です。その場合には、19世紀から、20世紀、21世紀‥と経過するにしたがって、社会全体の「平均利潤率」は、減衰曲線を描きながら下がってゆく……振り子の揺れが収まって行くように、最後は静止に限りなく近づいてしまう……そういうイメージになります。――――【A】
しかし、別の見方もあります。マルクスはこれを「法則」としてではなく、資本のやむにやまれぬ衝動の結果として主張している。資本は、「剰余価値」を増やし「価値増殖」をめざして「有機的構成」の高度化にはげむのだが、その結果は、(ほおっておけば)「利潤率」が低下してしまうというパラドキシカルな事態になる。他方で、資本には、「利潤率」を増大させる衝動も、もちろんある。この相矛盾する傾向の鬩ぎあい、”動力学”をマルクスは分析しているのだ、と。――――【B】
↑最初にリンクしたウィキペディアの「利潤率の傾向的低下の法則」記事は、基本的に近代経済学からの説明ですが、かなりレベルが高いので、一読をお勧めします。【A】に関しては、著者の本章よりも先まで言及しています。たとえば、置塩信雄氏は、資本間の競争を考慮した『資本論』第2巻以後の枠組みでは、搾取率一定を仮定しても「利潤率」が増大すること(置塩の定理)を数学的に証明しました。著者の説明には、これが抜けています。
ただし、【B】については、ウィキペディアにはほとんど書いてありません。著者の考えは、最終的には【B】であるようです。
それでも、【A】の「傾向的低下」が現実なのかどうか、どうしても気になるという人は多いでしょう。そこで、ウィキペディアにもあるように、実際の統計に基づいた実証研究が、多数行なわれています。どうも、概観してみると、最近はマルクス経済学系の学者のほうが「傾向的低下」に否定的なようです。大企業が、労働者の賃金も税金も出し惜しみながら、巨額の内部留保を計上している現状で、「利潤率の傾向的低下」を言うのは説得力がない、と感じるのではないでしょうか。かえってトマ・ピケティのような近代経済学系のほうが、マルクスの「傾向的低下法則」を再評価しています。
おおざっぱに言えば、「利潤率」はともかく、市中の利子率は、先進国ほど低いし、歴史的にも資本主義の発展とともに低くなっています。少なくとも20世紀半ば以後は、中央銀行は、利子率が利潤率よりも低くなるように操作しています(そうしなければ、誰も産業に投資しなくなる)。しかし、「利潤率」が高くなり過ぎた時は、利子率を上げて景気の過熱を抑えようとします。そうやって、長期的に見れば利子率は「利潤率」といっしょに動いているので、利子率の低下が歴史的趨勢だとすれば、それは、「利潤率」の長期的低下傾向を反映している――と言えるのではないか? そんなふうにも考えられます。
〔19〕 資本の「弾力性」、自然の「弾力性」
「弾力性」の定義を近代経済学の教科書で見ると、なにやら数式が出てきて、イメージを持ちにくくなります。しかし、これはもともと物理の用語です。『資本論』の場合には、スポンジとかゴム風船とかタイヤの「弾力性」のイメージで十分通用します。
「例えば、労働力は弾力的であり、〔…〕同じ賃金のままでより長い時間働かせたり、より労働強度を高めたりすることも可能である。〔…〕労働力の弾力性が市場の需要の変動に合わせ」るための「調整弁となってくれるのである。〔…〕大工業が生み出す様々な技術革新にも労働者は柔軟性をもって適応できるのである。
〔…〕自然は弾力的でもある。資本は自らが生み出す廃棄物に対して支払いをしなくとも、それがすぐに生産が依拠する自然条件を悪化させることはない。環境は生産や消費から生じる様々な否定的帰結を弾力的に吸収してくれるのだ。〔…〕土壌は〔…〕養分を返さなくても、翌年も収穫をもたらしてくれるだろうし、石炭や石油も短期間であれば、需要に合わせて、比例的な追加費用を要さずに生産量の増大を可能にしてくれる。」
『大洪水の前に』,pp.273-274.
こうして、資本は、「労働力、科学、および大地(自然)」(p.272)すなわち「素材世界」の弾力性を徹底的に利用して、資本自身の「弾力性」を獲得します。そうやって、予想しがたい需給の変動や恐慌による打撃を吸収し、「利潤率低下」にも対処することができるのです。
「資本が価値増殖を目指すとき、資本は様々な障害にぶつかる。」資本は、「みずからがこうした障害をつくりだしている以上、資本は繰り返し、不可避的に障害に直面し、その度に新たな障害を乗り越えなくてはならない。マルクスはこの絶え間ない運動を『生きた矛盾』と呼んだのである。〔…〕
矛盾含みの傾向性はあらゆる制約を乗り越えようとする資本に特徴的な性質である。」
これは、『利潤率』にもあてはまる。資本は、「自己価値増殖を最大限にする」という「目標を達成するために、競争のもとで、生産力を上げ、機械化を進めていくわけだが、ここでもまた自らが生み出す障害に繰り返しぶつかりながら、それを反作用で乗り越えようとする。その現われの一つが資本の有機的構成の高度化にともなう利潤率の減少と・相対的過剰人口の形成による賃金低下を通じた利潤率の上昇である。」
『大洪水の前に』,pp.266-267.
「有機的構成の高度化」は、他の条件が変らなければ、「利潤率」を
減少させてしまう。しかし、資本はイノベーションを進めながら
「利潤率」増大に寄与する手立ても、さまざまに講じてゆく:
「資本は労働日を延長する〔一日の労働時間を増やす〕ことで」利潤を増やす「ことができるし、機械化を通じて労働強度を高めることもできるだろう。また、生産力の増大は〔生活資料の低廉化を通じて〕労働力の価値を下げ、」利潤を増やす。「さらに、生産力の増大は不変資本〔原燃料、機械設備〕を廉価にし、資本の有機的構成を下げ」て、『利潤率』を増大させる。機械化で不要になった人員の解雇、すなわち「相対的過剰人口の創出も、労働者間の競争を高めることで、労働力の価格を下げ、剰余価値率を上昇させる〔…〕マルクスは不変資本の節約〔による『利潤率』の増大〕についても論じている。例えば、『生産手段の集積』は、建物、機械、暖房などは労働者の人数の増大に比例して増大しないので、固定資本部分が節約される。ここに原料などのリサイクルを付け加えることもできるだろう。〔…〕
不変資本の節約は安全対策や衛生対策のための出費を節約することでも実現可能である。』」
『大洪水の前に』,pp.268-269,275.
こうして、資本は「弾力性」を発揮して、「利潤率低下」というパラドキシカルな事態を乗り越えていこうとするのだが、「資本の弾力性」は、最終的には「労働力、科学、自然」という「素材的世界」の弾力性に頼っている以上、無限の弾力性を発揮できるわけではない。「素材的世界」の「弾力性」には限界があるからだ。
「労働者の肉体的・精神的能力の掠奪は資本そのものが依存している素材的担い手の質を悪化させてしまうことで、生産過程そのものにも悪影響がもたらされ」る。
生産の効率性、したがって『利潤率』は、原料の質にも大きく依存する。ところが、原料を生産する農牧業や鉱業に、廉価で大量の原料の供給、したがって生産性と生産量の飛躍的増加が要求されると、地力の疲弊、質の良い鉱脈の枯渇といった《自然》の限界に突き当たり、原料の質の低下が避けられず、さらには、産出量そのものが大きく減退することになってしまう。
「1870年代の抜粋ノートを見てみると、〔…〕自然的条件における変化がもたらす経済的影響を考察している。例えば、〔…〕鉄への需要が増大するにつれて、より悪い条件の鉱山でも採掘が継続されるようになると述べている。」
『大洪水の前に』,pp.275,283.
「自然条件の悪化は利潤率にも〔悪い〕影響を及ぼす〔…〕『農業における社会的生産力の増加は自然力の衰退を〔一時的に〕埋め合わせるにすぎないか、または埋め合わせることさえなく、』〔…〕慢性的な掠奪は、予期しないような不作や枯渇をもたらす〔…〕
利潤率低下への反作用としての資本の集積も問題をより一層深刻化させる。〔…〕自然による供給が資本蓄積のペースについていける保証はどこにもないからだ。〔…〕新しい機械の導入」による生産力の倍増は、必要とされる原燃料の投入量を「比例的に増大するだろう。だが、そのような変化は自然のサイクルとはまったく無関係のところで生じている〔…〕
恐慌の瞬間には 資本の自然への依存性が明らかとなる。資本による掠奪が自明の前提条件として扱ってきた素材そのものを破壊した後で、収益性に影響が出るようになってから、資本ははじめて問題の深刻さに気がつくのである。にもかかわらず、資本はこうした限界を受け入れずに、絶えず新たな障害を乗り越えようとし、世界中を駆け回って、新たな使用価値や原料を開拓し、新しい技術を開発していく。だが、それは〔…〕環境帝国主義という形で、人々を抑圧し、さらには人間と自然の物質代謝に『修復不可能な亀裂』を引き起こす。」
斎藤幸平『大洪水の前に』,2019,堀之内出版,pp.276-278.
このあと著者は、マルクスの抜粋ノートから、
「利潤率」や「資本の回転」との関係で《自然との物質代謝》、
その「亀裂」について研究している箇所を紹介していますが、
内容的には繰り返しになるので、まとめの部分のみ引用します。
「これらの〔抜粋をした〕事実から、まさに自然という領域においても、マルクスは掠奪と〔技術〕改良という〔資本の〕正反対の傾向性が生み出す、『生きた矛盾』を展開しようとしていたことがわかる。〔…〕様々な反作用する傾向をその素材的弾力性に着目しながら、把握しようと試みていた〔…〕晩年のマルクスが利潤率の傾向的低下に言及することがなくなったとしたら、それはマルクスが資本の弾力性により大きな力能を見出したからであり、その力能を経験的次元でより一層詳しく考研究する必要を認識していたからだ、と言える。マルクスによれば、利潤率の変動は資本の素材的担い手と密接に関連しているのであり、両者を切り離して考察することはできない。
マルクスは〔…〕障害を乗り越えようとする〔資本の〕絶え間ない試みが資本主義の時間稼ぎを可能にするものの、他方で、価値増殖の論理と自然的条件の素材的論理の間の緊張関係を高めていくことを強調していたのである。例えば、石油価格の上昇は、タールサンドや、フラッキング、シェールガスといったより地球温暖化にとって有害な採掘方法や資源への資本投資を可能にしてしまう。〔…〕石油の価格上昇は、資本にとってむしろチャンスなのである。〔…〕資本の適応能力は甚大であり、資本主義的生産は仮に地球の大部分が人間やほかの動物の生存にとって適さないような状態になったとしても継続可能なのである。〔…〕市場メカニズムは自然の状態を価格にフィードバックすることは十分にできない〔…〕環境危機の問題は利潤の減少ではなく、資本主義という社会システムが人間の自由で、持続可能な発展という観点にとって非合理的なシステムであるということであり、だからこそ、それは人々の手で意識的に変革されなくてはならないのだ〔…〕
オコンナーやムーアの論じる資本蓄積の危機から、人間と自然の物質代謝の亀裂における環境危機へエコ社会主義はその力点を移さなくてはならない。〔…〕マルクスのエコ社会主義は、資本の立場から把握されたものではなく、持続可能で自由な人間的発展の立場から展開されるものなのである。」
『大洪水の前に』,p.285,287-288.
〔20〕 マルクスとエンゲルス、エコロジーをめぐって
第7章「マルクスとエンゲルスの知的関係とエコロジー」は、“マルクス主義”において永らく誤解されてきた・マルクスとエンゲルスの自然科学研究をめぐる関係、およびマルクスの自然科学研究の目的について、新しい光を当てるものです。
伝統的に、「マルクス主義」圏では、マルクスは経済学・社会分析、エンゲルスは自然科学という“知的分業”があったように理解してきた。エンゲルスには、『反デューリング論』『自然の弁証法』という自然科学に関する著作が知られていたし、マルクスの膨大な自然科学・抄録ノートの存在は、ソ連崩壊まで知られていませんでした。エンゲルス自身が、“マルクスとちがって、自分は力の及ぶ限り数学と自然科学を(文献で)研究した”という意味の言葉を書き残している(『反デューリング論』第2版「序文」)ことも、誤解のもとになったと言えます。
この誤解は、ソ連を中心とする「公式マルクス主義」を批判した「西欧マルクス主義」にも尾を引くことになります。というのは、「西欧マルクス主義」は、機械論的・経済決定論的なソ連流の「弁証法的唯物論」からの脱却をはかるために、新しく公刊された『経済学・哲学草稿』『ザスーリチ宛て手紙』などに含まれたマルクス独自の思想を追究するとともに、『自然の弁証法』と自然科学研究からマルクスを切り離したのです。
「事実、『反デューリング論』と『自然の弁証法』はエンゲルスが物理学、化学、生物学の領域を詳細に検討したことを記録しており、伝統的マルクス主義の世界観構築に大きな影響を与えた。
〔…〕エンゲルスの自然科学研究の狙いとは、自然のうちに、人間からは独立した形で弁証法的に実在する運動をそのままの形で『法則』として把握することである。エンゲルスのプロジェクトは、〔…〕自然についての『存在論的な』考察である。」
しかし、「もし人間とは独立した自然そのものに弁証法が存在すると考えるなら、自然の観察から弁証法的な概念把握が可能であることになり、自然科学の実証主義的な思考がマルクス主義の社会分析へ逆輸入されることになる。」
『大洪水の前に』,pp.294-295.301.
つまり、決定論的な自然法則に支配された物質世界が弁証法的に発展して、生物界と進化の諸法則を形成し、さらに弁証法的に発展して、人間社会の諸法則が帰結する‥‥という構想が、エンゲルスの『自然の弁証法』にはあります。しかし、この“上向”関係が機械的に理解されると、人間社会の分析に決定論的思考が入り込んで来てしまうことになります。そこから、ソ連の「公式マルクス主義」は、「史的唯物論」や「社会の発展法則」を、客観的に存在する絶対的法則――ニュートン物理学の法則のように考え、人間の「自由」の存在する余地をなくしてしまう欠点があったのです。
そこで、「西欧マルクス主義」は、「公式マルクス主義」の決定論からマルクスを“救い出す”ために、「弁証法の適用範囲を社会に限定」したのです。たとえば、ルカーチは『歴史と階級意識』のなかで、
『エンゲルスの弁証法に関する叙述から生じてくるさまざまな誤解は、本質的には、エンゲルスが』ヘーゲルの誤りを引き継いで、『弁証法的方法を自然の認識にも拡大しているということに根ざしている。』しかし、『弁証法の決定的に重要な諸規定〔…〕は、自然認識のなかには存在しない。』
『大洪水の前に』,p.294.
と述べて、弁証法の適用範囲を「歴史的・社会的な現実に限定」することを提唱しています。
しかし、そうして“マルクスを救い出す”ために「西欧マルクス主義」が行なった“切断”は、マルクスが実際には生涯をかけていたエコロジー研究までも切り捨ててしまい、『資本論』はじめ著作の各所に見られる《自然との物質代謝》に関する言及に、目をつぶらせる結果になってしまったのです。マルクスの『経済学批判』が、マルクス本人の意図に反して、《自然》とも《大地》とも無関係な純経済学理論として理解されてきたのは、「西欧マルクス主義」の責任でもあるわけです。
〔21〕 あえて“違い”にこだわる斎藤式レクチューレ
第7章の続きです。マルクス、エンゲルスとエコロジー。この問題に対する著者の視角をひとことで言えば、↑このタイトルに尽きます。
マルクスとエンゲルスは、おのおのの研究内容について晩年まで意見交換を続けており、そのことは、二人のあいだの往復書簡が証言しています。したがって、両者の間に意見の違い、関心の方向の相違はあっても、たがいに相手の意見の影響を受けている部分も少なくありません。たとえば、マルクスが詳細にノートしたフラースの『時間における気候と植物界』を、エンゲルスも読んで、一部を『自然の弁証法』で使用した後で、さらに要約抜粋をノートにまとめています。そのノートは、「着眼点が、マルクスによって影響されていることをはっきりと記録している。」(p.313)
したがって、フォスターとバーケットが、マルクスとエンゲルスのエコロジーを同一視して、両者からの引用を併せて論じたのは、理由のないことではなかったと言えます。マルクスとエンゲルスを“切断”したあおりで、マルクスとエコロジーを切り離してしまった「西欧マルクス主義」の理論的陥穽を克服するには、二人の同一性を強調することが有益であったからです。「『資本論』に内在する形で『物質代謝の亀裂』概念を練り上げ」、それによって、「マルクスは経済学批判の一環として環境問題を捉えようとしていた」との認識を得たことは、彼らの大きな先駆的業績でした(p.292)。
これに対して、著者がマルクスのエコロジーとエンゲルスの自然科学を、あえて区別し、両者の相違点に注目するのは、また別の認識を狙った方法であると言えます。エンゲルス自身の思想・意図とは別に、エンゲルスを受容して「公式化」したソ連流の「マルクス主義」理解では、《自然》に対する人間の「意識的」な支配が強調され、自然との《物質代謝》の担い手である生産者とその『アソシエーション』が軽視された結果、国家とテクノクラートによる“指導”ないし支配が、無批判に受け入れられてしまったからです。そうした“国家社会主義”への方向を避けて、マルクスが強調する『アソシエーション』による生産者の自律性・主体性の回復を主題化するには、マルクスを純粋に取り出すのが有効な方法であると言えます。
リービッヒが《掠奪農業》批判を提起し、『物質代謝の亀裂』という暗い未来を予示し、マルクスがこれを資本主義批判として『資本論』に取り入れた 1860年代は、エンゲルスとマルクスのエコロジーの違いが表れてきた時期でもあります。
たしかに、「エンゲルスもまた、リービッヒの掠奪農業批判の意義を認識してい」ました。しかし、それは彼の場合には、ケアリー、デューリングによるリービッヒ受容のレベルに留まっていたと言えます。エンゲルスは『住宅問題』(1872年)において、‥‥
「『都市と農村の対立』という矛盾とその克服の必要性を指摘している。『リービッヒ〔…〕ほどに、声高くこのことを要求したものは誰もいない。そこでは人間が耕地から受け取ったものは耕地に返すということが、つねに彼の第一要求になっており、また都市、ことに大都市の存在だけがこれを妨げていることが証明されている。』」そして、「『工場生産と農業生産の緊密な結びつき』の再建を要求したのだった。」
『大洪水の前に』,p.298.
「『反デューリング論』でも次のように述べられている。『都市と農村を融合させることによってのみ、今日の空気や水や土壌の汚染を除去できるし、〔…〕彼ら〔都市の大衆〕の堆肥が、病気を生みだすかわりに植物を生みだすために、使われるようにすることができる。』」
『大洪水の前に』,p.305.
エンゲルスの文章からは、しかし、ケアリーとデューリングが主張する『タウン・コミュニティ』以上のものは見えて来ないように思われるのです〔それが「反デューリング」とは皮肉でしょうか〕。「大都市の存在だけが……妨げている」工業生産と農業生産の結びつきを回復するということならば、資本主義には手を触れなくとも可能だからです。
「『これまでは、人間自身の社会的行為の諸法則が、人間を支配する外的な自然法則として人間に対立してきたが、これからは、人間が十分な専門知識をもってこれらの法則を応用し、したがって支配するようになる。これまでは、人間自身の社会的結合が、自然と歴史によって押し付けられたものとして人間に対立してきたが、いまやそれは、人間の自由な行為となる。これまで歴史を支配してきた客観的な、外的な諸力は、人間自身の統制に服する。〔…〕これは、必然の国から自由の国への人類の飛躍である。』〔エンゲルス『自然の弁証法』〕
ここではっきりと述べられているように、エンゲルスによれば、人間の意識と行為から独立した物象の支配を廃棄することだけでなく、自然において作用する諸力の法則性を認識することによって、自然を人間の意識的な制御のもとにおくことが、『自由の国』への跳躍なのである。」
『大洪水の前に』,p.302.
たしかに、ここでエンゲルスは、「人間自身の社会的結合が……人間の自由な行為になる」と述べて、未来社会における『アソシエーション』が、人々の自由な結合によって形成されることを定式化しています。しかし、彼の言う「意識的な制御」とは、極論すれば、自然と社会の「諸法則」を認識することにほかならない。その場合、人間社会もまた自然と同じように、客観的な「法則」によって支配されていることになります。それはたとえば「史的唯物論」のような不可侵の「法則」でしょう。それを体現するのは、「十分な専門知識をもっ」たテクノクラートです。
エンゲルスによれば、資本主義による「自然の支配が失敗に終わるのは、自然の諸法則を無視した結果であ」る。エンゲルスの「批判の対象は、自然法則を認識せずに目先の利害を追求する人間の振る舞いに向けられている。」(p.303)
エンゲルスは、「科学による自然法則の認識が人間の自由をもたらすという」フランシス・ベーコン以来の近代的科学観に立っています。彼の「自然の弁証法」は、法則認識を通じた「外的自然の『支配』による『自由』の実現という実践的要請に結びついている」(p.301)、そして、自然のみならず社会もまた、唯一客観的な「法則」の認識(「十分な専門知識」の所持者による)によって支配することができ、それが「人間の自由」だとされるのです。
これに対して、マルクスの場合の「意識的」とは、これもエンゲルスとの違いを際立たせて極論すれば、「法則」認識よりも、生産者たちの自律的、主体的な労働に力点を置いています。マルクスにとっては、それが『アソシエーション』の実質的内容でなければならなかった。
さらに、マルクスとエンゲルスの相違点は、リービッヒの『物質代謝』概念の受容にあります。マルクスの『物質代謝』概念は、「人間と自然の関わり合いを超歴史的・歴史的の両側面から分析し、資本主義における人間と自然の関係の歴史的特殊性ならびにその矛盾を明らかにする」ものでした。しかし、エンゲルスは『自然の弁証法』においてリービッヒの『物質代謝』概念を批判し、生命とは、外界との間で「不断の物質代謝」を行なう「蛋白体の存在様式」であるとして、生命の非生命体からの歴史的進化を説くのです。そのため、マルクスが考えるような:‥「社会的物質代謝(資本主義的生産・交換・消費活動)」と「自然的物質代謝」の連関と矛盾‥という観点は、見落とされてしまいます(pp.299-305)。
「マルクスは、いかなる社会においても人間は労働しなくてはならないという認識から出発し、そのうえで、資本主義的生産様式における歴史的に特殊な労働のあり方を分析することで、主客の転倒した社会における疎外がなぜ、どのようにして生じるかを明らかにしようとした。それゆえ、エコロジー問題は、根源的な生産条件である自然からの人間の『分離』(『自然からの疎外』)から説明されなくてはならず、」資本の論理の浸透が「いかにわれわれの思考行動様式を変容し」物質代謝を攪乱するかを「経済学批判は解明しなくてはならない」
『大洪水の前に』,pp.306-307.
マルクスによれば、「エコロジー危機に直面した労働する諸個人が、自然との物質代謝の意識的・能動的な制御を行なうようになることが、未来社会の実現にとって不可欠なのである。〔…〕
『本来の物質的生産の領域〔すなわち、最終的な『自由の国』に至る前の段階では〕〔…〕自由はこの領域のなかではただ次のことに〔…〕だけある。すなわち、社会化した人間、アソシエイトした生産者たちが、〔…〕物質代謝を合理的に規制し、自分たちの共同的制御のもとに置くということ、つまり、力の最小の消費によって、自分たちの人間本性に最もふさわしく最も適合した条件のもとでこの物質代謝を行なうということである。
この国のかなたで、自己目的として認められる人間の力の発展が、真の自由の国が始まる』〔『資本論』第3部草稿 1863-65〕
マルクスは、際限なき資本の価値増殖による物質代謝の攪乱に直面した生産者たちが問題解決のためにアソシエイトし、自然の『盲目的な力』を意識的な管理のもとにおくことを、持続可能な生産にとっての必要条件と見なしていた。」
『大洪水の前に』,p.310-311.
第7章で見たように、資本の無際限な価値増殖は「労働力、科学、自然」の限界にぶつかり、それらから「抵抗」を受ける。マルクスは、「科学」から資本が受ける「抵抗」についても述べている。「科学は単に、生産力を高め……るだけではない。」リービッヒ、フラースらが示すように、科学は「掠奪の非合理性を示し、より持続可能な生産の実現を求めることで、資本主義の正当性に大きな疑問を投げかける」(pp.317-318)
「マルクスは自然の限界をはっきりと認識していたがゆえに、より注意深い自然の取り扱いを社会主義構想のなかではっきりと強調したのだった。それは自然を私的所有の制度から切り離し、コモンとして民主主義的に管理することにほかならない。」
1848年の革命が失敗し、「恐慌待望論」が無効化するなかで、マルクスは、労働時間短縮、職業教育などを求める「改良闘争」の重要性を強調するようになった。「重要なのは上からの直接的な政治的決定・政策ではなく、むしろ物象的力の自立化を生み出すような社会的な振舞いそのものを変えていくような実践を社会的領域で生み出していくことである。」
それは、「労働」のみならず、「自然」の領域についても言えるはずである。マルクスは、「自然についても具体的事例を丹念に調査することで、資本の容赦なき採取主義に対する対抗戦略を構想しようとしたのである。」
『大洪水の前に』,pp.324-325.
以上で、斎藤幸平・著『大洪水の前に』のダイジェストを終ります。