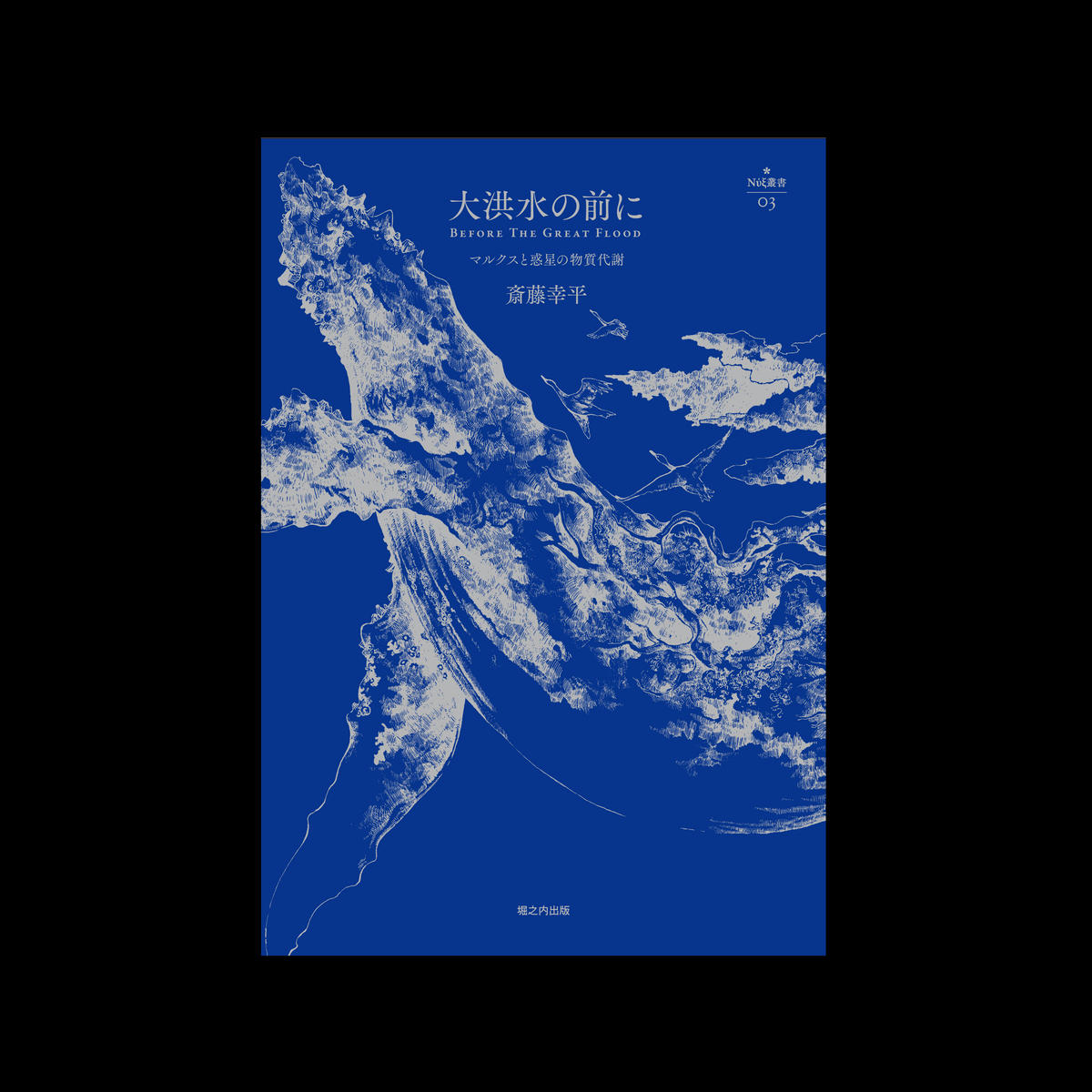〔15〕 リービッヒ論争とマルクス
第5章「エコロジーノートと物質代謝論の新地平」をダイジェストします。
1862年にリービッヒが『農芸化学』第7版に書き下ろした「序論」は、農学、化学の枠を超えた大論争を巻き起こしました。《掠奪農業》批判は、当時ドイツのあらゆる教養人のサロンで話題になり、経済学者にもよく読まれました。また、海外でも評判になったのです。以下、マルクスの抄録にしたがって、各論者の主張を見ていきます。
「ドイツ歴史学派」の経済学者ロッシャーは、リービッヒの名は「国民経済学史」に永く残るだろうと称賛しつつ、「経済学の立場」からは、「掠奪農業は……利潤を生む限りで正当化されうる」としています。なぜなら、もしも掠奪が行き過ぎれば、「市場の価格調整メカニズム」によって、それは止むことになるからだ、と言うのです。農業経済学者アウも同じ見解を述べています。価格変動によって、「掠奪農業に対する社会的な自主規制が働く」から、心配はないのだと。
当時産業革命がはじまっていたルール地方デュイスブルクの自由主義者ランゲも、リービッヒ理論の「自然科学的な正しさにもかかわらず、掠奪農業は『国民経済学』の観点からは正当化される」と述べました。
これに対して、リービッヒの《掠奪農業》批判を正面から受け入れたのは、アメリカの経済学者ケアリー、そして、ドイツでは主流派でないデューリング★でした。
「ケアリは農業生産における土壌養分の浪費を批判し、そのような無責任な『大地からの掠奪』は将来の世代に対する深刻な『犯罪』であると訴えた。〔…〕
ケアリは、生産者と消費者が近くに住んでいる場合には、地力は〔…〕人口の増大とともに、肥沃さを増すことができると考えていた。だが、現実には、」アメリカでは、農業生産地と消費都市が広い大陸に散らばっているうえ、「イングランドへの穀物輸出によって、充足律を満たすことは不可能になっていたのである。
それゆえ、ケアリの掠奪農業批判はイギリスの帝国主義批判と結びついており、『資本論』と同じように、アイルランドやインドにおける土地疲弊を、植民地支配の問題と絡めて論じている。
〔…〕デューリングはリービッヒの理論をケアリの経済学体系に取り込み、生産者と消費者が互いに近距離に居住する自給自足的なタウン・コミュニティの構築と保護貿易の必要性を説いたのだった。つまり、長距離輸送がなければ、地力が疲弊することなしに、」また工業から農業への資材供給も可能になり、「農業と工業の調和した発展が実現するというわけである。」
しかし、結局のところ「ケアリとデューリングにとって必要なのは保護貿易を通じて国内産業の発展を促進することであり、解決策は関税の導入であった。〔…〕イングランドとの貿易を諸悪の根源とみなし、〔…〕『保護関税』を究極の『万能薬』としたのだった。保護関税以外には、経済的自由主義の原則を堅持し」た。ケアリは、リービッヒが警告する「自然の限界を十分深刻には捉えておらず、保護関税さえ導入されれば」地力はおのずと改善されてゆくと考えていた。
斎藤幸平『大洪水の前に』,2019,堀之内出版,pp.210-214,217,219-220.
註★「オイゲン・デューリング」: 経済学者としては、「歴史学派」のリストを批判して、国家社会主義を構想した。唯物論、無神論を唱える。反ユダヤ主義(アーリア人種至上主義)の創始者でもある。そのためか、(のちに)彼のマルクス批判は激烈を極めた。
しかし、「近代農業」に対するリービッヒの批判は、
ケアリやデューリングよりも、ずっと厳しいものでした。
市場メカニズムも農業生産性向上も楽観せず、
資本主義の利潤追求欲が、農地への技術の投入を妨げて
地力を疲弊させ、資源を枯渇させると、正しく判断しています。
リービッヒは、『農芸化学』第7版と同じ年に出版した『農学入門』で
こう書いています:‥‥
「『あと数年でグアノ資源が枯渇し、そうなれば、」人間の生命条件は自然法則によって保持されていて、自然法則を侵害すれば人間は報復を受けるのだ、ということは理論的に説明する必要もなくなるだろう。「諸民族は自己保存のために均衡に達するまで悲惨な戦争の中で絶え間なく相互に傷つけ合い、殲滅し合うことを余儀なくされるだろうし、」もしも飢饉に襲われれば、「数十万人の死者が路上に斃れているのを見るだろう。』
〔…〕リービッヒは飢えと戦争に満ちた暗いヨーロッパの未来を予言している。」
『大洪水の前に』,pp.216-217.
リービッヒの将来予想は、おおざっぱな文明史的推断になって
しまっていますが、それは経済学者でも社会学者でもなく
自然科学者なのですから、しかたないことでしょう。むしろ、
彼のペシミスティックな予想が、「戦争に明け暮れた 20世紀」を
正しく予言していたことに、私たちは驚くべきです。
リービッヒとジョンストンに触発されて『資本論』第1巻に
「『資本主義のあらゆる進歩は、〔…〕土地から掠奪する技巧における進歩でもあり、一定期間のあいだ土地の肥沃度を増大させるためのあらゆる進歩は、同時に、この肥沃度の持続的源泉を破壊するための進歩である。』」
『大洪水の前に』,pp.192-193.
と書いた(1872年[第2版])マルクスにとっても、経済学者たちの
リービッヒ受容は不十分と思われた。第1巻初版に、マルクスは
次のように書いています。農業史に関するリービッヒの概観は‥‥
「『現代のあらゆる経済学者の諸著作を合わせたよりも、多くの光明を含んでいる。』」
『大洪水の前に』,p.209.
ただ、マルクスとしては、リービッヒのような文明史的な結論で満足することはできません。著者が指摘するように、↑上の讃辞は、[第2版]では削除されています。リービッヒが、自然科学者としての限界から遂行しえなかったエコロジカルな資本主義批判を、マルクスは独自に開拓する必要を感じたにちがいない。そのためには、リービッヒをも・「現代のあらゆる経済学者」をも・超える農業史、自然環境史の分析材料を求めて、自然科学文献を幅広く渉猟してゆく必要があったのです。
〔16〕 フラースの気候変動論
「リービッヒ論争」を検討するなかで、マルクスが注目したのは、バイエルンの農学者・植物学者カール・フラース(Karl[Carl] Nikolaus Fraas 1810-1875)でした。語学に堪能だったフラースは 1835-42年アテネ大学で植物学を(現代ギリシャ語で!)講ずる傍ら、古代ギリシャ,ローマの文献を広く調査して過去の植物相を研究。ドイツに戻ってからは、農学を専門領域としてミュンヘン大学教授を務め、バイエルン農会で活動し、リービッヒとも連携して農業教育や農漁業開発に努めます。ところが、60年代に入ると、リービッヒとの不仲が表面化し、「リービッヒ論争」では攻撃の急先鋒となるのです。
リービッヒの「鉱物説」(植物の養分として、K, P, Si を重視)、ローズらの「窒素説」(N を重視)に対して、フラースは化学肥料よりも土壌と《自然》の回復力を重視する「自然説」を唱えた。
「フラースによれば、岩石の風化による土壌形成においては、『寒暖や乾湿の変動』、『大気中の酸素』、『アンモニアと二酸化炭素を含む水』、『生きた有機体〔土壌微生物?〕』の運動などの化学的・物理的運動が大きな役割を担う。そのため、〔リービッヒのように〕地質を化学的に分析するだけでは実用的な観点にとっては不十分である。〔…〕『農芸化学が土壌の活動と呼ぶ部分は、まだほとんど研究されていない領域のままである。』〔…〕
〔…〕フラースは、〔…〕土壌の形成や植物の生育にとって不可欠な自然的条件である気候・気象の作用へ注意を向けたのだった。」
『大洪水の前に』,p.226,228.
つまり、岩石に含まれる有用元素が《可給態》(植物が吸収できる水溶性の化合物)となるためには、温度・湿度などの気候条件が決定的だというのだ。「それゆえ、化学肥料は『気候的条件の補正』としてその役割を認識する必要がある。〔…〕植物による土壌成分の浸透と吸収は『気候条件に比例する形で進行する』」
『大洪水の前に』,pp.227-228.
そうすると、そこから、「リービッヒが指摘する土地疲弊の問題も気候条件を考慮にいれることで、修正しなくてはならない〔…〕実際、肥料を投入しなくとも、〔…〕何年にもわたって多くの収穫をもたらす事例があるからである。」
フラースが注目したのは、「熱帯などの温暖な地域での伝統的農業」でした。リービッヒが、人間や家畜の糞尿や堆肥を耕地に戻す「中国や日本の伝統的農業」を評価したのに対し、フラースが着目したのは、「自然の力そのものによって土壌養分の補充が行われるような伝統的農業」だったのです。「『いたるところに豊富に存在している植物栄養を適切に利用できるよう処理すること、これが農学の近い将来の課題をなす』」
『大洪水の前に』,pp.228-230.
じつは、フラースが実践的な農業研究者として、このような見解に至ったのは、当時の化学肥料には"莫大なコストがかかる"という問題があったからです。「ヨーロッパの農業危機は〔…〕『土地がより豊かで、より廉価に生産できる諸国からの大規模な穀物輸出が台頭することによって生じる』〔…〕そのことは西ヨーロッパの『生産者たちにとって極めて破滅的な作用』をもたらす。」
『大洪水の前に』,pp.228-230.
そこから、フラースは、「自然の力そのものをうまく利用することで、より安価で持続可能な方法を模索した。」必要なのは、「土壌養分を増やすための多くの源泉を開拓すること」であった。「その一つが、マルクスが〔エンゲルス宛て〕手紙に書き留めていた」フラースの「『沖積理論』である。」
『大洪水の前に』,pp.232-233.
↑少し前の引用部分でフラースも言及していたように、ここでもっとも必要な方策は、「農芸化学が土壌の活動と呼ぶ部分」‥すなわち、地理的な気候区分ごと、場所ごと(沼沢地、砂質地、乾燥地‥)の土壌の形成作用と、耕作・施肥による土壌の変化を究明することであったはずです。地層の岩石とも気象とも別に、土壌自体が研究されなければならない。究明の対象は、土壌の化学的成分のみならず、コロイド作用、毛細管現象といった構造的物理的特性、バクテリア、真菌類、ミミズによる生物的作用をふくみます。たとえば、ウクライナの「黒土」地帯は、人の手による施肥も、河川の「沖積」作用もないのに、連年豊富に小麦を生産します。(そこから、20世紀にはロシアを中心に、近代土壌学が成立します。)しかし、当時としては、それは一朝一夕に解明できることではありませんでした。そこで、フラースは、古代の植生と古気候に関する自身の研究に基いて、「沖積理論」と気候変動論に向かい、マルクスはそれに追随したのです。
「沖積」とは、河川が水流及び洪水によって、上流の表土、粘土、砂礫などの地表物質を運び、下流の沿岸や低地にもたらす作用のことです。沖積土には、風化して《可給態》となった鉱物質や、腐植に富む・肥沃な森林土が含まれています。ナイル川、黄河の沖積作用は、文明の揺籃となりました。
「フラースは『人工沖積』を構築することを提唱し、河川の流れを一時的な堰によって止め、耕作地を河川の水で浸し、必要な無機質を土壌に供給することを、安価で半永久的な土壌養分充足の方法として推奨したのである。〔…〕マルクスは、〔…〕それが『もっともラディカルな農業のための方法』であるというフラースの指摘をノートに書き留めてい」る。
『大洪水の前に』,pp.233-234.
これは、エジプトで古代から近代まで行われていた「ベイスン灌漑」という方式です(ナイル川のダム建設のせいで不可能になりました)。ただ、じっさいに南ドイツの地形・水文条件で「人工沖積」を利用できたかどうかは、たいへん疑問ではありますが‥‥
「マルクスの〔エンゲルス宛て〕手紙で最も高く評価されているのは、『時間における気候と植物界』という著作であ」る。
『大洪水の前に』,p.236.
マルクスは、フラースの著作を遡って、30-40年代のアテネ滞在時に行なった植物相と古気候の研究成果をまとめた本にたどりついたのです。フラースは、古代ギリシャ人の記述を詳しく調べて、そこからわかる植物相を現在のものと比較することによって、植生の変遷を明らかにし、そこから、長期にわたる気候の変化――乾燥化と温暖化――を推定しました。エジプト、メソポタミア、ギリシャの文明によって、森林の伐採と耕地化が進んだ結果、気候は乾燥化・温暖化し、ステップ草原化・砂漠化が進んで、諸文明は崩壊した、というのがフラースの結論でした。地中海地域に特徴的な植生――棘の多い硬葉樹の灌木林と疎林、短草草原――も、乾燥した長い夏季をもつ地中海式気候も、文明による森林破壊と掠奪耕作の結果だというのです。フラースの気候変動論は、地中海地域に関しては、現在でも自然地理学など広い分野の専門家に支持されています。ただ、完全に証明されているわけではないのでしょう。
とくに気になるのは、農業に関して、フラース自身が 60年代に主張している見解と食い違っていることです。57年以後のフラースは、ギリシャやトルコのような「古代文明のあった国々」では無肥料で持続可能な耕作を実現していると主張して、リービッヒを批判していました(p.229)。しかし、47年の『時間における気候と植物界』では、それらを含めて、古代文明はみな、掠奪的な土地利用の結果として乾燥化を招いて崩壊した、というのです。
「『時間における気候と植物界』において、気候変動がもたらす長期的影響を過小評価してはならないとフラースは繰り返し強調する。なぜなら人間によって引き起こされる気候条件の変化は、元来自生していた植物の植生にとって不利な形でしか作用せず、しかも、けっして元の状態を回復することができないからだ。〔…〕
『一地域における森林伐採は、〔…〕気温を上げる顕著な原因として数えられる。〔…〕植生に覆われた、つまり、樹木が生い茂った地域は、不毛な地域よりも、湿度をよりしっかりと保ち、太陽光によって熱せられることもより少ない』」
大気を湿潤にしていた森林が減って、「気温が上がり、雨量が減る結果、〔…〕地域の植生的多様性は徐々に失われ、短草草原(ステップ)が形成される〔…〕その土地で伝統的に営まれていた耕作に対しても、悪影響を及ぼすことになる。」
『大洪水の前に』,pp.240-242.
メソポタミアの土壌は、水路灌漑によって「継続的に水に浸り、泥に覆われ、塩分を溶け出させてい」たあいだは肥沃な耕地だったが、灌漑施設が放棄されて水に浸されなくなるやいなや、「塩と砂礫が多くなり、ステップの植物相が姿を現わす」。すなわち、硫酸ナトリウムなどのソーダ類が地表に析出して固まり(塩析)、植物の生育を阻害するのです。
『大洪水の前に』,p.243.
「森林伐採による気候の変化が、古代ギリシャの伝統的農業を困難なものにしていったとフラースは考える。〔…〕
フラースとリービッヒの歴史観の違いは明らかであろう。」古代文明崩壊の「原因は、フラースによれば、充足律を無視したことによる土壌中のミネラル物質の不足ではなく、過剰な森林伐採による地域全体の気候変動〔乾燥化、温暖化〕なのである。」
『大洪水の前に』,p.248.
アマゾン。森林破壊による土壌侵食の被害。(『ガーディアン』より)
ところで、以上のような歴史的変動のスケッチから、近代についてはどんなことが言えるのでしょうか?
「『時間における気候と植物界』は、近代社会の生産活動が森林伐採を一層早めることを指摘しており、19世紀のヨーロッパ諸国で森林が急速に減少している」状況を述べたフラースの叙述を、マルクスも抄録している。フラースは指摘している:「文明の発展はより多くの木材を必要とするようになるだけでなく、技術の進歩は、増大した需要を充足すべく、以前には利用できなかった山岳部の森林さえも伐採するようになっていく〔…〕こうして、長期的には、耕作の一般的な自然的条件は悪化していくことになると、フラースは考えていた。
〔…〕人工造林などを用いて、人間は〔気候変動の〕悪弊に力強く抵抗するだろう。しかし、悪弊を完全に取り除くことはけっしてできない〔…〕文明化して、人口の多い国家は、必然的に〔…〕森林の代わりに耕地を必要とし、沼や湿地を干上がらせ、湿気を保つ泥炭や森林を燃やすことになる。」
『大洪水の前に』,pp.251-252.
これがフラースの、この 1847年の書での結論です。ちょっと気になるのは、森林の『潤沢な富』と農業生産者とのあいだのつながりを、もっぱら《気候変動》を通して考えていることです。そのため、考察は時間的にも領域的にも、巨大なスケールのものにならざるをえません。森林の存在が耕地の地盤を保全し、採取された落ち葉や枯れ枝が耕地の地力回復に貢献する、といったミクロな関係は、ここでは言及されていません。(60年代の著書は、それに触れているのですが、マルクスはまだ読んでいません。)この欠点は、読んだマルクスにも影響を及ぼしたと思われます。マルクスは、この本について、エンゲルスに、こう書き送っています:‥‥
「『耕作の最初の作用は有益だが、結局は森林伐採などによって荒廃させる、うんぬん、というわけだ。彼の結論は、耕作は――もしそれが自然発生的に前進していって意識的に支配されないならば(この意識的な支配にはもちろん彼はブルジョアとして思い至らないのだが)――荒廃を後に残す、ということだ。〔…〕』
〔…〕マルクスは、フラースと異なり、人間と自然の持続可能な関係性を構築しようとする。それは将来社会において、アソシエイトした生産者たちが、人間と自然の物質代謝を意識的に制御することで実現されなくてはならない。しかし、『この意識的な支配にはもちろん彼はブルジョアとして思い至らない』のだ。」
『大洪水の前に』,pp.223,252-253.
「『資本論』第3部草稿のなかで、マルクスは、農業と工業の対立の彼岸において、『アソシエイトした生産者たちが合理的に自然との物質代謝を制御する』ことを未来社会が実現しなくてはならない実践的課題として定式化していた。」
『大洪水の前に』,p.215.
「意識的に」制御すべき「人間と自然の物質代謝」が、全ヨーロッパレベルの広域の森林減少による《気候変動》……というような巨大なスケールのものだとすると、その制御の構想も、特定の村の農業者がアソシエイトして事にあたれるようなものではなくなるでしょう。つまり、少なくとも国家レベルのプロジェクトにならざるをえない。その場合、アソシエーションのイメージは、どんなものになるでしょうか? 「アソシエーション」と言いながら、じっさいにはソ連型の強大な国家権力の出現を招くことにならないか?‥‥マルクスが使いたがる「意識的」というコトバが、くせものです。
「ブルジョアとして」とは、資本主義の市場メカニズムを信頼してすべてをゆだねる‥ということでしょう。だとすると、その「ブルジョア」が思い至らない「意識的な支配」とは?‥‥国家とテクノクラートによる一方的な規制・管理ということになりはしないでしょうか?‥‥
この部分では、私は著者の解釈(p.253)には同意しないのです。
1863-65年の『資本論』「第3部主要草稿のなかで、私的所有のもとで森林管理はうまくいかず、国家所有のもとでのみ多少の持続可能性が担保されることをマルクスは指摘していた。」
『大洪水の前に』,p.255.
ここから直ちに、マルクスは生産手段の国有・国家管理を望んでいた、と結論することはできませんが、1867年の『資本論』第1巻刊行、そして 68年の『時間における気候と植物界』抄録ノートの段階では、「アソシエーション」の内実について、それ、ホントは独裁国家じゃないの?‥若干の疑念が生ずるのです。
なお、この 1868年にブリュッセルで開かれた『第1インターナショナル(社会主義インター)』大会は、森林保護について次の決議文を採択していますが、こちらのほうが、同時期のマルクスよりも「国有」色が薄まっています。また、森林は「良質な土壌の保全」のためにも重要だ、との"ミクロ"な《物質代謝》関係の認識が表明されています。
「『私的個人への森の譲渡が、水源地や、そしてもちろん、良質な土壌の保全、ならびに人々の健康と生活のために必要な森林の破壊を引き起こしていることを考慮すれば、森林は社会の所有物であり続けるべきだと大会は考える』」
『大洪水の前に』,p.257.
〔17〕 マルク協同体
1868年のマルクスの・フラース以外の著者からの抄録ノートのなかには、森林が農業に対して持つ"ミクロ"な役割に触れたものがないではありません。ジョン・タケットの本からの抄録は、先祖が植林を怠ったため、森林の破壊が引き起こされ、防風林の役割をするものがないために家畜の成長が阻害されている、と記しています。
68-70年に書かれた『資本論』第2部第2稿では、キルヒホーフ『農業経営提要』から長い引用をしています。その部分には、森林の生育には長い時間が必要なために、資本の回転期間をできるだけ短くしようとする「資本の衝動」とのあいだに緊張を生ずることが述べられています。引用のあとで、マルクスは次のようにコメントします:‥‥
「文化および産業一般の発達は、昔からきわめて能動的に森林を破壊するものとして実証されてきたが、それに比べれば、この発達が逆に森林の保全および生産のためにしてきたいっさいのことがらは、まったく微々たるものである。」
『大洪水の前に』,p.255.
じつは、1866年の時点でフラースは新しい著書『農業危機とその治癒手段』を出しており、そこに引用されたマウラーの「マルク協同体」(初期ゲルマンの農耕協同体)に関する叙述は、共有地である森林・牧草地の"ミクロ"な耕地地力維持の役割についても言及していました:‥‥
「『もちろん村落マルクが木材、干し草、藁、あるいは堆肥さえも、それどころか家畜(豚!)でさえ、村落の構成員以外に売ることを許しておらず、マルク内で収穫された農産物やワインが、マルク内で消費されるよう命令するならば(そのことから、様々な罰令権が生じた)、耕地の地力維持のための手段に事欠かないのみならず、森林や牧草地からの補助を利用することによって、あるいはさらに川によって栄養分を与えられた草地を利用することによって、いたるところで地力の増大が起きたに違いなかった。』」
斎藤幸平『大洪水の前に』,2019,堀之内出版,pp.315-316.
つまり、フラースも、60年代の著書では、古代の共同体農耕による地力の維持・増進を認めていました。メソポタミアやエジプトとは違ってゲルマンでは‥、ということかもしれませんが。
この一節をマルクスが読んだのは、68年か、それ以後と思われます。70年代にかけて、マウラーの著書に遡って、抄録を数回作っています。ともかく、68年3月のエンゲルス宛て手紙では、当時まで「ドイツに残存している非資本主義的要素に」十分に注意を払って来なかった自分は、「判断力の欠如」にとらわれていた、と告白しています。
マルクスが「マルク協同体」に関心をもって、マウラーの法制史を何度も読んだことは重要です。そこには、協同体メンバーの共有地である森林との直接の”ミクロ”な《物質代謝》の関係が描かれているだけでなく、「マルク協同体」という平等で自立した社会の歴史像は、未来の「アソシエーション」社会のイメージ形成に寄与したと思われるからです。リービッヒはでしょう。
「1868年以降、マルクスは自然科学と並んで、前資本主義社会や非西欧社会といった非資本主義社会を研究するようになっていったのである。
〔…〕ゲルマン社会においては、土地利用に対する共同体の規制が働いており、それが平等な社会における持続可能な耕作を実現していた〔…〕
重要なのは、〔…〕共同体的生産においては、人間と自然の物質代謝の持続可能性が、その『生命力』の源泉になっていたというマルクスの認識である。よく知られているように、1881年2・3月のヴェラ・ザスーリチ宛の手紙でマルクスはマウラーに直接言及しながら、アルカイックな共同体の生命力に依拠した農業共同体の残るロシアが資本に対する抵抗拠点となり、西欧とは異なった社会主義革命への道を切り拓く可能性を認めたのだった。〔…〕つまり、資本主義とはまったく異なった人間と自然の物質代謝の管理の仕方が――それがたとえ伝統や慣習に基づく制度によるものであり、近代自然科学による自然法則の認識によって意識されていなくとも――より持続的な生産を可能にしており、その力が資本に対する抵抗の物質的基盤になりうる。」
『大洪水の前に』,pp.315-317.
つまり、「意識的」である必要はない!‥‥というところまで
80年代のマルクスは到達していた、というのです。
しかしながら、これはまだ著者の構想、ないし展望であり、
詳細な内容は、「68年」と「81年」のあいだを埋める
著者の今後の研究に俟たなければなりません。
次回は第6章に進んで、「利潤率の傾向的低落」法則の成否など
『資本論』の有名な理論的争点を扱います。