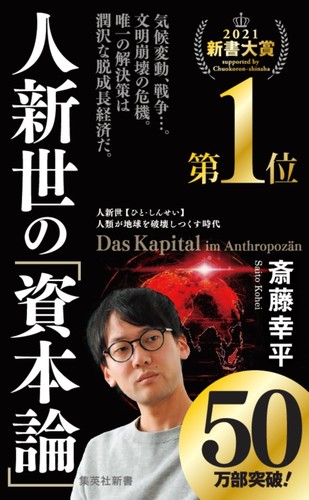「経済成長を諦め、脱成長を〔…〕真剣に検討するしかない。では、どのような形の脱成長が必要なのか。 〔…〕
電力や安全な水を利用できない、教育が受けられない、食べ物さえも十分にない、そういった人々は世界に何十億人もいる。そうした人々にとって経済成長はもちろん必要だ 〔…〕」
『人新世の「資本論」』,p.102.
“経済成長か? 脱成長か?”という形の大上段な議論は、
不毛な結論しかみちびかないでしょう。どこで、どんな場合には
経済成長が必要なのか? どんな成長は有害で、どんな脱成長が
必要なのか? 問題は、そのように立てなければなりません。
「まず、水や所得、教育などの基本的な『社会的土台』が不十分な状態で生活している限り、人間はけっして繫栄することはできない。社会的な土台の欠如とは、自由に良く生きるための『潜在能力』を実現する物質的条件が欠けていることを意味する。人々が本来もっている能力を十分に開花できないならば、『公正な』社会はけっして実現されない。これが今、途上国の人々が置かれている状態である。」
『人新世の「資本論」』,pp.103-104.
そこで、↓下のグラフを見てほしい。
タテ軸の「社会的閾値」とは、「水、所得、教育」などといった「基本的な
『社会的土台』」の・最低限必要なレベルのこと。達成されている数が
多いほど、「生活の質」は高くなる。しかし、人間の「生活の質」が
向上すると、それだけ自然環境に及ぼす負荷も大きくなり、
《プラネタリー・バウンダリー〔地球が耐えられる限界〕》を越えて
しまうことになる。残念ながら、この2つのあいだには正の相関がある。
人間生活が向上すればするほど、後戻りのできない破壊作用を
自然環境に及ぼしてしまう。
しかし、上のグラフを細かく見ると、おおざっぱな全体的傾向とは
違った局面も見えてくる。
グラフの右側3分の1は、《地球限界》を越えてしまっている領域だが、
ここに、世界の先進国・中進国のほとんどが位置している。
ただ、その中で、3列目のドイツ、日本、チェコ、2列目のオランダ、フランス
などは、アメリカよりも高い「生活の質」を実現しながら、環境に及ぼす
負荷は、アメリカほどひどくない。
グラフの左下には、自然には悪影響を及ぼさないが「人間生活の質」は
十分でない途上国群がならぶ。しかし、そのなかでベトナムだけは、
比較的に「社会的土台」が完備し、そこそこに良い「生活の質」を
実現している。タイ、ブラジル、ギリシャといった中進国と同程度の
「生活の質」を実現しながら、自然環境に大きな負荷を及ぼさない
ベトナムの例は、注目に値する。アルジェリア、ヨルダンなども、準ずる
位置にある(これらがフランスの旧植民地なのは偶然だろうか?)
途上国が経済成長を進めるには、先進国が差し出すODAや
開発プロジェクトに頼らざるをえないのが現実だが、途上国の側が
選択性を発揮するかどうかで、結果は大きく異なってくる。
フランス、アメリカに戦勝して独立したベトナムの場合には、相当の
抵抗力と選択力を備えていることが推測できる。アルジェリアも
同様だろう。日本、韓国、チェコは、かつての近代化過程で発揮した
選択力が今に及んでいると考えることができる。逆に、大部分の
途上国群の場合には、先進国の言うがままに開発を受け入れて、
その結果、国内の自然は破壊され、資源は奪われ、国民生活は
いっこうに良くなって行かないことがわかる。
国民生活の向上につながるような経済成長が選択されるかどうかは
途上国の側に民主主義がどれだけ実現されているかとも関係する。
先進国に迎合しない知識層が、民主主義を通じて指導力を
発揮する場合には、経済成長で得られた富は比較的公平に分配され
自然環境への悪影響も抑制することができるのだろう。
(ベトナムと対照的なのが、ロシア、中国、アルバニア。
「生産力至上」社会主義の弊害が基にあるのだろうか)
どんな経済成長でも生活を向上させるわけではないし、経済成長だけが
向上させるわけでもない。資源配分の平等、公正さの問題が重要なのだ。
経済成長が“すべて”ではない。
「独仏や北欧などのヨーロッパ諸国の多くは、ひとりあたりのGDPがアメリカより低い。しかし、社会福祉全般の水準はずっと高く、医療や高等教育が無償で提供される国がいくつもある。一方、アメリカでは、無保険のせいで治療が受けられない人々や、返済できない学生ローンに苦しむ人々が大勢いる。〔…〕
生産や分配をどのように組織し、社会的リソースをどのように配置するかで、社会の繁栄は大きく変わる。〔…〕
経済成長しなくても、既存のリソースをうまく分配さえできれば、社会は今以上に繁栄できる可能性がある」
『人新世の「資本論」』,p.108.
ただ問題は、そうした公正な資源配分を、資本主義システムの下で
恒常的に達成することは、はたして可能なのかどうかです。
かりに先進国1国の中では達成されたように見えても、
途上国との間の資源配分まで視野に入れれば、結論は違ってきます。
先進国と途上国の間では、分配は不公正にならざるをえない。
コストと弊害の「外部化」によって利潤を最大化することが
資本主義システムの至上命令だからです。
《気候危機》に示されるように、グローバルな不平等、不公正さは
地球環境全体を危機に陥れ、その影響を受けて、先進国内部の
平等と公正さもまた、損なわれてゆくことになります。
「気候変動問題が示すように、地球はひとつで、世界はつながっている。先進国が浪費を続けたり、自国の製品を〔また開発プロジェクトを――ギトン註〕売りつけたりするために、途上国にも同じような経済発展の道をたどるよう求めることは、どう考えても持続可能ではない。
〔…〕
グラフの右上に位置している先進国が、膨大なエネルギーを使って、さらなる経済成長を求めることは明らかに不合理である。ましてや、経済成長がそれほど大きな幸福度の増大をもたらさないなら、なおさらである。〔…〕同じ資源とエネルギーをグローバル・サウス〔=「グローバル化」の被害を受ける領域・住民。〕で使えば、そこで生活する人々の幸福度は大幅に増大する 〔…〕
〔…〕
問題の本丸は、公正な資源配分が、資本主義のもとで恒常的にできるのかどうか、である。
〔…〕外部化と転嫁に依拠した資本主義では、グローバルな公正さを実現できない。〔…〕このままの生活を続ければ、グローバルな環境危機がさらに悪化する。その暁には、トップ1%の超富裕層にしか今の生活は保証されないだろう。
〔…〕明日は我が身だということを想像してほしい。最終的に自分自身が生き延びるためにも、より公正で持続可能な社会を志向する必要があるのだ。それが、最終的には人類全体の生存確率も高めることになる。
それゆえ、生存の鍵となるのは『平等』である。」
『人新世の「資本論」』,pp.109-112.
そこで、↓つぎの図を見ましょう。「『人新世』の時代に私たちが
選びうる未来の形は、どんなものだろうか?」
ヨコ軸は、左に行くほど「平等」で、右に行くほど「自己責任」が
重視される「不平等」な社会。
タテ軸は、国家権力の強度で、上に行くほど権力が強く統制的。
下に行くほど、人びとの自発的な相互扶助が重視される。
① 気候ファシズム
権力強い 不平等 自己責任
20世紀半ばころまで、資本主義はコストと不経済を好きなだけ「外部」に放出して利潤を獲得し、それによって"無限の"技術革新と成長を遂げてきました。「外部」――途上国――にまだ広汎に存在していた前資本主義社会を切り崩して底辺に編入し、そこから低廉な資源と労働力を吸収することができました(《原始的蓄積》過程)。ところが今や、"フロンティア"は消滅し、おびただしい数の"難民"が「外部」から押し寄せて来ます。彼らの一部は先進国の教育を受け、先進国住民を凌ぐ頭脳とパワーで、先進国の支配中枢を乗っ取ろうとするかに見えます。こうして高まった先進国住民の不安と排外主義は、権力の強化によって環境と社会の《危機》を乗り切ろうとする「気候ファシズム」を抬頭させます。
「気候危機が人類に突きつけているのは、採取主義と外部化に依拠した帝国的生活様式を抜本的に見直さなくてはならないという厳しい現実にほかならない。
だが、転嫁がいよいよ困難であることが判明し、人々の間に危機感や不安が生まれると、排外主義的運動が勢力を強めていく。右派ポピュリズムは、〔…〕排外主義的ナショナリズムを煽動するだろう。そして、社会に分断を持ち込むことで、民主主義の危機を深めていく。その結果、権威主義的なリーダーが支配者の地位に就けば、『気候ファシズム』とでも呼ぶべき統治体制が到来しかねない。
〔…〕
〔他方、〕一部の超富裕層は〔《危機》から莫大な利益を得る。〕〔…〕惨事便乗型資本主義は、環境危機を商機に変えて、今以上の富を彼らにもたらす。国家はこうした特権階級の利害関心を守ろうとし、その秩序を脅かす環境弱者・難民を厳しく取り締まろうとする。これが第一の未来、『気候ファシズム』である。
〔…〕
貧困層など社会的弱者がどうなろうが、自己責任であると突き放すのだ。」
『人新世の「資本論」』,pp.54-55,113-114,281.
しかし、資本主義を野放しにする・このようなやり方では、《環境危機》の進行を食い止められないでしょう。その結果、環境難民の増加、食糧危機の激発によって反乱が起き、②の野蛮状態に陥る危険性が出てきます。国家の統制力を維持するためには、もはや1%の超富裕層の優遇などしていられなくなります。もっと平等に、「みんなのためにやっているんだ」と、幻想でもいいから思わせなくては、誰も国家を信用しなくなってしまう。そこで、③の形態が要請されてくる可能性があります。
③ 気候毛沢東主義
権力強い 平等
「こうして、社会が野蛮状態に陥るという最悪の事態を避けるための統治形態が要請される。〔…〕『1% vs 99%』という貧富の格差による対立を緩和しながら、トップダウン型の気候変動対策をすることになるだろう。そこでは、自由市場や自由民主主義の理念を捨てて、中央集権的な独裁国家が成立し、より『効率の良い』『平等主義的な』気候変動対策を進める可能性がある。」
『人新世の「資本論」』,pp.114-115,280.
《危機》が深まれば深まるほど、国家による強い介入と規制が専門家から要請され、人々も、《危機》に対処するためにはやむを得ないと考えるようになります。こうして、個人の自由に対する制約に反対できる者はいなくなる。その過程は、まさに「コロナ・パンデミック」によって現在進行しているものと同じでしょう。しかも「コロナ」とは違って、《環境危機》では、《危機》も「非常事態」も時限付きではありません。人びとは、期限なく永久に自由を手放すのです。
「危機においては、不安な人々は隣人ではなく、国家に頼ってしまう。危険が深まるほどに、強権的な国家介入なしには、自らの生活が立ちゆかなくなると考えるのだ。
〔…〕国家が企業や個人の二酸化炭素排出量を徹底的に監視し、処罰する」
『人新世の「資本論」』,pp.282-283.
この③の統治形態では、人びとは「平等」ではあっても、隣人同士のつながりも連帯もなく、ばらばらです。「自発的な相互扶助」もありません。もしも人びとが自発的に相互に連帯するならば、国家の強権支配にとっては邪魔になるからです。人びとは徹底的に分断され、相互監視と密告が奨励され、ただ「党」と思想当局の指導の下でのみ、「全体への奉仕」として集団活動が行われるのです。
② 野蛮状態
権力弱い 不平等 自己責任
「統治体制は崩壊し、世界は混沌に陥る。統治機構への信頼が失われ、人びとは自分の生存だけを考えて行動する。『万人の万人に対する闘争』」
『人新世の「資本論」』,p.114.
《気候危機》の回避に失敗すれば、これが人類の未来となる可能性は低くないでしょう。グレタ・トゥンベリが、異常と思えるほど激して警鐘を鳴らすのは、この戦慄すべき"明日の世界"が目に見えるからではないでしょうか。彼女は、史上北欧人にしばしば現れる「幻視者」のひとりではないかと私〔ギトン〕は思っています。
④ 脱成長コミュニズム
権力弱い 平等 自発的な相互扶助
「専制的な国家主義にも、『野蛮状態』にも抗する試みもあるはずだ。強い国家に依存しないで、民主主義的な相互扶助の実践を、人々が自発的に展開し、気候危機に取りくむ可能性がないわけではない。それが公正で、持続可能な未来社会のはずだ。」
『人新世の「資本論」』,p.115.