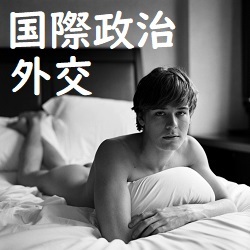↓こちらにレビューを書いてみました。
ドゥルーズ『スピノザ――実践の哲学』(3)―――
―――理性と情動と共同社会
ドゥルーズのスピノザ論を読む、今回で完結。
《共同社会》論は、ドゥルーズの面目躍如。その点、スピノザはどこまでも現実主義で、 「自然状態」… 「社会契約」… そんなものは非現実だとばかり、「理性」ではなく「恐怖」によって支配すれば、万事まるくおさまり、人びとは従順に、平和に暮らすだろうと、一見、現実政治の権化のようなことを言う。
しかし、ドゥルーズの読みは深い。スピノザの《触発》の論理から、他者との「出会い」を秩序立て、《構成関係》を構築する新しい《社会》の形成、ないし《社会》変革の道すじを探究する。「出会い」の選択と秩序立ては、《共通概念》――ローカルな普遍性の発見と実践――「理性」の力能増進とともになされる。つぎつぎに《構成関係》は増殖し、《共通概念》は拡大し、狭いローカルな緊密結合から、より広汎な意見の異なる人びとを包摂する寛容性へと、「出会い」は進展する。
ドゥルーズがここで、動物生態学者ユクスキュルを引いているのは興味深い。‥‥何のことはない。「出会いの秩序立て」などは、とうの昔から、ダニもボウフラもイトミミズもやっていたことだった! 蜜蜂もアリも、精巧な社会を作っていた。彼らは、本能でそれをする。人間が「情動」にとらわれたくらいでできないことがあろうか。こうして《構成関係》の輪は拡がり、《社会》のすみずみに張りめぐらされていた権力の組織化は、しだいに「理性」の導く結合に置き換えられてゆく。
ドゥルーズ=スピノザの「理性」とは、啓蒙的“覚醒”ではない。「理性」は「情動」と深くつながっている。かんたんにいえば、「理性」とは、洗練された欲望にほかならない。《構成関係》とは、さまざまな「情動」が対応し、結び合い、速くあるいは遅く昂進し、絡み合う場にほかならない。それはあたかも交響楽のように進行する。というより、交響楽とは、《構成関係》の場のひとつにほかならない。
しかし、ドゥルーズが描いて見せる《構成関係》構築のありさまは、その野放図さといい、なんぴとも予期しえない思いがけない「出会い」といい、そこにつねに貫いている柔らかな力線、無限に多くの必然性の力線といい、秩序の中のアナーキー、アナーキーの中の秩序、それは交響楽よりもジャズ・セッションに似ていないだろうか?
たがいに和合する方向をむいた「情動」の力線が《構成関係》を延伸させ、《社会》に「理性」を浸透させてゆく。それはリズムと音をともなって進行する。いま、街角でどんな音楽が聞こえるだろうか? お仕着せのBGMが支配しているうちは、変革などはおぼつかない。
ドゥルーズとスピノザの《共同社会論》は、ミクロポリティックな《生権力》を乗り越えたのだろうか? いまだ結論には程遠く思われるが、スピノザからドゥルーズへの“つなぎ”としてのレヴューは、このへんで締めくくりとしたい。