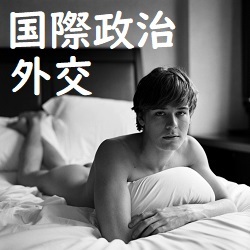「衆院内閣委員会は15日、検察官の定年を引き上げる検察庁法改正案に関する質疑を行った。与党が採決する構えを見せる中、立憲民主党など野党4党は、武田良太国家公務員制度担当相の不信任決議案を提出。これにより同委は改正案の採決を行わず散会し、委員会採決と衆院通過は来週以降に先送りとなった。
武田氏は、検察庁法改正案などを束ねた一括法案の中核である国家公務員法改正案を所管する内閣委の担当相。与党は19日に不信任案を否決した上で、21日にも衆院通過を図る考え。野党側は松本文明委員長(自民)の解任決議案提出などで徹底抗戦する方針だ。」検察定年延長、採決先送り 野党、武田担当相不信任案を提出(時事通信)
質疑の最後が維新の足立議員で、持ち時間4分。質問そこのけ、野党が不信任動議出す前に、足立(前科一犯)が採決動議→混乱の中で強行採決成立‥‥てなシナリオだったんでしょうな。シナリオ通りにやる勇気なかったね。今度やったら、ほんとにギロチンだもんなw
【追記】 タグ #憲法破壊 「?」の人のためにいちおうご説明。法律で憲法(権力分立原理)を破壊できてしまうという意外な盲点です。日本では、検察が刑事起訴権を独占。これは法律で決まっているし、珍しくない制度。しかし、その検察の人事を内閣が左右できたら、内閣は恐いものなし。内閣は国会の与党で、最高裁判事を任命できる、この2つを押さえたうえに、残った唯一の重しも取れたら、事実上の独裁になる。こんな盲点、憲法学の先生は教えてくれませんよ。‥‥え?違憲な法律は裁判で無効? ダメですよ。検察庁法みたいな、直接国民に適用されない法律を訴える手段はありません。訴えたら必ず門前払い。‥‥以前、台湾の裁判所を訪問した時に、裁判官がおっしゃってました:「法律も制度も“ひと”だ。」ってね。どんなにいい建物をこしらえたって、中に入る人がダメなら、ダメなんです。
法律条文など、詳しい説明はこちら ←ぜひ見てください。なま半可な思いこみは、いけません !!
【追記2】 とんでもないことに気づきました! ↑上のリンク先で、甲南大学の園田教授が書かれているのですが、1月31日の閣議決定で“解釈変更”した国公法によると、定年延長には、「その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるとき」という要件があって、この「十分な理由がある」かどうかをチェックするために、人事院の「承認」が必要とされています。内閣は、1月31日に、解釈変更とともに黒川検事長の定年延長を閣議決定していますが、人事院の承認はあったのでしょうか? これまで国会質疑で問題になってきたのは、解釈変更について人事院の意見を聞いたとか聞かないとかであって(しかも日付のない奇妙な文書で‥)、黒川氏の「延長」に関する承認手続(日付と人事院総裁印のある正式文書で!)があったという話は出てきていませんよね?! 国公法が定める「人事院の承認」が無いのではないか?!
しかも、5月15日の衆院内閣委での森法相の答弁によると、「延長」(をどんな場合に認めるか)についての内閣の準則は、これから(法改正後)人事院が決める準則に準じて決めたい、とのこと。(この答弁自体不可解ですが、それはさておき‥)。つまり、1月の時点でも今の時点でも、人事院は「準則」を持っていないのです。人事院は、今まで検察官の人事に介入したことなどないのですから、「準則」がないのは当然でしょう。国家公務員の延長の準則を、そのまま、職務の性質が全く違う検察官に適用することなどできないはず。「準則」がないのだから、「承認」手続などできるはずがない!
けっきょく、国公法が定めている「人事院の承認」がない以上、1月31日の黒川定年延長は、本来的には無効なのでは? (行政行為には「公定力」がありますから、「承認」なしでも、とりあえずは有効として扱われるでしょうけれど‥)。しかし、放っておいたら大問題になりますから、そこで、この穴を埋めるために、あわてて検察庁法改正をしようとしているのではないですか?
とにかくもう、この国の行政府は、法解釈も法手続も、めちゃくちゃですね!!!