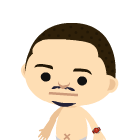義理と人情と心意気と・・・ときどきてきと~に2
元JKF重量級日本代表。 国際玄制流空手道連盟 武徳会 会長
プロフィール
テーマ
最新の記事
このブログのフォロワー
2013-12-05
国歌 君が代の意味を分かり易く
テーマ:人生訓&心に残る言葉。 昨年書いた備忘録を読み返す機会がありましたので、
国歌 君が代について日本の心の教育よりシェア致します。
こういうことを書いたり、日本のことを書くと右だ左だという人もいますが、
私は純粋に日本人として、その歴史、気質、文化、DNAが好きで、
日本人としての誇りを持っているだけで、強いていうなら真ん中です。
もし右だ左だと言うがいるとすれば、その人が左に曲がっているだけです。
(イエローハット創業者の鍵山秀三郎)
ごもっとも。
さて、本題です。
国歌「君が代」について
ちょっと、気になることがあります。
それは、よく、女子学生から
「先生、君が代の意味を教えて」とか、
「君が代のうたは、どの詩集にのっているんですか?」とか、
「君が代は、だれがつくったの?」とか、
つまり「国歌」についての質問が、
このごろとても多いのです。
あなたは「君が代」のうたが、いつごろできたと思いますか。
昭和の時代、いや、大正時代、いや、もっと古く明治時代……
このうち、みなさんが答えてくれるもっとも多い時代は、
明治時代でした。
ところが、「君が代」のうたが生まれたのは、
実はもっと、もっと、ずーっと前、いまから、
およそ800年も前の鎌倉時代だったのです。
1228年に書き写された『和漢朗詠集』という
歌集に出ています。
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いはほとなりて
こけのむすまで
冒頭にある「君が代」の「君」とは、
あなたとかキミという意味です。
「代」とは、寿命とか、生命とかいのちという意味ですから、
「君が代」という言葉の意味は、
あなたのいのち、あなたの寿命となりますね。
「千代に八千代に」とは、いつまでも、
いつまでも長く続きますように……です。
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで
これは、いつまでも長く続くということの譬えです。
細かい小さな岩が、長い年月の風化によって、
大きな岩のようなかたまりになって、
その岩にいっぱいこけが生えるようになるまで、
どうぞ、それくらい、いつまでも、
元気に長生きしてください……と。
「君が代」のうたは、
いまから約800年も前からあったことに、
わたくしたちは、ちょっとびっくりしますが、
実は、この「君が代」のもととなったうたは、
もっと、古くからあったのです。
「君が代」のもとの歌は、「古今和歌集」に載っています。
題しらず 読人しらず
わがきみは
千世にやちよに
さざれいしの
いはほとなりて
こけのむすまで
(古今和歌集 343)
古今和歌集の原歌では、「君が代」が
「わがきみ」となっていることに、
注目してください。
「わがきみ」とは、昔は、女性が尊敬したり、
愛したりした男性に対して用いたことばです。
すると、このうたは「読み人知らず」で
だれが詠んだかは、まったくわかりません。
が、平安時代のある女性が、
敬愛する自分の男性に送った
「恋のうた」であったことがわかります。
解釈すると、つぎのようになります。
「わたくしの愛する人のいのちが、
どうかいつまでも長く続きますように、
たとえば、小さな小石が寄り集まって、
ギッシリと固まって大きな岩となり、
それに苔が生えるまで、どうかおすこやかに生きてくださいませ」
わたくしたちの国歌「君が代」の原歌は、
平安時代の女性の、愛する男性への恋のうただった。
素敵なことだと、思いませんか。
軍国主義の歌だなんて、どこでどう間違えてしまったのでしょうか。
とても、悲しくなります。
この「君が代」の「君」は天皇さまをさしているという見方もありますが、
上代では、天皇さまをさして「君」というご無礼な表現は、見つかりません。
国歌 君が代について日本の心の教育よりシェア致します。
こういうことを書いたり、日本のことを書くと右だ左だという人もいますが、
私は純粋に日本人として、その歴史、気質、文化、DNAが好きで、
日本人としての誇りを持っているだけで、強いていうなら真ん中です。
もし右だ左だと言うがいるとすれば、その人が左に曲がっているだけです。
(イエローハット創業者の鍵山秀三郎)
ごもっとも。
さて、本題です。
国歌「君が代」について
ちょっと、気になることがあります。
それは、よく、女子学生から
「先生、君が代の意味を教えて」とか、
「君が代のうたは、どの詩集にのっているんですか?」とか、
「君が代は、だれがつくったの?」とか、
つまり「国歌」についての質問が、
このごろとても多いのです。
あなたは「君が代」のうたが、いつごろできたと思いますか。
昭和の時代、いや、大正時代、いや、もっと古く明治時代……
このうち、みなさんが答えてくれるもっとも多い時代は、
明治時代でした。
ところが、「君が代」のうたが生まれたのは、
実はもっと、もっと、ずーっと前、いまから、
およそ800年も前の鎌倉時代だったのです。
1228年に書き写された『和漢朗詠集』という
歌集に出ています。
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いはほとなりて
こけのむすまで
冒頭にある「君が代」の「君」とは、
あなたとかキミという意味です。
「代」とは、寿命とか、生命とかいのちという意味ですから、
「君が代」という言葉の意味は、
あなたのいのち、あなたの寿命となりますね。
「千代に八千代に」とは、いつまでも、
いつまでも長く続きますように……です。
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで
これは、いつまでも長く続くということの譬えです。
細かい小さな岩が、長い年月の風化によって、
大きな岩のようなかたまりになって、
その岩にいっぱいこけが生えるようになるまで、
どうぞ、それくらい、いつまでも、
元気に長生きしてください……と。
「君が代」のうたは、
いまから約800年も前からあったことに、
わたくしたちは、ちょっとびっくりしますが、
実は、この「君が代」のもととなったうたは、
もっと、古くからあったのです。
「君が代」のもとの歌は、「古今和歌集」に載っています。
題しらず 読人しらず
わがきみは
千世にやちよに
さざれいしの
いはほとなりて
こけのむすまで
(古今和歌集 343)
古今和歌集の原歌では、「君が代」が
「わがきみ」となっていることに、
注目してください。
「わがきみ」とは、昔は、女性が尊敬したり、
愛したりした男性に対して用いたことばです。
すると、このうたは「読み人知らず」で
だれが詠んだかは、まったくわかりません。
が、平安時代のある女性が、
敬愛する自分の男性に送った
「恋のうた」であったことがわかります。
解釈すると、つぎのようになります。
「わたくしの愛する人のいのちが、
どうかいつまでも長く続きますように、
たとえば、小さな小石が寄り集まって、
ギッシリと固まって大きな岩となり、
それに苔が生えるまで、どうかおすこやかに生きてくださいませ」
わたくしたちの国歌「君が代」の原歌は、
平安時代の女性の、愛する男性への恋のうただった。
素敵なことだと、思いませんか。
軍国主義の歌だなんて、どこでどう間違えてしまったのでしょうか。
とても、悲しくなります。
この「君が代」の「君」は天皇さまをさしているという見方もありますが、
上代では、天皇さまをさして「君」というご無礼な表現は、見つかりません。