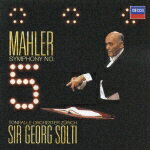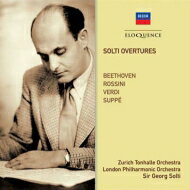ショルティ/ラスト・コンサート
曲目/マーラー
交響曲第5番嬰ハ短調
1.第1楽章: 葬送行進曲(威厳ある歩調で、厳格に、葬列のように) 12:24
2.第2楽章: 嵐のように激動して、最上の激しさをもって 14:43
3.第3楽章: スケルツォ(力強く、速すぎずに) 16:42
4.第4楽章: アダージェット(きわめて遅く) 9:58
5.第5楽章: ロンド=フィナーレ(アレグロ) 14:43
ベートーヴェン:
6.《エグモント》序曲 作品84* 8:08
指揮/ゲオルク・ショルティ
演奏/チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団
録音/1997/06/12.13 Schweizer Radio DRS
1947*
DECCA 475 9153
9月5日はゲオルグ・ショルティの命日ということもありバーンスタイン引き続いて取り上げることにしました。白鳥の歌はゲオルグ・ショルティと縁のあるオーケストラで縁のある曲でした。不思議な運命を感じます。つまり、オーケストラがチューリヒ・トーンハレ管弦楽団ですがが、このオーケストラはショルティがデッカと契約して最初の録音を行ったオーケストラ(1947年のこと)だということがまず一つ。そして、ショルティがシカゴ交響楽団と最初に録音した曲もマーラーの交響曲第5番(1970年のこと)だったことがもう一つ。さらに言えば、ショルティが迫害を逃れて、世界大戦時を過ごしたスイスで最後の録音となったことにまで運命的なものを感じてしまいます。
今回取り上げる第5番は、ショルティが得意とする作品で、すでにCDが2種(1970・1990)、映像ソフトが1種(1986 廃盤)リリースされていますが、オーケストラはすべてシカゴ響だっただけに、今回のトーンハレ管との演奏は興味津々です。1997年7月12、13日、チューリヒ、トーンハレでのライヴです。この年に創設されたチューリヒ芸術祭におけるコンサートということです。13日のコンサートはスイス放送協会(DRS2)によって生中継されたとのことで、これを主体に12日の録音も編集素材となっていると考えられます。ということで、録音データにはいつものデッカのクルーの記載はありません。
当時のトーンハレ管は、この演奏の2年前、1995年に着任したデイヴィッド・ジンマンのもと、改革精神に満ちた活動をすでに開始していただけに、御大ショルティの指揮下でも、そのフィジカルな魅力は遺憾なく発揮させられていたことはまず間違いないと思われるからです。 ショルティとトーンハレ管弦楽団と言うとまず、彼のオーケストラ作品初録音となった1947年の『エグモント』序曲と『レオノーレ』第3番が思い出されますし、最近では、1996年にマーラー第10番のアダージョを初めて演奏するというコンサートで話題を呼んたのが記憶に新しいところです。現代の世界的マーラー指揮者として知られたショルティが、意外にもこの作品を演奏していなかったという事実が、少なからぬ驚きを持って迎えられていたものです。
これがショルティにとって最後のコンサートとなり、9月5日、フランス、アンティーブにて自伝の最終校正を終えた後、就寝中に亡くなってしまう。その自伝についてはこちらで取り上げています。
客演ということもあってか、他流試合の面白味と興味深さがあり、良くも悪くもショルティの豪腕ぶりは鳴りを潜めています。第1楽章冒頭におけるトランペットの輝かしさはいかにもショルティらしい響きです。その後は力みを感じさせず、しなやかでむしろ柔らかいくらいですが、このオーケストラの個性でもあるのでしょう。いつものショルティが聴かせる強引なまでの腕っぷしの強さは稀薄で、それゆえかドライブ感の弱さはありますが、その分美感が削がれていないのは皮肉でしょうか。
第2楽章はパンチには欠けますが、伸びやかで開放的な音色が心地良く、そつなくこなしています。これはかなりオーケストラの名人芸に助けられている部分があります。ジンマンに鍛えられたアンサンブルの良さが光ります。
第3楽章はオーケストラの各セクションにおける、室内楽的な掛け合いの愉しさが際立ちます。一方でショルティはしっかり手綱を握り、くっきりした造型は彼の至芸のなせる技でしょう。
有名な第4楽章はショルティにしてはややオーケストラ任せで、食い足りない感がありますが、第5楽章に入るとパンチが効いた盛り上がりを聴かせているのはさすがといえます。解釈のコンセプトも以前と大きく変わっていない はずなのですが,いつもの肩をいからせたハイテンションな指揮ぶりとは異なっ た,力みのない的確なフレージングと,落ち着きのあるなじみの良い響きを聴 かせていることに驚かされます。
フィルアップされているのはショルティの指揮者としての初録音となったベートーヴェンの「エグモント」序曲です。これが初CD化のようです。聴き手からすると一気にタイムスリップする形ですが、不思議と違和感は感じさせません。キビキビとした若々しい息吹と、このオーケストラの伸びやかな音色は50年の時を超えても良い意味で保持されているのだと微笑ましく感じさせます。若干のスクラッチノイズは聴こえますが,鑑賞上はほとんど問題にな らないレベルだろうと思います。 肝心の演奏の方は,ショルティの指揮の下で整然とした演奏を行っており, プロフェッショナルな演奏の記録として不足のないものではあると思うのです が,アンサンブルの締まりというか求心力はいまひとつで,駆け出しの指揮者 の演奏だなと思ってしまったのも事実です。