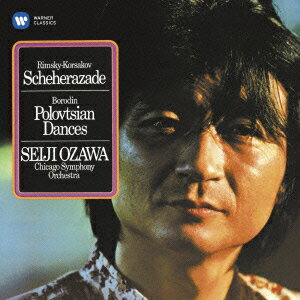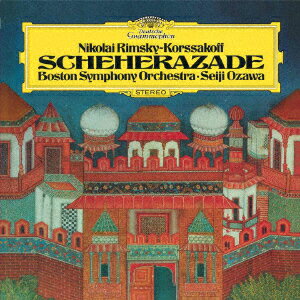小澤征爾
最初の「シェエラザード」
曲目/
リムスキー・コルサコフ/交響組曲≪シェエラザード≫作品35
1.第1曲:海とシンドバッドの船 9:37
2.第2曲:カランダー王子の物語 11:50
3.第3曲:若き王子と王女 9:43
4.第4曲:バクダッドの祭、海、青銅の騎士の岩での難破、終曲 12:01
5.歌劇≪イーゴリ公≫より ダッタン人の踊り 13:25
指揮/小澤征爾
演奏/シカゴ交響楽団
録音/1969/06/25、07/01 メディナ・テンプル シカゴ
P:ピーター・アンドリュー、リチャードC.ジョーンズ
E:カーゾン・テイラー
独EMI CDZ2523672
小澤征爾(1935~2024)は1964年から69年(29歳から34歳)に、シカゴ響の夏の本拠地であるラヴィニア音楽祭の音楽監督を務めていました。その縁でこの時期にRCAとEMIにこのオケと録音を残しており本盤はその一枚ですこの録音は小澤征爾にとっての25枚目のLP録音となっています。ただ、EMIへのシカゴ京都の録音はこのシェエラザードと同時期にバルトークコダーイわ録音しているものともう一枚、ヤナーチェクの「シンフォニエッタ」とルトスワフスキの「管弦楽のための協奏曲」を収録したものの3枚分しかありません。シカゴ響との最晩年の録音ということができます。
小澤征爾はこの「シェエラザード」を生涯に3度録音しています。こののち1977年に主兵のボストン響と、そして1993年にウィーンフィルとこの曲を再録音しています。名曲ですが「シェエラザード」を3回もセッション録音している指揮者は他にいたでしょうかねぇ。そういうことではこの曲を得意としていたと言ってもいいでしょう。多分に東洋的旋律に溢れた作品ですから、そういうところで小沢の感性に合い通ずるものがあったのでしょう。
これはEMIに録音したものですが、録音スタッフの名前を見るとどうもキャピトルのクルーがメインで収録していると思われます。まずサウンドがEMIらしくない響きでいつものやや靄のかかったくすんだ響きがしません。そして弦の音が艶やかに響きます。小生など、当初RCAの録音かと聴き間違えたほどです。収録会場はRCAと同じメディナテンプルです。
録音セッションの一コマ
この録音は「ラヴェニア音楽祭」の最後の年の録音です。そういう意味では6年間の集大成ということができます。初期のRCAとの「運命」や「展覧会の絵」を録音していますが、そこではまだ硬めの演奏で音にゆとりが感じられませんでしたが、ここに来てスケール感と柔軟さが増し、シカゴ交響楽団を思う存分ドライブしているように感じられます。それは、シカゴ響のスター・プレーヤーの個性をうまく引き出しているからです。
第1楽章から実に豊穣な低弦の響きが収録されています。そして、シェエラザードの語らいのソロのヴァイオリンも雄弁な語り口です。この時代のコンマスはスティーヴン・スタリックです。スタリックは1950年代にロイヤルフィルでビーチャムと共にこの「シェエラザード」を録音しています。そこでもノーブルな演奏を披露していましたが、ここでも同様なことを感じることができます。
スティーブン・スタリック
ところで小沢の3つの演奏の変遷ですが、楽章感の伸び縮みはありますが、全体的にはほぼ同じ演奏時間になっています。ボストン響でのソロはシルヴァースタイン、ウィーンフィルはホーネックでした。
シカゴ響(69) 9:38 11:52 9:45 11:58 計 43:13
ボストン響(77) 10:18 12:12 10:02 12:18 計 44:50
ウィーンPO(93) 9:53 11:30 9:22 12:29 計 43:14
この小沢がラヴィニア音楽祭を担っていた頃の本家はマルティノンの時代と重なりオーケストラと指揮者の関係がギクシャクしていた時代で、そういうものを目の当たりにしながら小沢はある意味違った視点からこの音楽祭にアプローチしていたんでしょう。新しめの音楽にも取り組みながら、自分の得意の曲目を録音できたのはよかったんでしょう。
ソロのコンマスのスタリックは同じカップリングでビーチャムと録音していて手慣れたものだったでしょうし、そういう意味では小沢も組みしやすかったのでは無いでしょうか。情感たっぷりにアラビアンナイトの世界を描き出しています。
各パートのシカゴ響も素晴らしく、第1楽章ではオーボエ、ファゴットの競いあいが楽しく描出されています。このファゴットはシャーマン・ウォルトが素敵な音色でソロを何度も聴かせてくれます。第2楽章ではクラリネットとフルートが速いパッセージを気持ちよく吹き鳴らしています。3楽章は、ラスト近くでホルンが燻し銀の光を放っており、毅然とした佇まいがしみじみ感動的。ホルンはデイル・クレヴェンジャーによるものでしょうか。この人は1966年に音楽監督のジャン・マルティノンに招かれてシカゴ交響楽団に移籍、2013年に退任するまで50年近く首席奏者を務めていました。要するに黄金期を支えた奏者がこの録音にはすでに集結していたといえることです。
そして、この曲で大活躍するトランペットはアドルフ・ハーセスです。第4楽章では彼の軽快なタンギング妙技を聴くことができます。
トランペットのアドルフ・ハーセス
カップリング曲にポロディンの「歌劇≪イーゴリ公≫より ダッタン人の踊り 」をチョイスしたのは多分EMIのスタッフの意向だったのでしょう。以前にビーチャムでの成功体験がありましたからねぇ。まあ、同じロシアものとしても収まりが良いものです。ちなみにボストン京都の録音はカップリングなし。ウィーンフィル盤では同じリムスキー・コルサコフの序曲「ロシアの復活祭」がチョイスされていました。しかし、こちらは小澤征爾はこの録音しか残していないんですなぁ。
結構はちゃけた演奏ではありますが、ちょっと音楽にゆとりがありません。金管は頑張っているのですが、なんか囲いの中で踊っているような感じがします。編集の後がくっきりわかるのも賂ポイントかもしれません。もう少しスケール感があるとよかったのでしょう。この曲では昔、サロネンが演奏したものが中々の快演だったのを覚えています。