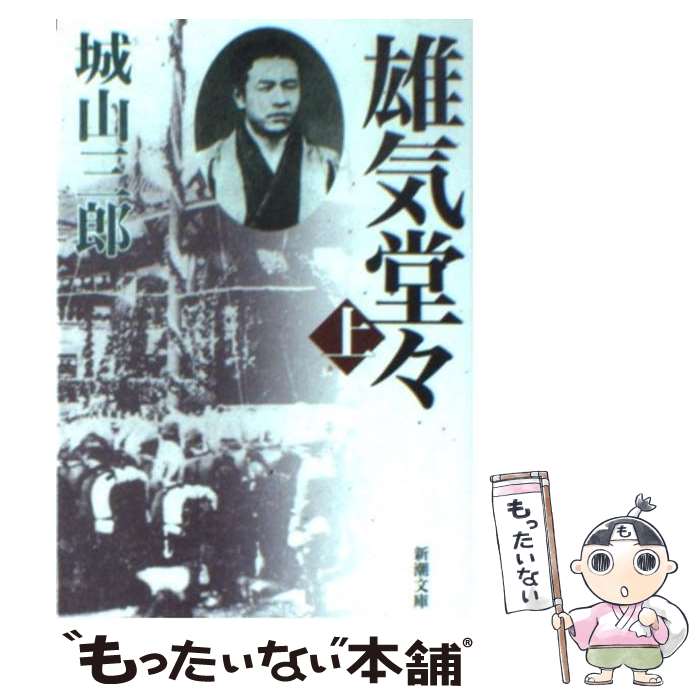城山三郎展
あいちゆかりの人物伝
今愛知県図書館では「城山三郎展」が開催されています。経済小説の大御所と言われる存在で、今では城山三郎賞と言う賞まで設定されています。この人物が名古屋市の出身であったと言う事はすす知っていましたが、このたびの展示を見て些か感動した次第です。
今回の展示では、その幼少期から作家生活を始め、経済小説作家として大成していくまでの道のりと名古屋の関係を詳しく展示しています。
これまでに経済小説作家としての作品は、古くは清水一行氏、高杉良氏などの作品から、現在の池井戸潤氏までかなり読んではいるのですが、恥ずかしながら肝心な城山三郎氏の作品は読んだことがありません。(^^;;
この展示では、作者の少年時代、つまり名古屋市中区で生活していた時代の資料も展示されています。本名は杉浦栄一と言い名古屋の栄にほど近いところに生まれています。ここには少年時代の作文や絵が展示されていました。そこで書かれた夢は動物が好きだったと言うこともあり、将来は東山動物園の園長になりたいと言うものだったようです。
彼の子供の頃栄には、名古屋公衆図書館というものがあったようです。現在、中区には名古屋市立の図書館がありませんが、その代わり、愛知県図書館が存在します。ところで、その堺図書館に出かけた時、奥さんとなる容子夫人と偶然に出会って、そこから交際が始まっています。人生への奇跡の瞬間です。
wikiによると名古屋市立名古屋商業学校(現在の名古屋市立向陽高等学校)を経て、1945年(昭和20年)愛知県立工業専門学校(現在の名古屋工業大学)に入学。理工系学生であったため徴兵猶予になるも、大日本帝国海軍に志願入隊。海軍特別幹部練習生として、特攻隊である伏龍部隊に配属になり、訓練中に終戦を迎えた。これについて城山は「日本は明治維新と敗戦の2度、上の世代が飛んで、すっかりいなくなったからね。それが良かったのかもしれないねぇ」と語っている。という記述があります。まあ、そこから終戦を迎えて人生が大きく変わっています。
資料もたくさん展示されており、創作ノート何かにはびっしりと細かいメモが綴られています。
展示資料の中で、「城山三郎、名古屋文学マップ」という張り出しがありました。これを見ると幼少期の活動範囲が分かります。一般には転居した城山神社のそばに住んだことがきっかけで、ペンネームを白山三郎としたということが言われています。ただ、ここにはわずか3ヶ月程度住んだだけの様です。
彼の足跡をたどるターニングポイントとなった建造物の懐かしい写真も提出されています。自分の中では幻の存在であった名古屋公衆栄図書館と言う存在も、今回の展示で場所とともに明らかになりました。この図書館移転後は、名古屋市の西図書館として生まれ変わっています。小生も親戚が西区にあったこともあり、この西図書館には足が通った記憶があります。
普段この城山三郎の展示は東区にある「文化の道、双葉館」の2階に書斎が再現されている程度ですが、今回はその足跡をたどるかなり詳しい展示がなされているので非常に興味深いものになっています。さて、城山三郎は一般には経済小説家と言われていますが、上の表にあるように、かなり広い創作活動を続けていましたその中で現在の10,000円札のモデルになっている渋沢栄一についても「
」という書籍を残しています。その渋沢について語った講演の様子が下記に記されていますので、貼り付けておきます。興味があったら覗いてみてください。
『少しだけ、無理をして生きる』 城山三郎 | 新潮社 (shinchosha.co.jp)