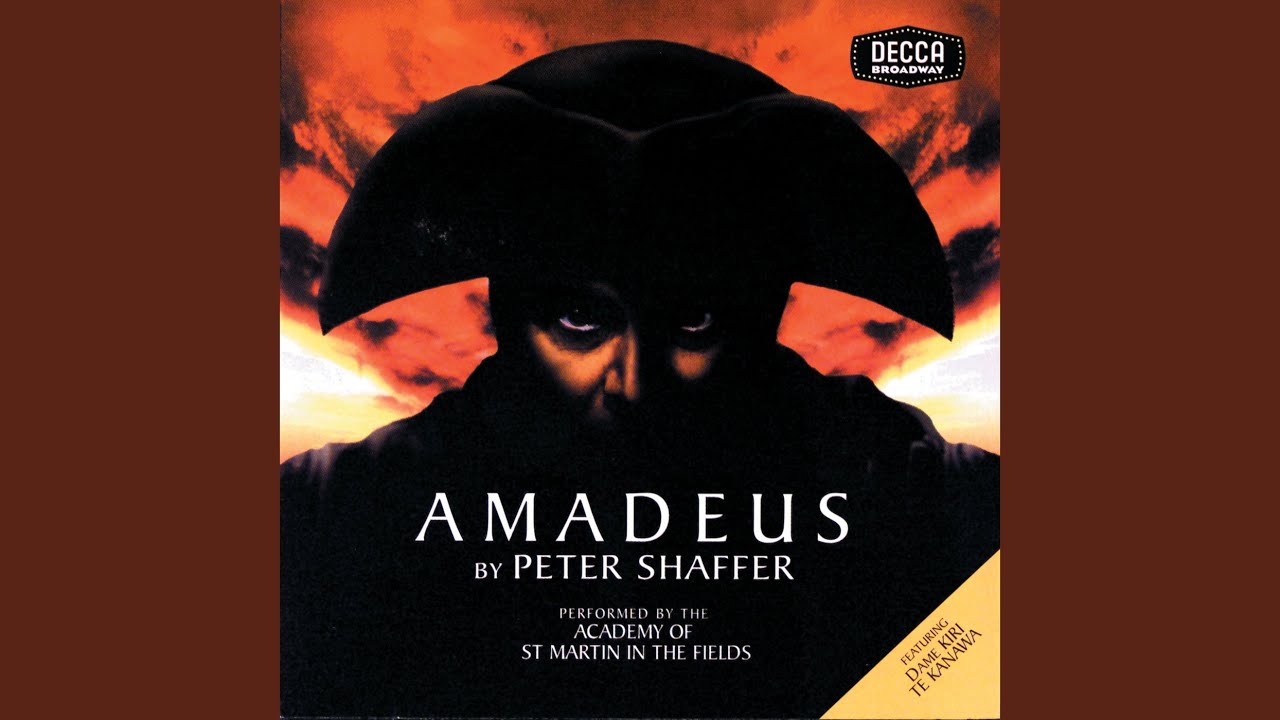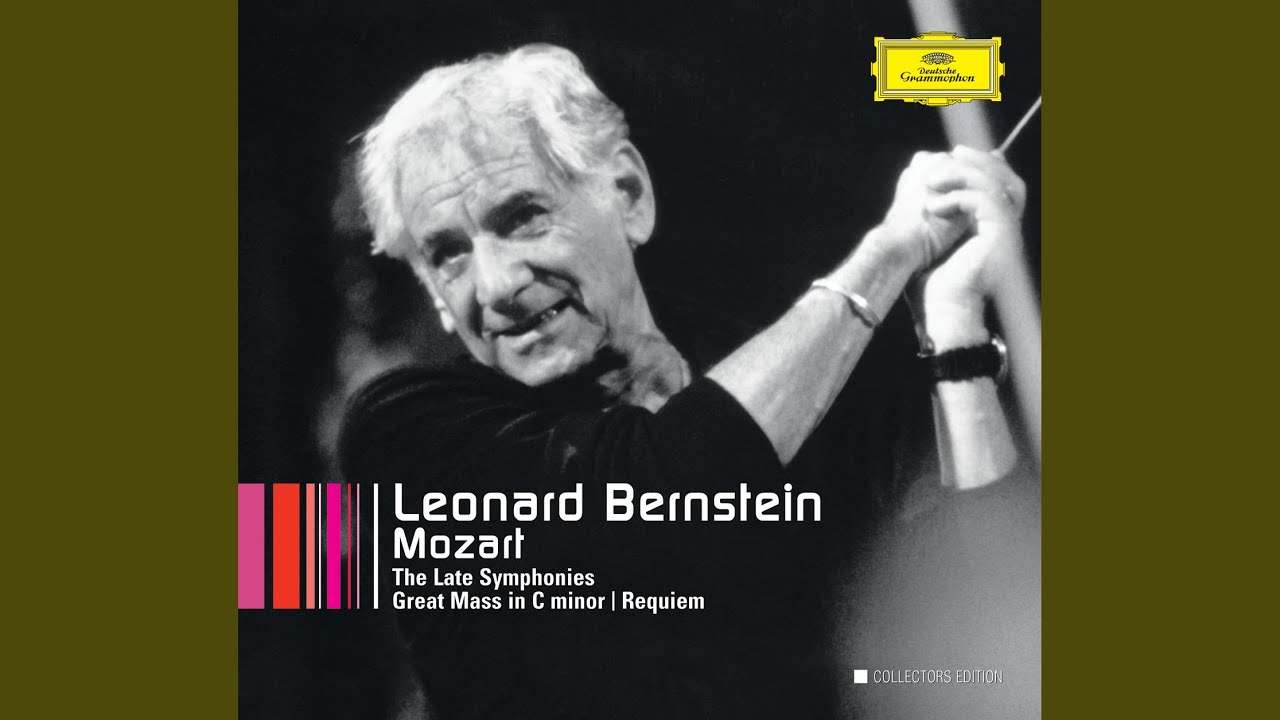ホグウッド
モーツァルト交響曲第25番
曲目/モーツァルト
交響曲 第25番 ト短調 K.183(173dB)
1.第1楽章:Allegro con brio(10:45)
2.第2楽章:Andante(5:59)
3.第3楽章:Menuet & Trio(4:14)
4.第4楽章:Allegro(7:18)
指揮/クリストファー・ホグウッド
演奏/エンシェント室内管弦楽団
録音/1979/06 セント・ポール教会
P:モートン・ワインディング
E:ジョン・ダンカーリー、サイモン・イードン
演奏/エンシェント室内管弦楽団
録音/1979/06 セント・ポール教会
P:モートン・ワインディング
E:ジョン・ダンカーリー、サイモン・イードン
DECCA 452496

1764年4月22日はモーツァルトが生涯で初めて船に乗った日です。モーツァルト8歳で、パリ・ロンドン旅行の途中です。この日、彼はドーヴァー海峡を渡ってフランスのカレーからロンドンを目指したのです。この旅行が契機となってモーツァルトは交響曲の作曲をスタートさせています。そして、この交響曲第25番は3度目のイタリア旅行から帰った後のウィーン滞在期間中に書かれています。それまでの交響曲とは劇的に違う、モーツァルトらしさに溢れた交響曲へと進化させています。初期の交響曲の代表作ということでこの交響曲を取り上げることにしました。
承知のように近年は映画「アマデウス」の冒頭に取り上げられたことに拠って、モーツァルトの波乱に富んだ生涯を暗示じさせることとともに一躍有名曲に仲間入りしました。CDには29,30番も収録されていますが、ここでは、ホームページで取り上げているアーノンクールの演奏と比較させる意味でこの25番だけを取り上げることにします。
古楽ブームの中で真っ先にモーツァルトの交響曲全集に取り組んだのはこのホグウッドでした。1978年からスタートしたこの企画は1985年に完結を見ます。丁度時代はアナログからデジタルに変わっていった時期で、全集としてはちょっと中途半端な印象になった感がありますが、いろいろ新しい試みを取り入れて画期的な全集という位置付けは変わりません。何しろ異稿版も含めて収録しているという徹底ぶりです。アーノンクールは初期の作品はウィーン・コンチェントゥス・ムジクスを、後期の曲はアムステルダムコンセルトヘボウ管弦楽団というフルオーケストラを使用して全曲を録音しています。この第25番についてはその両方のオケで録音していますから、やはりこの曲辺りがターニングポイントとなっているのでしょう。録音時期はこの曲はほとんど同じですが、そのスタイルの違いは明確です。
このホグウッドの演奏で驚かされたのは、通奏低音としてチェンバロが採用されていることです。マリナーの演奏でヴィヴァルディの四季がオルガンという楽器を通奏低音で使用した演奏が登場した時も驚きましたが、このホグウッドの演奏でモーツァルトの交響曲でチェンバロが使われているのを耳にした時も少なからず衝撃がありました。録音も古楽器を使っている割に典雅というより、どちらかというと先鋭的な表現のため突き刺さる様な刺激を感じたものです。国内での発売に際しては、レーベルとしてのポリシーか、1982年になっていきなりザルツブルク編第2巻として7枚組のボックスセット(なんと15,400円です)と単売が同時にリリースされました。この交響曲第25番は初出はLPレコードで第29番とのカップリングで発売されています。

さて、第1楽章から鮮烈的な演奏で始まります。楽譜を見ても分かるようにアレグロ・コンブリオはフォルテで始まります。この交響曲はホルンが使われているということで、斬新です。それも、当時としては異例な4本のホルン(しかも両者とも2本のト音管と2本の変ロ管)を使用しているのです。このあたりは、1768~69年頃作曲のハイドンの交響曲「第39番」ト短調を参考にしている節があります。同じ短調でハイドンも4本のホルンを同様に使用しています。木管はファゴットとオーボエを使っているだけでこれだけの音楽を表現しているのですから大したものです。ホグウッドは、時代考証とともにピリオド楽器を用いて実はかなりモダンな表現でこの曲を再現しています。第2主題は楽譜通りの音型で処理しています。まあ、管楽器を含めてノンヴィヴラートで処理されていますからいますから、響きに揺らぎがありません。普段モーツァルトの曲を聴いて、ゆらぎのα波が発散されている演奏とは一味違います。また、リピートをすべて繰り返していますから、普通は大体7~8分ぐらいと言ったところですが演奏時間は10分越えです。刺激的ですが、テンポはあまりいじらず、そういう点では時代考証的な学研的な姿勢を伺い知ることが出来ます。まあ、その第1楽章を聴いてみましょう。
| ホグウッド/エンシェント |
この演奏、個人としてはレコード発売時には聴いていません。先に聴いていたのはカール・ベームの全集の演奏であり、頻繁に耳にしたのは映画「アマデウス」で使用されていたマリナー/アカデミーの演奏でした。ですから、この演奏を耳にした時は、こんなモーツァルトがあるのかと目から鱗の状態でした。しかし、この後CDを入手し、さらにアーノンクールの演奏を手に入れてまたびっくりです。当時は、アーノンクールがコンセルトヘボウを振ってモーツァルトを録音したということだけで驚いたのですが、この25番は更に驚かされました。こんな演奏です。
| アーノンクール/コンセルトヘボウ |
どうです、普段聴き慣れた旋律とは違う旋律が聴こえてくるでしょう。細部にわたってもホグウッドとは解釈が違います。冒頭のフォルテも譜面通りには処理していません。楽譜には書かれていませんが各小説の頭にアクセントを付けて処理していますし、それよりも、ホルンが登場する5小節目の3拍目にフォルの比重をかけて処理しています。そのホルンも刺激的な吹かせ方です。そして、なによりも59小節目に登場する第2主題のヴァイオリンの旋律処理が独自なんですね。でも、この後に登場する部分では普通の音階で演奏しています。何故こういう解釈になったのかぜひ知りたいものです。さらに、聴き進むに従ってかなりテンポに変化をつけていますし、アクセントの処理も独自なところが多々発見出来ます。こういう演奏ですから、好き嫌いがはっきり出るんでしょうね。

ピリオと奏法では、ホグウッドを追っかけるように完成したピノックは、こんなものでした。
| ピノック/イングリッシュコンソート |
フォルテで始まり、ややホルンを強調して吹かせるところに特徴がありますが、小生にはあまり心を動かされません。チェンバロを入れてはいますがごく控えめでそれほど目立ちませんし、テンポはホグウッドよりやや早めですが、どうもお茶漬けさらさら的で印象に残りません。
さて、多分、一番耳にする機会が多かったマリナーの演奏では々だったんでしょうか。こんな演奏でした。
改めて聴くと、冒頭のヴァイオリンの響きは鮮烈な印象がありますが、ホルンの響きは以外におとなしめです。そういう意味では万人向きの演奏だったのかもしれません。
| マリナー・アカデミー |
改めて聴くと、冒頭のヴァイオリンの響きは鮮烈な印象がありますが、ホルンの響きは以外におとなしめです。そういう意味では万人向きの演奏だったのかもしれません。
では、王道のカール・ベームの演奏はどんなもんでしょうか。ベームはベルリンフィルと全集を録音しています。上はそのベルリンフィルとの演奏。下は晩年に残した映像版のウィーン・フィルとの演奏です。ベルリンフィルの冒頭は、今聴くと何処となくのんびりしていてちょっと違和感を感じます。
ところが最晩年の1978年の演奏では、意外とマトモな演奏をしているのでびっくりです。これはベームのモーツァルトというよりはウィーン・フィルのモーツァルトなんでしょうかね。
| カール・ベーム、ベルリンフィル |
| カール・ベーム/ウィーンフィル |
そう感じたのは、バーンスタイン・ウィーンフィルの演奏がこれに近いものだからです。まあ、テンポはこの頃はバーンスタインはめっきり遅くなっていますけどもね。最後はそのバーンスタイン/ウィーンフィルで全曲を聴いてみましょうか。
| バーンスタイン/ウィーンフィル |
一つの曲をこうやって比較して聴くことが出来るのも、クラシックの楽しみ方なんでしょうなあ。いい時代に生まれたものです。