1937年7月7日。北京近郊の盧溝橋で日本軍と中国軍の偶発的な戦闘から日中戦争と呼ばれる長い戦いが始まりました。日本政府は、この衝突を“不拡大・現地解決”を謳って矮小化し、戦争勃発の引き金を引く責任を回避しようとします。当時の政府はこれを支那事変と呼びます。この名称は何も戦争の定義について考えた結果ではなく、全面戦争を遂行する覚悟や責任感の欠如の表われと見たほうが正しいはずです。
キャリア官僚によるタテ割り行政という意味では、帝国陸海軍の内部は正に象徴的です。
この衝突の遠因となったのは暗殺された張作霖の息子・張学良の存在です。1936年、古都西安に共産党軍との戦いの督戦に来た蒋介石を拉致監禁し、中国共産党の周恩来と会談させ、国共合作と呼ばれる国民党と共産党の対日共同戦線を張らせようとしたのを西安事件と呼びます。

左から張学良、蒋介石、周恩来。
1925年に張作霖を暗殺したのは河本大作大佐、護衛したのは儀我誠也少佐。どちらも帝国陸軍の軍人です。
この時も日本政府は“満洲某重大事件”という責任も覚悟もない名称で呼び、首相の田中義一はキャリア軍人を正当に処罰することも出来ずに引責辞任します。
張作霖の軍事顧問団を形成していたのは日本の帝国軍人であり、彼らも乗り込んでいる列車に爆薬を仕掛けてまとめて爆殺しようとしたのも帝国軍人。それでいて停職処分で済まされたのです。
この裏切り行為に張学良は激怒していたと言います。しかもこの満洲某重大事件とやらが発生したのは張学良本人の誕生日。さらに満洲国建国によって地盤を追い出された張学良は国民党と共産党に連合して日本軍と戦おうとするのです。

この時の首相は近衛文麿公爵。最後の元老と呼ばれる西園寺公望公爵の後ろ盾と国民的人気を背景に首相に就任しています。写真の左は孫とひ孫と一緒に写る西園寺公爵、右は近衛公爵です。
西園寺家は清華家に属し、近衛家は五摂家に属する平安時代の藤原北家以来の名門貴族で、彼らに荒れた当時の日本の政情を安定させることを人びとは望んだのでした。
盧溝橋事件から始まる帝国軍と国民党軍の戦闘は実質的には数日で停戦協定が望まれることになるのですが、現地からの情報伝達は現在と同じく首相まで届きません。停戦協議の真っ最中に近衛は中国大陸への軍の増援を発表。しかもそれは“不拡大・現地解決”のために必要だと本人は認識していたのです。
現状を把握できずにいる近衛首相に、バラバラの情報源からバラバラの情報が入り、誰も整理することができないまま対中政策は迷走していきます。
石原莞爾らの外交工作により、蒋介石との首脳会談がセッティングされ、近衛首相本人は受け入れるも政府内部での意見の相違からキャンセルさせられ、首相特使を蒋介石に送ろうとすると今度は首相特使が帝国陸軍に捕えられてしまうのです。

当時の国民党軍はドイツ軍人の支援を得て、大日本帝国軍や中国共産党との戦闘に臨んでいました。
左はポーランド侵攻にも従軍しドイツ軍将校でもある蒋介石の養子・蒋緯国。右はドイツ軍装で行進する国民党軍。
蒋介石をはじめとする中国側も日本の意図が分らなくなります。現地司令官が停戦協議をしていると突然、増援軍を送ると発表し、首相自らの首脳会談を求めてきたと思うとキャンセルされ、その代わりに特使を送るといってはやって来ない。日本政府の迷走は中国側の不信感を高めるばかり。国内外の中国系の世論も日本への怒りを高めて蒋介石に強硬に対応するよう求めています。
ここで、蒋介石はひとつの決断をします。
それが後に第二次上海事変と呼ばれる戦闘行動です。
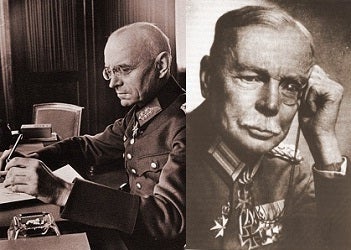
ドイツから派遣され、国民党軍の軍事顧問をしていたアレクサンダー・フォン・ファルケンハウゼンとハンス・フォン・ゼークトの写真です。
“有能な怠け者。これは前線指揮官に向いている。
有能な働き者。これは参謀に向いている。
無能な怠け者。これは総司令官または連絡将校に向いている、もしくは下級兵士。
無能な働き者。これは処刑するしかない。”
と、軍オタ経験者なら誰でも知っているであろう、こんな言葉は本当に彼が言ったかどうか別として、ゼークトの言葉とされています。
そのゼークトですが、国民党軍の顧問として日本のアジアへの野望を阻止することが求められていました。
上海には租界と呼ばれる列強諸国の居留地がありました。
この居留地を守るとして各国は自国軍を送り中国大陸進出への足がかりにしていたのです。
ゼークトは、この上海を包囲する要塞線を構築しました。これを俗に“ゼークト・ライン”と呼んでいます。そのゼークトですが、1935年にドイツに戻り、36年に亡くなりますので、その後任としてやってきたのがファルケンハウゼンということになります。
キャリア官僚によるタテ割り行政という意味では、帝国陸海軍の内部は正に象徴的です。
この衝突の遠因となったのは暗殺された張作霖の息子・張学良の存在です。1936年、古都西安に共産党軍との戦いの督戦に来た蒋介石を拉致監禁し、中国共産党の周恩来と会談させ、国共合作と呼ばれる国民党と共産党の対日共同戦線を張らせようとしたのを西安事件と呼びます。

左から張学良、蒋介石、周恩来。
1925年に張作霖を暗殺したのは河本大作大佐、護衛したのは儀我誠也少佐。どちらも帝国陸軍の軍人です。
この時も日本政府は“満洲某重大事件”という責任も覚悟もない名称で呼び、首相の田中義一はキャリア軍人を正当に処罰することも出来ずに引責辞任します。
張作霖の軍事顧問団を形成していたのは日本の帝国軍人であり、彼らも乗り込んでいる列車に爆薬を仕掛けてまとめて爆殺しようとしたのも帝国軍人。それでいて停職処分で済まされたのです。
この裏切り行為に張学良は激怒していたと言います。しかもこの満洲某重大事件とやらが発生したのは張学良本人の誕生日。さらに満洲国建国によって地盤を追い出された張学良は国民党と共産党に連合して日本軍と戦おうとするのです。

この時の首相は近衛文麿公爵。最後の元老と呼ばれる西園寺公望公爵の後ろ盾と国民的人気を背景に首相に就任しています。写真の左は孫とひ孫と一緒に写る西園寺公爵、右は近衛公爵です。
西園寺家は清華家に属し、近衛家は五摂家に属する平安時代の藤原北家以来の名門貴族で、彼らに荒れた当時の日本の政情を安定させることを人びとは望んだのでした。
盧溝橋事件から始まる帝国軍と国民党軍の戦闘は実質的には数日で停戦協定が望まれることになるのですが、現地からの情報伝達は現在と同じく首相まで届きません。停戦協議の真っ最中に近衛は中国大陸への軍の増援を発表。しかもそれは“不拡大・現地解決”のために必要だと本人は認識していたのです。
現状を把握できずにいる近衛首相に、バラバラの情報源からバラバラの情報が入り、誰も整理することができないまま対中政策は迷走していきます。
石原莞爾らの外交工作により、蒋介石との首脳会談がセッティングされ、近衛首相本人は受け入れるも政府内部での意見の相違からキャンセルさせられ、首相特使を蒋介石に送ろうとすると今度は首相特使が帝国陸軍に捕えられてしまうのです。

当時の国民党軍はドイツ軍人の支援を得て、大日本帝国軍や中国共産党との戦闘に臨んでいました。
左はポーランド侵攻にも従軍しドイツ軍将校でもある蒋介石の養子・蒋緯国。右はドイツ軍装で行進する国民党軍。
蒋介石をはじめとする中国側も日本の意図が分らなくなります。現地司令官が停戦協議をしていると突然、増援軍を送ると発表し、首相自らの首脳会談を求めてきたと思うとキャンセルされ、その代わりに特使を送るといってはやって来ない。日本政府の迷走は中国側の不信感を高めるばかり。国内外の中国系の世論も日本への怒りを高めて蒋介石に強硬に対応するよう求めています。
ここで、蒋介石はひとつの決断をします。
それが後に第二次上海事変と呼ばれる戦闘行動です。
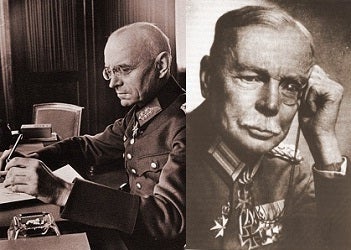
ドイツから派遣され、国民党軍の軍事顧問をしていたアレクサンダー・フォン・ファルケンハウゼンとハンス・フォン・ゼークトの写真です。
“有能な怠け者。これは前線指揮官に向いている。
有能な働き者。これは参謀に向いている。
無能な怠け者。これは総司令官または連絡将校に向いている、もしくは下級兵士。
無能な働き者。これは処刑するしかない。”
と、軍オタ経験者なら誰でも知っているであろう、こんな言葉は本当に彼が言ったかどうか別として、ゼークトの言葉とされています。
そのゼークトですが、国民党軍の顧問として日本のアジアへの野望を阻止することが求められていました。
上海には租界と呼ばれる列強諸国の居留地がありました。
この居留地を守るとして各国は自国軍を送り中国大陸進出への足がかりにしていたのです。
ゼークトは、この上海を包囲する要塞線を構築しました。これを俗に“ゼークト・ライン”と呼んでいます。そのゼークトですが、1935年にドイツに戻り、36年に亡くなりますので、その後任としてやってきたのがファルケンハウゼンということになります。