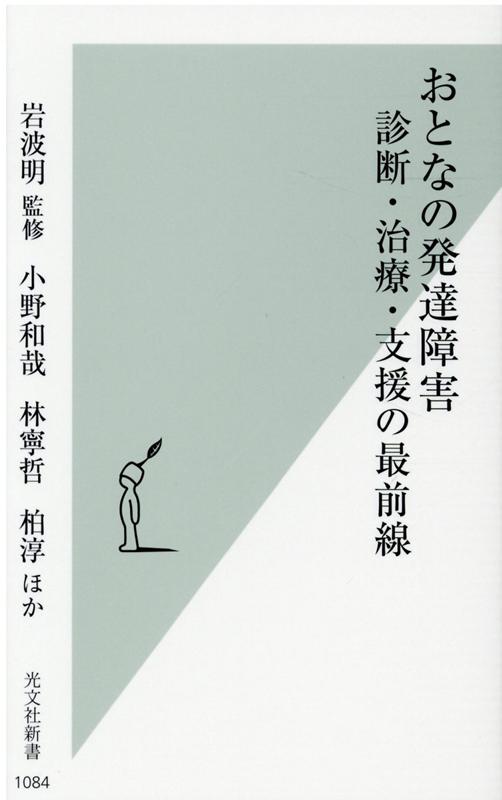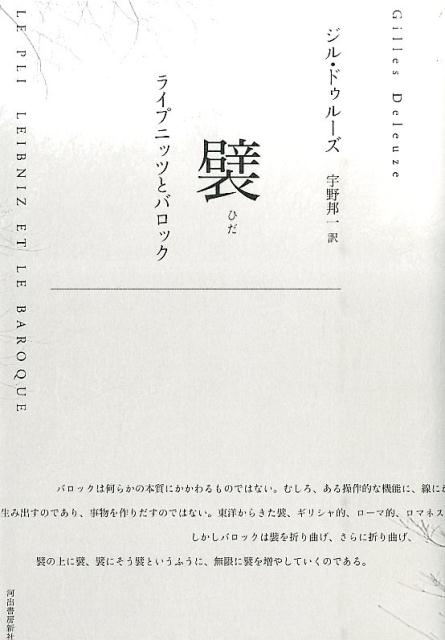仲野徹著『エピジェネティクス――新しい生命像をえがく』読了。
内容紹介(「BOOK」データベースより)
ゲノム中心の生命観を変える、生命科学の新しい概念「エピジェネティクス」。遺伝でもない、突然変異でもない。ゲノムに上書きされた情報が、目をみはる不思議な現象を引き起こす。自然の妙技と生命の神秘。世界中のサイエンティストが熱い視線を注ぐ、いま一番ホットな話題を楽しく語る。
目次(「BOOK」データベースより)
序章 ヘップバーンと球根/第1章 巨人の肩から遠眼鏡で/第2章 エピジェネティクスの分子基盤/第3章 さまざまな生命現象とエピジェネティクス/第4章 病気とエピジェネティクス/第5章 エピジェネティクスを考える/終章 新しい生命像をえがく
「ワディントンのエピジェネティック・ランドスケープ」というものを始めてみたのは、岩波明監修の「おとなの発達障害」という本だった。
発達障害の研究においてもこの「エピジェネネティクス」という概念/技術が現在大きな存在感を持ってきている分野だと知り、俄然興味が湧いた。
人体の細胞は3ヶ月以内にすべて入れ替わると言われる。
いわゆる新陳代謝だ。
それに対してゲノム(DNA=遺伝子情報)というのは、基本的、総体的には終生変わることはない、とされてきた(がん細胞などは例外とする)。
ところが遺伝子の塩基配列(アデニン、グアニン、チミン、シトシンの4種で構成される)の変化によらない遺伝上の変化があることが、ヒトを始めとした様々な動植物のゲノム解析が進むとともにわかってきた(乃至は以前からわかっていた現象がエピジェネネティクスで説明されうるものになってきた)。
遺伝子そのものを取り巻き、その支持体となっているヒストンというものの修飾と、遺伝子のメチル化/脱メチル化が、遺伝子の発現/抑制のキーとなっていることがわかってきたのだ。
本書でも「コード」という語がしばしば出てくるが、たしかにそのメカニズムはまるでコンピュータのプログラミングのようでもある。
同時にそれは「修飾」というものの重要度において、バロック的なものにも通ずるように、僕には思われる。
音楽にしろ絵画にしろ建築にしろ、バロック芸術はまさに修飾によって特徴づけられるからだ。
生物学、特に現代的な分子生物学がバロック的になっていく、と言えば言いすぎかもしれないが、その響きにある種の魅惑を覚えるのは僕だけではあるまい。
バロックといえばG.ドゥルーズが同時代の哲学者ライプニッツと関連付けて論じていたことが知られているが、時代はまさにバロック的なものへと移り変わっていっているのかもしれない(ただしより高次の段階として)。
それはバロック期、ライプニッツのモナド論やホムンクルスのような発想を再考する良い機会になるのかもしれない。