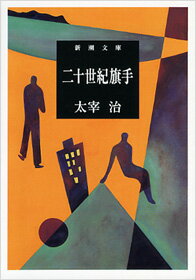太宰の短編『二十世紀旗手』読了。
イメージからイメージへ、連想から連想へ、あるいは、言葉から言葉へ。
その混沌から、一つのロマンスが生まれる。
「文学」誕生のプロセスを追った、一つのドキュメントとして読める。
しかしその影にあるものは、
一語はっするということは、すなわち、二、三千の言葉を逃がす冷酷むざんの損失を意味して居ります。
という選言的命題であり、
そこでは単語だけでなく、いくつもの物語が絞め殺されているのだ。
主人公の苦しみは、それ故に深い。
作家にとって物語とは、それ自体が一つの生命体であり、
またその中に息づく登場人物たちは、文字通り息をした人物たちなのだ。
この作品(または他の諸作品でもだが)でよく引き合いに出される、
作者・太宰のバイオグラフィー的な背景を、僕は敢えてここで書かないでおく。
それは、太宰がここで目指そうとしたものは、明らかに、
純粋なフィクション、それも革新的なフィクションであったろうと思うから。
それが達成できているかどうかはまた別の話としても。