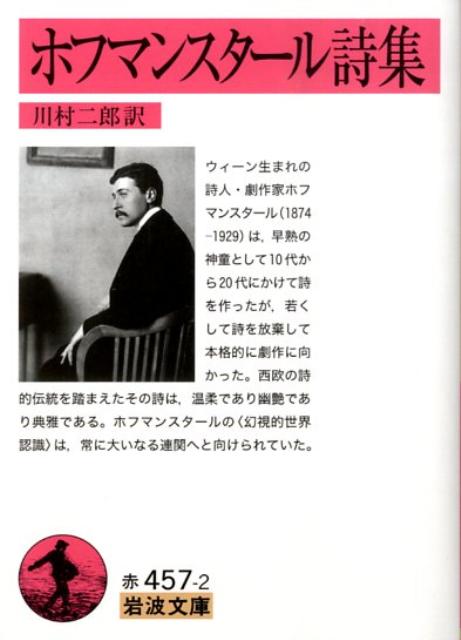そして子供らは成長する 何も知らない
深い眼の色をして 成長して そして死ぬ
そして人はみな それぞれおのれの道を行く
そして酸い果実はやがて甘く熟れ
夜となれば 死んだ鳥のように地に落ち
そして幾日かが過ぎ そして腐る
そして風はたえず吹き くり返しわれらは
数多の言葉を耳にし 口にし
そして肉体のよろこびと疲れとを感ずる
そして往還は草のあいだを走り 村々が
そこかしこに横たわる 到る所に松明 木立 池
そして威嚇にみちた また死のように荒れはてた村……
何のためにこれらは設けられたのか? どうして同じい
ものがないのか? どうしてこれほど数多いのか?
どうして移り変るのか 笑いと 涙と 死が?
こんなことが何になるのか このはかない戯れが?
無心の日々を遠ざかり 永劫に孤独な
さすらいの目途(めあて)をついにもとめ得ないわれらにとって?
こんなことを多く見たとて何になるのか? だがしかし
誰かがふと「夕ぐれ」というならば その味いはどうだろう?
たった一つのこの言葉から 深い意味と哀しみがしたたる
さながらうつろな蜂窩(はちのす)から 濃い蜜のしたたり出るように
ウィーン生まれの詩人・劇作家ホフマンスタール(1874-1929)は、早熟の神童として10代から20代にかけて詩を作ったが、若くして詩を放棄して本格的に劇作に向かった。西欧の詩的伝統を踏まえたその詩は、温柔であり幽艶であり典雅である。ホフマンスタールの“幻視的世界認識”は、常に大いなる連関へと向けられていた。