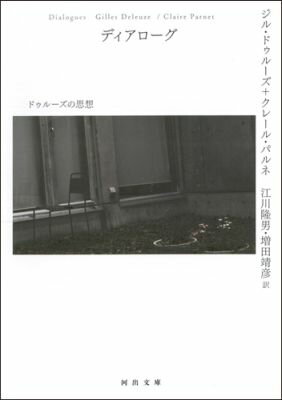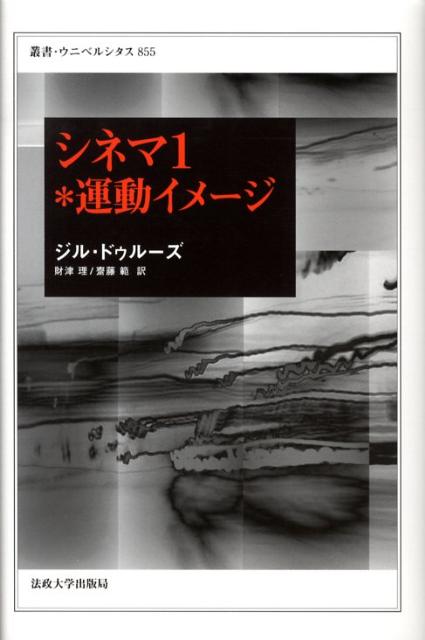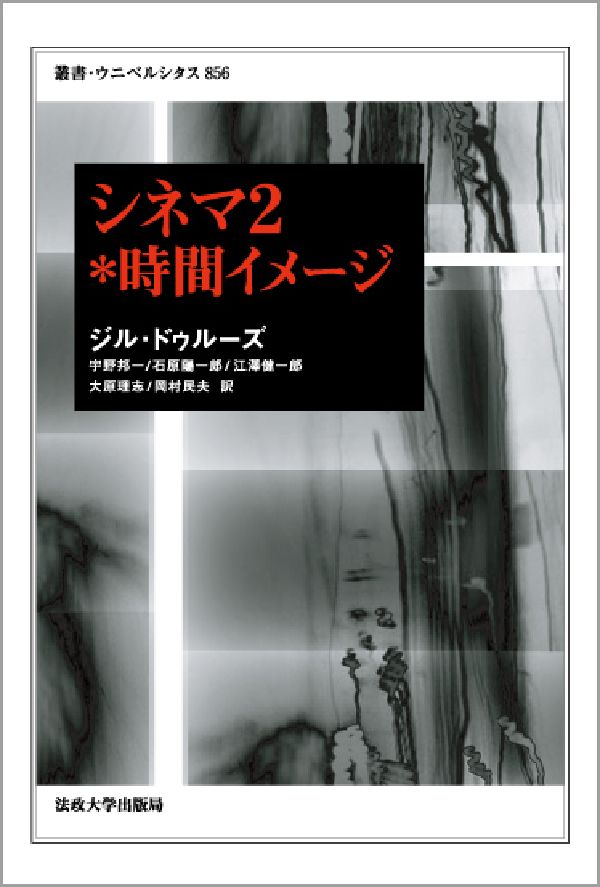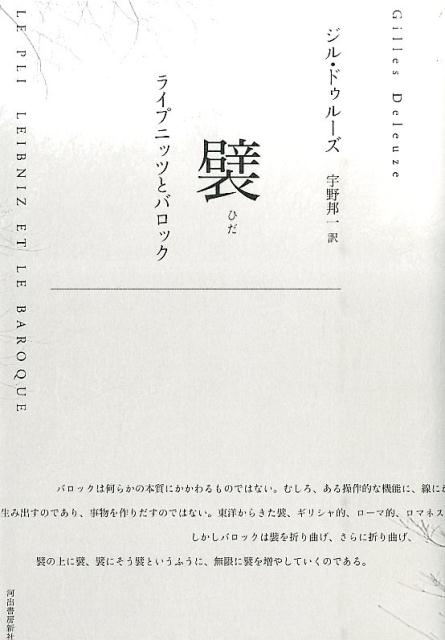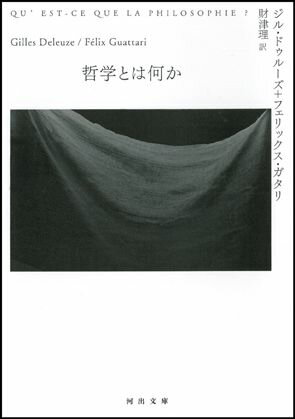ドゥルーズとパルネの共著『ディアローグ』読了。
『アンチ・オイディプス』と『千のプラトー』のはざまの一九七七年、もうひとりの盟友パルネとの共著として書かれ、とりわけ『千のプラトー』のエッセンスを凝縮した名著。ガタリとともに新たな思想を生成させつつあったドゥルーズの思考の息遣いを伝えながら、「実験としての生」を実践し、来たるべき哲学を開く。ドゥルーズを読むなら、この一冊から。
裏表紙には「ドゥルーズを読むなら、この一冊から。」と書かれてあるが、
解説1で訳者の一人江川隆男も書いているように、「入門書としては難しすぎる」。
僕の場合は先に『プルーストとシーニュ』や『スピノザ 実践の哲学』を先に読んでおいてよかったなと思った。
特に『スピノザ~』の方は本書の問題意識と通底しているものを持っているので、
本書を読む前に読むことをお勧めしておきたい。
さて、本書を要約するのは大変な作業だが、
キーポイントの一つとなり得るのが、
解説2でもう一人の訳者増田靖彦も指摘しているように、
「ベルクソンへの回帰」であろう。
本書の原書が出版されたのが1977年という事もあって、
性格的には『アンチ・オイディプス』から『千のプラトー』へ架橋するような内容
とも言えるが、
そこに留まらず、『シネマ1・2』でのベルクソン再考の影響が大きいのではないか
といったようなことを増田は書いている。
そしてそれはこの後の『襞』や『哲学とは何か』まで通ずる、
後期ドゥルーズを読み解くひとつのキーとなるのではないかとも。
ドゥルーズのベルクソン論はまだきちんと読んでいないので、
準備が出来たら読もうと思う。